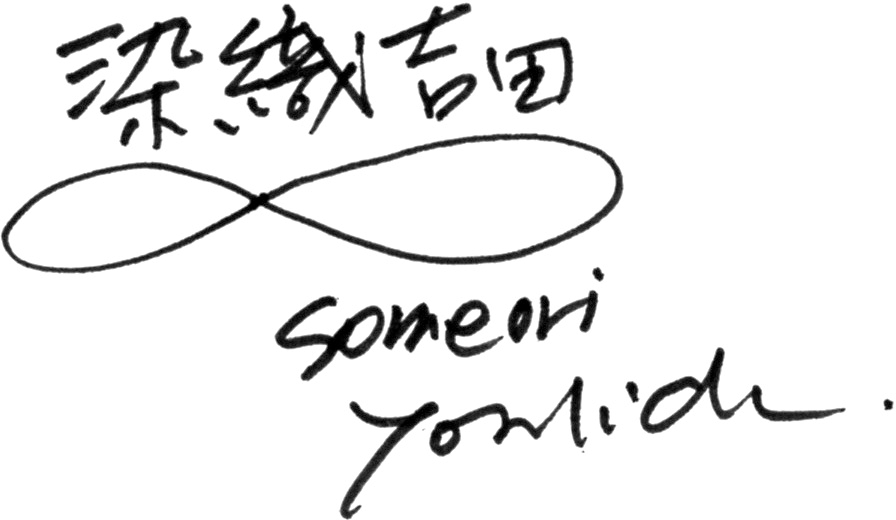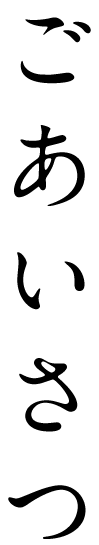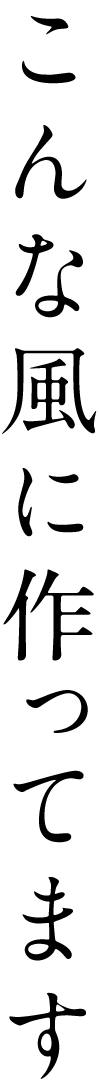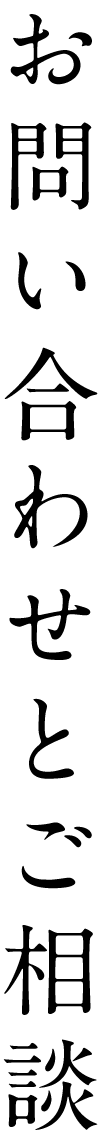吉田美保子の some ori ノート
Blue Blessing (ブルーブレッシング)完成記

ずーっと取り組んでいたきものが織りあがりました。

「Blue Blessing(ブルーブレッシング)」【青の祝福】と名付けました。

制作の様子は、着物ライター安達絵里子さんが、note「蚕から糸へ、糸から着物へ」につぶさに書いてくださってますので、そちらに譲ります。

素晴らしい記録です。ぜひ、お読みください。

芥子粒みたいだった蚕の卵が、蟻ん子みたいな虫になり、桑の葉だけをむしゃむしゃ食べて、4回眠って、繭を結んだ。

冷凍されて埼玉に旅立って、少しずつ解凍され、お湯に浸かり、ぎゅっと固かった繭がダンスを踊るようにほどけていく。ゆっくりゆっくり座繰りされ、丁寧に合糸され、撚糸され、精練され、つるっと脱皮し変身し、糸になった。
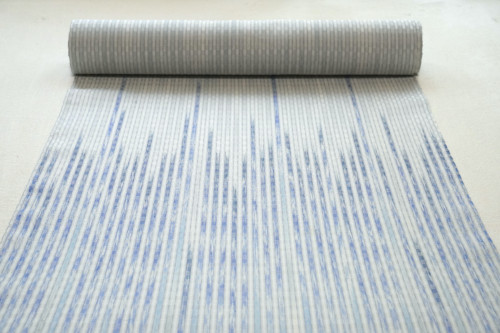
迎えにきたヨシダに抱き抱えられて、神奈川に。染められ、糊をつけられ、叩かれ、巻かれ、整経され、テンションを整え巻き取られ、綜絖や筬に通され、結びつけられ、緯糸を投げられ、打ち込まれ、とうとう布になった。
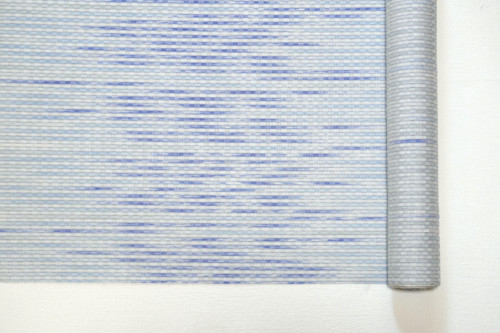
それがこの状態。
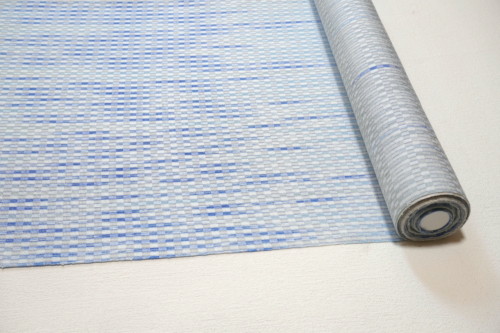
今現在は、絵羽にするために、仕立て師さんのところに行ってます。
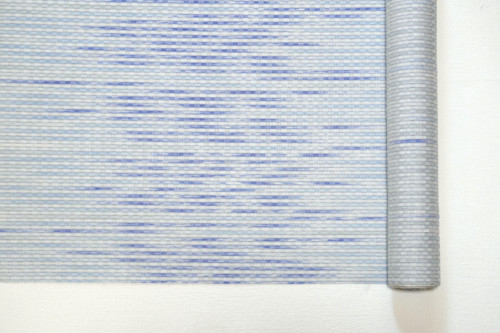
絵羽って、羽ばたく直前の形みたいなんだよね。広げるとちょっと蝶々のようだしね。またご紹介しますね。

この写真は、絵羽でなく、反物をマネキンに巻きつけてます。

これはこれで、どんな着物になるか、なんとなくわかるね。

「Blue Blessing(ブルーブレッシング)」は大空に羽ばたくのに、5人目のメンバーの方との出会いを待っています。
もし興味をもっていただけましたら、お気軽にヨシダまでお尋ねください。詳しくご説明いたします。

以下は、振り返り。じーんとします。
小島秀子さん、おたすけさん、江田朋百香さん

きのうは忙しくも充実した、とてもよい日でした。朝からきものを着てお出かけ。いろいろ行き先があるんで、よくよく調べて廻ってきました。
まずは、染織家の小島秀子さんの個展を拝見しに、青山八木さんへ。
帯がたくさん。どれを見ても本当にすばらしかったです。現代的な色づかいで、様々な技法がさりげなく駆使され、完成度高く。締めたら映えるな。楽しいだろうな。ただただ、うっとり。
織りをやっている身としては、キリッと引き締まりました。拝見させていただき、本当によかったです。ありがとうございました。

青山一丁目からめざしたのは神保町。学士会館。きものおたすけくらぶさんの盛装オフ会です。

全国からきもの好きのおたすけファンが集う楽しい会でした。
こういう場を催すの大変と思います。そのご苦労をものともせず、ニコニコ笑顔の富田社長。すごいなあ。そして、富田社長を支えてるみなさんもすばらしいです。
きもの好き同士もなかなか合うチャンスないので、その場を作っていただいて、ありがたいことでした。おかげさまで、久しぶりの方、はじましての方、いろんな出会いがありました。

その後、日比谷へ。帝国ホテルのギャラリーへ、画家の江田朋百香さんの個展を拝見しに。
朋百香さんは、お帰りになった後でお会いできなかったのですが、情熱をたたえたお作品に囲まれて幸せでした。ギャラリーの方や居合わせた方によくしていただいて、すっかり意気投合。

私は、この二枚がとくに好きでした。見ていると、頭の中がスッキリして、体ごと軽くなるような気がします。
*小島さんの個展、朋百香さんの個展、ともに終了しています。
登喜蔵さんご夫妻と

丹後の最終日、佐橘登喜蔵さんをお訪ねすることができました。
私、佐橘さんの織られるもの、大好きなんです。繭からずり出してひいた糸を丹後の植物で染めて織るその織物は、素朴だけど洗練されてて、強さと優しさが同居してます。その生まれる場所を見てみたかった。大変に光栄なことでした。
佐橘さんご夫妻、なんと、私のこと、迎えに来てくださったんですよ。もったいない〜〜。車に乗せてもらって、早速お話に花が咲き、、。
そのお宅は神社の参道にありました。わあ。そういえば、佐橘さん、なんだか神主さんぽいもんね。奥さまは天女ぽい。場所そのものが神域のようです。そっか、こんなところであの織物は生まれてるのね。
上がってすぐのお部屋に、織り機3台。その奥にずり出しの単純な装置、綛あげ。たったそれだけ。織物とはなんとシンプルなものであろうか。シンプルだからこその強さ。まっすぐさ。
私、自分が織った帯を持って行ってたので、おそるおそるもお見せしたら、ご自分の反物を出して、その上に乗せてくださいました。ピタリと合って、大感激でした。

そのあと、天橋立まで連れて行ってくださいました。いいのでしょうか、こんなにしてもらって!!一日使っていただくことになり、ありがたいやら、申し訳ないやら。
まず、真名井神社を参拝。ここ、知らなかったのですが、いわゆるパワースポットで、霊気がただよっている場所でした。ああ、神様がいらっしゃるんだなあ。私、見えないけどね。水筒にお水をいただきました。
その後、元伊勢籠神社を参拝。こちらもなんだかすごかった。由緒正しきとはこのことか。

そして、なんと、リフトに乗って、高台まで登ったのですよ。こんなのちょー久しぶり!!!リフトを降りても、階段を登って(相当がんばった!)、一番上までいきました。
眼下に天橋立が見えます。あ、本当に神様のハシゴだ。やっぱり、特別な場所なんだなあ。
いい空気をいっぱい吸って、私、生まれ変わりました!
帰りは福知山の駅まで送ってくださるという、ありがたさでした。
丹後、すばらしかったです。ものを作って生きていく、その根っこのところに、良いお水をたくさんふりそそいでいただきました。さあ、むくむくと動き出しましょうか。
丹後・染め修行ツアー

丹後の小林染工房へ、染めの修行に行ってきました。友禅の作家さんたちの研修ツアーに混ぜてもらったんです。本当に本当に、すばらしい機会で、私は目からウロコが落ちまくりでした。

教えてくださったのは、小林染工房の小林知久佐さん。丹後ブルーという、とても美しい青の引き染めをされることで有名な方です。が、もちろんそれだけじゃない。

小林さんのすごいところは、染料や助剤を知りつくしていて、それを的確に使いこなし、ぼかし染めやシケ引き(刷毛目を使って極細の線を染める技法)をなど、表現の幅広く、自由自在に美しい染めをされているところ。根本のところを押さえているから、失敗しないと。

小林さん曰く、
「若い頃は、テストに明け暮れ、失敗もたくさんしたし、お金も時間もつぎ込んだ。自分はさんざん苦労したけど、こんな苦労はみんなはしなくてええやん、だから、技術や知識は伝授する」。
うぅぅ、感涙。

本当に何から何まで教えていただきました。さて、どこまで受け止められたか、、、、。

私は八寸帯のタテ糸を仮織りして持ち込みました。

染料は、小林さんの染料と私が持って行った染料を両方使って、染め比べます。
小林さん、この、ブラッシングカラーズ (タテ糸に直接染めるやり方)、面白がってくださいました。
「いくらでも伸びしろあるやん」
がんばるぞ!

今回、仲間に入れていただいてご一緒したのは、5人の友禅の模様師さんたち。

毛色の違う私をこころよく受け入れてくださいました。

今回、ガチで着物を作る仕事している人たちに囲まれて、みんなオープンに、悩みや疑問に思っていることなど言い合って、いい方に変えていこうという、明るい空気に満ちてました。

新しい時代を感じた。そういえば、令和の発表、工房でした。時代、変わるね!

丹後での二泊三日は、参加したメンバーみんなの大きな宝物となりそうです。

小林さん、ご一緒したみなさん、本当にどうもありがとうございました。

おまけ画像。よろこぶヨシダ。最大級の防寒対策をして臨みました!
雅楽に行ってきました
 昨日、皇居に雅楽を聴きに行ってきました。
昨日、皇居に雅楽を聴きに行ってきました。
お誘いいただいたのだけど、私は雅楽などまったく知識もなし。お正月にラジオから流れてくるとか、神社付属の結婚式場でテープ(?)が流れてるってイメージしかない。いいのかしらん。ま、興味がまさり、ドキドキで行ってきました。
北桔橋門から入場。これ、「きたはねばしもん」と読むのですよ。知らなかったなあ。
上の写真は、となりの平川門のあたり。清々しいよい天気でした。
 場所は、皇居東御苑にある楽部という建物。上の写真ね。古い講堂って感じ。
場所は、皇居東御苑にある楽部という建物。上の写真ね。古い講堂って感じ。
 会場内はこんな感じ。始まる前に、舞台に火鉢が置かれました。楽器を温めて乾燥させるみたい。演奏中もくるくるとあててました。
会場内はこんな感じ。始まる前に、舞台に火鉢が置かれました。楽器を温めて乾燥させるみたい。演奏中もくるくるとあててました。

いかにもな色彩。赤、緑、黒、金。
演奏が始まると写真は撮れませんので、下はいただいたパンフレットの写メです。
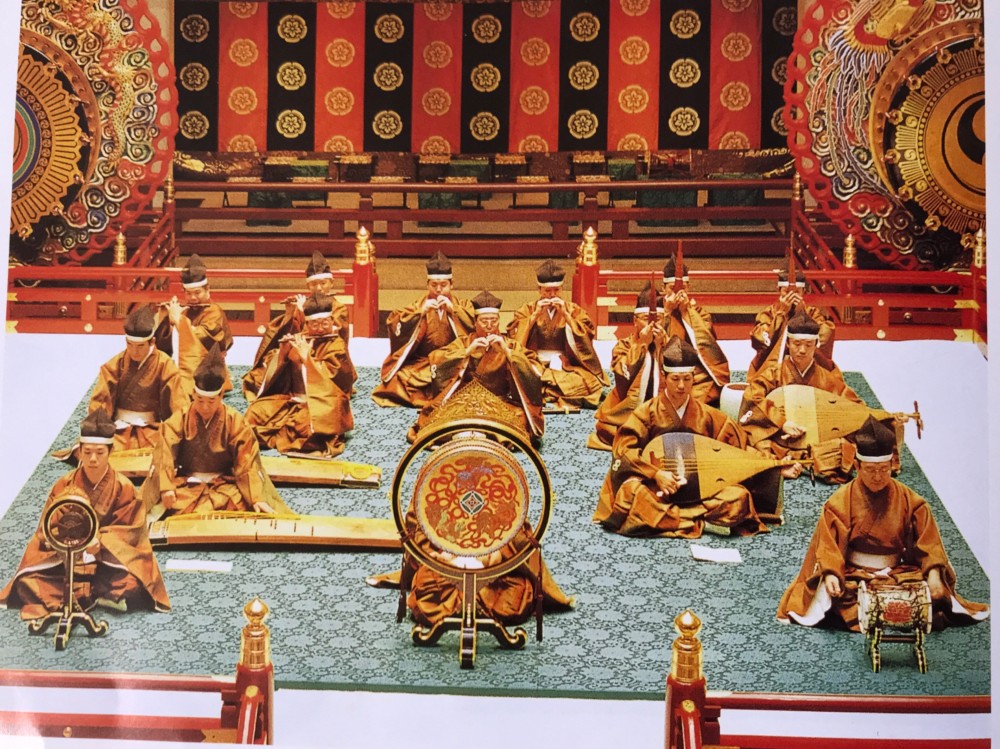 いやはや、まさに完璧って感じしました。磨き上げられたっていうか。それぞれの楽器のハーモニーが溶け合ってました。それが目の前で!ライブっていいですね!
いやはや、まさに完璧って感じしました。磨き上げられたっていうか。それぞれの楽器のハーモニーが溶け合ってました。それが目の前で!ライブっていいですね!
今聴いている音色は、1000年前の人たちが聴いた音色と同じなんだなあ。
まったくもって、いわゆる「和風」ではありません。大陸文化との融合なんだろうな。それを、日本がめんめんと大事に受け継いできた。それもすごいな。
変えることなく、正確につなげていく、、文化ってなんだろうなあ。
昨年の秋、奈良の正倉院展に行ったけど、あれがいまだに続いているのだものね。それも「なま」で。すごいことだ。
上の写真が前半のプログラムの管弦。

こちらが休憩をはさんで後半の舞楽です。若い男性が舞い手です。エグザイルとか興味ないのかなって思った。
 パンフレットの表紙。かわいい。
パンフレットの表紙。かわいい。
 休けい時間に2階に上がってみましたら、装束や楽器の展示がありました。うぉー!本物感ビシバシ。間近に見られてうれしい。
休けい時間に2階に上がってみましたら、装束や楽器の展示がありました。うぉー!本物感ビシバシ。間近に見られてうれしい。
 いつ、どこで、だれが、どんな素材で、この素晴らしい衣装を作ったんだろう?その辺の説明はまったくないけど、ここは博物館じゃないからね。
いつ、どこで、だれが、どんな素材で、この素晴らしい衣装を作ったんだろう?その辺の説明はまったくないけど、ここは博物館じゃないからね。
しかし、染料は植物だろうか?すごくビビッドです。刺繍もいいなあ。
 履き物もかわいい。ズック靴みたい。実際に舞台で演舞してた人たちも履いてました。こういうものの製作も、受け継がれているのね。
履き物もかわいい。ズック靴みたい。実際に舞台で演舞してた人たちも履いてました。こういうものの製作も、受け継がれているのね。
 ご一緒したのは、染織家の大先輩の小熊素子さん。楽しい一日をありがとうございました。
ご一緒したのは、染織家の大先輩の小熊素子さん。楽しい一日をありがとうございました。
 お花が今にも咲きそうでした。
お花が今にも咲きそうでした。
*聞いたところによると、皇居での雅楽の演奏会は、毎年春と秋に開催され、春は招待者、秋は一般公募で入場できるようです。すばらしかったですよ。ご興味の方、調べてみられてはいかがでしょう。
落合陽一さんの、質量への憧憬へ。

落合陽一氏の個展、「質量への憧憬」展を拝見しに、天王洲アイルへ行ってきました。
りんかい線に乗ったのも初めて。天王洲アイルで電車を降りるのも初めて。スマホを頼りに行ってきました。

写真とインスタレーションによる展示って言っていいのかな。世界観が作り上げられてて、私はとても好きでした。
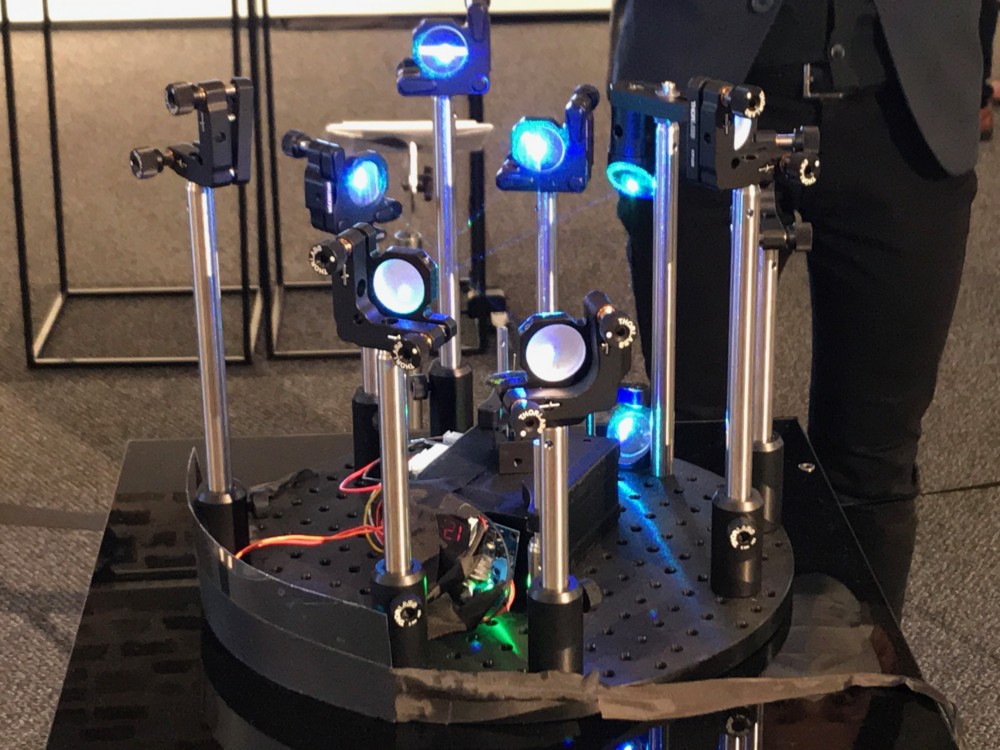
インスタレーションは、よくわからんかったけど。それでもなんか、いいんだよな。

きれいなギャラリーで、コーヒー飲めるようになってて、会場に入るとコーヒーの良い香り。奥に進むと、たくさんのお花が来てて、生花の香り。
展示されている作品は、被写体など生きてるものも、静かで無機的に感じました。

お客さんたくさんですごい〜。老若男女。若い人、多かった。
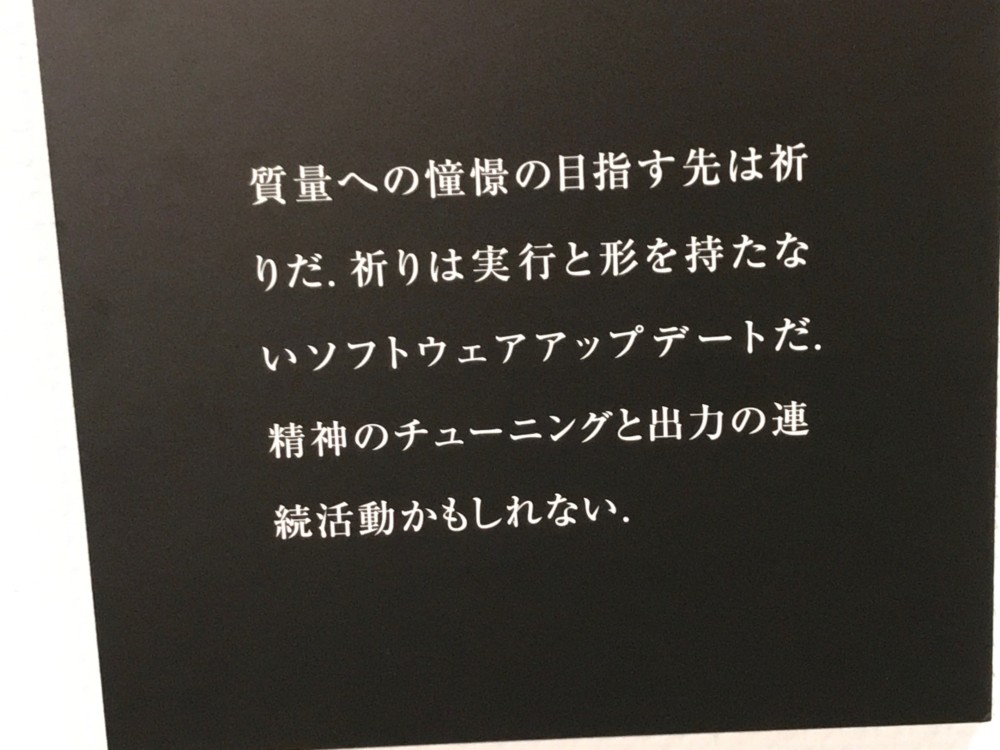
私、ちょうど、明日配信予定のメルマガを書いてて、そこに洲之内徹を登場させた。もろ、昭和。
1月に熊本に帰った時、村上隆のキュレーションの展示を熊本現代美術館で見て、ああこれは平成時代のアートだなあと思った。
(インスタやってる人、この展示について、村上隆本人が、詳しく載せてたよ。一週間くらい前に。コンセプトも写真も。すごく面白かった。さかのぼって探してみて)
んで、落合陽一には、やっぱ、次の時代を感じるな。

んな、ことを思いながら、川っぺりを歩きました。水辺っていうのは、いいもんですな。(上の写真はギャラリー、出たところ)

天王洲には、もう一つ、行きたい場所がありました。ずーっと、行きたかったー。

はい、PIGMENT (ピグモン)です。寺田倉庫がやっている伝統画材のお店です。通販で、箔を買ったことはあるのだけど、来たのは初めて。

血が湧くわ。
-華麗(加齢)についての雑感

今日はこちらに雑感を書こうと思います。
最近、雑感はメルマガの方に書いているので、ブログに書くのは久しぶり。
ブログとメルマガ、どういう風に使い分けようかなと思ってきたのだけど、最近、気合を入れて書くのは、メルマガの方になってきました。どうしてかというと、メルマガっていうのは、配信したら、訂正が効かないから、しっかり考えて、推敲を重ねて書くからです。気合を入れて雑感を書くというのも変だけどね。(あ、仕事の話も書いてますよ!)
で、たまには、本家に戻ってみようと思った次第。(もしよかったら、メルマガに登録、お願いします。配信数が増えると、燃えるので、ぜひ♡ )
では仕切り直して。最近、思うのことのひとつは、老化についてです。私は50歳。更年期まっただ中。
およそ日本女性というものは、30歳を過ぎた頃から、「もう若くない」みたいな圧を感じるものだというけれど、、、しかし、私はその実、つい最近までそんなこと、まったく感じなかった。
というのは、一般に、若い方がいいと言われることは、容姿であったり、体力であったり、記憶力であったりすると思うけど、私の場合は、若いころから、別に容姿もよくなく、ヘタレの体力なしで、生来の健忘症であった。
だから、若いころも、中年となってからも、何も変わらなかったのである。違いといえば、図々しさが増した分だけ、生きやすくなったこと。これはプラスである。はっきりいえば、ただの能天気だ。
そんな私であったが、数年前に目がしょぼしょぼになったので、メガネをかけることになった。私はずっと視力2.0を誇ってきたので、変化であったが、メガネ姿にあこがれを持っていたので、ちょっとウキウキ要素もあった。
それが、この数週間前、夕方になると目が痛いのだ。困ったなあ。市販の目薬も手元にないし、いっそ眼医者さん行こうかなと出かけてきた。
診察結果は、よくあるドライアイ。で、原因は華麗現象とな。目を酷使しますかと聞かれたので、機織りをしてますと答えたら、ああそれなら仕方ありませんねって。
目薬が処方された。一つずつ個包装された、いかにも眼医者さんの目薬って感じの。
デメリットとして苦味がありますよと説明を受けた。目と口はつながってますからねって。
で、一日4回、点眼する日々を送っている。初めの数日は苦味は気にならなかったが、だんだん、上あごの奥の方に感じるようになってきた。起きている間中、いつもうっすら苦いのだ。
慣れない苦味を、不断に感じる。あれ、これがもしかして、老化の味?若いころはなかった苦味。今後もずっとこの苦味をつきあっていくのかな?そう思うと、気の遠くなるような薄い絶望。若いころはよかったなとほぼ初めて思った。なるほど、なるほど。老いるとはこういうことかと実感したのである。
*写真は、うちのベランダ猫。
熊本にて

お正月休みと三連休の合間の飛行機が安い時期をねらって、ちょいと、ふるさとの熊本へ帰ってきました。

朝のフライトでしたので、窓にかじりついて、景色を見ていました。

ここに載せてる写真は、九州に入ってからのもの。急に景色が変わるのですよ。あ、帰ってきたって思う。

有明海。向こうは島原。

江津湖。

はい、到着。

帰った次の日は、盛りだくさんの1日でした。
お昼は着物ライターの安達絵里子さんとお会いしました。この日のことは、安達さんが連載されてる「婦人画報ウェブ版」に書いてくださいましたので、そちらもぜひ。

次の約束まで時間があったので、熊本現代美術館をのぞいたら、「バブルラップ」という展覧会やってました。村上隆のキュレーション。
ほお!これは見なくちゃ。

んで、めちゃくちゃ面白かったです。
バブルの頃から現代までというと、もろ私がアートや作ることやひいては人生とはってことに、ガチにぶち当たっていた時代で。その頃から今まで、ずーっともんもんと悩みながら作り続けてきた私としては、ぐっとくるものがありました。
展示は、前半はいわゆる現代アートだけど、後半は現代陶芸です。それも大半が日常雑器。それがだーっと並ぶ。特別ないくつかを除けば、値段的には、数千円から数万円でしょう。アート作品と比べると、ゼロが数個少ない(場合によっては5つほど?)。この地つづきの、手が届く感じが、「今」なんだなあ。
その点、着物はどうなんだろうなあ〜。課題です。
それと、熊本現代美術館の立地のよさにブラボーと言いたい。街の一番いいところ。それこそ、発信の場だよね。私が住んでた頃はなかったのが残念だけど、熊本はいい方向に進んでるね。自慢の街です。

夜は、ふるいお友達に会いました。二組のカップル。お一人だけ若く、あとは同世代。で、自然にそれぞれ夢を語ってよかったな。
「50歳を超えた人間の情熱こそ信じられる」っていうのは、私が今年の年賀状に書いた言葉だけど、まさに、情熱を語り合ったよい晩でした。
帰ったら、午前3時ってのにはびっくりしたけど〜。
あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。今年がみんなにとって、こころ豊かな楽しいよい年でありますように。
ちょっとごあいさつが遅れましたが、いかがお正月をおすごしですか?
私はといえば、大晦日の夕方までいろいろ終わらず、それからやっぱり掃除しようと、小掃除をしたおかげで、お正月はスキっときれいな状態で迎えられました。一夜明けて、わ〜お正月ぽい〜とウキウキしました。
いろいろなお正月の行事をしなくなる傾向ですよね。それも時代の流れだし、かえって良いのではと思うことも多いのですが、掃除をしてさっぱりと新年を迎えるっていうのは、いいものですね。関東は特に晴天のことも多いし。今年もきれいな青空でしたね。

元旦には映画「ボヘミアン・ラプソディ」を見ました。二日には、15年ぶりくらいのお友達のところに遊びに行きました。思いがけず手作りの「the おせち」をいただいてしまった。お酒もおいしくいただいて、ほろ酔いで帰ってきまして、よく寝て、元気。まずまずのお正月です。

いただいた年賀状を読んでいると、「ブログ、楽しみにしています」って書いてくださっているのがチラホラあってうれしい限り。続けててよかったー。ありがとうございます。
ブログを更新していないときは、ツイッターやインスタグラムの方、のぞいてくださいね。それから、よかったら、メルマガに登録くださいね。メールマガジンって、出したら訂正できないから、毎回、衿を正して、伝わるように一生懸命書いております。
今年もどうかよろしくおつきあいくださいね。
*写真はこの年末の試行錯誤の帯地と、ベランダ猫。
はやしのりこ展に行った

鞄の作家のはやしのりこさんの展示会に行ってきました。
はやしさんとは、長く親しくさせていただいていて、展示会も行ける時は行きます。毎回、ちょう楽しみ!

はやし作品、毎回、新しいチャレンジがあるのです。毎回って、もう何年やってられるのだろう?もしかしたら30年くらいかな?もっとかな?とにかく、コンコンと作り出し続けているのです。年に何回もだから本当にすごい。そして、完成度が高い。作り上げ切ってる感じします。そして何より創造性にあふれています。

上の写真のきんちゃくなど、着物姿にも合いそうですね。相性バッチリだよね。着物きる人いかが〜。

私は、この丸っこいの、ふくらませた風船に水を入れたものを型にするのですって。この発想の自由さ。脱帽です。

カラフル。

このタイプも好き。

上の写真は、会場の「ノーション」さんのブログから拝借。
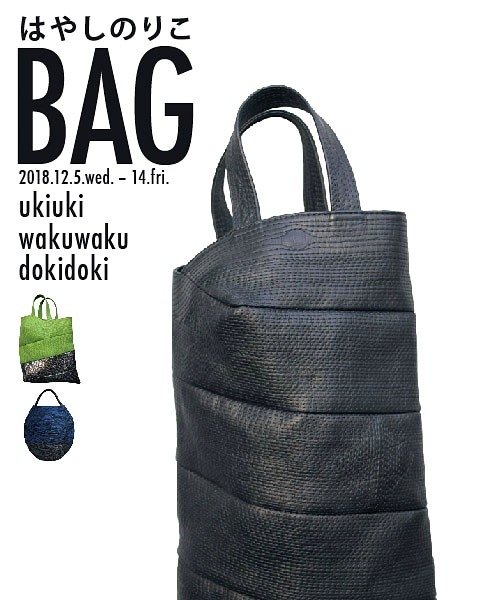
銀座6丁目。14日まで。地図はノーションさんのブログでチェック。おすすめ!

私もいろいろ手に持たせてもらいました♡
赤いショール、ご友人へ

先日のこと、「みるさま」からメールいただいた。赤いショールまだありますか、とのお問い合わせ。

なんでも、今、ふるさとに帰省されているとのこと。それで、ご友人に私のショールを贈りたいと。介護など、いろいろがんばっていらっしゃる50年来の親友の方へ、応援だと。
まあ、なんとすてきな!
(「みるさま」というのは、ONLY ONLY での愛称で、八寸帯「Spirit of Green」とコラボバッグ「My One And Only Bag」を作らせていただいた方です。そのほか、ショールもお求めいただいてます。)

みるさまが、ふるさとで、そのショールをしていたところ、ご友人が目をとめられたと。それで、このショールは、ヨシダが熊本地震後に作ったもので、売り上げの10%を熊本城復興基金に寄付したのだと紹介したら、その話にご友人、いたく共感してくださったと。
これまでシックな色ばかり着ていたご友人が、急にきれいな色を好み出したのは、色のパワーが必要だからだと考えられたみるさまは、ご友人を守るのは、ヨシダの赤いショールだと思ってくださったわけです。ブランド物や市販のカシミアのショールを贈るのは簡単だけど、ヨシダのがいいと。
じーん。ありがたい〜〜。

私としても、とてもうれしく、このご縁に意味があるように思いましたので、この分の売り上げの10%を災害支援金としてプールしておきたいと申し出ましたところ、大賛成してくださいました。
(通常は、コラボ鞄のみ、売り上げの10%を寄付金として積み立ててます。)
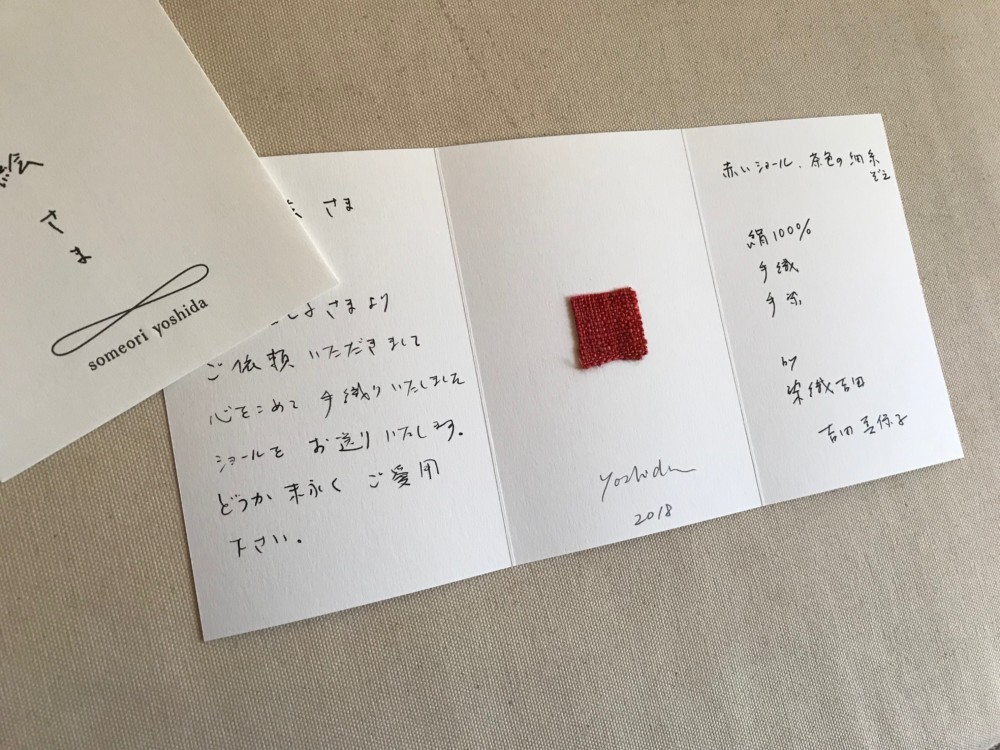
ショールは、うちからご友人さまへ直送することになったので、さっそく準備です。
もう一度ていねいにアイロンをあて、たたみ、薄紙に包んで、ビニールに入れます。
カードもご友人さまにあてに作りました。同じ布がありましたので、それを貼ってね。

ほら、発送しますよ。みるさまのお気持ちが届いて、喜んでいただけますように願いをこめて。
*大切な方へのプレゼントに、染織吉田のショールなどいかがでしょう?ていねいにお包みし、カードを添えて発送します。お気軽にお問い合わせください。
本出ますみさんをラジオで。
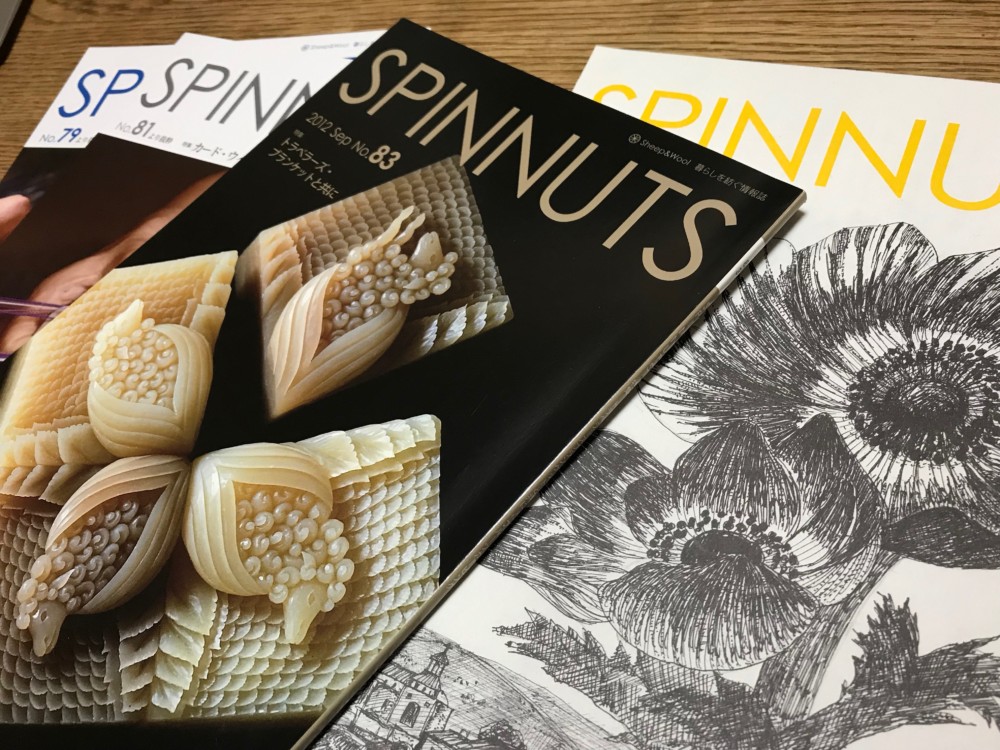 織りのそもそも論をします。
織りのそもそも論をします。
織りをやってみたいなって興味を持った人はみんな、まずはじめに、素材は何にするって問題にぶつかります。これ、知らず知らずの分岐点です。
素材ってのは大きく分けると四つ。絹、木綿、麻、ウール。で、みな、まずは大抵、全部に手を出します。
はい、私もやりました。25年以上も前のことだけどね。今は絹いっぺんとうだけど、ウールにも可能性を探って触りました。
そんな私達にとっての大きな人、本出ますみさん。織りをやってる人はみんな知ってるこのお方。通称、ポンタさん。出しておられる情報誌「スピナッツ」も食い入るように愛読しました。
私、20代半ばの織りを始めたごく初期のころ、大阪に住んでたんですけど、その頃、なんどか京都のポンタさんをお訪ねしました。まだまだ行き先の定まらないペーペーの私に、丁寧に応じてくださったの、よく覚えています。お店と事務所とたぶん住居を兼ねた、古い木造の建物、可愛らしく、誠実な空間でした。
その後私は、絹の道に、きゅーっと引き込まれていきましたので、ウールの道からは離れてしまったのですが、本出さんは、大きな大きなキーパーソンとして、深くきざまれました。
先週の金曜日の晩、なつかしい本出さんのお名前が、ふとラジオから流れてきました。私の愛聴しているNHKの「ラジオ深夜便」。その4時台の「明日への言葉」のコーナーで登場とのこと。
しかし朝4時のリアルタイムでは聴けませんでしたので、タイムフリーになるのを待ってました。今日、やっと聴くことができました。
とても、とてもよかったです。本出さん、すごいなあ。ウールの花がパーッと開いた感じ。牧場のシロツメグサに混じって咲いているようなかれんなお花。とてもきれい。小さいけど、存在価値抜群。試行錯誤していた、私の最後の青春の頃を思って聴き入りました。
よかったら、ぜひお聴きください。ものづくりっていいなーって思うよ。原点なのよ。全部、繋がってる。
ここから聞けます。下までスクロールして、4時台のところの「聴き逃し」をクリックしてください。おすすめです。11月26日まで聞けるようです。
*写真は手元にある「スピナッツ」の一部です。
奈良へ行ってきた

何年ぶりでしょう、奈良に行ってきました。
行った理由はいろいろで、それはメルマガの方に書いてますが、もう一つ、正倉院展を観たいというのもきっかけでした。
正倉院展、実は初めてでした。今年は、麻布系はじめ布ものもたくさん出ていると聞いたし、えいやっと行ってきました。
ものすごく混むと聞いていたのいろいろ調べ、平日の閉館2時間半前をねらって。
それで、1300年前の天平文化にひたってきました。なにげに三纈(サンケチ)出てて、おおっさすが正倉院て思いました。(夾纈(キョウケチ)・纐纈(コウケチ)・臈纈(ロウケチ))
赤い色のスカートのような衣、美しい。真っ赤なのだ。どんだけ染料使ったんだ。茜と思うのだけど。色、よく残ってるなあ。これを身につけた殿上人がいたんだし、作った人がいたんだなあ。1300年前だよ。本当にすごい。
あと、税金として徴収された麻布も展示されてた。租庸調の調ですな。で、これが、ものすごく、立派ないい布だった。大麻か苧麻かわからなかったけど(大麻ぽく見えたが、、)糸の太さもそろって、織りも整って、大したものだ。出品一覧見ると、長さが1253cm、幅が70cmとある。これ、織るの大変よ。麻を育て、糸にして、織って、、、、各地それぞれに専門家がいたのかしら?それ相応じゃないとできないと思う。

正倉院展は素晴らしかったが、いくつか行った寺院にも感激した。
興福寺の北円堂、秋の限定公開中で初めて拝見した。入ったとたんに、どかーんとやられた。
ああ、あなた様はここにいらしたんですか、、、って感じで、超有名な菩薩様(無著・世親)の立像がいらっしゃった。それだけで空気が違う。
運慶さんと運慶門下の作品。運慶、真の大天才だ。ひれ伏します。
北円堂の八角形の建物もよかった。このお堂にこの仏様。それを拝めるありがたさ。

それから、新薬師寺もとてもよかった。ありがたすぎ。
十二神将、すごくよかった。静かなお堂もすばらしかった。それに元々こちらにいらした香薬師様の右手が展示されてた。なんと、優しく清らかな手なのだろう!
この仏様、これまで3回盗まれて、2回は戻ってきたが、3回目は戻らず。で、この度、右手だけが出てきたそうだ。
なんとまあ。もっと警備がいるんじゃないの?今回も、切符を売ってる女の人が一人、境内を掃除していたおじさまが一人、本堂の中に一人の計3人しかお見かけしなかった。国宝、ゴロゴロあるのに。いいのかなあ。奈良の人は今も天平人でおおらかなのかなあ。心配。

久しぶりの奈良でしたが、変わってないなあという感じでうれしかったです。観光地化してないのが好きだけど(有数の観光地のはずだが)、日本全国インバウンドに心血注いでいる中、めずらしいんちゃう?秋の行楽シーズン真っ只中だったから覚悟してたけど、博物館以外は空いてるくらい。ま、うまく切り抜けられるよう計画したけどね。
写真は上から、新薬師寺の本堂。新薬師寺の屋根。志賀直哉旧居、写っているのは叔母、私もガラスに映ってる。帰りの新幹線の窓から。
メルマガには、パーソナルなことも書いてます。よかったら登録してね。→☆
本郷孝文先生の工房へ

信州松本、あこがれの本郷孝文先生のお仕事場へ、おじゃましてまいりましたー!
なんとまあ、ありがたいことなんでしょう。訪問のお願いに、「どうぞお出かけください」とのお言葉。こんな光栄、あってもいいものかしらと思いながら、よろこびいさんで、駆けつけてまいりました。

本郷先生のお作品は、ずっと以前から拝見してましたが、ご本人にお会いするのは初めてのこと。ドキドキでしたが、自然で丁寧で、お優しい方でした。
お仕事ぶりと同じです。
工夫と経験が詰まったすばらしい仕事場もつぶさに見せくださいましたし、膨大な量の織り作品の端きれも見せてくださいました。天然染色、手織りの仕事にとって、最高で自然でまっすぐな環境を整えられ、長い年月、日々仕事の積み重ねをやってらっしゃるように思いました。
私が持っていった帯や着物も丁寧に観てくださり、糸の使い方のことなどで、大きな気づきを与えてくださいました。自分でやってるだけでは見えなかったものが、こうやって、いくつも越えて先の先の先を行っている方に助言いただけると、一気にパッと目が見開くように思います。
ま、だからと言って、それができるかどうかは、また別の話。やるしかありませんが。
「こうやったほうが楽しいね」って、ものすごい面倒な作業を軽く言われるのが印象的。大変さは関係ないのだよね。いいものできたら、楽しいです。はい。先生、おっしゃる通り。ひゃー。やるしかありません。楽しくやって、将来を切りひらくのですね。はい。やります。

お弟子さんのサランさん。本郷織物の素晴らしさを受け継いで行かれることでしょう。

松本、本当にいいところでした。上の写真は松本城の天守閣から。

お蕎麦屋さんの窓。

コーヒーは、「まるも」で。
*ひとつ、ちょー自慢!宝物をいただいてしまったのです!
こちらのブログに載っている「手織物の織物組織図ノート」!本物!!
私は以前からこちらのページの愛読者でした。初めはどなたのブログか知らず、「これは只者じゃないな」と。で、読み込むうちに、あ、本郷先生だと気づきました。ずーっと遡って全て読みました。どのページも本当にすばしいです。ため息つきながら何度も再読しています。
*本郷先生の「手織物の織物組織図ノート」は、我が家にお越しになる織物関係者の方々にお見せします(だって自慢だもん!)が、貸してはあげません。コピーもダメです(製本が傷むから)。書き写してってくださーい。
芋、寿、パッションフルーツ、サンペレグリノ

うふふー。今日は特別な晩なのです。この1ヶ月ほど、ずーっとこの日を待ちわびていました。
実は!
一ヶ月ほど前に、お友達が、焼酎を2本、送ってくれたのです。「芋」っていうのと「寿」っていうの。どちらも知らなかった銘柄です。とても丁寧に作られてて、扱っている酒屋さんも少なく、入手が難しいとのこと。ふぁー!
おすすめの飲み方は、パッションフルーツと合わせて、サンペレグリノ(炭酸水)で割る。ひょー。
それで私は、まずは地元スーパーを片っ端からまわりパッションフルーツを探し、撃沈しまくり、それではと、町田(我が家から一番近いでかい街)の小田急百貨店のデパ地下まで出かけ、高級果物売り場に行ったのですが、なかったのです。季節柄取り寄せもできないと。その後、お江戸ど真ん中、日本橋にも行ったのだけど、なかった。
がーん。
がっくし。これじゃ、日本中どこにもないよ。半年、待つ?
くだんのお友達に伝えると、じゃあ、送ってやると。
え!
高級果物屋さんでも取り寄せられなかったものが、入手できるの!

それでわくわくと待っていたら、本日、送られてきたのです。たった一個の、屋久島産のパッションフルーツ。かわいい。よく来た。ようこそ我が家へ。
その上、サンペレグリノも送ってくれた。これも、近場のスーパーになかったのだ。町田まで行けば、さすがにあると思うけど。

で、満を持して、いも焼酎「芋」のパッションフルーツ、サンペレグリノ割をいただけるわけ。
パッションフルーツを二つに割ると、ちょうどよく熟れてる。食べごろじゃん!中身をグラスに出して、焼酎注いで、氷を入れて、サンペレグリノを注いで、かき混ぜる。
うん。おいしい。ほろ苦くて、かすかに甘い。パッションフルーツの独特のさわやかないい香りと、いも焼酎「芋」の、なんというか、檜風呂に入った時のような高揚感のあるいい香り(檜の香りというわけではないんだけど、高揚感が似てる)がミックスして、別次元に連れて行ってくれる。
炭酸水も、今まで、ウィルキンソンで十分とか思っていたけど、サンペレグリノ、すごいなあ。なにが違うのかわかってないけど、上手に取り持ってくれる感じで、すごくおいしいです。
それで、おいしすぎてまわるのが早い。きゅーっと効きます。早くも軽く酔っ払い。
この充足感、満ち足りた感じ。安心して委ねられる感じ。そこんところ、行ってみたい。
伝統工芸展へ行った

日本伝統工芸展を拝見しに、日本橋三越へ。
私、実は公募展ってちょっと苦手意識があるのですが、日本最高峰だし見ておこうって出かけたら(そのわりには結構見ていますが)、大変に面白かったです!「ザ・技」って感じしました。それぞれの出品者がそれぞれの技を出し切っている感じが、清々しかったです。
私は、染織しかしっかりは見ていないのだけど、ほかの分野もしっかり見たら、疲れ切りますね、あれは。染織だけでも力作ばかりで、胸いっぱいになりました。
今日は、土屋順紀先生による作品解説もあったためもあるでしょうが、雨でしたが、大賑わいでした。
土屋先生、展示作品についての解説をされていくのだけど、時々、ご自身が織っている時のことなど、挟まれるのが、ああいいなって思った。時折おとずれる感動とか喜びについてなど。すてきな先生です。
あと、北村武資先生の経錦(たてにしき)の作品、ものすごくよかった。完璧でこの世のものとも思われないくらい。この一点だけ染織コーナーでなく特別な場所に飾ってあるので、見に行かれる方、お見逃しなく!
日本伝統工芸展は、10月1日まで、日本橋三越本店にて。その後、全国を巡回するようです。
単衣で遊ぶ会

今日は、着物でお出かけ。「単衣で遊ぶ会」と銘打たれたパーティーです。
うわー、予報どおりのお天気だー。雨ゴートの出番ですよ。目指すは南青山です。

着物のパーティーに、なぜか来賓の方々はインドから。うふふ。サリーもめちゃくちゃ似合ってらっしゃったわ。

閉じこもりがちの日々ですが、こうやって外に出るといいですね。人と出会えてありがたい1日でした。

主催は、きものおたすけくらぶさんと、ワンズベストさん。楽しい時間をありがとうございました。

おたすけくらぶの富田社長です。役者でいらっしゃいます。
福畑ワークショップ

今日は、午前中からお出かけしました。
素敵なお友達の福永麻子さんが、何やら面白そうなことを始めてて、そのワークショップだというのです。麻子さんは、近頃、地元世田谷区で区民農園にハマってて、それがにょきにょき発展してるみたい、、、、というのは、彼女のSNSで知ってたのだけど、、、、
二子玉川の蔦屋家電で開催とのこと(広報はこちら→☆)(福永さんのSNS、私のフリンジ日記はこちら→☆)。ふむふむ。読んだだけではよくわからんけど、麻子さんの周りには、いつも素敵な人が集まるのだよな、出かけてみよう。
で、すごーく面白かったです。
ようは、農業初心者の麻子さんが、近くのレストランのシェフが地元の有機野菜を使って料理しているのを知り、それがめちゃくちゃ美味しくて、シェフの方が野菜を調達している農家さんとも懇意になり、農業の深さと面白さに目覚め、その素晴らしさをみんなにシェアしましょうという企画でした。
シェフの方も農家さんも、お話は得意でないということでしたが、話し出したら、深くて豊かで、面白かったのだわー。
世田谷区という大都会においての、区民農園、地元野菜のレストラン、地元の農家さん、それは珍しいけど、正直、別のところにもあると思います。それに、一つ一つにあまり光が当たってないように思います。
それが、今回こんなに面白かったのは、麻子さんのコーディネート力と引き出す力、大きいなあと。地元でコツコツ、自分がすべき仕事を、もっとよくしようと淡々と日々精進されている方々のカッコよさ、なかなか注目されませんものね。
ガスパチョを試食させていただいたのですが、あまりに美味しくて目が覚めた!
これぞプロの仕事と思いました。素材の良さを最大限に引き出して、最適の技術で手を加え、しかし余計なことはせず、、仕上げの完璧さ、、、。これらは、料理に限らずモノづくりを仕事にしている者でしたら、日々向き合っていることですが、、、はい、難しいです。それが完璧。さすがだなあ〜。
うーむ、ここのお店行きたいな。シェフの方、仕事をノリに乗って楽しんでるって感じでした。ここです→☆(二子玉バルIBERO)
私は今、お土産に持たせてくれた「夏をとじこめたトマトケチャップ」を、オムレツを作って、よく冷やしたお手軽白ワインに合わせて、うーむとうなっていただいてます。形のくずれたオムレツが引き立つわーー。ワインも上等にしてくれる。この何げなく完璧ってのが、いいよね。目指すところよね。

上の写真、いただきましたよ。右が福畑の福永麻子さん。左がIBEROのシェフ 坪井 健一郎さん。楽しむ私。
断捨離、続行中

先日配信したメルマガには書いたのですが、今、私、断捨離にはまっています。
一応の区切りがついたのでメルマガに書いたはずだったのですが、実はしつこく続けてて、今もやってます。染織の道具も、プライベートのいろいろも、よく見極めて、捨てるべきは捨ててます。
で、思ったこと。
断捨離すると、語りたくなる!笑
なのですよ〜。
いかに不要なものに囲まれていたか、それをどう取捨選択したか、などなど。。。
が、大抵の方は聞きたくないでしょうから、書きませんね。
聞いてやってもいいって方は、うちに遊びにきませんか?以前にお越し下さった方がいいです。で、前と比べて、ここがこうなったと熱弁をふるいたいです。あはー、うざいですね。
昨日今日と、キッチン周りを徹底的に掃除してますが、びっくりするのは、唐辛子のタネが至る所で、発見されるってことです。調味料置き場はもちろん、冷蔵庫のたまご置き場の下とか、扉のパッキンに挟まってたりとか。
野菜室の隅に、ピーマンのタネが干からびてるのもお約束。あと、魚のウロコ。ウロコがある魚を料理したのなんて、いつでしょう?それがひょいと発見される。。。
ちょいと遺跡発掘者の気持ちを味わっております。
「カメラを止めるな!」

映画見てきました。「カメラを止めるな!」。で、先ほど暑い中帰ってきて、ひとっ風呂浴びて、心地よい疲労感です。
見に行った理由は、ツイッターやノートでフォローしている方々が、口々に大絶賛&心からのおすすめしていていたから。これは見たいなと。よし!映画の日ねらいだ!
で、みなさん、「ネタバレ注意」「できるだけ事前情報を仕入れるな」と書いてて、そっか、ではそうしましょうと、無垢の状態で行きました。
で、泣いたり笑ったり、忙しかった。声を出して笑った。「ポン!」
なんか、すごくリアルに感じてしまって、登場する映画監督が、本当にこの映画の監督みたいな錯覚。登場していた監督さんは役者さんなんだよね〜。不思議だわー。
私も大絶賛&心からのおすすめです。特に物作りしている中年以降(笑)の方!事前情報はないほうがいいけど、ただ一つだけ言うと、前半は全て伏線ですよ。よーく観ておきましょう!楽しんできてください!!
*川崎のチネチッタで見てきました。映画の日とはいえ、満席。多分全ての回がソールドアウトと思う。すごい〜。写真は、映画終わって川崎駅に向かう途中。川崎、初めて行ったけど、庶民的ないい街でした〜。
7月26日、今日のよきこと

今日は、本当によい日でした。
まず、昨晩の久しぶりの夕立のおかげで、大地が落ち着き、よく眠れ、よい目覚めだったこと。
朝の涼しさのまま、今日は一日中、快適だった。神の恩恵のようだった。最高気温が30度って、なんて涼しいんでしょう!(西日本は今日も暑かったとのこと。本当にお見舞い申し上げます。特に、被災地は大変でしょう。お身体、くれぐれも。)
お昼はお客さまとのミーティングだったのだけど、それが、とっても建設的で、深い話もでき、これから織るお着物のご希望も飲み込め、全体像が見えてきて、本当にありがたかったこと。(このお話は、後日ONLY ONLY ストーリーとして書きますね。)
日本橋三越の特別食堂で、超絶おいしいうなぎをご馳走になってしまった!京都の銘菓もお土産に!なんか、怖いくらいの贅沢。
午後は、せっかく東京の東の方へ来たので、足を伸ばし、上野へ。東京国立博物館でやってる「縄文展」、観たかったんだ。
縄文、いい!なんかね、すごく自由。土偶も、土器も。為政者に命令されて作ったのじゃなくのびのびしてる。喜びに満ちてる造形なのだよ。神とか村おさとか、そういうものに捧げるためでもあっただろうけど、自由なのだよなあ。夢中になって作ってて、やり切ってて、カッコいいです。
あとやっぱ、「縄文ポシェット」を観たかったのだけど、これも存在感ありましたよー(このページの上から3番目の写真)。
この頃はまだ、織りはないのだ。編みはあったのねえ。木の繊維を編んでいるのだけど、その構造は綾織そのものでした。タテもヨコも、二本浮いて、織り込んで、また二本浮くの繰り返し。なんで、平織りの構造じゃなかったのかなあ。平織りの方が、単純だし、丈夫なんだけどなあ。綾織のいい点は、柔らかいことなんだけど、縄文人、くるみ採集の鞄に、柔軟性を求めたのかな?
*「縄文 – 一万年の美の鼓動」展は、9月2日まで、東京国立博物館にて。
*写真は、東博、本館の入ってすぐの階段あがったとこ。
地震、清正公
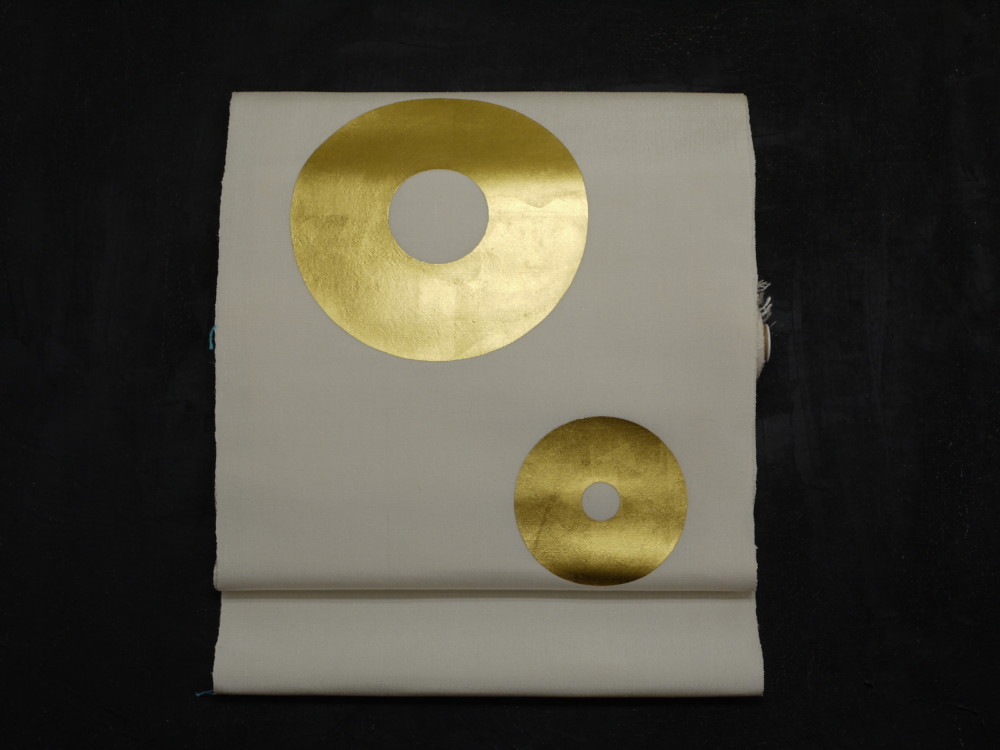
大阪で大きな地震がおきて、なんだか落ち着かない。亡くなられた方のご冥福を祈るばかり。
震源地の近くは特に、まだまだ大変と思います。これから本震がきたりどうかしませんように。大雨が降ったりして、これ以上の被害が広がりませんように。
今回の地震、「慶長伏見の地震」と断層帯が同じって聞いてふっと思い出した。
熊本地震の後、「清正公の陣羽織」という個展をさせていただくことになり、加藤清正公について、ずいぶん調べたのだけど、そういえば「慶長伏見の地震」というワードが出て来たよ。
この時、伏見城にいて震災にあった豊臣秀吉の元に、いの一番に駆けつけ活躍したのが、清正だったのだそう。さすが、清正公。せいしょこさんは、築城や治水に抜群の腕を持ってる方なのだ。
熊本地震後の個展「清正公の陣羽織」展でやりたかったことは、我々みんながそれぞれ「Petit せいしょこ」さんになって、力を出し合い復旧して行きましょうってことでした。
今回も、大阪に向けて、清正公が駆けつけてくれてることと思います。全国から、ぞくぞくと、道やガスやエレベーターを直しに。近いうちには、心が明るくなることを携えて。
*写真は拙作「九寸帯 清正ゴールド」。蛇の目紋は、加藤家のご紋です。
M’s HEART のまり子さんです

こちら、まり子さんです。鹿児島の着物好きな方々に大変頼りにされていて、着付け教室も主宰されてます。
締めて下さっている帯、私が織ったものなんですよ。お似合い。うれしいなあ。
先日、写真を送って下さったので、こちらでもお披露目させていただきますね。

うわー、さすが鹿児島!目の前は錦江湾ですね。雄大な桜島。地元鹿児島をこよなく愛するまり子さんです。

くるっとこちらを向いていただくとこんな感じ。エネルギーが湧いてくる帯です。

まり子さん、写真に添えて、こんなメッセージくださいました。
「今日は、午前中着付け教室でした。あなたの帯を締めて、生徒さんへもあなたの話をしたり、ブログをオススメしたりしてました。
この帯、いろんな場面でいろんなお着物に合わせています。紬や風通織の無地などにも。粋な着物もこの帯なら優しく温かな雰囲気に。軽めのお茶会なら気軽な感じではんなりと。本当に作り手の気持ちが、いい感じで表現されてて癒されます。」
ありがとうございます!

今回、まり子さんが、きよさま とのご縁を繋いでくださいました。とてもありがたいことです。まり子さんがいなかったら出会えなかった方と出会えました。
ONLY ONLYの制作 も、きよさま が信頼を寄せているまり子さんが間を取り持って下さったので、スムーズでした。めでたし、めでたし。
今回のように、ONLY ONLY 興味ある方で、懇意の着物屋さんやギャラリーさんがいらっしゃる場合は、その方を通して下さって、もちろんウェルカムです。私としても輪が広がって、うれしいです。
また着物屋さんの立場の方が、うちのお客様でヨシダのが合いそうな方がいらっしゃるわって場合も、ぜひぜひ繋いでくださいませ。
どうかなんでもお気軽にお問い合わせくださいね。
お出かけ

昨日は夕方からお出かけ。半蔵門線にひたすら乗って、三越前へ。目指すは、日本伝統工芸染織展。さすがレベル高くてピシッとしていて面白かったです。
岩井香楠子さんの染めの下図の展示もあって、ほおーと見入りました。作家の頭の中、見た感じ。微に入り細にわたり計画されてるなあ。ドキドキした。
あと、展示の中で一番心に残ったのは染めの人間国宝の森口邦彦さん。さすが、大胆で美しくて、よかったなあ。美と技術がピタッとあってる感じしました。(日本伝統工芸染織展は5月14日までの開催です)

で、三越新館から駆け下りながら、時計をチラ見。まずい、6時20分だ。半蔵門線に戻って、大手町で乗り換えて、乃木坂へ。はい、目指すは国立新美術館。国展に駆け込みます。金曜は夜間オープンの日です。
国展の会場は天井が高くてせいせいするね。染織しか見てないのだけど、染織も着物や帯に限らないのが自由でいいな。毎年出してる作家さんたちを見るのも楽しみです。ああ、この人、がんばってるなあ、よし私もって、勝手に元気をもらってます。初入選にも親しい人が!おめでとう!(国展も5月14日までの開催です。)

その後、同じく国立新美術館でやってる「こいのぼりなう!」を拝見。めちゃくちゃ面白かったです。須藤玲子さんのデザインされた数々の布がこいのぼりになって、大きな空間をダイナミックに泳いでいる。見るひとは床に置かれたソファーに体を沈めて、仰ぎ見る。これが気持ちよかった。
とても情熱的な布だった。その情熱が泳ぎまわるのだから圧巻でした。こちらのテキスタイルは、機械織りで作っているけど、手仕事って言っていいと思う。個人作家の手仕事ではなくて、もうちょっとだけマスプロダクツなのだけど。
こういうの見ると、個人作家がやらなきゃいけないもの、見えてくる。情熱で負けてない?
(こいのぼりなう!は、5月28日まで。写真は全てこの会場で撮りました。)
染織吉田、15周年です!
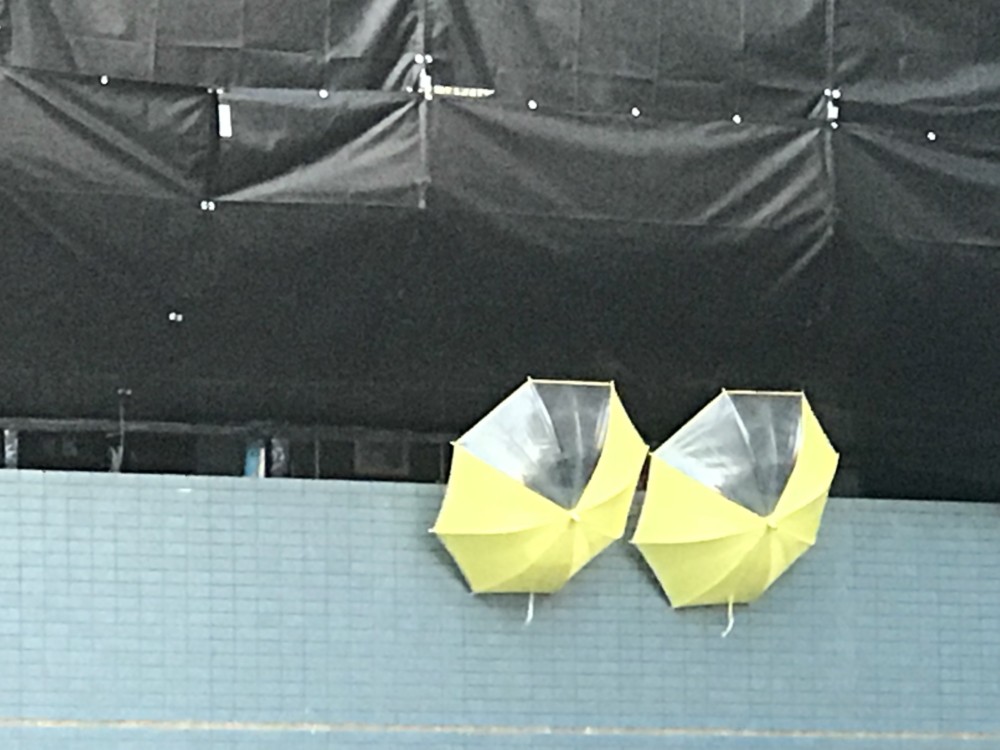
どうもありがとうございます。本日、5月1日は、染織吉田の独立記念日です。
なんと、今日で15年です。15年間、たくさんの方に助けていただきながら、織りを仕事として来れましたこと、本当にありがたいことだ思っています。いまだに、自分がこれで生きていることに、びっくりしてしまいます。もうダメだ、もう無理だとひやひやしながらも、人に恵まれたという、ただ一つのことだけで、なぜだか生きて来れました。景気や世相もなんのその。本当に「人」のおかげです。心から、御礼申し上げます。
独立15年ということは、織りを始めてからは、25年です。あっという間の四半世紀でした。織りの技術や知識は、少しは上達したかもしれません。しかし、一番大事なものは、そこ以外にあると思っています。これからも、そこのところを、しっかり見極めて、深く、美しく、豊かで、愛しいものを求めて、コツコツ織り続けます。どうか今後とも、よろしくお願いいたします。

今日の染織吉田は、普通の営業日でしたが、絵羽のONLY ONLY のご相談にお越しくださったお方と、いろいろお話ができた、とても良い日でした。
お着物が大好きな方でした。その上、ご実家筋が呉服屋さんで、お母様のお着物もたくさん受け継ぎ、人間国宝級の有名作家さんのものなどたくさんお持ちで、着付けの先生もされているという大の着物通のお方でした。
そんな着物のことを知り尽くしていらっしゃる方に、ONLY ONLY でご注文いただけ、ちょっとだけ、自分が誇らしかったです。(おっと、うぬぼれてはいけませんね)
お話を伺っていて、とても心に残ること、おっしゃってくださいました。
「ずっと着物を着てきて、この頃思うのは、平凡なものも案外いいなってことなのよ。」
うわあ、なんといいお言葉なのでしょう!ここに、着物の真髄があると思います。どうしても目立つものや、「私!私!」ってもの、作りがちですものね。平凡で、着やすく、コーディネートを楽しめる、ありそうで無いもの、一生懸命に作ろうと思いました。
*写真は我が仕事場のベランダから。雨上がりの朝。最近。
幡野広志展へ行った

幡野広志さんの写真展を拝見しに出かけました。これは行かなきゃって思ってて。行けてよかった。
幡野さんのことは、どなたかがリツイートしたツイッターで知り、すぐフォローして、ブログやノートもほとんどすべて読んで、最近では、ツイッターの「質問箱」に幡野さんが端的に答えるツイートをガン見してました。
思うことはいろいろありました。生と死。病い。余命。ビーガン。宗教。障害を持っている人とそのきょうだいについてなど。
どれもこれも、すぐそばにありながら、普段、蓋をしていたことばかり。蓋をしていたのがあふれてきたので、リアルをみようと写真展に出かけました。

その人が撮った写真は、深くて、ストレートで、誠実で、美しかったです。
お年でいうと、私より一回り以上も若い方だから、「青年」のように思ってしまうのだけど、その青年の濃い生き様を見たなと思いました。
今回の写真展は、狩猟の現場で撮ったもので、銃や弾丸なども展示されてました。着るものや手袋など、写メしてきました。脱皮したあとのようでした。
伊勢丹でのよきこと

伊勢丹での1週間は、悲喜こもごも、いろんなことがありました。素敵なこともいっぱい。ふたつ、ご紹介しますね。
初日のこと。お昼頃だったと思います。まだ始まったばかりで、緊張気味。お客様とお話ししていたら、ふと感じる視線。「?」と振り返ると、なんと、高校の同級生の「あこちゃん!」。一挙に緊張がほどける不思議。幸せ度が上がって元気が出てくる不思議。お仕事場が近いこともあり、会期中、5回くらい会いました(笑)。おかげで楽しい日々でした。
あこちゃんのブログにご紹介いただきました♪→☆
そして、このページの写真は、あこちゃんからいただいたお花です。黄色なのは、我らがスクールカラーだから。一輪のピンクが可愛いね。
「じつはさー、昨日で半世紀だったんだー。でもボロボロに疲れて帰って料理したくなくて、焼そばとビールだったんだー」なんて、同級生だからこぼせる軽口をつい口にしたら、数時間後に届けてくれた。本当に驚いた。優しいなあ。
その晩は、お花を飾って、いただいた獺祭純米大吟醸のスパークリングを開けて、同じくいただいた阿蘇高菜の新漬けきざんて、一日遅れの、じんわりうれしい宴でした。人生、なかなか悪くないぜよ、って思ったよ。

そして、もう一つの素敵なこと。これは、最終日の遅い時間。そろそろ終わりかって頃。お若い方が、ずっと私の作品を見ている。目が合う。ん?
– ヨシダさんですよね。私、ずっと前におじゃまして、話しを聞いていただいた〇〇です。
– あ!ああー、覚えてますよ!
– 藍染の工房に就職したので、ご報告に来ました。ずっと、ヨシダさんにお礼を言いたくて。
うわあ、感激。こんなの初めてだ。ぐっと大人っぽくなった表情。仕事を楽しんでいらっしゃる様子。がっぷり取り組んで、いろんなこと、受け止めてらっしゃる感じ。
その上、この時売っていた、レターカードを買ってくださった。2千円なり。これも本当に感激した。売ってるものの中では一番お安いものだけど、私の売っているものは、生活必需品では全くなく、なくても困らないものばかり。それなのに。就職したって言っても、まだ2年目くらい?一人暮らしを始めたそうだし、そんなに余裕ないよね。それなのになあ。
モノを作って売ってる人間にとっては、「買っていただく」ってものすごく大きいことなのです。何よりも、絶対的に大きいです。金額の大きさじゃなくて、「買っていただく」そのもの。生きることに直結なのだし。
若い方に相談されること、たまにあります。私は、決してこの道にくることをおすすめしません。あまりにも大変だから。もう来ちゃってる人には、どう生き残るかってこと話すけど。マイナス向きだからこそ、真摯に話しているつもり。
でも、大抵の場合、それきりとか、メールだと返信もくれないとか。がっかりすること多いけど、こうやって成長なさった姿を見ることできて、すごくうれしかったです。
お互い、美しいもの、豊かなもの、作り出し続けましょうね。
伊勢丹展、ありがとうございました。

新宿伊勢丹展、無事、終了いたしました。
いらしてくださったみなさま、ネットで応援してくださったみなさま、伊勢丹の呉服売り場の頼りになるスタッフのみなさま、一緒に出品した、久保紀波さん、峯史仁さんご夫妻、松永恵梨子さん、大城令子さん、富沢麻子さん、本当にどうもありがとうございました。
おかげでさまで、なかなか面白い1週間でした。1週間、新宿に通って、伊勢丹にいて、たくさん、気づきやモチベーションをいただきました。どんなものを作って、どう手離して行くか、、、、。普段、仕事場に閉じこもっていたら得られないインスピレーションもいただきました。本当に感謝しています。ありがとうございました。

昨日、きものなど片付けて、先ほど、伊勢丹から宅急便が届き片付けて、やれやれしております。展示会は、始める前と、終わってからも、一踏ん張りが必要なのよね。
さ、片付きましたよ。次に行きましょう!
織り作家のためのスキルアップ講座に参加
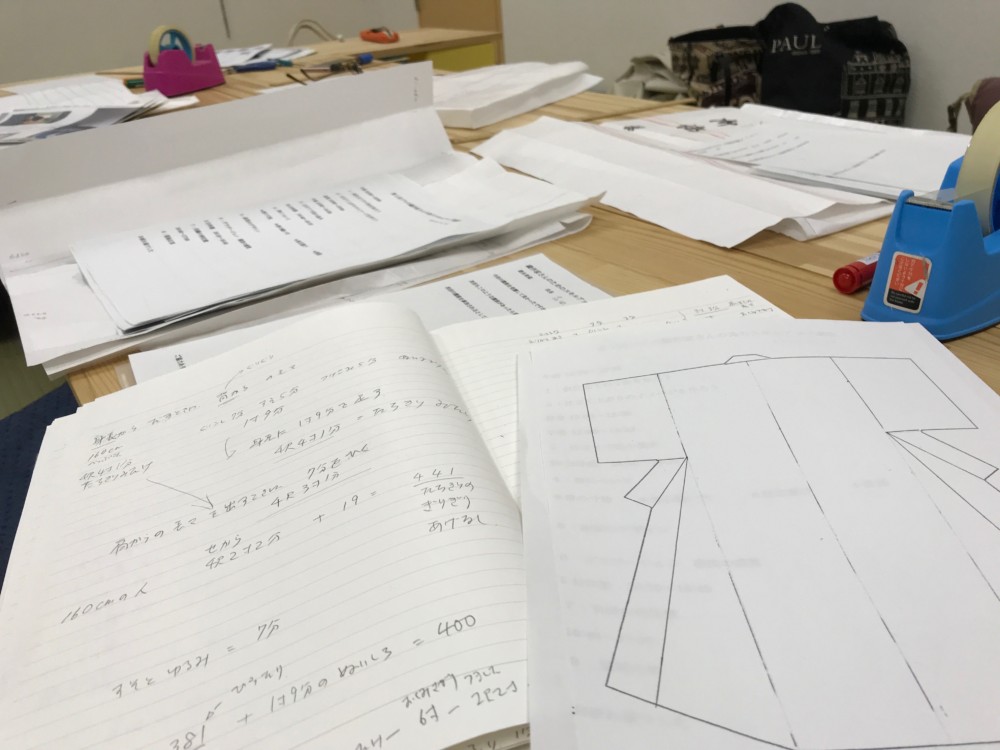
和裁士の平山留美さんによる、「織り作家のためのスキルアップ講座」に参加してきました。伊勢丹展直前で切羽詰まってますが、これは外せません。てか、これを受けねば、次に進めないって思いで、受講してきました。思っていた通り、稀有な、素晴らしい講座でした。
受講生5名でした。みんな本気。すごいね、マジで織りをやってる人が、こんなにいるのね。って思ったら、なんと、遠くは鹿児島から、八丈島から、みなさん、乗り物を乗り継いで、参加されているのでした。
マジの方々の中にいると気持ちいいです。なあなあな中からは何も生まれませんものね。
平山さんも、がっぷり受け止めてくださり、投げた球を、パコンパコンと気持ちよく打ち返してくださいました。
さあ、この球をどう消化吸収するかだね。それは、5人の受講生それぞれだけど、きっと皆んな、それぞれに飲み込んで、栄養にして、また吐き出していくでしょう。
仲間ができたのも、とてもうれしいことです。ささ、影響しあって、もっともっと、どこまでも素敵な織物を、作り出して行きまっしょう!
お出かけ、つらつら日記
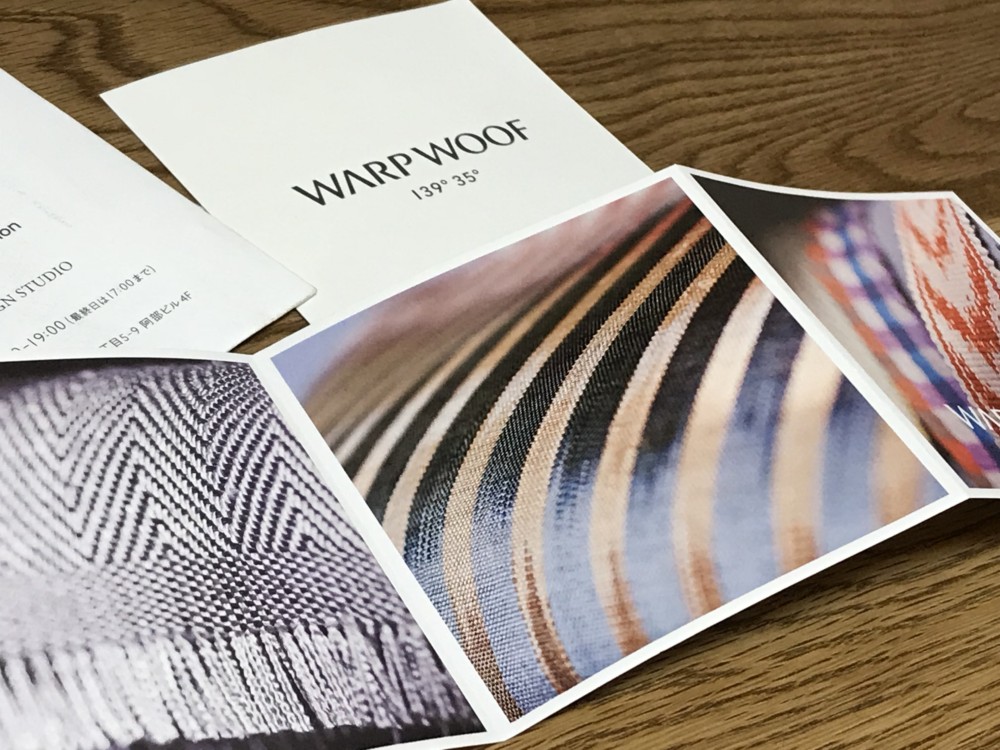
昨日は、エネルギーをいただきに、お出かけしました。
まずは銀座へ。小島秀子さんの新しいこころみ、「WARPWOOF」を拝見しに、ワクワクと。
会場には、小島さんの、すごく精神の行き渡った、それでいて、なんかホッとする可愛らしさを持った布が、きものの世界から飛び出して、日常に使えるものに展開され、生き生きと存在してました!小島さんの生み出す美しさが、新しい息吹と混じり合って、新しいジャーニーをはじめています。
会場を辞して、せっかく銀座にきたので、ちょろっとGINZA SIXによりました。ここは日本か?、って来るたびに思います。私はどうも落ち着きません。
ふらふらと銀ブラ。松屋銀座に寄ったら、ザ・日本のデパートって感じがしてしまった。そのドメスティックさに逆にビックリ。銀座、GINZA SIXができて、流れが変わったね。やっぱ、何かできるってすごいことなのね。
で、地下鉄移動。銀座線を赤坂見附で乗り変えて、新宿三丁目へ。新宿三丁目と言えば、伊勢丹です。ちょっと7階に用がありまして、この話は後日また。詳しく書かせていただきますね。
用事を終えて、む?今日は水曜日?映画が安いかな?気になっていた、「ドリス・ヴァン・ノッテン」、まだやってるかな?早速調べて、あ、武蔵野館でやってる!1000円だ!予約して、時間まで「ベルグ」でビール。新宿とちょっと休憩と言えばベルグです。
「ドリス・ヴァン・ノッテン」、20:45からの最終回を見ました。
ドリス・ヴァン・ノッテンのファッションショーにフォーカスしたドキュメンタリーフィルムだったのだけど、私、ドリスってどんな人か全く知らなかったのだけど、すごく、端正なナイスミドルと言った風で、ちょっと拍子抜けしたくらい。見かけは全くエキセントリックでもなく、アーティスティック気取りもない。
が、自宅で撮影の段で、ああ、こりゃあエキセントリックはなはだしいって思ったよ。建築もインテリアも庭も、完璧すぎる。普通でないです。やっぱ、何事かなす人は、振り切れてますな。
モノ作りに対する真摯さはさすがです。そして、ものすごいハードワーカーです。美しさを希求する、そこまで持ってく。そうだ、そうだ。そうでなくちゃ!
photo by Yanagawa Chiaki
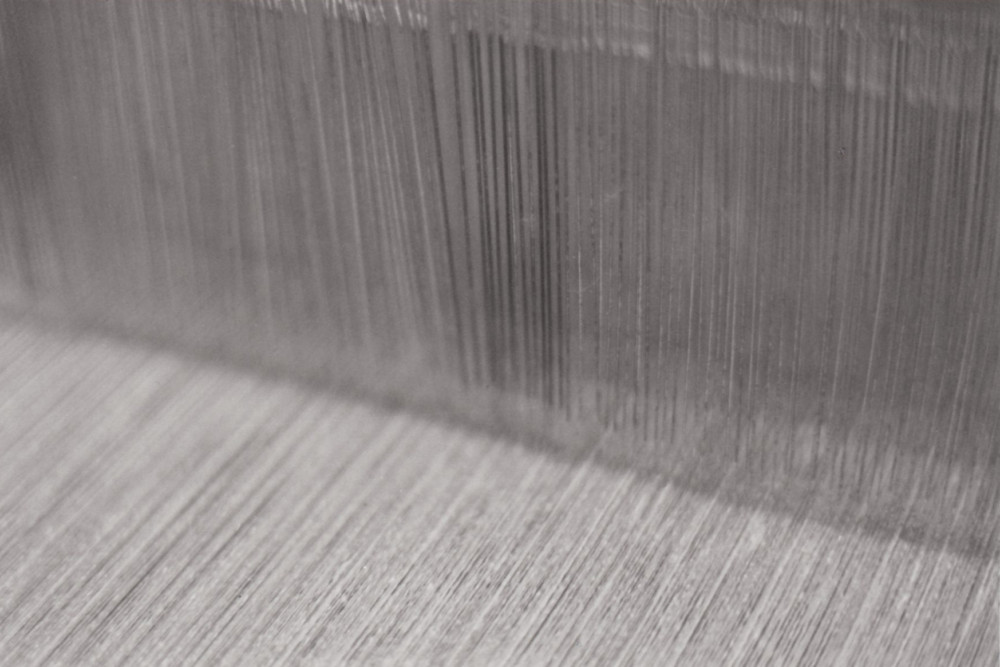
染織家で写真家の、柳川千秋さんが、写真を撮ってくれました。
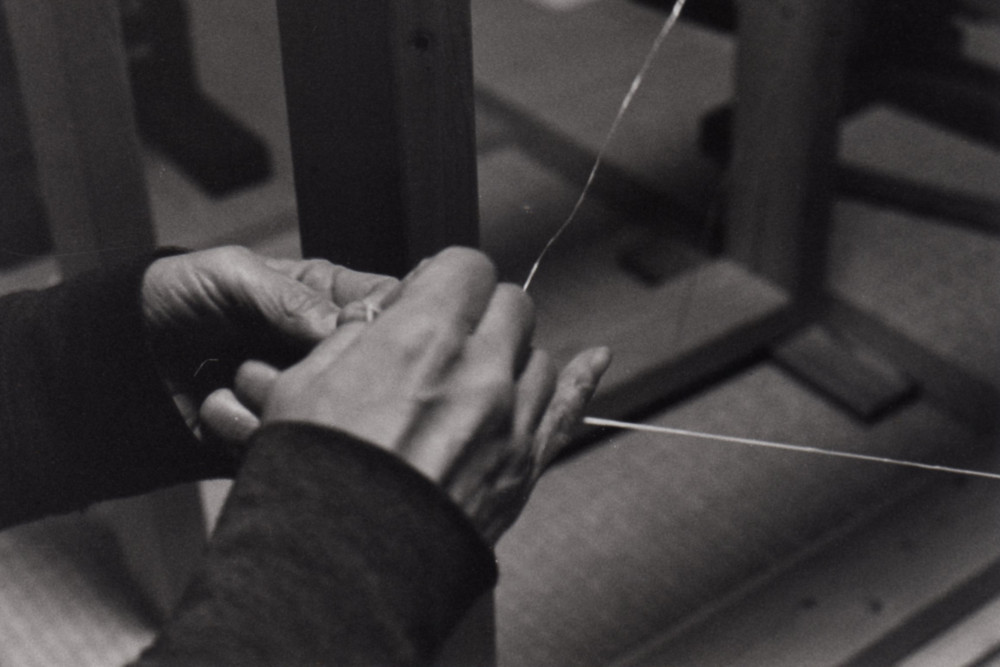
すっごく自然で、丁寧で、撮る人の優しさが伝わります。撮られている方は、少々恥ずかしいけど、いい写真だなあって思います。

糸。
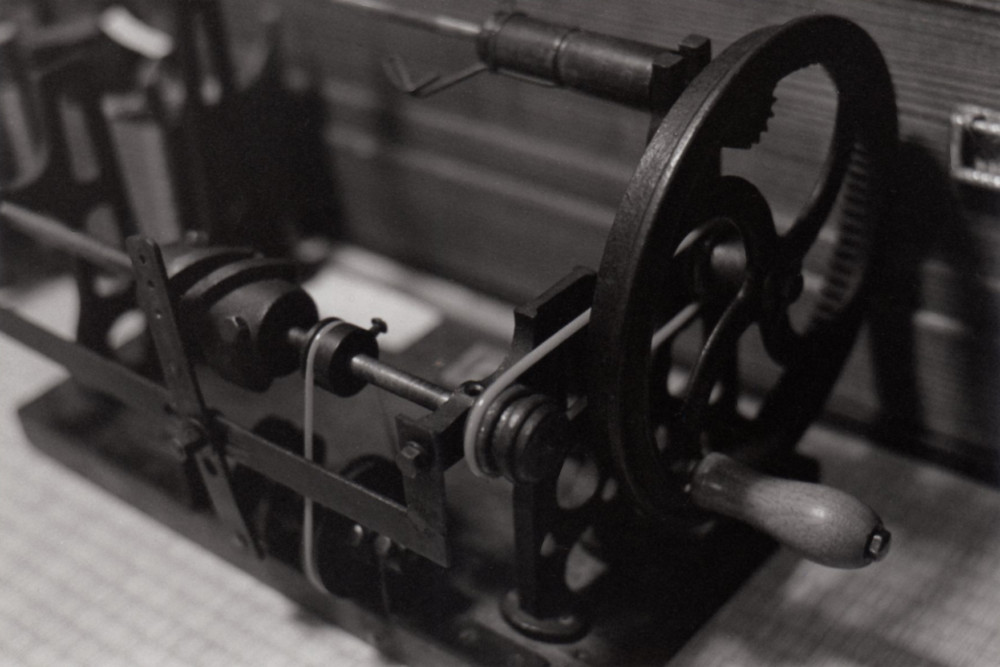
道具。

糸を巻く私。

出番を待つ糸たち。
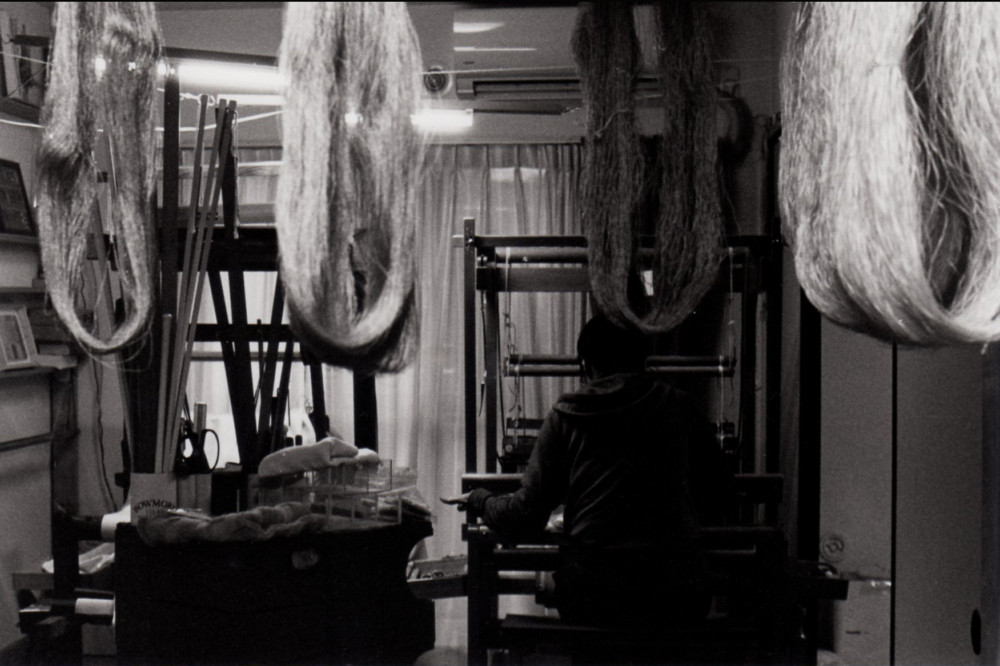
私。もくもくと。
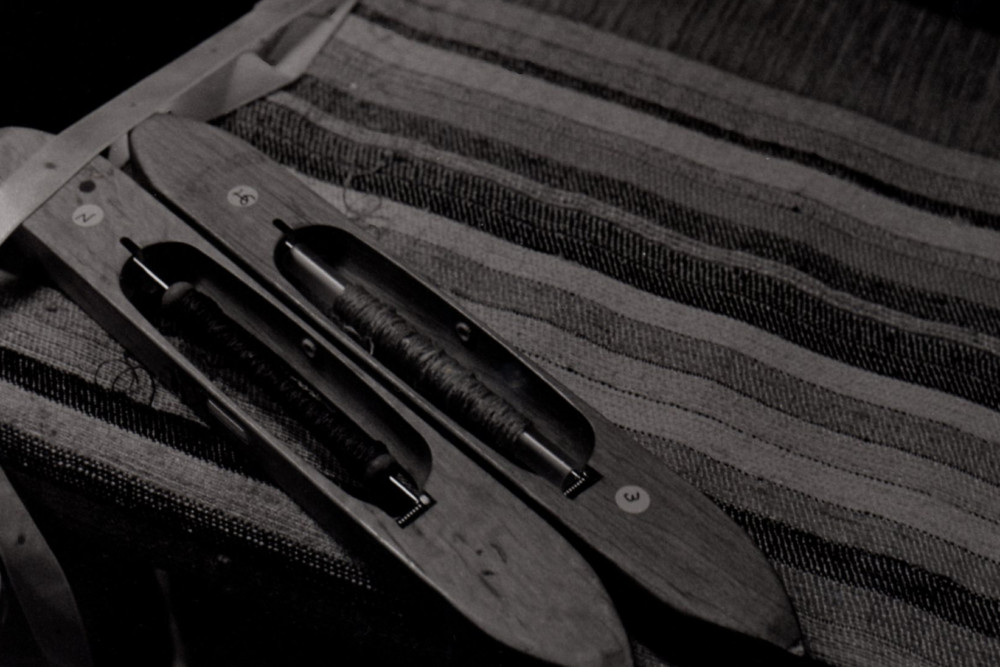
織ってます。

柳川千秋さん、どうもありがとうございました!
オリンピックと確定申告

たまには時事ネタ書きますね。今、世間は、オリンピックと確定申告ですね!
うちにはテレビはないのですが、それでも気になるのは、動画で見ています。フィギアスケートも見ましたよ。宇野昌磨くんは、甥にそっくりなので、特に応援してます。
オリンピックが始まると、いつも思うのは、人間は進化しているのか否かってことです。この前まで、あんな氷の上で何回転もするなんて、誰も思いもしなかったのに。毎回毎回、どんどん難易度をあげて、高度な技をこなして行く。本当にすごい。
これは人間の進化なの?
もし進化だとしたら、美しさの追求についても進化してる?うーん。
織りの世界は進化している?うーん。
それについては大変疑わしいですが、染織をやって生きて行くには進化せざるを得ないです。
今、せっせとやってる青色申告と確定申告ですが、ソフトは弥生会計の「クラウド」です。ついこの前まで、「クラウド」って一体それ何っ、理解不能っ、て言ってましたが、どうも、それが一番便利なシステムらしいってことがわかってきました。他にもやり方はいくらでもあるけど、お金もそれほどでもなく、時間も短縮できるのはこれかなと。
使いこなせてるのって問われれば、微妙な感じの私ですが、弱小自営業者は、一番便利なシステムに乗っかれるだけの、進化をしなければ、成り立たないと思った次第です。。。

このページに載せている二枚は、メルマガの方のお話の写真です。メルマガはテキストメールで配信してるので、写真はこちらで見てもらおうという戦略です。よかったら、この号から配信しますので、ご登録くださいね。
メルマガのアーカイブは、ノートに残していますが、そちらは、有料設定(100円)です。ノートが有料なのは、メルマガの記事は無防備に書くので、少々のハードルを設けさせていただくためです。よろしくお願いします。
タイムマシンに乗ったのれん

大変に、大変に、大変に恥ずかしいですが、これ、私が20年くらい前に織ったのれんです。
まだ、染織家として独立する前に注文いただいて、織ったものです。勤め人をしながら、機織りしていた頃の話。指定されたサイズも大きくて、そんなデッカいの織ったことなくて、でもうれしくて、ドキドキしながら、織ったのおぼろげに覚えてます。

のれん、なんとなんと、20年間、ずっとご愛用いただいたとのこと。
20年間、お仕事場の屋根はあるけど、半分外のようなところで使っていて、それを今度、うちの中で使いたいから、ほつれの修理はできますかとの問い合わせいただいたのです。
送ってもらって見せてもらうことにしましたが、内心ドキドキです。20年も前の自分が、今、こちらに向かっている。クロネコさんはタイムマシンか?

で、ヒヤヒヤで待っていたところ、荷物がついて、オープンして、「うううわああ。。。あわわわ、、、、」
想像以上に恥ずかしい!!!穴を掘って、ビバークしたい。勢いだけで恐ろしいほど強引に織ってる。ぎゃー!

お客様にお電話し、織物として再生することは難しい旨、お話しする。タテ糸とヨコ糸を拾って、合わせていくことは無理ですわ。
すると、電話の向こうで、がっかりして、「それでもこれは捨てたくないから、修理できないなら、額にでも入れて飾るかなあ」とおっしゃいます。
えっ!額!!
こんな大きな額はないでしょう。だったら、織物として再生させることは無理だけど、テキスタイル作品として、ほつれを縫い止めることはできますよ。それでよければ、喜んでやらせていただきます。

それで、できる限りの補修をしました。縫いながら、20年前の自分と対話します。どうしようもなく稚拙ではありますが、精一杯でぶつかって、ガチで向き合ってる感じ、20年後の私にも伝わってくる。問題は多すぎだけど、なかなかいいじゃないの!愛しさだけはピカイチというのは身内の身びいきね。(身内というか、本人だけど)

修理を終えて送り返しますと、とてもよろこんでくださいました。メールにあった「本当に力作です。」の言葉がうれしい。

*こののれんの話は、先日配信したメルマガ《 some ori 通信 》にも、速報チックに書きました。ブログはどうしても遅れ気味です。メルマガの方には写真は載せられませんがね。
メルマガ、よかったらご登録くださいね。月に2回の配信で、もちろん無料です。
*1月15日に、メルマガ申し込みいただきました、TNさま(docomo のメールアドレスの方)、確認メールが戻って来てしまいます。メルマガ、届いてませんよね?お手数、おかけいたしますが、もう一度こちらからご連絡、くださいませ。よろしくお願いします。
織物以前 タパとフェルト

リクシル のギャラリーで開催中の、「織物以前 タパとフェルト」展へ出かけました。私、こういうプリミティブ系、弱いんです。魂にくるのだよな。私の作りたい布の根っこはここにあると思っている。福本繁樹先生と岩立広子先生のレクチャーにも申し込んでましたので、ますますウキウキと出かけました。

レクチャー、とても面白かったです。以下、ノートした走り書きより。備忘のために。
—人はなぜ装うか?もともと、入れ墨、ボディペインティグに大きな意味があった。(部族間の戦いに行くときの化粧など)布はその代わりとなるものである。布は第二の皮膚。それが布の本質。
紐衣(ちゅうい。腰に巻いた紐)が衣服の原点。
布はお金であった。
タパそのものは、物質的な財産であった。
タパに描かれてる文様は、知的財産であった。それも、とても高価な。
文様は、ストーリーがある。ストーリーとセットで受け継がれる。
資本主義が入らないところで、ものすごいものが出来る。文化にすごい高い価値を置く。—
などなど、ビンビンくるレクチャーでした。
資本主義の入らないところで、ものすごいものが出来るってのは、わかる。生まれたときから、どっぷり資本主義に浸かってる私など、どうしても破れない壁があるのだ。思考的にも。もっと根源的にも。しかし、それを無いものにしないと、本当にいいものはできない。便利なもの、流行りなもの、を作りたいんじゃない。心揺さぶるものをこの世の中で作って行くのが使命だなあと思った次第。
さらにここ数日

お正月が終わってからこっち、パソコンの移行であたふたしています。まあー、大変なこと、大変なこと。
実は昨年の夏頃からずっとパソコンの調子が悪く、いつ壊れるかいつ壊れるかとドキドキしていました。突然落ちるのですよ。固まるし。心臓に悪かったです。
しかし、サイトのリニューアル中の私は、買い替えるより、なだめすかして使いつづける方を選びました。その時の自分に移行のエネルギーはないのわかってたから。
んで、辛抱して、辛抱して、やっとサイトのリニューアルが落ち着いたのが、12月31日。ホッとしたのもつかの間、私は、その足で買いに行きました。こういうのは勢いで行かないとね。大晦日の夕方遅く、町田のヨドバシ前は、福袋ねらいと思われる徹夜組が並び始めていました。
IT弱者の私は、ネットではどれを買っていいか分からず、それまで使っていたパソコンのスペックをメモしていって、「これと似た感じのください。」とお兄さんに訴え、オススメを買う。(←カモのようだが、的確な買い物したと思ってる。)ただの番号であるが、オフィスとイラストレーターとマックケアも買う。とんでもない出費である。
散財した高揚感と、大晦日のしんみり感をないまぜにして帰宅。ヨドバシの黒い袋はポンと放置したまま。開ける気全くないのが、IT弱者のIT弱者たるゆえん。
そのまま年を越し、故郷に帰省して、こっちに戻り、着物なども片付けて、さあもう逃げられません。
しかし、世間の皆さん、みんなこれやってるの?これ、できるの当たり前?リテラシーってやつ?いつの間に世の中こんなにハードル高くなったんだろう。
外付けハードディスクと、ドロップボックスの中も、ぐちゃぐちゃだった私は、いま、大変ひどい目にあってます。
*ちなみにこのブログの投稿は、初の新しいパソコンから!できたよ!できたよ!
*写真は帰省復路の窓から。曇りの日だったけど、空の上の眺めはいつも気持ちいい。
ここ数日

熊本でお正月を過ごしています。
いつも居場所がないような私ですが、居ていい場がここにあるというのは、幸せなことです。
おとといは高校の同窓会で、朝から幹事手伝いとしてはせ参じ、名札係をしました。
高校卒業30年。みんなそれぞれ、よくやってるなあ。数人としっかり話せたの、よかった。
二次会からの帰り道、長六橋の上で大きな満月を見ました。幸先いいぞ、2018。
昨日は、昼間ちょっと時間が空いたので、特に目的もなく熊本の街を歩きました。
通町筋でバスを降りて、教会の裏の小さな神社に参拝。私、この神社、前から好きなんだ。巫女さんが頭ぽんぽんしてくれた。
角にあるワインとチーズ「デコラーレ」。昔からここは本当にそそられっぱなし。なかなか買えないけど、変わらず営業しているのがうれしい。今回も外からのぞいて、指をくわえる。
藤崎宮に参拝に行こうと思い立つ。「さかむら」の前を通るもお正月休み中。
藤崎宮、久しぶり。こんないいお宮さんだったっけなあ。
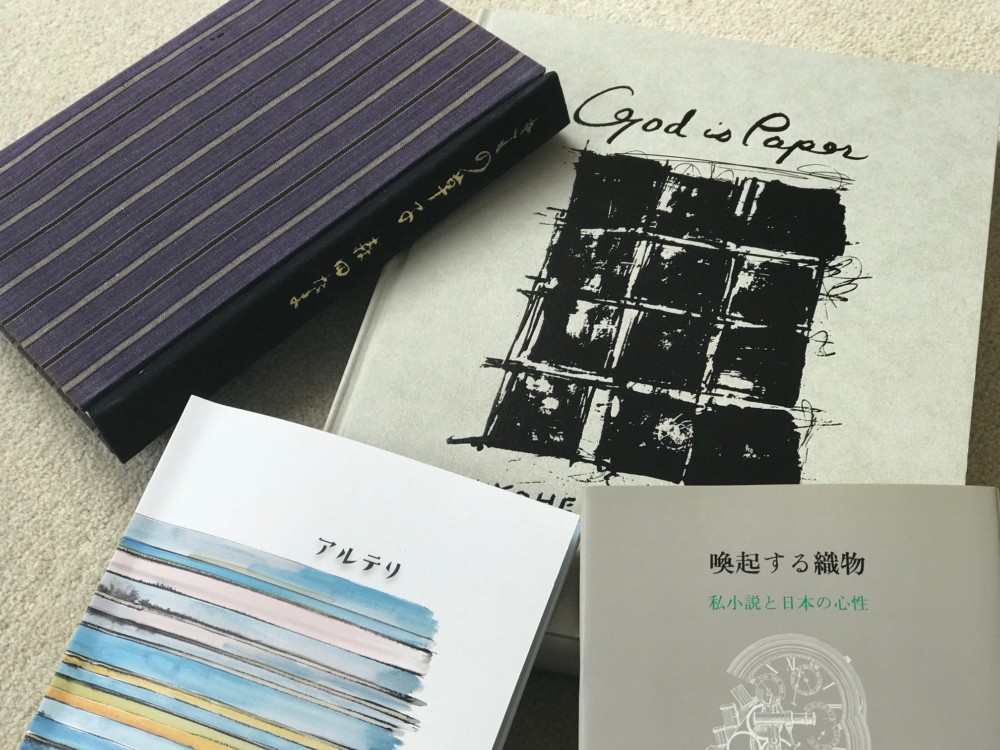
並木坂をふらふら歩いてたら、「汽水社」発見。うわさの古本屋さん。ああここなのか。初めて寄りました。
なんかすごく落ち着く好みの店で、長居してしまった。4冊買って、一万円弱。いい買い物した。
夜の宴会までもうちょい時間ある。映画でも見ようか?スターウォーズかな?何十年ぶりで新市街の「電気館」に行ってみました。
大衆向け正月映画でも思ったら、なんのなんの。もろにオフシアター系。東京だったら、岩波ホールか、ポレポレ座か、イメージフォーラムでしかやってないような映画が、一ヶ所で固まってやってる。スクリーンは三つ、時間差で五作品上映。それも水曜日でレディースデイ、1,100円。東京のオフシアターは割引きないよね。すごいな、電気館。
どれも面白そうだけど、時間の関係で、「笑う故郷」を観ました。主人公の芸術家魂、すごく好きだ。
夜は小学校の集まりへ入れてもらう。同時代を過ごした近所の人たち。なんだか自然に超リラックス。
今日はうちの手伝いなど。孫疲れの母にテルミー。
明日移動して平常運転に戻ります。さあ、がんばりましょう。
明けましておめでとうございます

2018年、はじまりましたね。青空きれいな、あたたかい神奈川のお正月です。
私は故郷の熊本へ帰るため、今、電車に乗ってます。iPhoneからのブログ投稿にチャレンジ中。元旦移動の方、けっこういらっしゃいますね。キャスター付きのスーツケースを転がす人、目に付きます。私もですけどね。
うちを出る前に、ベランダの物置の上に、水とカリカリを準備してきました。このところノラ太がくるので、ニャンと言われれば、あげてました。今日は、顔は見なかったけど、数日いないので、先まわって。納豆のケースを洗って、新しい水とカリカリを入れて、物置の上を少々きれいにして置くと、なんだかお供えしているようでした。ここには居ない何かのために。
神棚も仏壇もない我が家ですが、なんだかお正月にふさわしいような気がしました。
写真は、おとといの夕方。我が家の近くから。真ん中に見える山は大山です。
今年もどうかよろしくお願いします。よい一年にいたしましょう。
今年の締め!
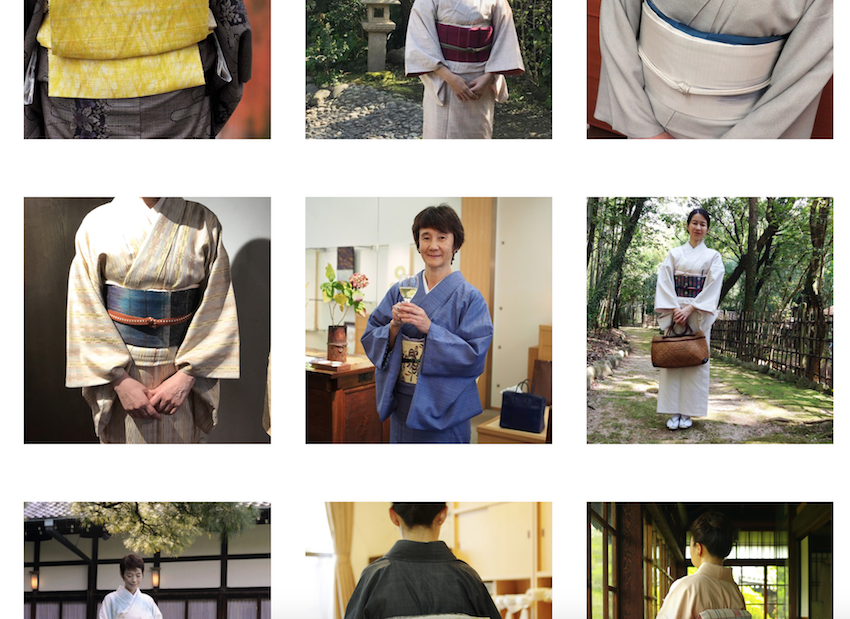
今年もあと数分、、、、。今日は私、一日、パソコンに向かっておりました。
サイトに、新しいページをオープンさせましたよ。その名も「着姿ギャラリー」。今まで私が織ったものを、身にまとって、お写真におさまってくれた、とびっきりにステキな方々に、一堂に会していただきました。
今年中にアップするぞって心に決めてました。ひゃあ、ギリギリセーフ!
作品ギャラリーが「年代別ギャラリー」と「着姿ギャラリー」の二つに別れた格好です。ここが作品ギャラリーのトップページです。ここから入って、「着姿ギャラリー」に進んでね。カテゴリーが「すべて」「きもの」「帯」「ショールといろいろ」とありますので、それを選んでね。
実はまだ、写真を見つけきれてなかったり、画像が小さすぎて載せられなかったり、出来上がったわけではないのです。「ああ、あの人がいない」ってわかってるのですが、少しずつ充実させて行くということで、とりあえず公開いたします。
今年は、何と言っても、サイトをリニューアルのが大事件でしたが、これで、だいたい一段落かな。サイトも本当におかげさまでできました。担当してくださってる「アカオニのゴトーさん」とは、今年、何回、メールのやりとりをしたでしょう?1000回は超えてるね。2000回かもね。超絶うるさい私に付き合ってくれて大感謝しています。
さて、来年は、もっともっと、織る年にしようと思います。機に座らなければわからないことをわかりたい。そんな感じです。
来たる年も、どうかよろしくお願いします。
もういくつ寝ると

あと二つ寝るとお正月ですね。
お正月はきものを着るぞと、ごそごそ準備をはじめました。さあ、どれを着ましょうってチョイスはとても少ないです。数少ない中で、一応、上の写真が私の袷、ベスト組み合わせのつもりなのだけど、、、、
うーん、お正月ぽくないな。どうにかならんか?

あ、いただきものの帯締めがあるぞ。パープルピンクで、少々幅ひろ。今まで一回も使ったことない。めでたっぽいし、使って見るか。
帯揚げは、、、、合うのがなーい!
ふと、先日青森からのお客様がくださったプレゼントが入っていた紙袋が目に入った。ふむ、濃いローズ色。あら?もしや?ぴったり?
んじゃ、染めちゃおっか?
いそいそと染色鍋と、帯揚げの白生地を用意する私。えいやっ!

この紙袋をかたわらに置き、少しずつ、染料を入れ、合わせていきます。ローズ系、オペラ系、ルビン系、青味もけっこう入れましたよ。黄味もね。
これでどう?

きゃ、ちょっと可愛すぎ?もうちょっと茶味を入れた方がよかったか?染め重ねてもいいんだけど。ま、お正月だから。このくらいいいかな?
_____
染織吉田では、ただ今、きものか帯を、通販サイトからお買い上げ下さった方とONLY ONLY のご注文くださった方へ、「期間限定!帯揚げ、染めます。プレゼント!」を開催しております。お好きな色に、帯揚げを染めますよ。この機会に、ぜひ、ご利用になりませんか?
ONLY ONLY は、期間中(2018/5/1)までに、打ち合わせを始めさせていただいた方も対象です。実際にお作りするのは、ずっと後でも、この機会に相談を始められ、ONLY ONLY な帯揚げもゲットなさいませんか?
_____
また、帯揚げだけが欲しいんだけどというお問い合わせも、ちょこちょこいただいております。布染めは本業ではないためお断りしていましたが、ご要望が多いので、お受けしてみようかなと思ってきました。(それに、私、けっこう得意なのですよ、自分で言うのもなんですが。)ご希望の色味をお伝えいただいて、すり合わせして、お染めいたします。代金は、15,000円(税別)からとなります。白生地によって、違ってきます。ご興味の方、お気軽にお問い合わせください。
復興城主、感謝状贈呈式
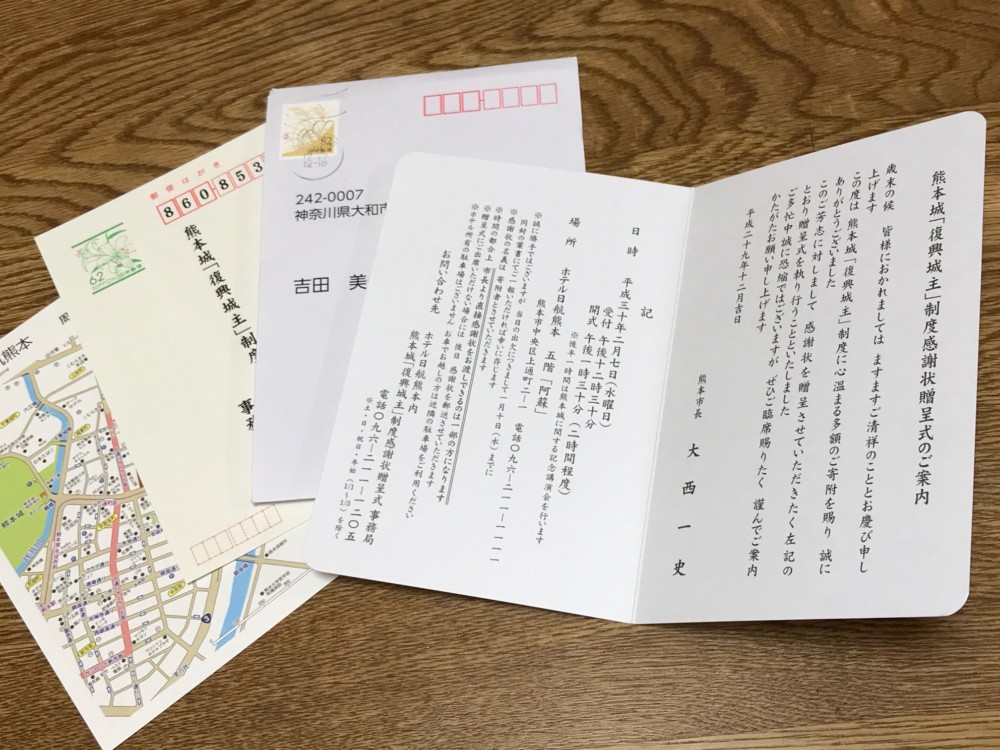
本日、郵便受けに立派な封筒が入っていた。開けて見ると、、
『熊本城「復興城主」制度感謝状贈呈式のご案内』とある。
内容を見ると、市長さんが熊本城に多額の寄付をしたのを褒めてくださると。で、感謝状をくださると。日時は来年2月7日で、会場はホテル日航熊本という熊本では有数のお高い箱だ。出られない人には、後日感謝状を郵送してくださると。
なんじゃこりゃ、と思いました。
なんでこんなことにお金使うの?アホかいな。感謝状が欲しくて寄付したんじゃないよ。あれは、熊本地震の後開催した個展「清正公の陣羽織」での売り上げの10%で、お買い上げくださった皆様のお気持ちなのだ。それにすでにいただいている城主証だって立派すぎるほど立派でもったいないなあって思っていたのに。
はー、なんと、がっかり。ウーマンラッシュアワーがこの前「熊本の仮設住宅に住んでいる人、いまだに4万7千人」って言ってたじゃん。ムダ遣いしないでよ。
市長さんだって、役所の人だって、まだまだすごく忙しいでしょう。感謝状渡してる暇があったら、ちょっと休んで鋭気を養えば?
と思ったが、、、、、
ちょっと待て。
これは、もしかして、県外在住者をねらった、観光きっかけキャンペーンか?熊本城へ寄付するとは、熊本へなんらかの思いをもっている人が多いに違いない。期日は2月。観光客が閑散とする時期。観光業の方々がドーンと落ち込むのは必至。何か事前に手を打たねば。それが、この感謝状贈呈式?これを呼び水に、もともと熊本に思いを持ってる人たちに観光に来てもらおうと?
ふむ、、、そういう目で案内状をみると、呼びかけているのは市長だが、差出人は市役所でなく、熊本城総合事務所。問い合わせ先は、ホテル日航内の事務局。
ふーん。なるほど。観光客、バンバン来るといいね。街が賑わうのはなんにせよいいもんね。
私はとりあえず感謝状の郵送を断るね。それだけで、印刷代と封筒代と切手代で300円くらいは節約できん?
ゆうど20周年

ゆうど開業20周年の展示会に、行ってきました。久しぶりの目白、久しぶりのゆうどです。私は、この店に勤めるために、21年前に、2度目の上京をしたのです。それから、6年、働かせてもらいました。
20年前のオープンの日、雪が降ってたよね。福娘っていう樽酒を叩いて開けたのだったよね。
それからいろいろあったなあ。ここは私にとって、とても大きな存在です。

しんみりしつつも、ここが存在してくれてて、うれしかったです。存続するの、大変よね。お店も仕事も、、、
私が貼った壁紙もそのままだったし、私がいる頃からゆうどを縄張りにしていたトラも出てきてくれました。変わらんねえ。。。。
ゆうど20周年記念展は、今日、12月16日までです。写真は、宙吹きガラス作家の荒川尚也さんの作品、ガラスの船。すごくよかったです。
池田重子展に行った

横浜のそごう美術館で開催中の「池田重子 横浜スタイル展」に行ってきました。招待券をたくさんいただいたので、メルマガで「おふくわけ」企画をして、お申し込みいただいた方のうち、今日都合がつく方々とご一緒しました。
池田重子さんのコレクションは、増えているわけではないと思うので、膨大なコレクションの中から、どう選び、どうコーディネートし、どう魅せるかが見所だとは思うのですが、なぜだかとても新鮮さを感じ、さすがだなあって思いました。
入ってすぐの、横浜スタイルのコーディネートのブースは、特に面白かったなあ。船やヨットの帯とか。魚の帯留とか。明るくてのびのび。「私はこれなのよ」って感じがして気持ちよかった。横浜ってつくづく海の町なんだね。私、神奈川県在住で、横浜までも小一時間なのでたまに行くけど、生まれ育ってないせいか、年代のせいか、海を感じたことない。でもここは港町なんだ。池田さんが、生まれ育った時代は、特に色濃かったんだろうなあ。
あと、着物を着ているボディが小さくて、昔の人のサイズはこのくらいだったのだなあ、などなど思いながら、眼福、眼福で、会場をぐるり。
5人でランチもいたしました。(5人の内一人は男性で、御年はなんと4ヶ月!)
なんか、みなさん、布好きで、それぞれにきものライフを楽しんでいる方々で、リラックスして、いろいろ話せて、楽しかったです。上の写真は私だけですけどね。みなさん集合写真を撮ろうってタイプの方々ではないと思ったので。
メルマガでは、またこういうお誘い企画したいなって思っていますので、よかったら、お気軽にご登録ください。
「池田重子 横浜スタイル展」は、そごう美術館で、1月8日まで、会期中無休だそうですよ。ぜひ!
じざいやさん、ありがとう

本日で、じざいやさんでの展示会を終わりました。お越し下さった皆さま、本当にどうもありがとうございました。昨日も今日も、とっても充実していました。上の写真は、今日のベストショット。帯にご注目。うふふ、きいさまですよ。「Let’s go to Opera」締めてくださってます。
今日はなんと、青森県からのお客様もいらっしゃったんですよ。それも私の織った着物を着て。びっくりしたなあ。お求めくださってたの知らなかったから、心底驚きました。とても似合ってらして、輝いてらして、うれしかったです。
じざいやさんにいらっしゃるお客様がたは、みなさん、本当にきものが好きで、楽しんでらして、いいなあって思いました。じざいやさんは、そういうきもの好きな方々のたまり場なんだな。
作品たちは、引き続き、じざいやさんにてご覧いただけます。まだまだいいのありますからね、ぜひ、見に行ってくださいね。
メガネを買った

今日は、めちゃくちゃ面白かったです。
夕方、友達と待ち合わせていたのですが、「何か買い物でもないの?あれば付き合うよ」と言ってくれるので、ついつい「メガネ」と言ったら、高い店、安い店、イマドキの店、などなどフルコースで付き合ってくれ、下見のつもりがついつい、、、、。
そのエスコートが、とっても素晴らしかったのです。彼女が、売り場ですっと手にするメガネが私に似合う不思議。一瞬でわかる人っているのね。天賦の才能だね。
直感もすごいけど、ちゃんと諸事情も考慮してのアドバイス。こういう風に使うだろうからこのタイプが便利とか、見た目があまり大人しすぎるの違うよねとか、おサイフ事情ももちろん大事よねとか、、、、
うーん、ステキ。メガネだけでなく、洋服も、インテリアも、生き方も相談に乗って欲しいよ。
って、そのあとの、めちゃくちゃ美味しい中華を食べながらそんな相談にものっていただきましたがね。頼りになるは、よき友人。フリンジの福永麻子さんです。いろいろ仕掛けそうで、目が話せない人です。
上の写真は検眼用のメガネですよ。買ったのは、ほっそりした金縁フレームですからね。

後ろ姿はこんな。このあと、ビールと焼酎+中華で上機嫌。
小林布未子先生の着付け

ファンキーで超カッコいい小林布未子先生に、着付けを教えていただくチャンスをいただきました。やった!小林先生、雑誌などあちこちで拝見し、その自由で独自のきもの感にあこがれてました。
上の写真が、小林先生。紐に滑り止めをつけて、ずれないようにするのです。ほお。ほお。
小林先生、「自分がどう着たいか、自分の意思で、自分流で着れば良い」「大事にするのは、自分のありよう、意識のありよう、内臓のありよう、骨のありよう」と。
で、それを押さえれば、小さいことは決めなくて、その場で感覚でやると。美意識の問題だから。決めすぎるとつまらなくなる。
うーん、さすが!
合わせて、細かいところまでの気配りも相当です。市販の帯板は狭すぎてダメとか。手先にも厚紙を入れるとか。帯揚げにティッシュをくるんでふっくらさせるとか。一ランク上の、自分がそうありたい着姿になるためには、努力は欠かせないと。
写真にはちょうど写ってないけど、先生、ネイルがとても綺麗で品が良くて素敵だったのだけど、マニュキュア100均のですって。で、マニュキュアが大事なんじゃなくて、その前の段階で爪を磨くのが大事って。まずは土台。さすがー。

ご一緒した方々。上の写真は画家の朋百香さん。この日のことはこちらのブログに。


ライターで、人気きものブロガーの神奈川絵美さん。最高の笑顔が撮れました。この日の記事はまずはこちら。続編も楽しみ!

これは私。衿の角度がね、このくらいがいいんじゃないのってアドバイスいただく。鋭角すぎず、コケティッシュな感じが出るって。ほお。うん、いいかも。問題は一人でできるかってことだけど。

座学もしっかり。ぐいぐい引き込まれます。小林先生、お話も面白い。

おまけ画像。帯締め、にっこりマークなのだよ。うふっ。
最近の悩み

昨年の12月からヨガをはじめて、もうすぐ丸一年。今ではすっかり日常に組み込まれ、平均すると週に3日ほど通っている。我ながらよく続いていると思う。体重も減らないし、体脂肪も減らないけれど、唯一の運動だし、姿勢がよくなった気がするので、よしとしている。
で、何が悩みって、クラスが終わって、スタジオを出るまでの時間が、他の人たちと比べて遅いってこと。
ホットヨガなので、汗びっしょりになる。終わるとシャワーを浴びて、着替えて、身繕いをして、退出する。人によっては、シャンプーしたり、ボディソープで体を洗ったり。お化粧したり。着るのに面倒な服装したり。
私はといえば、シャワーは汗を流すだけ。お化粧しない。簡単普段着。もちろんストキングはいたりもしない。
なのに、すごく遅い。最後から3番目くらい。あとの二人は、念入りに眉毛かいたりしてるタイプの人。
なぜだろうか。
これでも仕事柄、段取りっていうのはいつもすごく考えていて、スタジオからシャワーへの動線とか、着替えをまとめて袋に入れる手順とかまで考えてるのに。。。。。
どうしてかなあ。悩みである。
18:20からのクラスが、19:20に終わって、19:40にスタジオを出て、20:00までのスーパーに寄って、閉店間際で値引きされた肉など買って帰ってきて、ジューッと焼くのが至福のとき。
*写真はヨガには関係ありませんよ〜〜。ショールのタテ糸たち。このページの2枚目からの6枚を整経したときの写真。
今日のこと

今日は昭和10年代生まれの人たちにとても縁があった愉快な日でした。
母と叔母が上京しているので、今日いちにち、上野見物に出かけてきました。
プランを立てたのは私です。考えたのは、なるべく歩く距離を短くするということ。電車をうまく乗り継いで、目的地の一番近い駅の、一番近い出口に出て、最短距離で行く。
行った所は、旧岩崎邸、湯島天神、鈴本演芸場、アメヤ横丁。
で、泉岳寺の駅に迎えに行き、都営浅草線、都営三田線、千代田線。ちゃっちゃと乗り継いで第一目的地、旧岩崎邸に着きました。なんといい天気。澄んだ青空!
岩崎邸は11時からガイドさんがついてくれます。これも折り込み済み。おかげで、岩崎家のすごさと、時代のうねりがよく分かった。我々についてくれたのが、物知りなおじいさんガイドさん。
地震や戦争もくぐり抜けてきた岩崎邸の、和風建築の大部分を、壊してしまって無粋な裁判の施設にしたのを大変悔しがっておられました。「あなたは生まれてなかったでしょうけど、昭和44年だったんですよ」「いえいえいえいえ、残念ながら、生まれてました。あはは」「あら、私は昭和19年です。」
その後、湯島天神経由で、鈴本演芸場へ。席を確保して、私は一人で、松坂屋のデパ地下に、お弁当を買いに。まずはお化粧室を借りましょう。と個室に入ったら、荷物かけに、ショルダーバッグが下げてあります。あら、忘れ物。すぐに持って出て、出たところの果物売り場のお兄さんにお預けして、私はUターン。
用を済ませて出てきたところに、駆け込んできた年配のご婦人あり。大変慌てたご様子。「ああ、バッグですね、さっき店員さんにお預けしましたよ。」「え、あんた見つけてくれたの!ちょっと一緒に来て、お願い!」
で、付き添って、さっきの店員さんのところに行き、6階の遺失物詰所に行き、係の人が確認している間に話をきく。
「このバッグ、私の大事なものが全部はいっとるんよ。ほら、保険証。私、昭和13年生まれ、あと5ヶ月で80歳」「まあ、私の母は14年で、叔母は16年です。今、一緒に鈴本に来たんですよ。私、お弁当買いにきて。」「あらあら、じゃあ戻らないと。ありがとうね。」と涙ぐまれる。
デパ地下でお弁当を買い、コンビニでお茶と缶ビールを買って、鈴本へ戻る。実は寄席、初めてだったのだけど、ゆる〜い感じがいいね!ビール飲みながらってのが最高!足りなくなって買い足した!
終わって、アメ横ぷらぷら、お土産など買い、御徒町から品川へ。3人でご飯。2人を京急へ乗せて、私は大井町線へ。
こんな日も、たまには良い、後で思い出すときっととても良い。そう思う1日でした。
サイトリニューアルの挨拶状

遅ればせながら、サイトリニューアルの挨拶状ができました!
やったー!苦節一ヶ月半。やっとやっと完成しました。
新しいサイトの解説マップも作ったんですよ。新しいサイトが、どういう流れになっているのか、どこにご注目いただきたいのか、制作にかける思いや素材のことはどこに書いてあるのか、などなど詳しく書いてます。
サイトって、それぞれだから、「私のサイトはこういうの」って明らかにしたいと思って。はい。力(リキ)入ってます!
早速、お送りいたしましたので、ご住所いただいている方々へは、そろそろお手元に届いているのではないかしらん?よかったら、じっくりとご覧いただければうれしいです。
ご住所いただいているのに、お手元に届いてない方、たいへん申し訳ございません。完全なる私のミスです。パソコン、プリンター、住所ソフトの不調という三重苦に見舞われ、何も解決せぬまま、大半の方へは、力技で(手書きで)お送りしましたので、今回ポカだらけです。
本当に申し訳ないのですが、ご一報いただければ、すぐお送りします。ぜひよろしくお願いします。
また、ヨシダに住所は知らせてないけど、これちょっと見てみたいなって方、よろこんでお送りします。ぜひお知らせください。お気軽に!
すでに一通きたけど、紹介したいなどで、もっと欲しいって方、大歓迎です!飛び回ってよろこんで、すぐお送りします。ぜひぜひお知らせください。
以上、どうかよろしくお願いします。
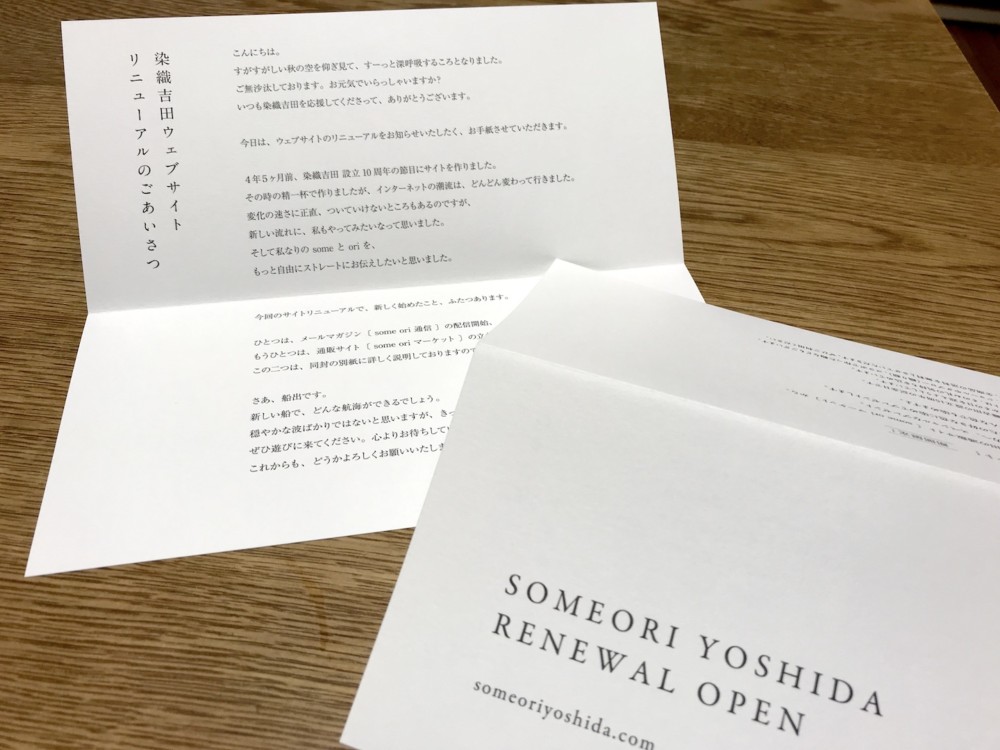
しかしなあ、、、しまったなあ、、、、ご挨拶状冒頭、
「すがすがしい秋の空を仰ぎ見て、すーっと深呼吸するころとなりました。」で始まるんです。
どこがやねん!!冷たい雨が降りしきってますやん!
これ、書いた日はそうだったんです。自然も物事も、どんどん移り変わっていくもんですねえ、、、
大木道代さんの染織展に行きました
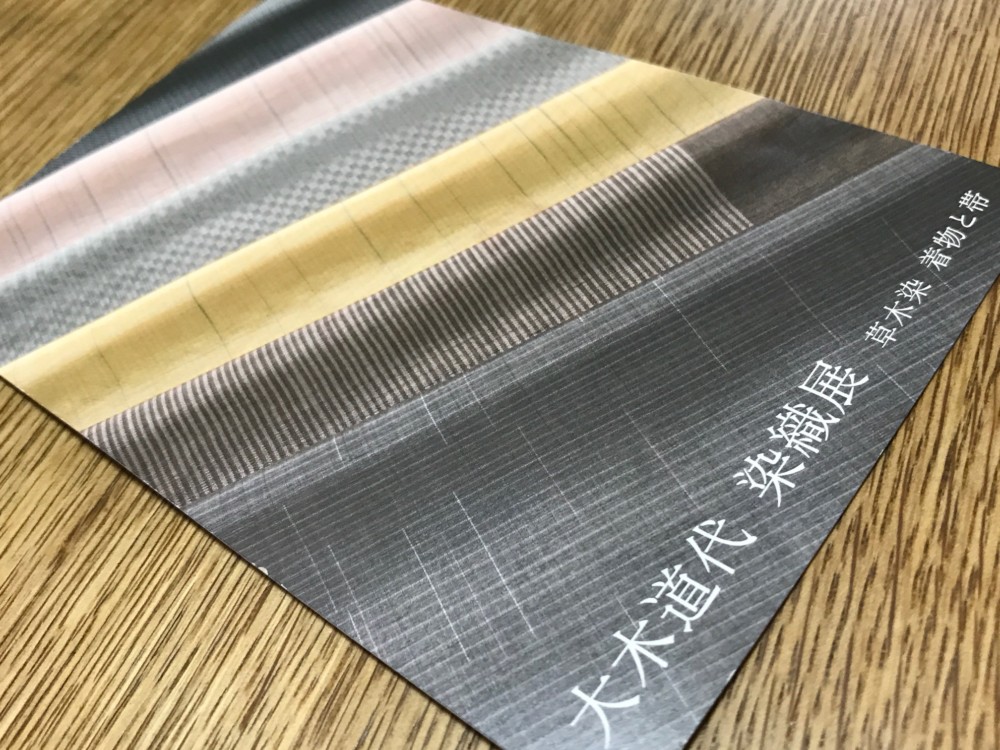
染織家の大木道代さんの、展覧会に出かけました。
そぼ降る雨の中、電車を石川町で降りて、いかにも古き良き横浜って感じの山手の急勾配の坂をぽくぽく登りながら、この道の先で本当にいいのかなと思った頃、そのギャラリーはありました。
あ!大木さん、お久しぶり!
自作の着物と帯をお召しの大木さん。着物姿を拝見するのは初めてでしたけど、とても自然で彼女らしかったです。
お作品は、絹糸を草木染めで染めて、織っていらっしゃるのだけど、きちんとした仕事を淡々と積み上げた、気持ちの良いものでした。こういうのが一番いいのよねって思った。普通そうだから着やすいし、よく見ると決して普通じゃないのです。縞の入れ方や絣にちょっとした工夫がしてあって、心にくいのです。

大木さんは、昨今、近しくしていただいている織り仲間です。織り続けるには、横のつながりもとても大事で、それ深め合ってます。って、私は教えていただいてばっかりで、恐縮しきり。大木さんの実力、たいしたもんです。
*会場は小さいながらも、モダンなギャラリーでした。写真は1階から2階を見上げて。
*大木道代染織展は、石川町のアートギャラリーATHLE での開催ですが、今日が最終日でした。
ただつらつらと
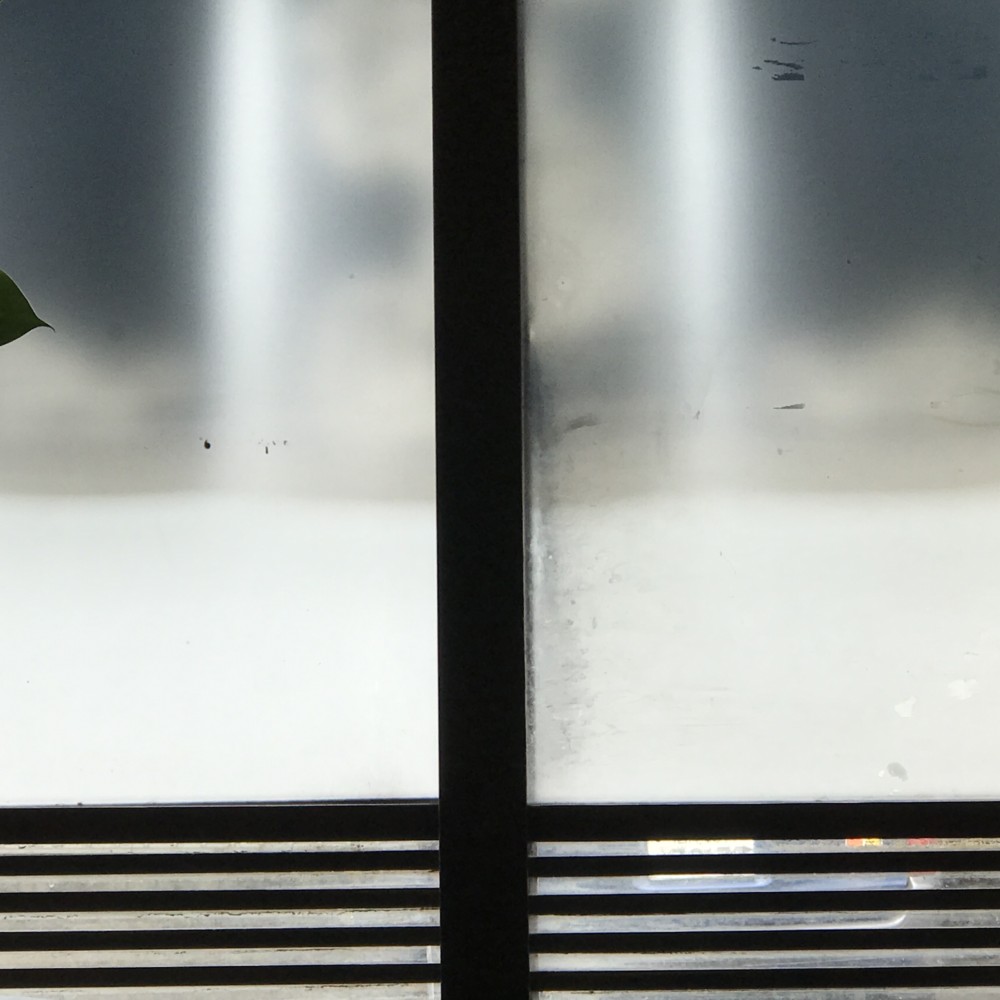
仕事中はラジオを聞いていることが多い。NHKの朗読の時間がお気に入り。今は、夏目漱石の坊っちゃんの朗読を楽しみに聞いている。ふっと思ったは、その「坊っちゃん」というタイトルの秀逸さ。このストーリーが、「坊っちゃん」というタイトルなのか。
そっか、なるほどな。主人公の、若さ、無垢さ、無鉄砲さが、この一言で表現できてる。
夏目漱石、さすがだな。お札になってただけのことはある。
ラジオでは、以前、太宰治の朗読もやってて、それも大変面白かったけど、太宰はやっぱ、お札にはならんだろうな。小説家としての実力は勝るとも劣らないのじゃないのかなと思うけど。なんだろうね?好感度?私生活??
100年後には、我々世代の方がお札になるのかしらん?どういう基準で?ノーベル賞受賞者とかかな?山中伸弥さんとか一万円札にぴったりそうね。笑。ま、お札になりたいとは思っていらっしゃらないでしょう。
*あ、100年後はきっとお札ないですね。電子マネーと、まだ見ぬ新たな何かで決済しているでしょうね。
*NHKラジオの聞き逃しサービスで、朗読も聞けますよ。このページ。下の方で、坊っちゃんも。
*ちょっとググったら、夏目漱石って、49歳で死んでるんだ!がーん。私の歳だよ〜〜〜。あれだけの仕事を残した人が死んだ歳。
*写真は、以前入った食堂の磨りガラス。
クラクラ〜〜〜
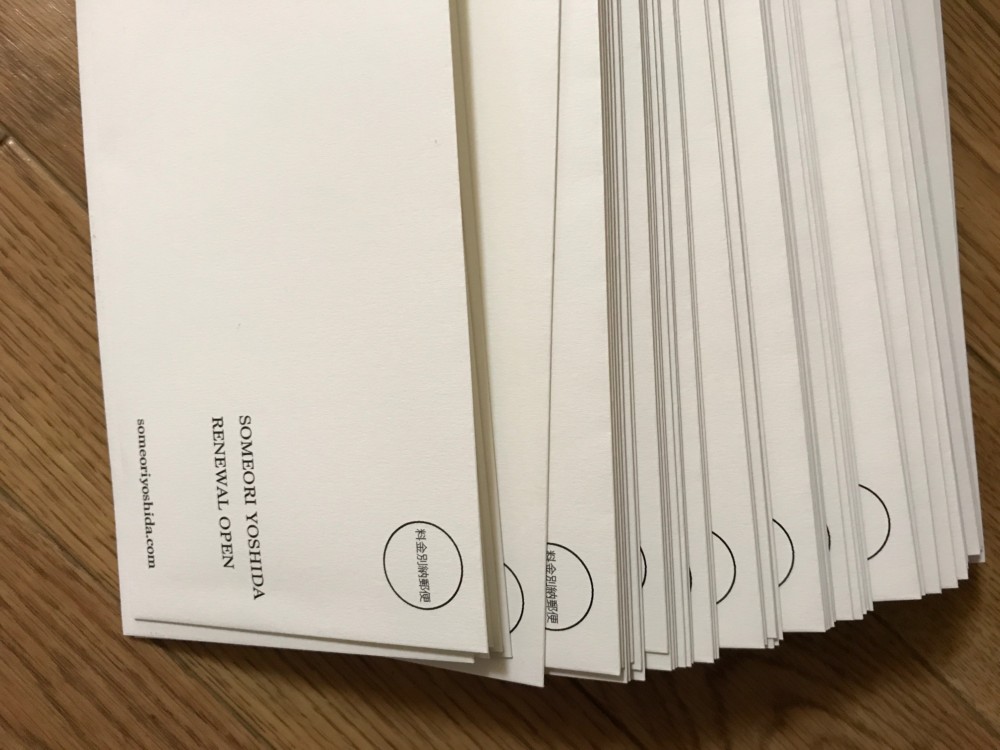
えっと。。。近況報告です。頭がいっぱいいっぱい、クラクラ状態が続いています。ええ、ここんとこ、ずっとクラクラなんです。
ここを読んでくださってる方は、私が先ごろウェブサイトをリニューアルしたってことは知ってくださってると思います。はい。8月はパソコンにかかり切りで不健康な夏を過ごし、サイトのリニューアルに明け暮れました。で、やっとやっと9月のはじめにオープン。
それが一段落したと思えるいま、ホッとできてると思いきや、思わぬ底なし沼にはまってあえいでおります、、、
せっかくリニューアルしたのだから、広くお披露目したいと、挨拶状の準備を進め、やっと校正に踏ん切りをつけ、印刷に回してもらうところまでいきました。
で、ひと足先に出来てきた封筒に住所印刷をしてしまおうと、格闘しているこの数日、、、、
住所録に使ってるファイルメーカーというソフトの設定に苦難し、(なぜか偶数回だけ印刷するという、わけのわからなさ)
封筒に印刷したい「料金別納郵便」などのデザインに使ってるイラストレーター(というソフト)が、突如、保存できないという前代未聞の不具合を起こし、(保存すると毎回強制終了する)
いつも使ってるプリンターがいうことを聞かず、
SOSを出した友人が送ってくれた(これは素早くて感謝!)、ずっと使ってないという同機種プリンターにドライバなどインストールし、動いたと思ったら、色がかすれた状態で、インクを替え、クリーニングしたら、ますますかすれ、あの手この手でクリーニングを繰り返すも、先は見えず途方にくれ、
仕方なく元のプリンターに戻るも、ときどき気まぐれに動くだけ、、、、、
(その上、マックが瀕死で、アイフォンの通話が途切れ途切れ、、、)(アイフォンはアップルさんにみてもらったのだけど、不具合発見されず、、周りがマンションだらけなのがダメなのかもと、、、そんな、、、)(パソコンはアップルケアの電話のお姉さんのおかげで、持ち直すも、いつ何が起きてもおかしくない状況です、と言われ、、、)
(その上、醤油と味噌と米が切れそう、、、、)
というのが近況であります。
ああ、もうすぐ挨拶状は印刷屋さんから直送されてくるはず。それまでに、宛名印刷、どうにか終わらすぞ!先は長い〜〜。

腹が減ってはいくさはできぬと、骨つき豚バラと大根を煮ました。ええ、現実逃避です、、、。(醤油は以前作った、ニンニク醤油を使い切る)
熊本に帰ってました

今日まで、熊本に帰ってました。なんと、中学校の卒業後37年の同窓会でした。台風直撃の予報で、羽田に着くまでは、飛行機、飛ぶのかドキドキでした。飛ぶと聞いて、思わず乾杯。(午前中から缶ビール)。台風は少々それて、我々にとってはありがたいことでしたが、代わりに直撃を受けた地域の方には、なんともお気の毒なことでした。

私の通った熊本市立城南中学校は、当時11組まであって、一学年450人以上の生徒がいました。当時だって、知らない人はたくさんいて、まして、卒業後一度も会ってない人が大半です。先生だって、私のようなひねくれ者のこと、覚えているはずがないと思っていました。
知らない人はいっぱいいましたが、、、まあ、面白いこと、面白いこと。37年が一挙にどこかに行っちゃった。
一年生の時の担任の上妻先生に、お忘れでしょうが、、、と挨拶すると、なんと覚えててくださいました。その上、「可愛かった!」と。当時は生意気で申し訳なかったです、、、と続けると、「それが可愛かった」と。
へ?可愛いなんて、ほとんど言われたことないセリフ、、、。13歳の私、絶対可愛げなかったよ。自信ある。それなのになあ。

中学の時のつながりというのは、独特なもので、いいものだなあと思った。公立の普通の中学だから、なんの選別もされてなく、いろいろ混じっているのが、なんとも心地よかった。それ以降のつながりって、分かれるものね。私だって、相当かたよった人間関係の中で生きているし。自然に生きているつもりで、自然にかたよる。ちょっと変だなあって思った。

着物で参加しようと思いましたが、台風のため断念。洋服だったおかげで(?)ムリなく3次会まで参加して、午前様で親の家へ帰りました。

一番上の写真は、熊本市立城南中学3年11組の面々。江尻先生を囲んで。2番目と3番目は、一泊旅行した天草の夕日と朝日。4番目は、熊本現代美術館で観た、坂口恭平さんの作品。5番目は旅のお供。
リニューアルオープン!

本日、染織吉田は、ウェブサイトをリニューアルオープンいたします!パフパフ!
なんだか、とっても感無量です。
思い起こせば、今年の春浅い、まだ寒い頃、私は、自分の今後の方向性を思い悩み、サイトをリニューアルして、ウェブショップを始めた方がいいのではないかと思い立ちました。
それから、ずいぶん悩んで、何人かの方々に相談させていただき、心からのアドバイスと励ましを胸に、決心して、突き進むことにいたしました。
それから、なんだかんだありました。今回のリニューアルも、山形のアカオニさんの素晴らしいお力ぞえあってのものなのですが、自分でする作業量もそりゃー膨大でして、パソコン、カメラ、キーボードで打った文章、もう見るのもやだってくらいです。
しかし、私は思います。
サイトを作る、またそれをリニューアルするっていいですよ。特にモノづくりの皆さんにおすすめしたい。どうしてかというと、否応なく、自分を突き詰めるのです。自分のことや、自分が作っているもの、どうしてそれを作っているのか、なんのために作っているのか、自分はどうなりたいのか、また作ったものをどう羽ばたかせたいのか、、、さらにそれをどう繋げるの?生きると作ると伝えるが、ガチンコなんですね。
ああ、やれやれ。サイトリニューアルして、疲れている暇はないけど、ああ、機織りしたいなってのが正直なとこ。この10日ほどは、パソコン漬けだったから。ぼちぼちやります。
どうか今後ともよろしくお願いします。
七緒に載った!(ちょっとだけ)
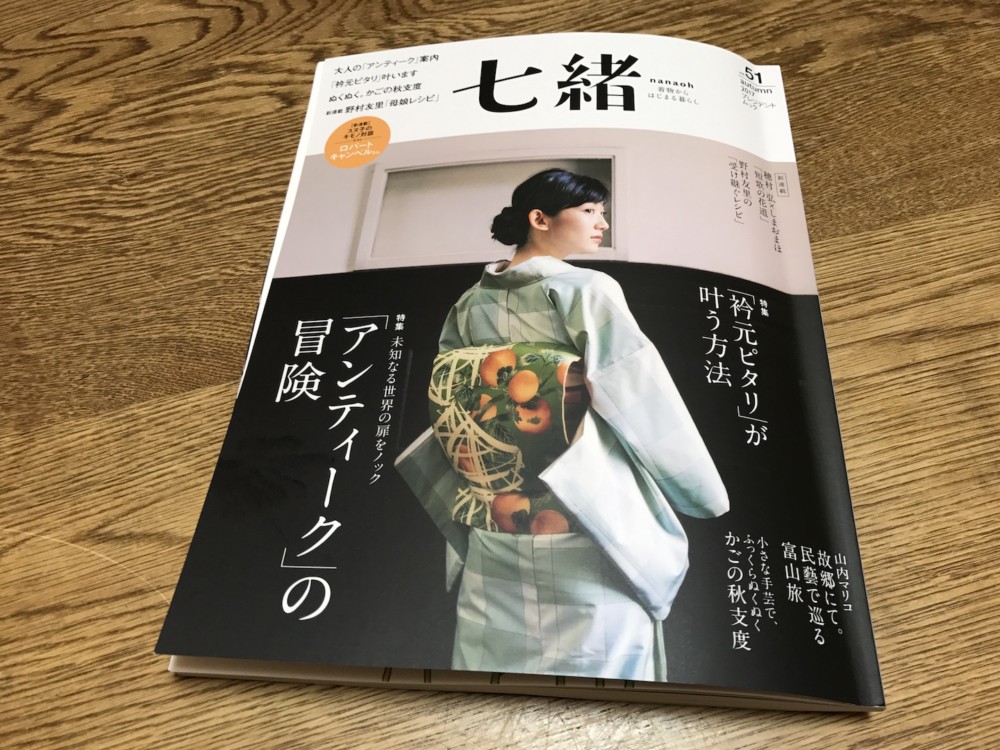
人気の着物誌「七緒」の最新号(2017 /秋号)が発売されました!うふふ、ちょっとだけ載ったのですよ。「衿元ピタリ。駆け込み寺」という特集で、大久保信子先生の生徒役で参加させてもらったのです。
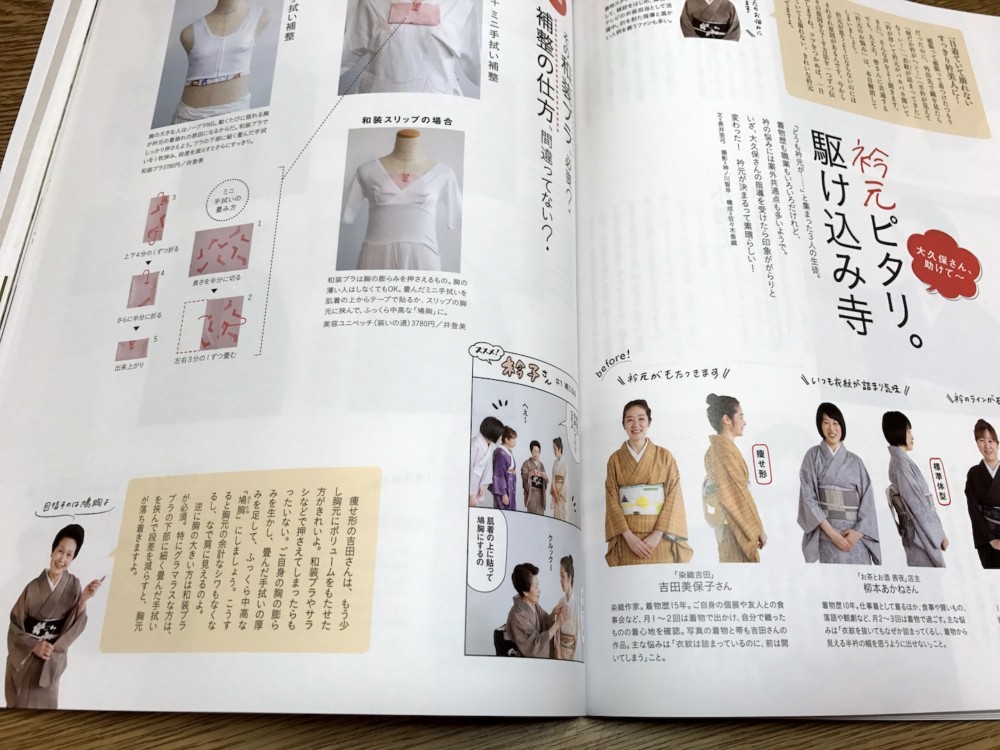
ほら、このページ。びっくりなことに、私、「痩せ型」の生徒役なんだよ。え、ほんと?普通体型のつもりのなのだけどなあ。
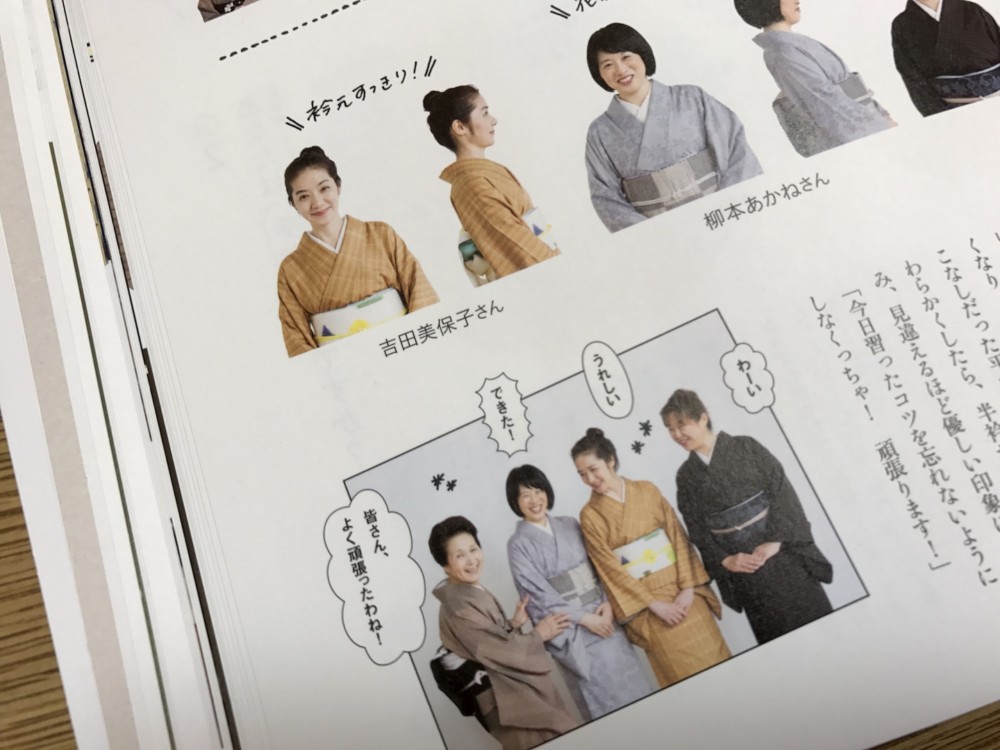
着物スタイリストの第一人者、大久保信子先生のご指導を、直接受けられるとのことで、ホイホイとうれしく参加させてもらいました。
大久保先生、さすが。おきれいで、お若くて、ハキハキ的確なご指導。みんなに愛され慕われるお人柄。すっかりファンになりました。さあ、習ったことを実践できるか、試されますなあ〜。がんばれよ〜〜。私〜〜〜。
生徒仲間の、和裁士の平山留美さん、お茶とお酒の茜夜店主の柳本あかねさんとご一緒できたのも収穫だったなあ。
平山さんのご活躍は、着物の世界にいると、自然に聞こえてきて、一方的に存じ上げていたのだけど、まあ、本当にすごい方です。やるか、やらないかの二択の人生、やる方を、バンバン選びとってる方です。じっくりお話できて、とっても励まされました。私もやる方!
柳本さんは、なんと、私が15年くらい前に、佐賀で展示したのをたまたま見てくださって、それを覚えてくださっていたのです。ビックリ!手織りってのと、私の名前と、印象的な色使いってことで、「あ、あの時の、、、」って思い出してくださって、当日言われ、驚愕、、、。ああ、やり続けていると、誰かが見ていてくれるのね。うるっときたよ。ご縁を感じてしまいました。
7月初旬の暑い日、二日にわたって、エキサイトした撮影でしたが、それがとうとう発売され、ああ、一区切りだなあって思う、しみじみの秋の夜です。
今度こそ!
 ブログのテスト投稿、こりずにもう一度。ほんと、パソコン、iPhone、難しいね。
ブログのテスト投稿、こりずにもう一度。ほんと、パソコン、iPhone、難しいね。
ここで投げ出さず、一歩一歩、歩くのみ。壊したら直してくれる人のいるありがたさ。
テスト投稿、第三弾

この写真は、うちのワンとニャンとビョンです。かわいこちゃんたちです。
さっきのテスト投稿は、どうも失敗でしたね。今度はいかに⁈
デジャヴ城主
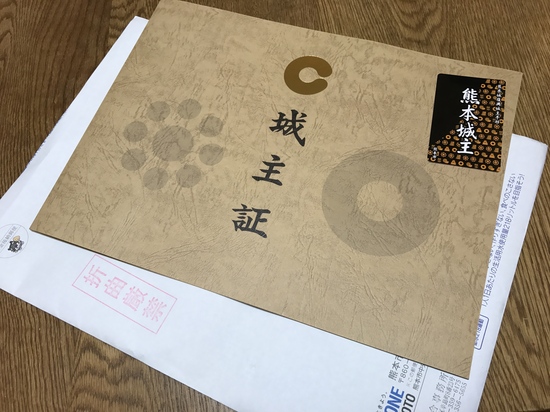
つい先日のこと、玄関のピンポンが鳴り、郵便屋さんに大きな封筒を手渡された。見たことあるぞ、この封筒。デジャヴ?
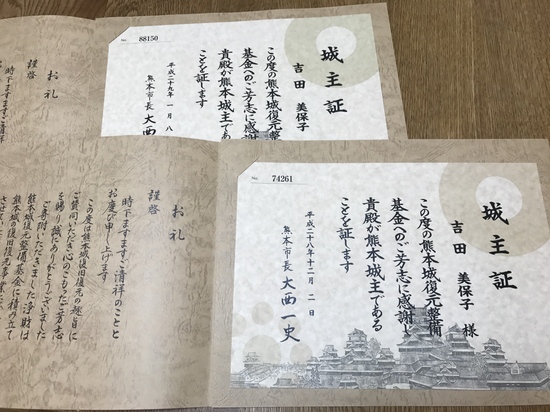
開けたらもっとデジャヴ。デジャヴというか、おんなじじゃん。2枚目?
確かに、寄付は2回したけど、2回目は10万円以下だったので、熊本城主手形のカードだけ、来ると思っていたよ。

2回目の寄付は、昨年の個展のあと、主に、このブログをお読みになっている方に、お買い求めいただいた分の、10%を寄付させていただいたものです。そのおりは、本当にどうもありがとうございました。おかげさまで、熊本城の復興も始まってるみたいです。ふるさとに動きがあるのがうれしいです。これからも、あたたかく見守ってください。
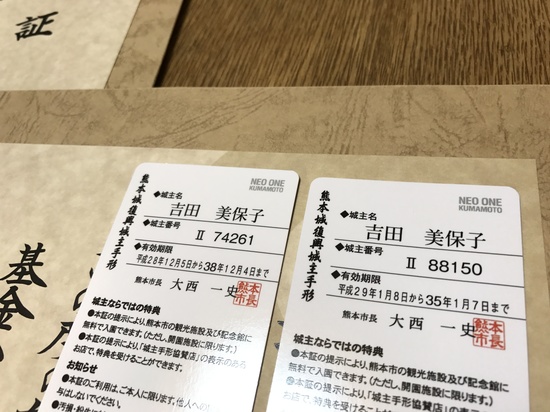
全く同じと思ったけど、有効期限が違う!寄付金が多い方が、有効期限が長い!!おお。特典(熊本市立の観光施設が入場無料)も金なりってことなのね〜。
朋百香さん、京都タロット。

今日は、画家の朋百香さんのところで「京都タロットの会」開催されるとのことで、おじゃましてきました。朋百香さんが描かれたタロットカードの原画も展示され、タロット占いもしてくださるとのこと。ちょっとオシャレしたく、今年は単衣を着てないじゃん、と引っ張り出して着始めましたが、暑いのとタイムアウトで断念。Tシャツにスニーカーで出かける。
朋百香さんは長平庵という素晴らしい場所をお持ちで、その空間と朋百香さんの絵がマッチしているのが、素晴らしかったです。あと、点数の多さと描き込みの緻密さに恐れ入りました。描くエネルギーに満ちているのです。
生まれてはじめてのタロット占いは、京都からお越しの岩倉ミケさんに占ってもらいました。不思議に痛いところつかれ、ズキっとくるんですよね。男っぽいカードばかりでました。ガシガシ働く運命みたい、、、、。それが幸せってことね、、、、。人生を全うしましょうかね。
その後、朋百香さんの墨の作品なども観せていただく。いつか帯にしたいと。元々が作品だから難しいけど、チャレンジし甲斐がありますな。やりたいです。
帰りは、イラストレーターの岡田知子さんと一緒になり、いろいろおしゃべりしながら電車に揺られたのも楽しかった。もう30年も前、高校の時、友達と一緒に帰ってる感じした。
今日はこんな日

今日は、久しぶりに染織をしない日だった。

美容室に予約を入れていたので、表参道へ。生まれて初めて、くるくるパーマをかける。あら、結構好きだわ。年相応に大人っぽくなったような、、、。

パーマ代を払ったらお金がなくなったので、コンビニでおにぎりを買って、歩道の柵に座って食べる。お茶は水筒を持ってる。この辺、旅行者だらけだから、きっと私も、アジア系一人旅に見えたに違いない。

その後、観たい展示がふたつあったのだが、検索したら、なんと両方とも定休日。影山秀雄さんと坂口恭平さん。残念。月曜トラップだなあ。

これからどうしようかな?ひらめいたのは、明治神宮の清正井(きよまさのいど)。ずっと以前に一度行ったきりだ。静謐な空気のある場所。清正公のスピリッツが流れているのかな。

清正井めあてだったのが、花しょうぶがちょうど見頃だった。井戸から流れでた清水が、花しょうぶ田を育てているのだ。

井戸は、以前来た時より、水量が少なく、ちょっと濁ってた。最近、雨が少ないからだそうだ。

その後、明治神宮に参拝して、来た道を戻り、表参道をふらふら、ルイ・ヴィトンのギャラリーに寄り道。ダン・フレイヴァンというアーティストの展示をしてました。

現代ぽいなあーと思って、ふとキャプションを見ると、1960年代の作品。50年前!私の生まれた頃の作品なのか。よく分からんと思って観てたけど、50年たって古臭くないというのは、すごいな。

さらに、ふらふら歩いて、半蔵門線に乗って帰りました。
織、激アツ、TOKYO
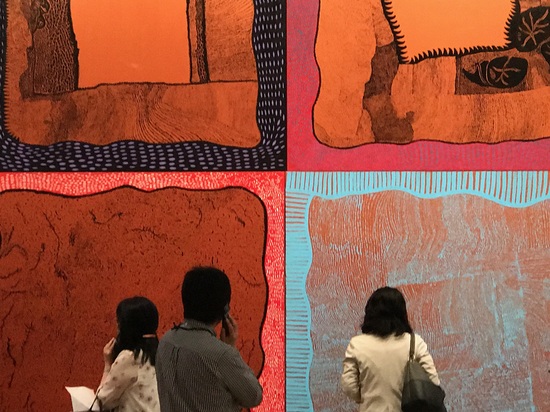
今、東京は織物が熱い!
今日は午後遅くからお出かけしました。
まず、青山八木さんで小島秀子さんの個展へ伺って、次に、南青山のイトノサキさんでの企画展拝見し、さらにギャラリーcomo さんで開催中の下地康子さんの個展へお邪魔してきました。熱い熱い、それぞれすごかったよ!
書いた順は、回った順。布好きの方には、ああ、あの青山墓地突っ切るコースで回ったわねってお分かりの方もおいででしょう。
気持ちの良い雨上がりの夕方、都心の緑の中や、都会なのにホッとする空間を歩き回り、力強い布たちを見ました。なんで、糸を染めて、布を織るだけで、こんなに強いものが生まれるかな?すごいね、織り手の力量だね。素晴らしかった。

小島さんと下地さんのお作品は、先日出かけた、国展でも拝見しました。国立新美術館のでかい部屋で、清々しさを、放っていました。
写真は、その時新美術館でもう一つ観た、草間彌生展で撮ったもの。織の展示会は撮りにくかったので、こちらを掲載。
草間彌生展、よかったわー。混みすぎて唖然としたけど、ここまですごいとは。どの時代も、とにかく、とにかく、やりきってる。私はニューヨーク時代の、白いでかい絵がすごく好きだった。
小島秀子展は、5月20日まで、青山八木さんにて。
「自然布と大人の半幅・夏衣」は、5月27日まで、イトノサキさんにて。
下地康子展「ウブスナ」は、5月23日まで、comoさんにて。
国展は、すでに終了しています。
草間彌生展は、5月22日まで、国立新美術館にて。
着物美人ですって!

先日、おたすけくらぶさんのオフ会に参加したおり、楽しいイベントがありました。カメラマンの山中順子さんに写真を撮っていただいたいのです。私はTさまと一緒にパチリ。その写真が送られて来ましたよ。
楽しそうね〜〜〜
私が手に持っている合財袋、ご記憶ある方いらっしゃいますかーー?

そうです、これです。善林英恵さんに、私のイメージで作っていただいた合財袋です。
うふふ、この写真だと帯がちょっと隠れてますね。帯と一緒に見て欲しいんだけどな。
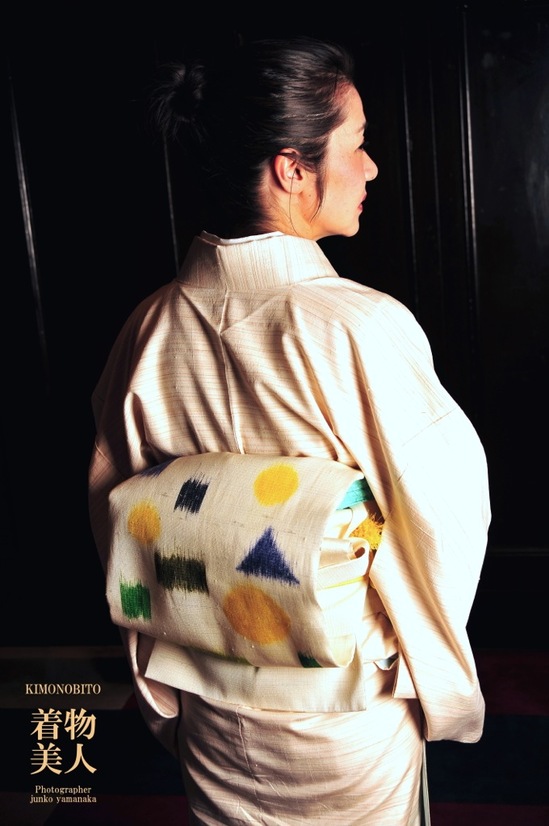
ほら、合財袋と帯、お揃いなのよ。
帯を作るときは、相当量の試し織りをしますので、資料として残す分以外は、合財袋やタブローやトートバッグの材料となります。
もし、帯のonly only でご注文いただいた際、ご相談いただければ、お揃いで作ることも可能です。お揃いって、なんか、気分上がりますよ(実証済み)笑。よかったら、お気軽にお問い合わせくださいね。
曜変天目をみたっ!その二

はじめて観た曜変天目茶碗の第一印象は、「まあ、お地味だわ」ってもんでした。小さいんです。抹茶茶碗の大きさを想定してると、ガクッと来ます。ご飯茶碗より小さいよ。それに、よく並び称される油滴天目が、ピカピカしてますので、そんな感じを思っていると、ちょっと見はマットな感じなので、アララっと来ます。
でも、近づいてよく観てみると、そこは宇宙への入口でした。お茶碗の内側は、宇宙のはじまり。そこから果てしない無限空間へ。「きおさま」のonly onlyの帯「Little Cosmos」(リトル・コスモス)を作っていた頃に、画像は何度も何度も観ましたが、まさに本当に宇宙です。
まずは滞在時間5分くらいで、後ろ髪ひかれながら後にし、「茶の湯」展の会場全体を見てしまいます。何しろ、お宝がザクザク出ている展示会なので、見なくちゃならんものが、いっぱいなのです。
お腹いっぱいになりながら、全体を見てしまった頃、4時半になりました。新しく入場することはできない時刻です。会場入口に戻ると、人はガラガラ。しめしめ。もう一度、心を落ち着けて、曜変天目にソロリソロリと近づいて行きます。
目的地の周りには人がまばらにいます。このお茶碗を目当てに出かけて来た人たち。ご同輩。
私は、ガラスケースの前で、おもむろに首から下げている単眼鏡を目にあてて、ピタッと静止。息を殺して覗きます。ピントを合わせる。合った瞬間、うううっわーー。こりゃ、一体なんなんだ。宇宙ってこんな?吸い込まれるってこんな?想像の宇宙でなくて、本当の宇宙だ。
単眼鏡で観ていると、世界は、曜変天目と自分のみのような錯覚におちいります。一挙に別世界です。
この体験がすごいのよ。単眼鏡なしに普通に観ていると、どんなに集中しても目の端にいろいろ入ってくるもんね。それが一切なく、丸く見える被写体と私だけ。忘れず持ってきてよかったよ。(単眼鏡ってのは、よく陶芸や仏像の展示会でマニアのおじさまなどが、使ってる黒い拡大して見るヤツ。双眼鏡の人もいる)
で、曜変天目は、内側もすごいけど、外側もすごいわって思った。ちょっと離れて観て、その形の完璧さにやられた。小ぶりで何気ないけど、どこから観ても完全に完璧。うーん、うなるしかない。
あっという間に閉館時間になり、追い出されましたが、すごいものを観せてもらいました。こんなすごいの1600円の入場料で観れるってのはお得だわって、損得勘定しちゃいかんけど、なんか、平和っていいなって思ったよ。
*写真は上野の森の新緑。
*この展示会は、6月4日までですが、曜変天目の展示は、5月7日までです。ご注意を!
曜変天目をみたっ!その一

先日の事ですが、東京国立博物館で開催中の「茶の湯」展へ行って来ました。
この展覧会、大変に前評判が良く、混雑必至と聞いていたので、行く気になれないでいました。人混み苦手なもので、、、。が、つい最近、なんと、あの「曜変天目茶碗」が出品されているという噂を聞きつけました。これは行くしかありません。それも、曜変天目は、会期前半のみの展示。急げ!
なんで私が、こんなにも「曜変天目茶碗」を観たいかと申しますと、それは、2015年に取り組んだ、「only only きおさまの帯」にちなむからです。あまりに偉大なテーマに、恐れおののきながら取り組んだよなあ。3つある天目茶碗(どれも国宝)の話になった時、きおさまが、「同じ国宝でも、静嘉堂文庫の曜変天目は格が違う」っておっしゃられていたのを思い出す。こりゃ観なくちゃよね。(制作ノートはこちらにまとまってます→☆)
実はその時、実物を観ないままに作りました。その直前に、静嘉堂文庫で出たのですが、見逃しまして、、、、だって展示期間、ちょー短いんだもん!
それ以後は、拝見できる機会には恵まれませんでした。そんな折に巡ってきたこのチャンス。今度こそ見逃さないぞ。混んでようと、なんだろうと、駆けつけるのだ。
で、東京国立博物館に着いたのが、午後3時半。閉館は5時。1時間半しかない。それで、前半の1時間で、会場全体を見て回り、後半の30分で「曜変天目」とガチで向きあおうと戦略をたてました。
会場に入って、とにかく、とにかく「曜変天目」へ。まずひと目この目で、、、。第1室の奥の方にありました。人が動けなくなってるので直ぐわかる。その手前には、大阪の東洋青磁美術館の「油滴天目」が!おお、お久しぶりです。これは3度目。
そして、その奥に、曜変天目がありました。
(続く)
*写真は、新緑の上野の森
布団屋のおっちゃん
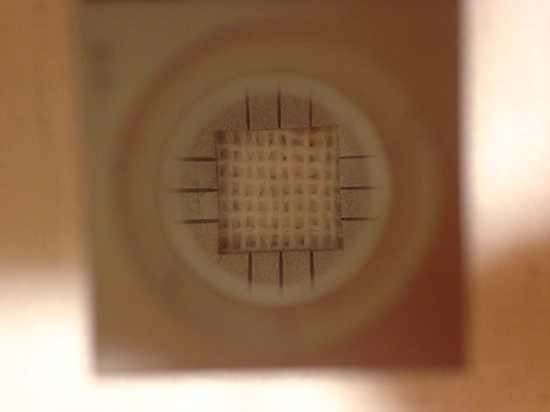
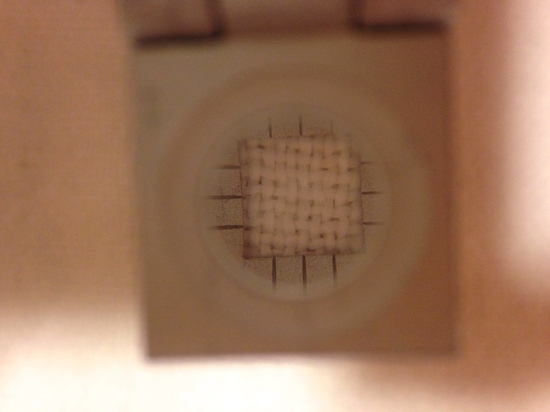

とっても驚き、うれしいことがありました。この前の日曜日、こだわりの布団でちょー有名な、大阪の「睡眠考房まつい」の松井さんご夫妻が、我が家にお寄りくださったのです。びっくり。なんでも、東京のお客様へベッドの配達の途中だそうです。私も小さな注文はしていたので、その配達もしてくださったのだけど。駐車の誘導に外に出た時、「なにわナンバー」が、なんか、うれしかったな。大阪を朝6時に出たそうです。
うふ、実は私、もう10年以上も松井さんのファンなんです。眠れないで悩んでた時、ネット検索で知って、ブログなど読み漁らせていただきました。著書の「寝たら治る」も読んだし、その後、少しづつ買い揃えて、現在、使ってる布団は、駱駝敷き、エアミール、おっケイ(オーガニックコットンケット)、おっパア(オーガニックコットン敷パット)。その上、体験宿泊ルームにも泊めてもらったことあるんだよ!
松井さんの何がすごいって、良いものをとことん突きつめ、身をもって検証し、売るだけでなく、その使い方もコツコツ広めていらっしゃること。本当にやりきっていらっしゃる。ここまでするかっていつも思う。
今回も、おっパア(オーガニックコットン敷パット)をいただいたのだけど、なんと、洗濯ネットが付いてきた。気持ちよく熟睡するためには、せっせと洗濯機でガラガラ洗うがよろしってことなのでしょう。以前別の買い物した時は、粉石鹸が付いてきた。化学の石鹸でなく、これで洗うのおすすめよと。頭で考えるだけ、口で言うだけ、手で書くだけでなく、行動する方だ。
駱駝の敷き布団は、真夏の暑い日に自宅で洗うのを推奨されてます。敷き布団を洗うなんて、思ってもみなかったよ。獣毛だもね。洗えるよね。なんか、当たり前のことなんだけど、目から鱗だわ。気持ちよく使うには、いいものを選び、自分で使いこなすってことか。気持ちよく生きるってことそうなのかも。
たぶん、いまどき布団を買う時って、大型スーパーとか大型家具店とか、そう言うところの通販とかで買うんじゃないかな?そして、適当な時に買い換える。潮流としてはそうだよね。町のふとん屋さんで買わなくなったよね。うちの近所のふとん屋さんも閉じられました。でも、松井さんのお店は、「超いまどき」なのよ。
それは一体なんなんだ?
松井さんは、自分がいいと思うことを、ただ一心にたんたんとやってらっしゃるだけのように見えるのだけど、何か、動かぬものが動いた感じなのよね。動かしたのか、動いたのか?
ふとん売るのも、きもの売るのも、同じように、大儀な時代。松井さんに学ぶこと多すぎ。仰ぎ見る。
*写真(上と中)は、私の使用済みのオーガニックコットン敷きパッドを、織りで使う拡大鏡でのぞいたところ。4層構造になってるってことだったから、のぞいてみた。上の写真が外側に出る1層と4層、次の写真が中の2層。実は、長年使って、表層が破れたのだ、だから中がのぞけたし、買い直した。あはは。
一番下の写真は、松井さんのサイトから拝借したオーガニックコットン敷きパッドの断面画像。
これね、糊の付いてない綿糸で織ってるんだって。その上、4層構造の中の2層は無撚糸だと。うわーーーー、そりゃかなわん。私、よう織らんわ。大きな機械がゆっくりゆっくり織ってるって。切れて切れて、大変らしい、、、、。
いや実は、この説明がすごすぎて信じられず、拡大鏡でのぞいてみたわけです。そしたら、目が釘付けになってしまった。きゅーん。なんと愛らしい糸の結集なのでしょう!プリプリのラブリーな糸たち♡
その上、糸の太さとか、密度とか、聴力とか、そうとう研究されてますよ、これは。
おたすけくらぶさん、盛装オフ会に行ってきました

今日はお出かけ。「きものおたすけくらぶ」さんの盛装オフ会に入れていただきました。こういう華やかな場には、滅多に出ませんので、いい機会をいただきました。誘っていただいた方に感謝、おたすけくらぶさんに感謝です。
朝から、必死で髪と化粧と着付けして、やっとのことで出かけました。今日はまあまあうまく着れたと思ってたのだけど、旧知のKさんに帯と帯揚げ、直してもらった。。。(とほほ&助かった)
Tさんに「ヨシダさん、いつもから化粧すればいいのに!」と言われる。いつもそんなにひどいっすかね。ひどいんだろうなあ、、、今日は持ってるもの、全部塗ったくって行ったからね。盛装オフなのに着物はいつもの紬だから、お顔は精一杯。

これは、反物巻きゲーム。金屏風の前で、キレイな方々が、必死に白生地を巻くのです。私のテーブルから出場したHさんがなんと、準優勝!私にもおこぼれで景品が!!

会場は学士会館。いい建物だわー。よい1日、感謝であります。
お出かけ、本番

さあ、それで、ほうほうの体で着物をきて、駅に小走り。電車に飛び乗り、いざ日本橋へ。待ち合わせはコレド日本橋。和食のランチをいただくことになっております。
上の写真の7名がメンバー。みなさん、すてきです。
前列右が、ブログ上のお名前で神奈川絵美さん。お召し物は、再会がうれしい拙作「シスレーの居る風景」。
中央のキュートな方はtさん。なんと、来がけの電車でお声をかけてくださった。面識ないのに帯でわかったと!電車の中で「ヨシダさんの帯をしている人がいるなあ。あ!ヨシダさんだ!」。おかげで幸先いいスタートでした。
左は、みるさま。うふふ。締めてくださってるのは、「Spirit Of Green」です。可愛がってもらってる〜〜
後列右は画家の朋百香さん。ウェブサイトはこちら。かっこいいです。
お隣はrさん。お着物と帯留め、写ってないけどお羽織も、お義母さまから譲られたものだそうです。ものっすっっごくステキだった。それにお似合いだった。
一人置いて、左はmさん。お写真からはわからないけど、こちらもすてきな薄いピンクの牛首紬で、振りと裾に水が表現されてて、まさにお題の「魚座」と「春」にぴったりでした。ご自身は魚座ではないというのが、またツボでした。

拙作まとってる3人寄って。
右の帯、みるさまの「Spirit Of Green」(メイキングはこちらにまとまってます→☆)
中央のお着物、絵美さんの「シスレーの居る風景」(絵美さんがご自身ブログにお誂えの記録を書いてくださってます→☆)
左の着物と帯は、名無しのごんちゃんです。(実は帯の名前は「大反省帯」。大失敗してしまった帯を、仕立てで生き返らせていただきました)

お食事のあとは、デジタルアートを見に行きました。初めての体験。会場全体いい香りがするのです。まさに五感で楽しむアートですね。

ここに写ってるのは、たぶん私。

デジタルアートの出口で記念撮影。お食事の時より、リラックスして楽しんでるのがわかりますね。

これはその後のお茶。もっと楽しんでる〜〜〜
*写真はそれぞれが撮ったものを、tさんに送って、まとめていただきました。そこから、それぞれダウンロードするの。こういうの、私できないので、感心します。tさん、ありがとう!
お出かけ、着付け編
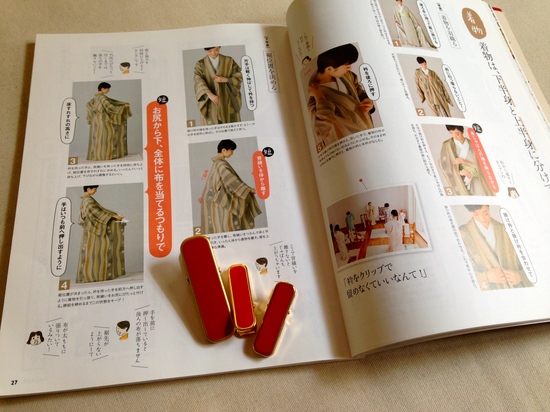
日曜日の朝、出かける1時間半前、着付けを始めます。1時間も見れば大丈夫なはずだけど、念のためと、着付けで疲れるので休むため(笑)。
着物を着てる私を知る人はみんな賛同してくれると思うけど、私は、ちょー着付けが下手。いつも出たとこ勝負で着ています。そして、いつも、かたわらに着物の着方のアンチョコを置き、それを見ながら、おっかなびっくり着ているのです。それは昔から、今もです。
数年前、そんな私を見るに見かねて、旧知のお客様が、七緒のバックナンバーを送ってくださいました。その号は、着付け特集で、自分で読んでためになったし、とても分かりやすくツボを抑えて書いてあるからと。この号は人気だったらしく、売り切れていて、アマゾンで新古本を探して取り寄せ、それを送ってくれたのです。感謝感激しました。
このお方は、まだ私が、注文制作をonly onlyと名付ける前から、着物と帯を注文くださり、育ててくださいました。事実、ものすごく助かりました。染織を続けていられるのは、買ってくださるお客様みなさまのおかげですが、その一翼をになってくださいました。
個展の前には、陣中見舞いに、小さな醸造元の特別に美味しいビールをお送りくださったり。お食事にも2度、誘っていただいた、、、自分では行けないようないいレストランで、本格的なディナーをいただいた。ワイン1本ペロリとあけたなあ。第一線ビジネスウーマンでもある彼女は、染織吉田の打ち出し方の相談にも乗ってくださった。。。
お客様というより、人生の先輩だった。最高にかっこよかった。
七緒を広げて、着物を着ながら、、、、思わず手が止まります。このお方の訃報を聞いたのは、2週間前。未だ、心の整理がつかずにいます。
お出かけ前夜

昨日の日曜日は、ランチのお誘いをいただき、久しぶりにお出かけでした。るんるん。
着物のお仲間に入れていただいたので、もちろん着物です。そして、せっかくだからと、ゆる〜いドレスコードがありまして、「星座」「魚座」「春」のどれかにちなもうと。大人のお遊びですね。
そのことはずっと頭にあったものの、日々の雑多に紛れ、準備ができずにいました。もう待った無しの、前日の土曜日の晩、コーディネートのために、色々ひっぱりだす私。着物と帯はすんなり決まります。だって、選択肢少ないもん。
帯締めは、菜の花の黄色。帯揚げは、鮮やかな青緑。ふむ、これで行こうか?課題のちなみものは「春」ってことね。どうかなあ??
うーーん、帯揚げの青緑が、若葉のようね。葉桜の季節ならまだしも。爽やかすぎじゃん?弥生三月の色じゃないなあ。

だったら、染める?白生地あるし。
というわけで、夜10時すぎ、いそいそと染色鍋を出す私。商品染める時は、緊張するけど、自分のだしね。ちゃちゃっと色を調整して、酸を入れて、ガーッと温度をあげて、ちょいと放置プレイしてる間にお風呂に入って。フィックスしている間に髪の毛乾かして。仕上げは翌朝ね。
はい、おやすみなさい。

というわけで、このコーディネートでお出かけしました。どうすかね?春らしくなった?
(ちなみに、上の写真の青緑の帯揚げも、自分で染めてます。私、帯揚げ染めるの、趣味かも。)
繭マスク、山鹿の花井さん!
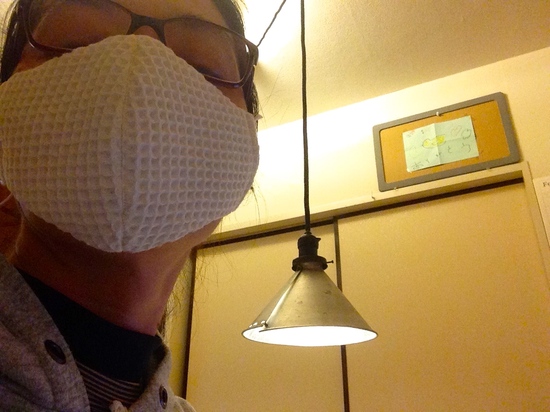
変な写真で失礼します。これは自撮りで、タイトルは「マスクする私」です。撮影場所は我が家で、後ろの壁に貼ってあるのは、姪のひなこが描いてくれた鳩サブレの絵です。
ご注目いただきたいのは、もちろん、ザ・マスク。
これは、昨年の12月に、熊本県山鹿市の養蚕農家、花井雅美さんが、我が家を訪ねてくれた時に、山鹿の織姫伝承塾で作っているものだと言って、下さったものです。私は、花粉症もなく、めったに風邪もひかないので、マスクってあんまり縁がないのですが、近ごろ、口内炎をこじらせ、口を閉じていたかったことから、おおそうだ、あの時、いただいた真綿のマスクがあるわと、つけているわけです。
それで、このマスクの良さに、メロメロ。マスク無しの普通の状態より、楽にいい空気吸ってるって感じ。マスクが結界にもなるのか、邪念もやってこず、目の前の仕事に集中できる。生産性アップの魔法のマスク!
布と布の間にはさんであるのは、真綿なんです。下の写真見て!これが真綿。すごいでしょ。繭を煮て、広げて、ふわふわの状態にほぐしたものです。真綿が、外の邪気を払ってくれるのかな???
(この写真は、花井さんのブログから拝借しました。ストーリー読むと、真綿のすごさがよくわかる。ほんと、お守りだね。)

で、年末に花井さんが、お見えになった時、このマスクがよく売れると話されたから、だったら量産したら?と言ったら、「いえ、真綿を大事に大事に、丁寧に丁寧にふわぁーっとほぐして、包み込むっていうのは、外注したらできないのと思うんです。だから、これは、仲間達でやるしかないんです」っておっしゃってて、それではビジネスにならんなあと思ったけど、今回、自分でマスクつけてみて、ああ、この愛情のあふれ具合は、外注できんなと思った。(私の周りでは、よく聞く話。私を含め、作り手、商売下手。そんなこと言ってられないが。)
この晩はとても楽しかった。夕方集合だったから、私は、お茶にもご飯にもお酒に合うように、鍋いっぱいのおでんを作っておいた。花井さんは、ずーっとお酒をやめていたとのことだが、今夜は特別と言って、たくさんお話をしながら、おでんをたいらげ、楽しそうに飲まれた。
*花井さんが、普段は飲まない理由は、仕事が忙しすぎて、飲んでる時間を節約するためと。私、己を省みる。。。。
山鹿の養蚕、目が離せません。
*花井さんサイト、お蚕ファーム→☆
When I wear this cough mask, I got totally concentrated on my work. This is the miracle mask, made by the silk from Yamamaga, Kumamoto.
友と地震とタブロー

今日、タブローをひとつ発送しました。お買い求めくださったのは、もう20年以上のお付き合いの、心の友です。彼女は今、和歌山県の奥の方に住んでいて、忙しくしているし、なかなか会えないのだけど、なんか、いつも繋がってるんだよな。
昨年秋の個展「清正公の陣羽織」展のご案内状は出したのだけど、もちろん来てくれるなどとは思っていない。私は元気でやってるよ、って近況報告のつもりで出している。
それが、その展示会はとうに終わったお正月過ぎてしばらくの頃、突然電話をくれた。熊本地震のお見舞いと、個展のDMのお礼と、寄付するとかヨシダちゃんらしい活躍しててうれしいよってことと、自分にも何かできないかってことだった。
彼女が言うには、ヨシダが作ったものを身近に置きたいと、それで、地震のことやいろんなこと、思うきっかけにしたいと。売り上げの10%の寄付にも今更ながら参加できないかと。
うん、もう熊本城への寄付はしちゃったけど、これからでも、もちろんできるよ!
それで、色々お話しして、ヨシダが作ったタブローを求めて、日々眺めたいって言ってくださった。で、選んでいただくのに、画像、サイズ、お値段など、メールすることを約束した。
そのメールのお返事が一ヶ月以上たってやっと来て、選んでいただいた上の写真のタブローが、本日、和歌山県に旅だったわけです。
電話で話した時に、10%の寄付先は、熊本城など大物ではなく、もっと小さく地道に活動してくださっているところにしたいねって話になった。
折しも、今、合切袋のコラボをしている善林英恵さんとも、今後、トートバッグなどでコラボしたら、売り上げの一部を寄付をしたいと話していて、その先として、アースウォーカーズさんはどうだろうと、ご提案いただいていた。
アースウォーカーズさんと言うのは、本拠地は宮崎県で、東北の地震では、子供のケアなどで、当初から現在までずっと活躍されている。熊本の地震では隣県と言うこともあり、いの一番に駆けつけてくださった。我が友人も、和歌山に移る前は宮崎にいた人なので、特にご縁を感じる。それで、ある程度、額がたまったら、アースウォーカーズさんに寄付することにした。

彼女が選んでくれたタブローは既成のフレームでなく、外枠も手作りしたもの。とってもオリジナル。だから、箱がないのよね。というわけで、箱、自作しました。
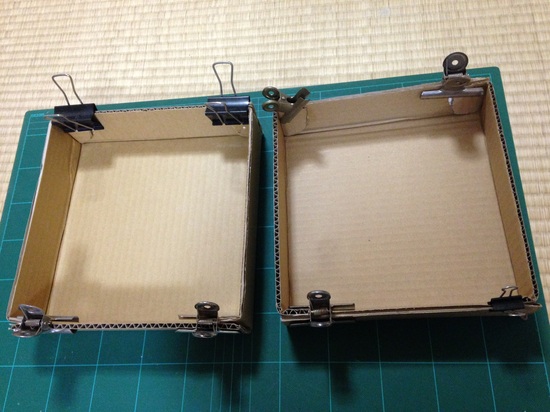
昔、NHKの教育テレビで、「できるかな」ってあったよね。知ってる?40代なら皆んな知ってるよね?50代の人も知ってるかな?30代も後半の人だったら知ってるよね?私、大好きだった。この箱、そのノリで作りました。私、今でもゴン太くんの大ファンです。
*売り上げの10%を寄付するというのは、熊本で開催した個展「清正公の陣羽織」展での試みでした。その後は継続できていません。(それはひとえに、売上高が不安定で、寄付する余裕がないと言う一身上の理由があります。情けなし、、)
しかし、もし、この友人のように、寄付したアイテムを身近に置きたいなど、特にあれば、ヨシダ、がんばります。どなた様でも、どのアイテムでも、売り上げの10%を寄付いたします。お手元に持っていただいるモノが、巡り巡って、熊本地震などの復興の一部になれれば本望です。寄付先は、ご相談に応じます。このページでご紹介したタブロー、プチマフラー、大麻のストールの茶色い方、などございます。そのほかにも新作ショールや帯やお着物もございます。お気軽にお問い合わせください。
Do you know old JAPANESE public TV program “DEKIRUKANA” means CAN YOU DO IT ?
Gonta-Kun is the main character for TV show. Almost all of my age range Japanese people watched this program regularly. I love Gonta-kun still.
影山工房公開講座
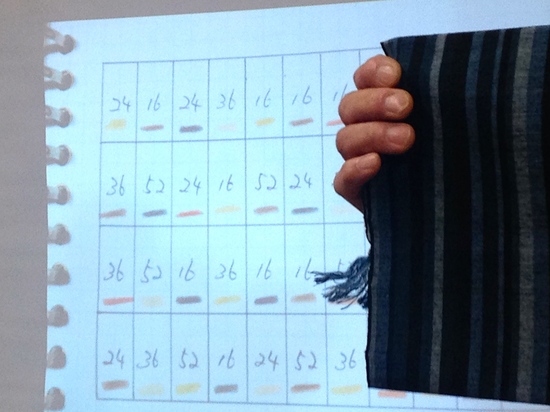
昨日は、影山秀雄先生による公開講座に参加しました。大変に大変に大変に、面白かったです。一日みっちりと、私の知らない織りの世界に浸ってきました。そうなんです。一番の感想は、私はなんと物を知らないんだろうっていうことでした。驚き!私、四半世紀ほど、織ってます。専業になって、14年。それなのに、なんと知らないままに来てしまったんだろう!!加えて、なんて、思い込みが強くて、頭を固定させているのだろう。あらら、私、もしかして頭でっかち?頑固?柔軟さが売りのつもりだったんだけどなあ。違うわ、私。ガチガチだったわ。大反省。
昨日は、「やたら縞を創る」と、「紬を織るということ」のふた講座を、受講しました。いつもの自分のやり方を、一歩踏みとどまって、よくよく見直して、もっとよくするための一投石、しっかりと投げ込んでいただきました。ものにするぞ!!!
いやはや。織りって本当にすごいね。無限大ね。きっと限定しないってことが一番大事ね。影山先生、本当にどうもありがとうございました。
* 写真は、やたら縞の乱数表について、説明くださる影山先生の手。この手でなんでも生み出すのね。
Yesterday I had the chance to have lectures and demonstration by Mr.Kageyama, great Japan kimono fabric weaving master. Deep and wide, I really frightened and moved to his way of making AYA, the most important basic technique to weaving. Oh my God, it’s totally deferent from my way. My technique is more normal, but his way is so established.
* もう何年も前に、ブログの英語バージョンもがんばると宣言しながら、ずっと怠けてました。今日、我が家に和紙作家のお客様が見え、近々ヨーロッパに行かれるとのことだったので、ご自分の和紙を広めるために、英語バージョンのサイトもやるべきだと力説しました。でも、私、全然やってないじゃーーん!反省し、慌ててアップします。
このブログをご覧の方で、もし、ヨーロッパ(イタリア、スイス、パリ、ロンドン)で、手漉き紙事情に詳しい方ございましたら、ご一報いただければ、その作家さんに繋がせていただきます。よろしくお願いします。
お出かけ

昨日は、久しぶりに都会の喧騒にまみれてきました。南青山、銀座、京橋、竹橋。やあ、都会だなあ。
まず南青山のイトノサキさんへ。いつ行っても気持ちいい空間です。今、私の帯も並べていただいてますのよ。私のかわい子ちゃんたち、店主のあびるさんに可愛がられながらがんばってました。ぜひ見に行ってやってくださいね。
それから、所用ありて銀座へ。伊東屋に寄り道して、空を仰ぐと、高架の向こうにLIXILが見える。さあ行こう。和紙の展示をやってるし、ちょっと気になる陶器の展示もやっている。本屋もチェック。
LIXIL のメインギャラリーでやってる「WASHI 紙のみぞ知る用と美」では、和紙のすごさに、恐れおののく。甲冑の下に着ていた紙縒りで作った肌着とか、素晴らしかった。実用のために極限までやる。同時に美が生まれる。そんな感じした。
それから、同じ階の小さなギャラリーで開催中の「美崎光邦展 -茫洋として- 」もすごくよかった。この展示会、この前、益子に行った時、ミュージアムショップにDM置いてあったのをもらってきて、我が家の「素敵なハガキやチラシを貼っとく場所」(上の写真)に貼って、ずっと気になってた。
DMからは分からなかったけど、作品はバーンと大きいの。青い色も清々しく、とても気持ちの良いオブジェだった。
作家さん、存じ上げない方だけど、好きだわ〜。陶歴拝見したら、お年、還暦はすぎてらっしゃる。やり続けている強さがあり、常に切り拓いている感がひしひしあり、仕事に乗っている感があり。すばらしい。

それから、竹橋の近美に、「endless 山田正亮の絵画」展に行きました。2回目です。金曜は夜8時まで開館しているので、ゆっくりです。
山田のストライプ、やっぱ、魅せる。ひきこまれる。目が離せない。山田が彼の代名詞となっているストライプを描いていた時期は、1960年代の前半だけなのか。たった5年でやりきったのか。
回顧展だと、初期には自画像などの人物画があること多いと思うけど、山田の場合は、静物画はあっても人物画はない。人には興味がなかったのか?それとも??
写真は、アトリエを復元したエリア。すごく整理整頓されたアトリエだったんだって。
夜に中央林間に帰ってきたら、雪が積もっていて、驚いた。
「endless 山田正亮の絵画」展をみた
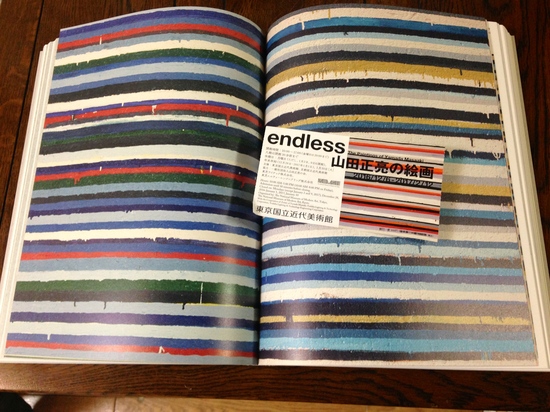
昨日のことですが、竹橋の東京国立近代美術館で開催中の、「endless 山田正亮の絵画」展を拝見しに行ってきました。この展示会、開催中とはつゆ知らず、旧知の「わださま」から、教えていただき、これは見逃せんと行ってきました。(「わださま」については、後日語らせていただきます!)
山田正亮のことは、大昔の美大生時代から知っていて、当時必ずチェックしていた懐かしの佐谷画廊で実物をみて、ものすごく感激した覚えがあります。その後、まとまった作品群を拝見する機会なくきましたが、久しぶりにお名前を聞き、つき動かせれるように行ってきました。
で、山田が、こんなに多作で、情熱的で、湧き出る血潮のようにエンルギッシュにバンバンバンと作品を世に送り出した作家だったと初めて知りました。有名なストライプは乗りに乗っていて特にすごいけど、それに行き着くまでとそれからもすごいのよね。展示の作品数もものすごくて、クラクラしました。あてられたってやつです。かつ、綿密な作品ノートも残されていて、情熱を支える冷静さも観てきました。すごい〜。一回じゃ受け止めきれんわ。もう一度観に行きたい。ちょーおすすめです。東京のあとは京都に廻るそうですので、関西の方もぜひ!
昨日は、本江邦夫氏による講演会があり、せっかくだからと参加しました。本江氏は元近美のキュレーターで、山田正亮とも近しい関係だったそうで、色々突っ込んだ話が聞け、面白かったです。
びっくりしたのは、山田の学歴詐称です。私、大昔、山田展で、経歴に東大中退って書いてあったのを見て、はあ、頭のいい人の描いた絵なんだって思ったの、今でも覚えているのです。それが、今回の講演会で、嘘だったって知りました。ショックだったのは、山田が詐称したことより、自分がそれを鵜呑みにして、色眼鏡で見ていたことです。私、経歴とか、所属とか、全く関係ないと思ってるのだけどな。深層心理ではそうではないのみたいね。自分のこと、色々考えさられた1日でした。
「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、3
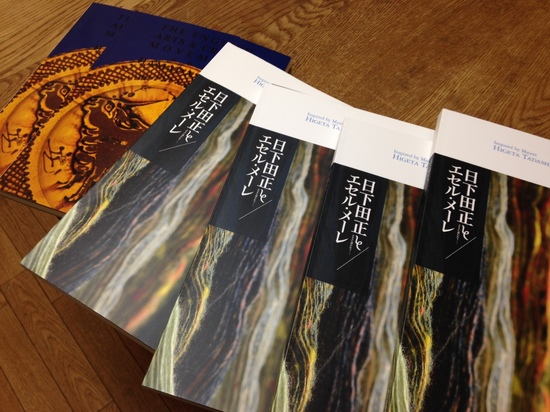
日下田正さん、とてもお優しい紳士で、素晴らしい作家さんでした。遠くから自分の展示会を見に来た熱心な人、というだけのことで、見も知らぬ私のことを、ギャラリーに再度招き入れ、ソファーに促してださり、お茶も出してくださいました。
年譜拝見すると、御年77歳。はつらつと明るく、柔和で、かつ、第一線で作り続け、発表し続け、生き抜いて来た強さを感じます。
私はここぞとばかり、聞きたかったことを、いろいろ突っ込んで質問させていただきました。率直に何でも答えていただき、大感激でした。
私がこの日、益子に来たのは、展示会の図録を送っていただいて、それをみて感激したことと、青田五良を彷彿としたということが理由だということも、お話ししました。青田の名前はよくご存知でしが、「上賀茂織之概念」は未読とのこと。
他にも、私が織の中でも平織りを特にしているなど話すと、「それがいいです。やっぱり平織りです。」などとおっしゃったり。(日下田さんの綾織もすごい。)織の工程の話では、糊付けに難儀しますねとおっしゃられ、深く深くうなづいたり。。。手紡ぎの和綿を経糸にも使っておられるのに驚いていると、「経糸に行けるように作ればいいだけのことです」とおっしゃられ、それはそうだけど、それが普通はできないのよと思ったり。
展示作品の中では、栃木県の依頼で、正倉院所蔵の、調庸布の復元したのが、何より一番難しかったと話され、正倉院のものと同じにするために、砧打ちするか否かで、悩まれた話など、大変興味深かったです。
先ほど、松本の森島千冴子さんの話が出ていたのを聞かれ、懐かしそうに、話をつがれました。曰く、大昔、高校を卒業してすぐ、織の修行に東京の柳悦孝先生の内弟子に入られていた頃のこと、松本から森島さんが訪ねて来られたそうで、日下田さんもお会いされたそうです。その時、お土産にくださった、信州のりんごの味が忘れられないと。もう60年近く前の話です。
まあ、なんといい話。私、この話、師匠の高野久仁子さんにも伝えますね。
日下田藍染工房で、あっという間の3時間ほどの素晴らしい時間を過ごし、美術館にとって返し、もう一度、よくよく作品を観て、いただいたご恩をエクスパンドさせるぞっと、図録をたんと買いこみまして、帰りのバスに乗り込みました。ああ、昼ごはん食べ損ねたなあ。
*「日下田正とエセル・メーレ」展に行ったお話は、これにて中締めです。またご縁がつながって続きが書けるよう、私も日々がんばります。
「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、2

陶芸美術館で、「日下田正とエセル・メーレ」展を見た後、まずはとにかくと思って、日下田藍染工房へ向かいました。予約も問い合わせも何もしていないけど、とにかく。
そこは美術館から歩いて5分ほどの、江戸時代から連綿と続く、今もせっせと仕事をする場所でした。多分、紺屋さんの典型ではないかと思うけど、玄関入るとすぐに大きな染め場があって、向かいはご家族の居住スペースと思うのよね。奥に抜けると、中庭。そう、干場です。干場を囲むように、型場や洗い場。それから、ギャラリースペースもありました。
ちょうどお昼の時分どきで、どうぞご自由にご覧くださいって感じになっていた。ギャラリーを覗くと、そこに織り機があった。わあ、ここで織ってるんだ!
ほどなく、織り手の方が戻ってこられ、色々お話を聞くことができた。藍染の益子木綿でショールを織っていらっしゃった。隣の大きな機は飾り布かな。売ってる物の値段の安さに驚いていると「うちの先生は、商売には頓着がないから。。」などとおっしゃりながらも、深い信頼と尊敬が感じられた。

ギャラリーを出てると、干場で作業中の染め師の男性一人。これまた、色々丁寧に教えていただく。「うちの母ちゃんも、織ってるんだよ、松本の森島千冴子さんというところで、修行して。」と。まあ、森島先生って、私が着尺を習った高野久仁子さんのお師匠さんです。私、お会いしたことはないけど、孫弟子のつもりです。などの話で盛り上がる。

そうこうしてたら、そのおじさまが、「あ、先生。こちら、神奈川県からいらした、とても熱心なかた」と。なんと、日下田正さんご本人が、出先から戻ってこられたのです。
「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、1

昨日のブログの続きですが、終了迫る「日下田正とエセル・メーレ」展に滑り込むには、もうこの日しかないと決行したわけです。実は益子ってどこだっけってって感覚だった。それどこ?雪は降っとらんと?
交通は、下手に新幹線とか使うより、バスの方がいいとわかった。しかしそれは午前中一本しかない。朝8時20分、秋葉原発。うちを出るのは余裕をみて、6時20分。チョイスはない。
それで、早起きして、久しぶりの高速バス。秋葉原から上野を通って、合羽橋。藍熊染料さんのお店の前を通って、雷門の提灯もチラリとみて、隅田川を渡る。アサヒビールの○○こビル。それからスカイツリー。常磐自動車道に乗って、さあ北へ。
2時間半くらいで、益子の陶芸メッセの入り口付近にバスは着いた。意気揚々、るんるんと歩み入ります。
日下田正さんの作品の感想を簡単に述べることはできないので、大きく印象的だったことを書きますが、何よりすごいのは、ご自分の世界観をキリッと構築され、それが形になり目の前にあるってこと。
やはり、糸の力がものすごいってこと。その糸はご自分で棉花の栽培からされ、棉を収穫し、藍染か草木染めで染め、または染めずに生成りのまま、カーディングして色を混ぜ、繊維を整え、糸に紡いで、それから、機準備をして織っている。買った糸、ましてや紡績の糸ではこうはいかん。さすが、作品から迫りくる、深い深い説得力がある。
日下田さん、この糸を益子木綿と名付けておられる。日下田木綿でもよさそうなもんだがと思ったが、さすが、できる人は謙虚なのだ。
綾織りで織っているものも、平織りのものも、糸が効いてて、語るのだ。この糸でなければ無理だし、益子でなければ無理だし、日下田さんでなければ、絶対にあり得ないのだ。
素晴らしい作家さんはみな、「私の方法」を確立して、それを昇華させている。日下田さん、もちろん然り。それが人の心を打つんだなと思った。
*写真は、陶芸美術館の入り口。藍染のれんに、白抜きの「日下田」がいいね。効いてるね。さすがだね。展示会の入り口にのれんって初めて見たかも。
「日下田正とエセル・メーレ」展に行った、プロローグ
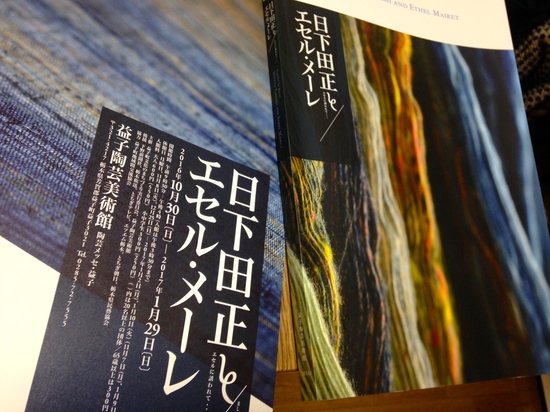
今日、「日下田正とエセル・メーレ」展に行ってきました。行って本当によかった。ご縁にご縁が連なって、最高でした。なんか、ぼーっとしています。感謝を込めて、ブログに記そうと思います。
昨年の12月のある日のこと、当サイトのお問い合わせ欄からメールを受け取りました。個展「清正公の陣羽織展」を終えて、展示会の様子などをブログでご紹介していた頃の話です。そのメールに、「とある展示会の図録を、お送りさせていただいてもよろしいでしょうか?」とある。
まあ。これはいったい?
展示会のリンクもしていただいている。見てびっくり。うわー。こんな展示会、やってるんだ。知らなかった。益子の藍染の日下田さんなら、以前、着尺のご注文をいただいた時、絹糸を染めてもらったことがある。しかし、ご当主が織りの作家さんとは知らなかった。
それで、恐縮しつつもご送付をお願いすると、数日してそれはやってきました。
大型の封筒を開けると、立派な、御本が現れ、パラパラめくって、、、目を奪われました。きちんとしつつ、自由で、強い。なんか、青田五良を彷彿とさせるなあ。青田と言えば、青田五良を知ったのも、本をいただいたのが、きっかけなんだよなあ、、、
益子かあ、、、ちょっと遠いが、これは行かねば!
*写真はお送りいただいた、展示会の図録とチラシ。
*もしも、私と青田五良の縁をお知りになりたい方は、こちらのページの一番上に載せてる記事をお読みください。さらにご興味の方は、そこにリンクしているレポートをお読みください。とっても長いから(なんと40ページだよ!)、本当に興味ある人だけね〜。
あけましておめでとうございます

2017年がはじまりました。いい天気で、美しい冬晴れの一日でしたね。どうか今年もよろしくお願いします。元気ないい年にしましょう!
昨年は、何といっても、熊本地震の年でした。「まさか、、」が本当になるという、あっけに取られ、自分の無力を思い知らされた年でした。
しかし、その後、ふるさとの友だちたちが、力強く生き抜いて行く姿も見、周りの方々が無償の応援をしてくれる姿も見ました。私も、売り上げの10%を寄附させていただくことを一つの目的に個展を開催し、おかげさまで多くの方にお買い求めいただきました。本当にありがたかったです。(第二弾の寄附は、年内に振り込み用紙が届かなかったので、もうすぐ出来る予定です)
今年も、お一人お一人の願いをかなえる布を織りたいと思っています。ハッピーになる布です。布を織る理由はそこにあるね。みんな、ハッピーで行きましょう。
*写真は、蝋梅。本日、谷戸山公園にて。すっごくいい香りで、思わず寄って行った。
美しいキモノ秋号に載った!

待ちに待った、「美しいキモノ」秋号が発売になりました!
今回なんと、「ありがとうの言葉に代えて 熊本から元気な姿でこんにちは」という、特別応援企画を組んで下さったんです。我が熊本は、地震で痛手を受けましたが、へこたれません。そんな熊本をご紹介くださっているページです。そこに、熊本ゆかり染織作家展のご縁で、なんとワタクシめも載せていただきました。P245です。見てね!
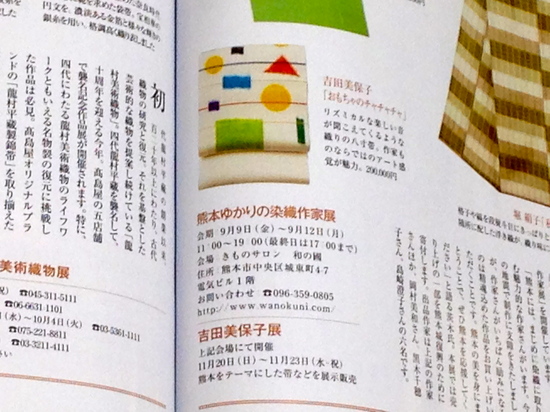
それから、もうひとつ、誌上ギャラリーのページにも帯の写真を載せていただいたのですよ。八寸帯「おもちゃのチャチャチャ」です。P136にご注目。
さらに写真の下の告知欄をご覧ください!
次回の熊本ゆかりの染織作家展のご案内を載せていただいています。
そしてなんとその下には〜〜〜!本邦初公開、ワタクシめの個展の告知も載せていただいています。うっわー、まじ〜〜?がまださんとーーー!(この展示会については、後日、イヤというほど書かせていただきます。笑)

えっとーーー、情報を整理させていただきますね。ヨシダ、熊本で、今後ふたつの展示会があります。
-1-. 熊本ゆかりの染織作家展 9月9日〜12日、和の國さんにて。ヨシダは全力で出品しますが、帰熊はしません。
-2-. 染織吉田・吉田美保子展 11月20日〜23日、同じく和の國さんにて。ヨシダ、全日、滞在します。
美しいキモノの表紙は美しい吉田羊さんです。ぜひ手に取って下さいね。
*この場を借りて、お詫びいたします。
本誌P245の私のプロフィールのところに、個展の情報はP76参照とありますが、正しくは、P136参照のあやまりでした。
また一部の方に、美しいキモノ秋号に載ることをご連絡いたしましたが、その際、P76とP245に載るとお伝えいたしました。正しくは、P136とP245でした。お詫びして訂正いたします。
京都

もう一ヶ月も前のことになるのだけど、6月にちょっと京都に行ったので書いておこう。

母と叔母と。桂離宮と修学院離宮に行こうと、計画した。

離宮の見学申し込みは3月のこと。ホテルの予約も早々に。

その後、思いもしない熊本の大地震。世の中ひっくり返ったかと言うくらいの衝撃だった。

一時はこの京都旅行もキャンセルかとよぎったが、母にとっても、ちょうどいい気分転換になった様子でよかった。

当日は、京都駅で待ち合わせ。それぞれ新幹線で。熊本からさくら号の母、名古屋経由のひかり号の叔母。新横浜からのぞみ号の私。京都って便利。集まりやすい。ほんと、日本の真ん中なのねえ、、

京都駅から乗ったタクシーを、修学院離宮で降りるとき、助手席に乗った私がお金を払いながら、「うるさくてすみません」って言ったら、運転手さん、「いえいえ、ウキウキが伝わって来ましたよー」って。

そうですね。ウキウキしてました。久しぶりに会う、おんな3人、平均年齢66歳。

京都っていいなーって思いました。見るところいくらでもあるし。桂離宮、めちゃくちゃ、よかった。(写真、上から12枚目まではすべて桂離宮です)
あと、「ギア」ってお芝居がよかったな。三条通の古いビルに専用劇場が出来てて、ロングランやってるのだ。マイムやブレイクダンスなどなど、パフォーマンスがすごいのだ。人間ってすごいなー、若いっていいなーって思った。(あ、おばちゃん発言してしまった)

あとよかったのは、母と叔母と別行動で、一人でささっと行って来た、一乗寺の恵文社という本屋さんと、木嶋(このしま)神社、別名蚕の社。本屋と神社だからぜんぜん違うけど、どちらも、「うわっ」って感じですごかった。すごいところって、空気が違うんだよね。

養蚕や織物の神さまである、蚕の社で、おみくじをひいた。「小吉」であった。教えの欄に「仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。」とあった。粛々と努力しよう。

思ったけど、私、もしかして、純粋に観光で京都に行ったの、はじめてだったかもしれない。
高校時代の修学旅行を皮切りに、京都にはずいぶん行ったけど、観光とは言いがたいものばかり。30代前半にやってた仕事では京都でのイベントを担当したから、よく通った。他にも、展示会を観にとか、友人知人をお訪ねして、、、などなど、何回も行ってはいるのだけど、観光客ではなかった気がする。
今回、私、京都観光客デビューしたのだろうか?

この写真は銀閣寺。スリーショット、見えますかー。

この写真、遠くに大文字が見えますね。老婆二人が登るのは吉田山。
「美しいキモノ」、取材!

今日は、「美しいキモノ」誌の取材を受けました。秋号に、熊本地震復興応援のページを企画いただいていているそうです。神奈川県在住の私も、「熊本ゆかりの染織家展」に毎回参加させていただいているご縁で、お声掛けいただきました。熊本への思いのたけをしゃべりまくりましたわっ!

熊本は、地震のあとの追い打ちを掛けるような大雨で、弱り切ってるんじゃないかな。遠くから見守る私も、地団駄を踏む思いです。鎮まれー鎮まれーと念じる日々。
しかし、今回の「美しいキモノ」誌さんのように、自分のテリトリーから、得意分野で応援したいって思ってくださっている方が、たくさんいて下さるんだってこと、ぜひ知って欲しい!すごかよ〜。どんどん届くけん、待っとってー。

美しいキモノ秋号は、8月20日の発売予定です。発売されたらまた書くね。
*写真は取材が終わってほっとしてセルフィー撮りまくる私。一人しかいないのにニコッと笑うのがいたいたしい。
「多士東京 No.46」に載った!
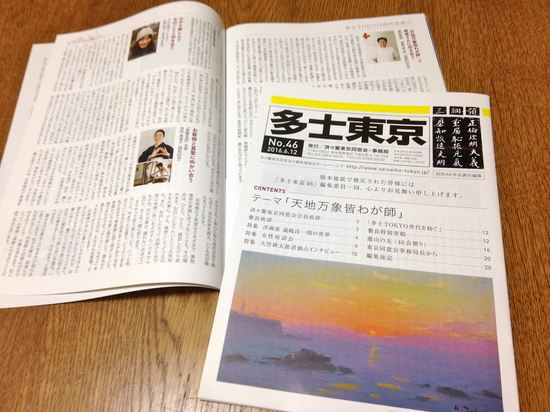
わーい!「多士東京 No.46」が送られてきた!これに載ったのだよ〜。
と言っても、何のことだかお分かりの方は、高校の同窓生で、それも主に関東在住で、先日6月12日に開催された東京同窓会に出席された方で、その時配布された冊子をよくよく読まれた方のみだと思う。
読まれた方は少ないかもしれないけど、じんわりうれしっす。
これは、私が通っていた、熊本県立済々黌高校の、東京同窓会が毎年発行している冊子なのだ。編集は、毎年、担当学年が順繰りでする。今年は、昭和46年卒の先輩方。御歳63歳だそうだ。卒業45年たって、ふるさと熊本を遠く離れた関東に住まう、職業もお立場も千差万別の初老(失礼!)方々が、一年かけて、編集なんて多分経験ないでしょうに、けんけんがくがく、一冊の冊子を作り上げるのだ。
寄稿を依頼された時は、ちょいちょいで書けるかなと思ったけど、実際書いたら難しかった。テーマに沿わなきゃだし、字数制限が厳しくて。
一度提出したら、「この部分を削って、ここを膨らましたらどうだろう?もっと良くなると思うけど」とアドバイスもいただき、「わー、こんなに真剣に作っておられるんだ」と感動した。
それで、今日、送られてきた「多士東京46」をじっくり読んで、すごく丁寧に大切に作られている様にじーんとした。たった20ページの冊子に、46卒の先輩方の、人生の機微や真面目さが詰まっているんだなあ。
済々黌の同窓会は、いろいろノルマがあって、われわれ62年卒は、おととし、東京同窓会の幹事を担当したのだ。大変だったよ。何の得にもならないしね。ただ働きだしね。いや、持ち出しもしちゃうのよ。でもすごく面白かった。
だから今年も2年下の後輩たちががんばって幹事をしているから、先日の同窓会出たかったのだけど、もろもろ段取り悪くかなわず、この冊子も受けとれず、、、ま、いろいろありますわ。
私の文章は以下です。テーマは「天地万象皆わが師」。黌歌の一節です。ご興味の向きはぜひ〜。
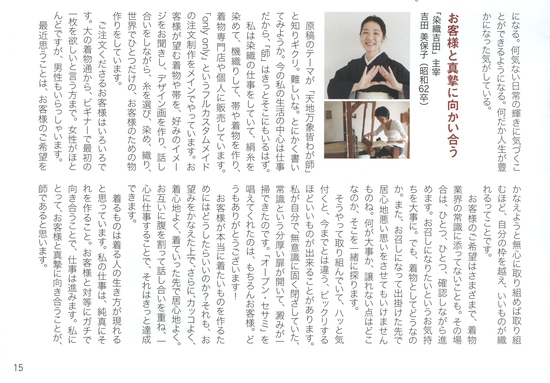
刺激的な。

この2日は、刺激的でした。
金曜日は、染織家の平山ふさえさんと下地康子さんにお会いしました。なんと下地さんの仕事場に伺えたのだ!仕事場、なんと一軒家。ビックリ。気持ちよい空間で、集中して仕事なさっているご様子。さすがだなあ。
平山さんも、下地さんも、いろんな壁にぶつかって、それをひとつひとつ、解決しながら、仕事されている。悩みつつ、苦しみつつ、切り開くしかないもんね。がんばろー!

土曜日は、八王子の奥田染工場での奥田塾でした。この日は、反応染料のプリントが課題でした。絹には最適ではないこともあり、私、反応染料使うのはじめてでした。反応染料って1956年に生まれた新しい染料で、今では綿素材の衣料品の90%がこれで染まってるんだって。ほー。私が着てる普段着もお出かけ着も、きっと反応染料ね。着物以外はね。
一日染め作業して、ボロボロに疲れましたが、「人はなぜ装うのか?」という永遠の課題にちょっと気付きがあったかな?現代人は現代の装い方をするのだ。それは本能なのだ。そこに訴える染織をしたい。
*写真は奥田塾にて。蒸したあとのソーピングの様子。
濃い一日
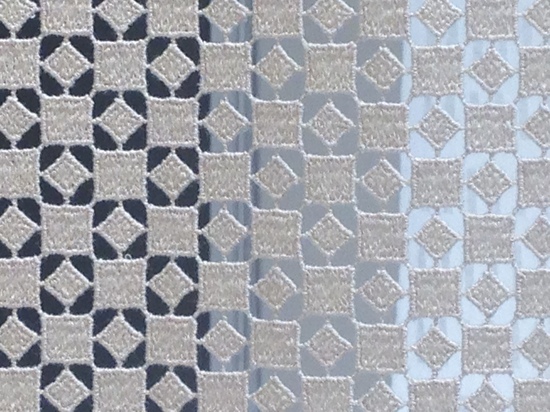
本日は盛りだくさんの一日でした。
朝から、松浦弘美さんのギャラリートークに銀座もとじさんへ伺いました。作品、トークともすばらしく、大感激でした。
松浦さん、4人の師との出会いがそれぞれに大きいと、しかし最後は独学なんだと。絽を織るのに、絹糸を精練するのだけど、その試行錯誤に7年かかったと。失敗の連続を詳細にノートに取って改善して行くのが、とても楽しかったと。
それから、銀座三越のデパ地下で、思いっきりカワイイお菓子を、熊本のお世話になってる方に送る。おしゃれな方だからね。銀座でしか買えないものを贈って、元気になってもらいたい。
そして、有楽町の無印良品へ、「日本の布ができるまで 展」を観に。現在の繊維産業。斜陽といわれ久しいけど、どっこいしぶとく生き抜いているなあと思った。布の魅力は魔力だなあ。上の写真は、こちらの展示会で撮りました。水に溶ける不織布にミシン刺繍して、あとで溶かして糸のみにする手法。
ここの無印は、本屋が充実しているので、つい長居。つい買ってしまう。重いのに。「よそおいの民俗誌 化粧・着物・死装束」っての。読むの楽しみ。
それから、地下鉄に乗って、日本橋三越へ。伝統工芸染織展、拝見に。入選されてる作家さん方の、自分の技を磨いている真剣さが伝わって来て、さすが〜っと思った。
帰りがけに、エスカレーターの上りと下りで、とっても感じのいいお二人連れとすれ違いました。遠目で、あら素敵なお着物お召しだわと思ったけど、ジロジロ見るのも失礼かと目線を反らそうとするのだけど、どうもあちらも、私の方をチラチラご覧になる。
あ!nkさんhyさん姉妹だわ!一度下りたエスカレーターをUターンして上って、うっわーーー、お久しぶりでっっす!お二人ともお変わりなく!相変わらず、それぞれにご自分らしいコーディネートでお着物お召しでいいなあって思いました。
実は、このご姉妹のショールをもうずっと以前に織らせていただいたのです。なつかしい、大切な時間でした。あらためて、ありがとうございます。
お姉様のショールはこれ。
妹さまのショールはこれ。
羽織っていただいているところ。
そのうしろ姿。
国展とルノワール

六本木の国立新美術館に行ってきました。
まず国展。工芸部のみでしたが、堪能しました。本日最終日だったためか、駆け込みで見に来る人や、出品されてる作家さんや、多くの人でにぎわってました。
下地康子さんとバッタリお会いすることが出来ました。今年も存在感のある、大きい、美しい作品を出品されてました。イキイキとした感じは、作家さんも作品も同じだなあ。マチュア(mature)、かつ若々しいのだ。
館山唐山の斎藤裕司さんにも、バッタリお会いできました。出品されていたのではなく、観に来ていた方で。斎藤さんは、半年前の私の個展にもお越しいただいていて、その時の感想など、率直にバシバシお伝えくださいました。ありがたい。作り手として大尊敬の方なのです。うれしかった。
国展工芸部、観ていて、これ好き〜と思うのは、染めや木工や陶ではなく、織りのことが大半で、私、やっぱ、織りが好きなのかななどと素朴に思った。

それから、同じく新美術館で開催中のルノワール展を拝見しました。こちらも国展同様、招待券いただいていたのだ〜。ありがたや〜。
ルノワール観てて、100年前のパリって本当にこんな感じだったんだろうなって思った。ルノワールは事実(とその印象)を描いているのだ。なんか、楽しそう。平穏な時代とは言いがたいように思うけど、明るいのだ。時代を感じるなあと思った。
あとやっぱ、ヌードはいいね。ルノワールのヌードはそそられると思った。服きてるとまどろっこしい。脱がせた方が本領発揮って感じした。
新美術館では、イッセイミヤケもやってたけど、急いで帰って仕事の続きをすることにした。国展で刺激もらったからね。私もがんばる。
*写真は国立新美術館の建物。
熊本ゆかり便り

染織吉田、連休中も普通に営業しております。心配事があるときこそ機織りだ。これ、本当だなあ〜と実感しつつ、せっせと織ってます。しかし織るだけで精一杯で、ブログ更新ままならず、という感じのここ数日です。
そんな中、熊本のきものサロン和の國さんのブログが更新され、「熊本ゆかり便り5月号」が掲載されました。私のタブローのこと、記事にしていただいてます。安達絵里子さんのいつもながらの、美しい文章です。ぜひお読みください。→☆
先日、熊本に帰ったおり、和の國さんをのぞきました。お店は震災のため休業中だと知っていたのですが、伺ってみると、ご主人の茨木國夫さん、女将さん、スタッフの方々、みなさんのお顔を拝見することができました。うっわー、うれしいー。大変なこと山積みで、お疲れもピークなのではと思いましたが、表情は明るいのが、和の國さんのめんめんです。さすがだなあ。茨木さんの一言が忘れられません。
「美保子さん、この地震の中、唯一よろこんでいるのは、木々ですよ。地震で揺さぶられ、根に空気が行ったのか、生き生きしています。緑がまぶしいです。」
この苦境の中、美しい緑に目を細める茨木さん。すてきだなあと思いました。きっと、乗り越えられ、もっともっといい店になって行かれるだろうなと思いました。
*和の國さんは、しばらくお店は営業できないそうですが、新潟を皮切りに、高知や茨城など方々で販売会を開催されるそうです。こちらのブログご参照の上、ぜひ。
*写真は先日、熊本空港を飛び立った飛行機の中から。きれいでしょ。キラリとひかる2本の川は、緑川と加勢川かな。そしたら、飛行機は益城の上あたり?嘉島?御船?いずれにせよ、深刻な場所だ。
戻ります
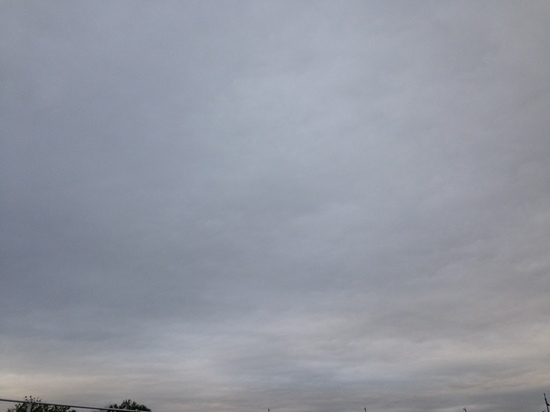
今回の帰省は、両親と妹一家のことで精一杯、他には何も出来ないだろうって踏んでましたが、友だち数人に会うことができました。同級生や着物のお友達で、みんな同じ年です。彼らに会って話せて、本当によかったー。同い年ならではの共感がありました。困りながら、疲れながら、考えながら、出来ることを誠実に、みんなやってるなー。すばらしい友人たちです。
我々、今年48歳になります。社会のど真ん中と言えるでしょう。若くはまったくありませんが、老成もしておりません。そんな年回り。そんな中で突然起こったこの天災。さあどうする?
私は、自分の非力を百も承知していますので、出来ることは家族を元気にすることだと思いました。そのためには自分が帰る。タイミング的には、飛行機とライフラインが復活した頃。水もガスも出ない時期、レンタカーで帰った人たちは本当にすごいけど、私にはムリ。
滞在5日目、出来ることをたんたんとしたとは思うけど、正直、自分の家族以外のことは、どうすればいいのか分からない。
一番思うのは、被災格差です。帰った日に、「何も変わってないように見える」と思いましたが、それは次の日にはふっとびました。我が家からすぐの、国道三号線一本越えると、その一帯、道が上下にうねって、ガタガタ。その上に家が建ってる。どういう状況かご想像いただけるでしょう。それがもうちょっと行くと、普段通りの平穏な田舎の住宅地に戻ります。手入れされた庭庭に、花が咲き誇っています。のんびりお散歩したくなります。
これは運が悪かったってことなの?
仕事だって、みなさん、いろんな巡り合わせで、今その職業をしている訳でしょう。それが、天災によって突然八方ふさがりになり先の見通しが立たないって、煎じ詰めれば、そもそもの巡り合わせの運不運?これが天災ってこと?うーん。
しかし、熊本の48歳は力強いです。友だちに会って、きっと大丈夫って思いました。遠くに住む熊本出身48歳は、目の前のことをがんばるしかありません。
そんなことを考えながら、明日、戻ります。染織吉田、通常営業に戻ります。

いろんな方々から、「出来ること、何でも言って」って申し出ていただいてます。ありがとうございます。
これから必要なのはたぶん、お金だろうなあ。ふるさと納税、ぜひ熊本と大分へ!義援金、各所へ!
支援物資は、もう緊急性のものは行き渡ったと思いますが、「誰かが思ってくれている」という証しとしての物はうれしいんじゃないかな。何かが届くってうれしいもんね。
熊本城もきっと再建されるでしょう。そしたらぜひ観光に来てね。
*上の写真は帰った日。下の写真は今。
帰った日
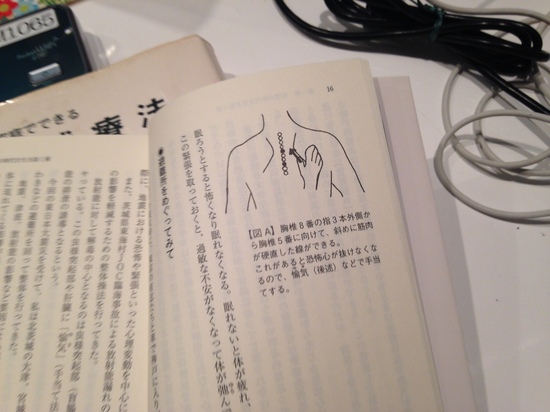
久しぶりの我が家も、一見変らぬように見えました。こわれた食器はおおかた片付けられていたし、部屋が散らかってるのは、いつものことです。母も、疲れていることをのぞけば普通に見え、父は仕事に出ていて不在でした。まあ、とにもかくにも帰り着いてほっとした。
飛行機の中では「緊急時の整体ハンドブック」(河野智聖著)を読んでました。この他にも「自然療法」(東城百合子著)、「整体入門」(野口晴哉著)をスーツケースにしのばせてます。ふふふ、この他にもテルミー温熱療法の道具と、アロマテラピーの電熱器と数種のオイルも持って帰ってきました。
お土産の柏餅を食べさせているうちに(4歳の姪が2個食べた!)、お風呂場にお湯が出るのと、冷蔵庫にコンニャクがあるのをチェックして、お湯を沸かしたり布団ひいたりバタバタ準備。
それで、まずは母を足湯させました。こういう時だから「もしよかったら」とかでなく「ほら、するよ」ってうながして。
足湯が一番ゆるむと、友人の善林英恵さん(高級帽子の作家さん。整体などに大変詳しく、「京都発自給自足的シンプルライフ入門」というメルマガを発行されてます。私はそれの愛読者。)から教えてもらってましたので、即実践です。その後、母に寝てもらって、熱いコンニャクのタオル包みを首と腰にあてながら、整体もどき。
びっくりしたのは、母が、背中の背骨の右側をさすっていると、効く感じだと言うのです。えー、その辺り、「緊急時の整体ハンドブック」のはじめの方に図入りで載ってた、恐怖心が抜けなくなる筋だ。ぎょぎょ、整体、すごいねえ、、、体、正直ねえ、、、、そりゃ、震度6を2度経験して、いつまた余震が来るかって身構えてる体は、こわばってるよねえ、、、、
母はちょっとは緩んだようです。妹は、私が姪を見ているうち、足湯とコンニャク温湿布して、寝落ちしてました。帰って来たかいがあるってもんです。
熊本のほとんど全ての方が、多かれ少なかれ、恐怖と不安と緊張と疲れでこわばっているでしょう。こわばりながら、復旧活動に日々取り組んでおられるのです。
熊本におります

熊本滞在3日目です。いつもの帰省とは全く違うのですが、まあ、正直な話し、自分を問われる、帰省となってます。なんて言えばいいんだろうねえ、、、
羽田から乗った熊本行きの飛行機は、作業服を着た一団もいらっしゃり、やっぱ、少々ものものしかったです。乗り合わせたのは、作業団の方々、行政関係も含まれるであろうお仕事の方々、私のような外にいる熊本人って感じの人々で、ほぼ満席に近い客席でした。
天気はどんよりだったので、上空から熊本の大地は見えないだろうって思っていたけど、低くなってきたら、見えてきました。江津湖が見えた!あの先が益城だ!
上空から見てる時は、いつも通りの、のんびりした美しい景色だったのだけど、降下してくると、目についたのは、真新しいブルーシート。景色にそぐわないよ。なにこれ?

飛行機に乗ってるとき、ああ、羽田でトイレに行っとけばよかったと思いました。降り立つ故郷はトイレ使えないかもよ。
熊本空港には、妹が車で迎えに来てくれてました。渋滞の一因となるからこなくていいって言ったのだけど、姪のお昼寝ドライブがてらだからって言ってくれて、実は、飛行機に預けられるギリギリの大荷物だったので、助かりました。
妹はすっぴんで、ちょっと疲れてる感じでした。姪二人は普通に見えた。
熊本空港から、我が家までのドライブは、混んでいたけど快適で、自衛隊の車が目立ち、崩れかけの道路や建物がところどころあったり、被災ゴミの山があったりするけど、そんなにいつもと変らない。
うちの辺りも、隣りの塀がくずれたと聞いていたけど、それは片付けがすんでいて、そんなにいつもの変らない。(ように見えた。この時は)
この数日

熊本のことで気持ちが高ぶったままのこの数日ですが、不思議に仕事は順調です。熊本の友人たちの、仕事を再開したとか、避難所と回って細かな支援をしているとかいうニュースが支えです。
遠い島に住む友人から、「どう過ごしていいかわからない時こそ、仕事だ、機織りだ、出来ることは元気に働くことだけだ、がんばれ、ソメオリヨシダ!」と強いメッセージいただいたことも大きいです。種火がポッと明るくなるメッセージでした。
かずさまの only only、ブログ上では、昨秋の個展にお越しくださって、スケジュールの変更があったってところまでですが、実作業は日々しゅくしゅくと進んでいます。この辛い時期、しっかり取り組めている仕事が目の前にあることが、どんなにありがたいことか。気が塞いても落ち着くし、その時間だけは無心になれます。
あらためて、かずさまに感謝します。
ブログの続きは、、、、また詳しく書きますね。
*写真は、午後5時の空です。春の夕暮れ。今日じゃないよ。春分ころだったかな。これはね、かずさまのonly only ストーリーの伏線です。おほほ。
がんばるばい

毎朝、ラジオのタイマーで目を覚ます。朝6時、NHKラジオ第一。しばらく寝床でぐたぐたしながら聞いているのが通例だが、今朝は飛び起きた。熊本をさらなる災害が襲っていた。すぐに母と妹にメールし、ほどなく無事との返信がきた。
被害状況を知るほどに呆然。不安におそわれ、今日の予定をキャンセルしようかと思ったが、ネットにかじりついていてもらちは開かないし、出掛けることにした。
7時20分にうちを出て、八王子の奥田塾へ染めの勉強に。結果、行って正解だった。普通は門外不出なことを教えて下さるので、夢中になる。体力的にも過酷なのだ。
途中、チラチラと情報チェックし、たまらず、父と母に電話したが、それ以外はぱっつんぱっつん。帰り着いたら午後8時。
駅前の東急ストアで、熊本産のアスパラとミニトマトを売ってたので買ってきた。横にあった千葉産より高かったけど、熊本のエネルギーを体内に取り込むのだ。うちには、先日、友人が送ってくれた、阿蘇高菜の新漬けもあるのだ。熊本の恵に満たされています。
がんばるばい!
*写真は奥田染工場。
地震

昨日から呆然としております。たくさんの方から、実家は大丈夫かと、電話やメールいただきました。ご心配いただき、ありがとうございます。両親、妹一家、親戚、大丈夫です。
熊本の友人たちが心配ですが、知る限り、みんな無事で、それぞれの仕事にまい進しているようで、心強い限りです。
それにしても、心が痛みます。熊日(熊本日々新聞のこと。熊本のローカル紙)の紙面をネットで見て、じわっときました。あんな中、朝刊が出たんだ。その後号外も。
これ以上太くできないと言うくらい太い白抜き文字で「益城町震度7」。熊本城の写真も涙腺ゆるむ。こんなことが、起きるんだ。
一日中流れてるラジオのニュースで、つぎつぎ連呼される地名が、知ってる名前ばかりなのが辛いです。ああ、あの辺かと。
熊本在住の人たちが、未曾有のことに対峙して踏んばっているのだから、遠くにいてもしっかりがんばろうと思っております。
熊本の方、お体、大事に。今夜はちょっとは体を休めてください。
*寝ていた二人の姪は、あの地震でも起きなかったそうです。妹(1歳)は余震で周りがざわついて起きたそうですが、姉(4歳)は朝までぐっすり。熊本市南区、震度6弱だよ。すごい。
森康次先生の展示会に伺いました

日本刺繍の森康次先生の個展を拝見しに、銀座もとじさんに伺いました。森先生とお弟子さんの佐藤未知さんにお会いしたかったのです。ギャラリートークに参加させていただきましたが、お話、すごく面白かったです。
森先生が、作品作りをなさるにあたって、大切にされていることは三つあって、それは、「時間差」「情緒」「着姿」だそう。
「時間差」というのは、例えば、裾模様に花を繍ったとすると、肩の模様には実を表現する。そうすると、春と秋を同時に表現できる。これは分かりやすい時間差だけど、それだけでなくもっと微妙な時間差を表現する。例えば柄の大小でリズムをつける。色に少し変化をつけて、奥行きを出す。奥の方は、地色に近い色を使う。
「情緒」というのは理屈でないところ。静かな場所を作る。強弱をつける。余白をつくる。
「着姿」というのは、着物も帯も、決して平面でなく、人を包み、円筒形になることを意識すること。前姿、うしろ姿。側面の美しさ。
そして、色数は決して多くしない。着物と相性のいい色はそんなにない。色数は少なく、濃淡を5〜6段使う。
なるほど、なるほど。お聞きしながら激しくうなずきます。あー、すぐ隣りに展示されている作品が、まさにそうなっている〜。上品で可憐で、はかなげでさえある作品たちは、確固たる技術とマインドに裏付けされてるんだな。
いいものには理由があるんだ。そう思い知りました。自省します。

写真は森先生と佐藤未知さん。なかなかいい写真でしょ?掲載許可はいただいてませんが、森先生は有名人だし、佐藤さんもウェブ上に取り上げられてらっしゃるので、いいかなと思いました。
佐藤さんの記事はここで読めます。すてきです。
ゆうどにて

昨日の晩のことですが、目白のゆうどへ行ってきました。単行本「更紗 いのちの華布」出版記念展のオープニングパーティーでした。
「インドで生まれた模様染めの木綿布、更紗。日本、ジャワ、ペルシャ、ヨーロッパ、行く先々で人々を熱狂させ、それぞれの地で独自に花開き、産業革命をも引き起こした、その布の魅力を探る・・・」と解説にあります。なるほど、なるほど。まさにそうね。「熱狂」という、普段の生活にはあまり使わない言葉が、ピッタリ合うのだよね。
パーティーで歓談のあとに、本に登場している方々が、一言ずつご挨拶なさいました。それがまた熱かったのだわ。更紗に対する熱烈な愛を感じました。その熱烈な愛を、皆々さんが、表現は違えど、腹の底からお持ちなのだ。すごいなあ。
布って、それだけの力、あると思う。染めもそうだし、織りもね。縫いもね。どうして、そうなのか、うまく説明できないけど。

会場のゆうどは、実は私の古巣です。13年前まで、勤めていました。28歳の時、ここで働くために再上京したのです。いやー、なつかしかったわ。いろいろ悲喜こもごもありましたけど、私を育ててくれた大事な場所です。
ヤマモモの皮

これは、ヤマモモの樹皮をチップしたもの。草木染めの染材としてすごく状態がいいです。きれいでしょう。いい色出そう。
これね、いただいたのだ。宅急便で送ってもらった。箱を開けたとき、心底から感動した。
先頃、大変お世話になった、大好きな植木職人の親方がなくなられた。私、親方にも奥様にもとても可愛がっていただいていた。亡くなったと聞いて愕然とした。
出会いは、まだ勤め人の頃。担当した東南アジアの染織家たちをお呼びするプロジェクトに、ものすごく協力してくださって、盛り立ててくれた。会場に竹林とか橋とか作ってくれたんだよ!「一生懸命やれば誰かが助けてくれるものだなあ。それって神さま?」って実感した。
時は流れ、私は退職し、染織で独立した。その後も、交流はつづき、京都で奥様と二人展されたときなど、観に行った。
で、写真のヤマモモは、植木職人のお弟子の方が、奥様にって持ってきたののお裾分け。奥様も染織なさるのだ。ウールの手紡ぎ。
ヤマモモの樹皮をここまで丁寧にはがして、煮出しやすいようにチップにするの、ものすごく大変。これ、お弟子さんの、親方と奥様への愛だなあ。愛、あふれてるもんね。親方、そのものでもあるな。とても大事なことがここにあるように思うのだ。分けていただいて、ありがとうございます。
モランディ展にいった
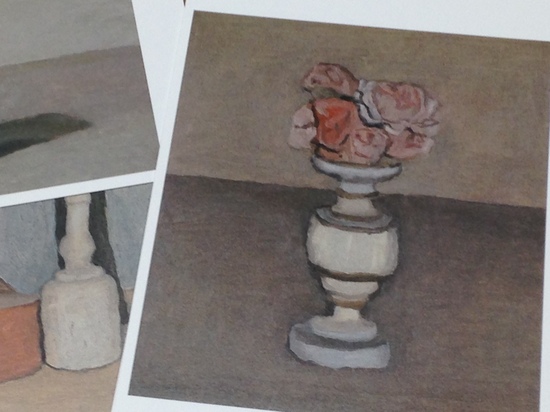
ジョルジョ・モランディ展を観に、東京ステーションギャラリーに行ってきました。観たかったんだ、モランディ。
モランディの本物、しっかり観たのはじめてでした。同じような瓶ばかり描いている朴訥なイメージがありましたが、なんの、なんの。狙いのするどいテクニシャンでビックリ。ますます好きになりました。
モチーフの瓶も、そこらにあるのを描いてた訳でなく、吟味して自分で色を付け、好みにして繰り返し描いていたのだと。アトリエはわざと掃除せず、ホコリを積ませてそれも重要なモチーフだったのだと。ほぉー。さすがだなあ。
瓶の絵はもちろん好きだったけど、最後に掛かってた花の絵も好きだったな。特にラストの3枚。花もね、モチーフは造花なんだって。で、ホコリももちろん描いている。へー。
で、モランディは、花の絵は売ろうとせず、家族や友人のために取っておいたのだって。なんだかいいな。だから、こんなにも優しい絵なのか。
上の写真は記念に買った絵はがきです。花の絵、私も大切な人に送りたくなりました。
ジョルジョ・モランディ展は、東京ステーションギャラリーにて、4月10日まで。

実は、モランディを観たかった理由がもう一つありました。

モランディ、2011年に日本に来ることになってたんです。私、年明け頃かに知って、とても楽しみにしていました。夏頃にくることになってたかな?よく覚えてないけど。

で、3月にああいうことになって、しばらくして、モランディ展が中止になったと知りました。まだ何も見えない頃で、それは仕方ないことだと思えました。それどころじゃなかったよね。

で、今年、モランディ展が開催されると知って、ああ、時間がたったんだなあって思いました。全てが解決した訳ではぜんぜんないし、根深くなった問題もあると思うけど、時間は流れたんだなあ。
3月に観たかったので、行けてよかったです。
*下の4枚の写真は、東京ステーションギャラリー内部と回廊からみた東京駅の丸の内北口改札。
「10年かけて旅をする〈半農半芸〉、佐藤香さん」の展示を観た

昨日は夕方ひと段落ついてから、上野に行きました。上野駅のギャラリーで、「10年かけて旅をする〈半農半芸〉」という展示をやってて、そこに出ている佐藤香さんというアーティストの作品がとてもいいと聞いたから。

佐藤香さんのことも、上野駅のアートスペースのこともちっとも知りませんでしたが、懇意にしてもらってるアーティストの方が、フェイスブックで押しておられました。とてもよかったと。伝わってくるもの、ピンとくるものあり、出掛けました。それに、最終日だわ。

上野について、駅の正面玄関の2階を探します。アトレのレストランにはさまれたスペース。ああーここだー!

麻布に、各色の泥で描いた、大きな、ド迫力の作品5点。うーん、すごい。吸い込まれそうだ。私、大好きだー。来てよかったわーん。

無限を感じるよね。作家の集中力がそうさせるのか。才能と実行力と集中力かな。すごいもんだ。

写真に写り込んでる蒼い色は、ガラスに映った夕闇です。これが、またよいわ。

上野ステーション。多くの人が行き交うが、ここにあるアートがあるの、ほとんどの人が気付かず。

ああ、でもそういうものかもしれない。ラスコー壁画だって、高松塚古墳だって、ずーっとただそこにあったのだ。発見される前、その前を幾多の人が行き交ったかもしれない。
奥田塾に行った

昨日のことですが、八王子の奥田染工場で月一回開催されてる「奥田塾」に初参加してきました。奥田塾の存在は、ずーっと前から知っていて、いつか参加したいなと思いながら、やっとやっとはじめての参加をお願いしました。ドキドキです。
「ソメオリヨシダ」と名乗っている私ですが、実は「ソメ」の部分、そうとう弱いです。個人の織り手の中では、「ソメ」に特化しているつもりです。しかし、染めのこと、どこまで分かっているのか、根っこの部分がヤワヤワなのを実感していました。
「ソメ」は分かってないって書くと、いかにも「オリ」は分かっていそうですが、そんなことはありません。しかし自分で選んでそうしてるって感じあるのです。「この部分は、手を付けないでおこう。そのかわり、こっちはどこまでも踏み込んで行こう」とか。

朝8時半、八王子駅に着きました。八王子というのは、繊維で栄えた町ですが、いままで縁はなく。。。唯一、大昔に中退した大学が隣りの隣りの駅だったので、なんとなくなつかしい感じはします。しかし知らない町です。
バスに乗って、たどり着いた奥田染工場は、、、、、度肝ぬかれました。宮崎駿の劇画に出てきそう。いろいろ無尽蔵に湧き出てくる感じ。なんか、豪快なの。これに比べると、手織りの現場はおとなしいなあ。

昨日は、酸性染料のプリントという課題でした。私は、自分で織った帯を持って行きました。納得いく出来にならず、お蔵入りにしている布、けっこうありますのよ、はずかしながら。これが息を吹き返せば。
導かれながら、夢中で作業しました。引き込まれます。新しい経験は細胞を活性化させるね。自分がよろこんでいるのが分かった。ものを生み出すのは、本当に面白い。
奥田染工場、さすがプロと思ったのは、私が染めた布、白場がほんの少々汚染したのですが、それを取ってくれたのです。熱湯で煮るのですよ。知らなかった。
寒い一日で、凍えましたが、心にポッと火がつきました。「染めとは何ぞや」に一歩近づけたか?
申告、おわった
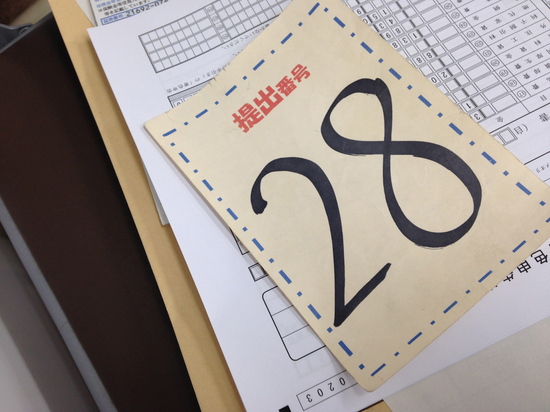
本日、いいお天気の日曜日、ふわふわと青色申告会に行ってきました。青空のもと、足取りは軽いんだけど、必死の形相だったかも。申告会は日曜日でもそれなりに混んでいて、30分ほど待ちました。担当してくださった、おじさまの所員さんが、2円の違いを訂正してくれて、その場で電子申告の種類を作ってくださって、無事に提出できました。バンザイ!
おじさまの所員さんの、華麗な電卓さばきに見とれました。あれはすごいね。午前の部の最終だったため、私が帰る頃には、コンビニで買ってランチされてた。年に一度のかきいれ時とはいえ、お疲れまです。おじさま、おじさまと書いてますが、私と同い年くらいかもなあ。
帰って、今年の資料を一袋にまとめて、申告関係の引き出しに入れ、代わりに、7年前の資料を捨てる。保管義務があるのは7年分だから。捨てる前に、しみじみと7年前の自分を見る。売上高が、今年の半分だ。私、倍、稼げるようになったんだ。それでも、ちっとも充分ではないけど。今でも不安で不安で、しょうがないけど。それでも、倍だ。
武藤奈緒美写真展「噺をせんとや生まれけむ」を見た

昨日はお出かけ。武藤奈緒美さんの写真展、「噺をせんとや生まれけむ」を拝見してきました。武藤さんは落語のお師匠さんの撮影を長く任されているカメラマンさんで、その集大成って感じの展覧会でした。
写真は、高座に上がってるオン状態の落語家さんもあり、普段のオフ状態のくつろいだおじさまって感じの写真もあり。その両方がシャッフルされて展示されてて、その両方を武藤さんの愛情あふれるキリッとした目で切り取られてて、素敵でした。
会期は3月6日まで。詳しくは武藤さんのブログでご確認を→☆
それはそうと、昨日は電車の乗り継ぎにまごまごしてしまって、自分にショックです。まず新宿から高円寺に行くのに、快速に乗ればいいのか、各停なのか、はたまた特快でもよかったか、とっさに思い出せません。ひー、こんなのパッと分かって当たり前なのに。とりあえず、黄色い電車に乗れば着くでしょうと、総武線でちんたら向かいました。
その後、表参道に行くのに、地下鉄を赤坂見附で、丸ノ内線から銀座線に乗り換えようと。しかーし、目の前の電車に乗ればいいのか、上の階か、一瞬分からない。ウロウロ。そっか、渋谷方向だから、上ね。
その後は、二子玉川に移動。進行方向後方に乗れば改札近いってのは分かるのだけど、どっちが進行方向か分からず、挙げ句の果てに、前方に乗ってしまいトボトボ歩く。
これは年のせい?個性ってやつ?
*写真は、サクランボの芽。山形産だそう。花瓶に挿してしばらくすると花が咲くらしいよ。表参道で買った。
イチゴと青色

スーパーで、不揃いのイチゴが、大きなパックに山盛りで売られているのを好んで買う。どんぶりいっぱい、ガツガツ食べる。デトックス効果があるのか、気持ちがすっきりする。
青色申告の準備しています。もうふらふら。
「きもの簞笥」を読んだ
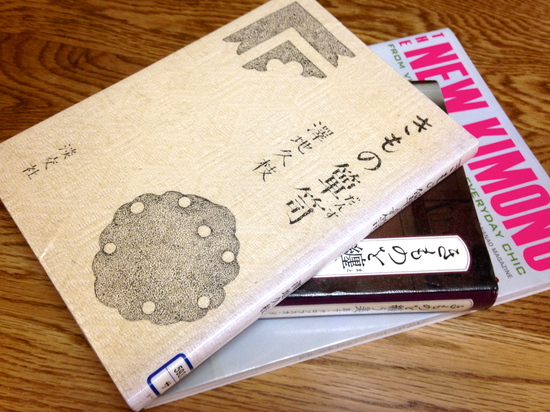
図書館で借りた本の一冊がとても心に残った。「きもの簞笥」澤地久枝著。読んでいて、澤地久枝さんの行動力、決断力、悲喜こもごもなど、小気味いい短めの文章からバシバシ伝わってきて、引き込まれた。好き嫌いも、天と地ほどハッキリしていて、胸がすく思いがする。
澤地さんも、着物の注文制作をよくなさってたようで、そのやり取りも面白く読んだ。
ある着物の注文したときは、「たのしい夢のある着物。あとはまかせる」というオーダーだったようだ。澤地氏自身もそう書かれているが、「作者にとっては自由なようで、じつは難儀な」注文だよねー。
注文を受けたのは、型染め作家の駒田佐久子さん。画像も載っているが、オーダー内容を、しっかり受け止め、しっかり打ち返した、すばらしいお着物だ。澤地さんの、その後の人生の時々を、おおいに彩ったことだろう。
澤地氏の文章の吸引力は、いいことばかり書かず、マイナスの事柄も、直球でビシバシ書かること。とある刺繍の帯の注文は、ガッカリされたらしい。自戒の念をこめて、書き写しておく。
「(前略)これは、特別に注文し、わが夢を託して作ってもらった。でも、二、三回締めたきりで、愛着をもてない。作り手たちの志の低さを感じてしまう。(中略)豊富な色も模様も、刺繍の技に魅力のない弱さばかりが目につくのだ。」
再会!

昨晩はちょー面白い夜でした。友だち二人と会いました。二人とも、同じ小学校と中学校に通った仲。一人は、今でも仲がよく一年ぶりくらいの再会。しかし、もう一人は、32年ぶりの再会!それも、当日になって、参加の連絡を受け。ドびっくりです。どんな子だったっけーと会うまではドキドキしたが、会ったとたんに、変ってなーい!
話しはこんこんと湧き続け、昔話や今の話し。しんみりする話しなど。16歳で亡くなった友人の話しもできてよかった。今まで誰にも話せなかったもんね。若くして亡くなった同級生のことを、繰り返す思い出すようになりました。

楽しい夜の記念写真、恥ずかしいので、小さく載せますねー。上の写真はバーニャカウダ。ワインも美味しく、私は少々飲み過ぎました。(いつも?)帰りの電車で眠りこみまして、車掌さんに起こされました。終点に住んでてほんとによかった!
「村上隆の五百羅漢図展」に行った(やっと)
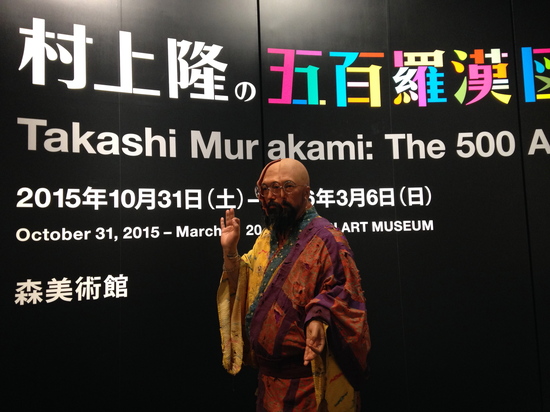
村上隆の五百羅漢図、観てきました。昨日のことなんだけど、なんか感動さめやらんわ。ヒシヒシ伝わるド迫力。デカさの迫力もあるし、圧倒的な仕事の量、徹底的だもんなあ。写真オッケーだったので、ちょこちょこ撮ってきました。

五百羅漢は200人がかりで作ったそうで、資料も展示してあった。その膨大さも迫力だった。200人の渦を感じた。村上隆がその渦を起こし、渦は有機体でどよめきながら、巻上って行く。500人の羅漢に、200人のスタッフ。

私、よーく考えてみると、村上隆の本物、はじめて見たかも。画像ではしょっちゅう観ているので、観た気になってた。本物は新鮮な驚きに満ちていた。こんなによかったのか。知らなかったよ。

実は私、昨年12月にもこの展覧会を観ようと、チケット売り場まで行ったんだ。すごく混んでたんだけど、なんか違うなあと思って聞くと、その行列は、展望台に上がるチケットの列で、森美術館はもうすぐ閉館時刻ですと、、、火曜日だったんだ、、、ガックシ、、、、(火曜のみ17時まで。他の曜日は22時まで。無休。)しかたない。蔦屋で立ち読みして、村上隆の本、数冊買って、すごすご帰る。

で、昨日、リベンジで出掛けました。土曜日に六本木なんて行ったら、人ごみにやられるかと思ったけど、出やすい日がこの日のみだったのよね。で、3時ころ着いたら、またまた大行列で、なんと、チケット買うのに30分待ちですと。展望台の列と間違ってないよ。村上隆の列だよ。村上隆ってそんなに人気だったの???アンチが多いんじゃないの???ドびっくりだ。並ぶのはイヤだから1時間半ほど時間をつぶして戻ってみると、まだ20分の列。お腹も空いた。六本木ヒルズは高いし、気軽な店がないので、ちょっと出てラーメン食べて時間をつぶす。

6時頃に戻って、やっと5分待ちでチケット買う。53階までエレベーターで運ばれて、やっとやっとたどり着いた。
入ったとたん、別世界。おどろおどろしいのだけど、清々しくもあるのよね。そこが好き。
お客さん、若い人が多かった。買い物のついでと言うんじゃなくて、この展示会を観に来たって感じ。チケット1,600円。決して安くないよね。それでも観たい人がこんなにいるだなあ。私は、会場を3周して、3時間も観てしまった。だって観ても観ても観たりないんだもん。出るころには美術館もガラガラ。週末でも夜間は狙いだと思った。
あまりさんち

ここに引っ越しして、6年半くらいになる。近所を徘徊散歩したり、ちょこちょこジョギングしたりするのが、唯一の趣味と言っていいくらいなので、よそモンにしては、近所に詳しいのではないかと思っている。
うちから歩いて15分ほどのところにある、相模カンツリー倶楽部の方への道すがらは、ちょっといいエリア。広々とした凝った家や、米軍住宅のなごりの家があったり、お茶室がある公園もある。程よく坂道で、気分がいいので、よく歩く。
そのエリアにこれまたいい感じのマンションがあって、玄関前に簡易作りの小さなブースができてて、お巡りさんが立っていた。朝も晩も。いつも暇そうに。目が合うと、「おはようございます」と言ってくれたりした。どなたのお宅?要人さんね。
それが、昨日通ったら、小さなブースとお巡りさんがこつ然と消えていた。ああ、やっぱりあまりさんちだったのね。
なんだかなあ、、、。悪いことは悪いけど、気の毒な気がしてならんわ。
あまりさんに投票してないけど。どちらかと言うとアンチだけど。選挙の時は、あまりさんが強すぎだから、面白くないと思ってるのだけど。それでも気の毒と思ってしまうなあ。
*写真はうちの近所。こういう街です。あ、あまりさんちは写ってないよ。ここから北に300mほどのところね。
*それはそうと、大臣さんとかの自宅前に立つ、あの警護のお巡りさんと小さなブース。あれをはじめて見た時(けっこうな大人になってた)、頭に「?」がボンボン浮かんだ。「何をやってるの?」と聞きたくなった。平和な日本、バンザイだ。彼らが活躍しなくて済みますように。
*お膝元ということもあるのか、近所にはあまりさんのポスターが、たくさん貼られてる。見る限り、落書きされたり、破られたりしているのは、一枚もないみたい。昔はガキンチョたちが、ヒゲを描いたりしたものだが。お行儀がよくなったのかな。軽犯罪の取り締まりがきびしくなったのかな。そんなダサいことしねーよってのが正解かもな。
最近の仕事

ただいま、only only5本と、オリジナル制作2本、水面下で準備中。もそもそと地道な作業の日々。なかなかGoサインが出せずにいたが、やっとやっと、動き出したぞ。(啓蟄かな?早すぎるね。)
お客様に試し織りを送って見ていただいてたのも戻って来たし、我が家に打ち合わせにお越しくださった明るい笑顔の方もあって、風が吹いた。春風ね。ありがたい。

それはそうと、先日、ずーっと長い間、悩んでいたことが解決した。パーセントの算出の仕方が分からなく困ってたのだ。1回だけなら分かるけど、2段階になると、うぅぅぅ、はずかしーーー。仕事の手伝いに来てくれているasakoさんに相談したら、あっという間に解決。すごい!ありがとう。
どんな問題かと言うと、、、
生糸6綛338gを酵素で練ったら、293gになった。この練った6綛のうち2綛の重さは102gだったが、それらを染めたら、さらに練り減りして87gになった。練り減り率は何パーセントか?
答え
16%。
さあ、復習しよ。
*写真は私の住む街。冬の夕方。
絹糸の精練

ここんとこ、帯の緯糸の精練をしている。精練というのは、蚕が糸を吐く時に繊維と一緒に吐くタンパク質を、取り除くこと。これがついたままだと、絹と言っても、固くてバリバリしているのだ。

実は精練、去年から再開して、いまだ試行錯誤しつつやっているのだ。
昔、着尺を織りはじめてからずいぶん長い間は、必ず自分でしていた。なんでも自分でやることが是だと信じていた。精練、難しいんです。特に灰汁でするとデータが取りづらく、安定しないから。それでも、頑固に自分でしてた。だって、そういうもんでしょう。
しかし、あるとき、お世話になってる糸屋さんに、いつもの通り、未精練の絹糸を注文しようとしたとき、
「ヨシダさん、精練、一度オレにやらせてみな。オレさ、絶対ヨシダさんよりうまいから。」
「う、、、、」と思った。灰汁ではないというし(自然派だったのだ、私)。しかし、思う所あり「お願いします」と即答した。
で、結果は上々だった。精練の具合も理想的だし、綛の乱れもなく、その後の仕事も支障なく進んだ。お支払いした精練代も納得できる金額だった。これはいい。今まで精練に費やしていた時間とエネルギーはなんだったんだ。私の仕事はいいものを作ることであって、全てを自分でやるってのは、かえって自己満足なんだなあって思った。

で、昨年から、八寸帯を積極的に織っているのだが、これに使う緯糸は、自分で精練するしかないのだ。半練りという、セリシンを半分残すのやってるのだが、こういうのは外注できないのだ。暴れん坊で、個体差が大きく、気分屋の糸は。

で、秤と計算機を座右に(というか、机上に)、せっせと作業中だ。
しかし、精練は絹織物の醍醐味とも言える。自分の制御によって、布味が七変化なのだ。これを自由自在に使いこなしてこそ、織りの真髄だな。がんばろう。
*一番上の写真は、大きなタンクを入れ子にして、湯煎しながら精練しているところです。今は酵素で精練しているため、湯温を55℃位にキープしなくちゃなので。精練終わると、内側のタンクはタンパク質が流れ出てグレーに白濁してますが、外側のお湯はきれいなままです。もちろん、このあと大洗濯〜。せっせと、バケツで汲み出して、洗濯機に運びます。お湯で洗うとさっぱりするねえ〜
熊本ゆかり便り、1月号にのった!
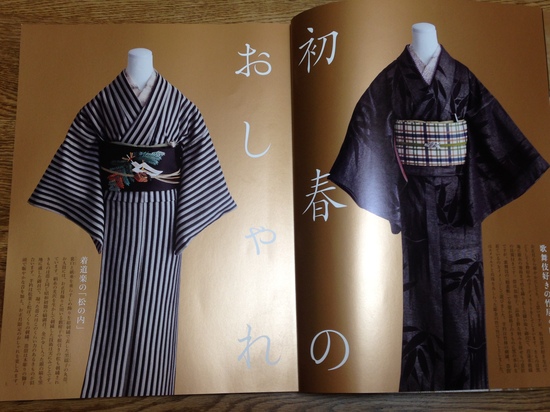
きものサロン和の國さんのブログに、隔月で掲載中の「熊本ゆかり便り」の1月号に、私のことを書いていただきました。(ご注意!上の写真は違いますよ!笑)
筆をふるっているのは、安達絵里子さん。「熊本ゆかりの染織作家展」実行委員です。
安達さん、きれいな涼やかな目をされてる方なんです。その目で、感じ取ったことを、優しく強い文章に書かれます。ぜひご一読を→☆
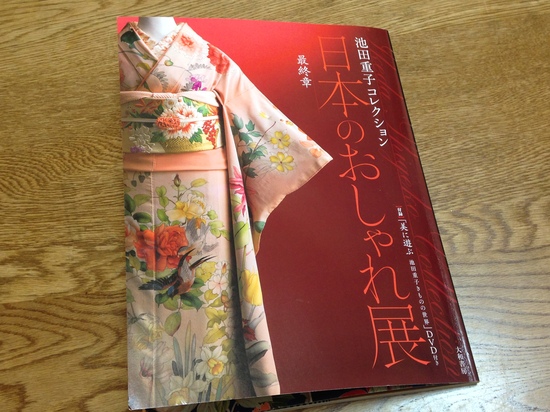
安達さんは、熊本在住のきものライターですが、その活躍は留まる所をしらず、ただいま、銀座松屋で開催中の「池田重子コレクション 日本のおしゃれ展」でもコアメンバーをされてます。写真は同展のカタログで、このテキストも安達さん。
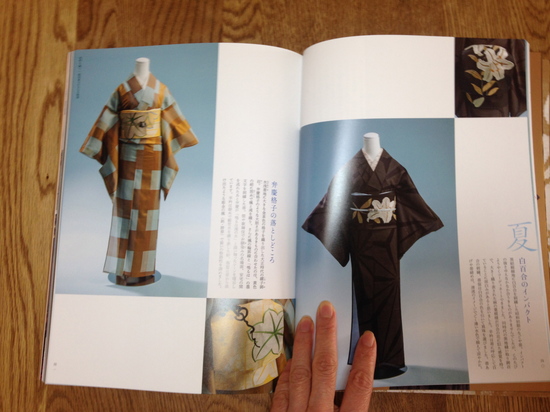
実は先日の熊本への帰省中、安達さんのご自宅にお招きいただくありがたい機会がありました。なんと、ご主人さまのお手料理をいただいたのだ!粉を二次発酵させて、角煮まんじゅうとか作ってくださったのだ。お手製ケーキまで!大感激。ご夫婦で、息子さんを大事に育て、生活を慈しみ、仕事にいそしみ、、、、、これこそ、豊かと言うんだろうな〜〜。
で、安達さんとのお着物のコーディネートの話しをして、「必然性」という言葉が心に残った。背景に物語のある、唯一の取り合わせ。ぱっと見て、色が合ってるとかだけではなく、ずっと強いものがある。それを作らねばと、思い知った次第です。ヨシダ、がんばる。
始動です。

明けてからちょいと帰省しておりましたが、本日、戻って参りました。さあさ、本格始動です。今年もがんばりましょう。

今日、熊本空港から羽田に飛んで、その足で銀座に出て、池田重子さんの「日本のおしゃれ展」と、濱野太郎さんの展示会を拝見しました。とことんやってる所が共通点だなあ。身につける物には意味があるんだ。そこまで、掘り下げなきゃダメなんだって、お二方から学びました。よかったわん。

上の2枚の写真は、雲仙に家族旅行した時のものです。フェリーに乗るとき撮りました。天気がイマイチで残念ね。みんなで変顔で撮ったチョー笑える写真もあるんだけど、母と姉に、絶対載せちゃダメときつく言われましたので、載せられません。残念。初笑い取れたのに。(「変顔で撮った」と言うより、「変顔になってしまった」。よっぽど変だよ。)

下の2枚は姪。かわいいでしょ。
今年もよろしく!

2016年、はじまりました。気持ちのよい青空の一日でしたね。遠くに富士山も見えました。
このブログを見ていてくださる、あなたさま、旧年中はありがとうございました。今年も健康ないい一年でありますように!

当方は、今年もバンバン、作って作って作りまくる年にする所存です。去年を越えねば。お着物のご注文を多数いただいているので、数は出来ないですが、ボリュームのある仕事したいです。
思うことは多々あれど、考えはまとまらないし、とにかく作ろう。手を動かすぞ!おー!
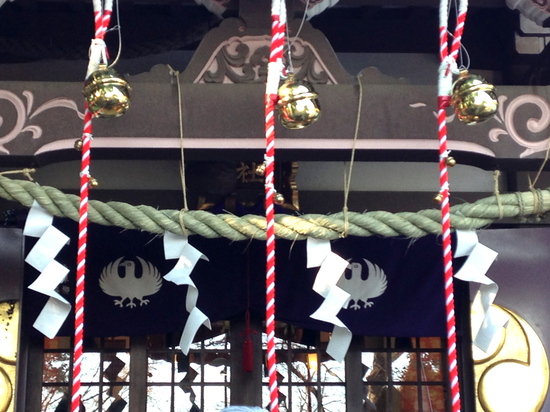
写真はうちの近所の神社なのだけど、ちょっとだけ遠出の散歩しててバッタリ見つけたのだ。近所と言っても知らない所、まだまだいっぱいあるね。獅子舞もやってて、びっくり。お獅子に頭をかんでもらったよ。
眼の話し

昨日の夕方、ふらりと出かけた南林間の生協で化粧室に入って、ふと鏡を見て驚いた。右目が真っ赤だ。充血の激しいヤツ。うっわー。
ただの充血かしら?どうしよう?明日は土曜だし、仕事手伝いに来てくれる予定入ってるし、病院行くなら今しかない。年末だしね、善は急げ。
で、近くの、以前一度行ったことある眼医者さんに行った。しばらく待って、呼ばれて、久しぶりだから、お医者さんに診てもらう前に、まず検査をしましょうと。
検査の結果は告げられはしないのだけど、看護師さんに話しかけ、アレコレ聞くおばちゃんの私。だって知りたいじゃん。そんなに混んでなかったしね。
視力検査。0.5 と 0.7 だそうだ。ガックシ、、、昔は、2.0 を誇っていたのに。
優しい看護師さん曰く、私、近眼の入った乱視だそうだ。昔からそうだったのだが、若かったから自力で補正していたんだって。年を取ると自力補正が出来なくなって、見えなくなってくると、、、
私、年を取ると人は老眼になるものだって思ってた。だから、自分も老眼になるのは覚悟してたけど、近眼の入った乱視になるとは思ってなかった。教えておいて欲しかったわー。
知らないことってたくさんあるものだなあ。知らないまま、こんなに年を取ってしまったわ、おほほ。
その後、お医者さまに診ていただいて、真っ赤なお目目はただの充血ってことでした。一安心ですが、今日も真っ赤でーす。
*写真は今日の夕方。うちの近所。月が大きくてびっくり。
クッピーラムネの思い出

封筒を買いに、近所の100円ショップに行った。けっこう混んでたので、いつもは通らない駄菓子のレーンを抜けて、目的地の文具コーナーに行こうとした。目の端に駄菓子のパッケージが入り込む。ん?足が止まる。
あっ!これは!!
クッピーラムネ!!!
なんと、これは、祖母との思い出のクッピーラムネだ。うううわーー、40年ぶりの再会だよ。

出会いは40年前、、、、いや、もっと前か、43年くらい前か。たぶん、母の里帰りに付いて東京に行った時に、祖母が近所で買ってくれたのではなかったか?
我が家は駄菓子は御法度なうちだったので、禁断な感じがしたのと、パッケージのウサギとリスに引き込まれた。(私のひいきはウサギだった)食べてみると、あまりの美味しさに目が丸くなった。はじめての味。東京の味だ。
(行動範囲がチョー限られている子どもの頃の話しよ。それに、味はご想像の通り。あと、発売元のカクダイ製菓は名古屋の会社と判明。名古屋の味だ。)
かくして、私はクッピーラムネのとりことなった。
ひらがなを覚えたての頃、祖母によく手紙を書いていたのだが、何度か返事が、箱買いしたクッピーラムネとともに送られてきた。感激して、大事に大事に食べたなあ。

という訳で、早速買ってきました。大人買いしてもいいのだけど、そんなに食べられない。一種類ひとつずつね。グミも出てたよ。私の小さい頃はグミなんかなかったなあ。
味は、変らない。重層が入っているからか、お腹がはる感じがたまらなく良い。
あ、おばあちゃんにお供えする前に食べちゃった!ゴメン、また買ってくるよ。
もうすぐ祖母の四十九日。(生きてる人間の都合で法会は済んでます)
昨日のこと

昨日は外出日。いろいろ行って、刺激ビシバシいただいてきましたよ。
まず目指すは西荻窪。大ファンの店がありましてね。アンタイディーというアンティーク屋さん。大ファンと言っても、今まで一度しか行ったことはなく。ブログのファンなのです。毎日昼ごろ更新されるのを楽しみにしています。普通の文章と凝りすぎない写真。好きなんだなあ〜。実店舗も、とても、とてもよいのです。(先日移転されたので、行きたかったのです)
それから、濱野太郎さんの個展を拝見しに、ギャラリーみずのそらに行きました。濱野さんの作品は、実物見なきゃです。うっわーって伝わってきます。その「うっわーー」は、膨大な仕事量から生み出されているのがよく分かった。
そして総武線に乗って東へ。目指すは浅草橋です。岩崎さんご夫妻の「増孝商店・冬場所’15」へ。
久しぶりにお会いする岩崎さんは、お二人ともいいお顔とたたずまいで、並べてある品物もいい感じで、ああ、この人らが生み出したものがこれらで、これらを生み出した人がこの人らねって、思わず見比べてうなずきます。身につけたいって思う人が多いのもよく分かる。
濱野さんとも岩崎夫妻とも、充分な時間はなかったけど、お話できてとてもよかった。彼らと話し続けられるよう、私もしっかりした仕事、やって行こう。
この後、実はもう一件、拝見したい個展があった。蔵前からさらに北東に行く予定だった。しかし、時間も経路もあやしい。その後さらに予定がある。うーむ、あきらめざるを得ないか、、、浅草橋の問屋街をふらっとのぞいてハマってしまったのが敗因か、、、
という訳で恵比寿に向かう。高校の同窓会の忘年会です。時間はじゅうぶん余裕のはず。が、恵比寿で降りて、はた、困った。どっちに行けばいいのかチンプンカンプン。iPhoneさまのマップが頼りだが、ああ見方が分からない。さまよい歩きながら「もうっ、田舎もんの集まりなのに、なんでこぎゃん分かりにっか所ですっと」となっかぶる。(「なっかぶる」は半泣きになるの熊本弁)そしたら、電話がなり、「大丈夫ねー、迷ってなかね?」と天の声。ひょー、同級生のありがたさよ。おかげさまで、大変たのしい夜とあいなりました。
*写真は、増孝商店の近く。
「増孝商店・冬場所’15」は23日まで。情報こちら→☆
濱野太郎さんの個展は、本日19時まで。
津田千枝子型染展、YANAGISAWA YOHJI展、四十九日イブ

先日のことですが、津田千枝子さんの個展を拝見しに、青山の八木さんにおじゃましてきました。津田さんの新作、見たかったんです。
やっぱ、津田さん、すごいです。色と形が、布と染めが、ピタリと合っている。くぅー、カッコいい!型や版が自由自在で、ゆったりしていて、その実、すごい完成度。
八木さんのあと、お近くのギャラリーで同時開催中の「津田千枝子型染帯のはぎれ100展」にもおじゃましました。こちらは、手に取って拝見できまして、眼福、触福。
その後、渋谷に移動して、ヒカリエ8階で開催中の、「YANAGISAWA YOHJI 2016SS Collection」に伺いました。墨染めの、パターンがきれいな洋服です。パリの街並とかに合いそうだなあ。お知り合いの方のおすすめで拝見しに行きましたが、大きく羽ばたいて欲しいなって思いました。
そして、東急東横店のフードショー(デパ地下)で、お刺身とお寿司と日本酒を買って、母の実家へ。祖母の四十九日の前日なので、叔母やらと一献かたむけたいと思って。
お仏壇に挨拶して、お線香あげて、祖母の写真を持って居間に移動。祖母が好きだった、脂おおめのお刺身を写真に供えて一緒に。叔母二人と、いとこと、祖母のことや、立て替える前の家のこと、ずっと前に亡くなった祖父のこと、叔父のこと、いろんな話し出来てよかった。
*写真はうちの近所。*青山八木さんでの、津田千枝子展は終了しています。
サンタ?

今、大麻の糸を染めている。最近寒いから、一日中、熱い大きなタンクがあるのはありがたいこと。湿度も上がるし、空気潤います。うふ。
で、染める時は、熱湯を触っても大丈夫な厚さがあるゴム手袋をするんだけど、その色が鮮やかな緑。たまたま赤いフリースを着ていたら、、、
あら!私ってサンタさん???染めてる色が茶色というのも、トナカイ彷彿か?薪も茶色ね。クリスマスの薪のケーキあったよね?
しかし、サンタさんはフリースを着ているのか?きっと現代のサンタはそうだと思う。色も鮮やかだし、軽いし、手軽よね。
大昔のサンタさんの着ていたものは、どんな素材で染料は何だったんだろうね?化学繊維や化学染料、開発される前から、サンタさんいるよね?(←当たり前!)木綿かな?毛織物?それに茜?いや、コチニールか??あの赤染めるの大変よね?うーむ。染め物職人、織り物職人、大変だったわ。インドか新大陸からの輸入だったりしてね。
ふだん、イベント事に関係ない生活をしていますが、クリスマス近いんだなあ。季節感は大事だなあ〜。さっきラジオで、今日は旧暦10月28日で、小春日和といえる最後の日になるかもって言ってたよ。
ずっと前のインタビュー

星読みで有名な、石井ゆかりさんのブログ「石井NP日記」を、久しぶりにつらつら見ていた。私、石井さんのファンなのだ。(とんとごぶさたしているけど、お着物もっても下さってるんだぞ、えっへん。)
んんん?!!!
上から2番目の記事に、「染・織と言えば、こちらの吉田さんだった!!」とある。「吉田」はよくある名前で、「吉田」と言われても自分のことではないことも多々だが、こ、これはもしかしたら???
リンク先は、まごうことなき、拙アドレス。ぎょ。ドびっくり。
個展に「いきそびれてしまった。。。。(涙)」とある。
いやはや、ご案内状はさし上げていたものの、遠方だし、お越しいただけなくて当然と思ってた。それが、会期後とはいえ、こうして気にかけてくださっていたとは、何ともありがたく、うれしい限り。石井さん、あったかいなあ。
添えてくださったリンクは全部で4つあって、一番上が先日の「三角・吉田」のレセプションの拙ブログ。
2番目が、ずーーーっっと前に、インタビューを受けた時の、石井さんのブログ。なんと2008年だよ。お会いしたのは2007年だ。
3番目が、5年前の個展に、石井さんがお越しくださったときのこと。
4番目が、その日いただいた御本をめぐる話し。(もちろん、この本は、今も大事に持っている)
まあ、どれも、なんとなつかしいこと。2番目のリンクのインタビューは、特にだな。
私、Wさんという仮名で登場している。これ、石井さんがはじめに書いて下さったときは、Mさんだったのだけど、読ませていただいて、ちょっと優等生過ぎるようで恥ずかしく感じて、Mを逆立ちさせてWに変えてもらったのだ。私、そんなにリッパじゃないし。ダメダメなところいっぱいあるし。
でも、書いて下さってることは、まったく私が話したこと、その通りなのだ。ダメダメなところも話したんじゃないかなあと思うのだけど、それは、この場に必要じゃなかったから、端折られただけ。
今だったら、Mのままで載せてもらったかもしれないなあ、、なんて思った。
石井NP日記はこちら→☆
*写真は、石井さんのインタビューで、撮ったもらったショール。記事の中で、「全然うまくいかなかった」とあったので、さっき引っ張り出して、撮り直してみた。が、緑色がちっとも出なくて、これでは石井さんが撮ったのの方がよいなと思った。
小島秀子織物展、シムラの着物ミナの帯展

昨日は、青山八木さんへ「小島秀子織物展」の最終日に駆けつけてきました。ぜひとも拝見したい展覧会でした。開店直後の時間をねらって伺いましたが、すでに複数のお客様。その後もぞくぞく。さすがー。
お作品は、静謐かつ、躍動感あって、チャーミングで、確かな技術に支えられてて、ものすごく素敵です。小島さんの世界にまよい込んだようでした。引き込まれました。
よいお天気の一日です。八木さんから、青山墓地を突っ切っててくてく歩いて、イトノサキさんに顔を出しました。発売になったばかりの雑誌「nid」を見せてもらいました。イトノサキさん、特集されているんです。店内の写真に拙作も!
イトノサキさんをあとにして、南青山の住宅街をふらふら歩いて、TOBICHI へ。「シムラの着物ミナの帯」開催中。人間国宝で文化勲章受賞者の志村ふくみさんと、「あの」ミナですものね。鳴り物入りって見えちゃってたけど、ぜんぜんそんなことなく、すっごく自然で楽しい展示会でした。何より、自作を着て、案内をしているアトリエシムラの若いお弟子さんの姿がまぶしかったなあ。いいなあ〜。
*写真はうちの近所。散歩の途中。(ちょっと走って、すぐギブアップして歩いてたとき撮りました。)
祖母のこと

先週、母方の祖母がなくなった。大正4年生まれ。100年のあっぱれな人生であった。
サバサバ、あっさりした人で、自然にみんなに好かれる人だった。99歳まで元気でいて、一年くらい施設にお世話になって、なくなった。
私は小さい頃からずっと、人付き合いが下手なのだが、この祖母とははじめから仲良しだった。
私が幼稚園の頃、双子の妹が生まれ、いろいろ大変だったので、祖母が東京から熊本に、手伝いに来てくれていた。二ヶ月くらいいてくれたのではないか。遊んでもらったなあ。バドミントンをした記憶もあるよ。約40年前。祖母60歳か。
祖母を熊本空港に送っていったとき、泣いたの覚えてる。
小さい頃、熊本では売ってなかった、、というか、存在をしらなかった駄菓子(ラムネやガムなど)を送ってもらってた。宅急便なんてなかったころ。小包で。
お葬式で、お坊さんの読経のとき、私はただただ座って、目をつぶっていた。親族席からご会葬の方々に黙礼しなければならなかったんだけど、末席の目立たない場所だったので。お坊さんの読経とお焼香の匂いに癒された。ああ、私、疲れているなあ。おばあちゃんが、みほちゃん、ちょっと休んで行きなさいよって言ってくれてるみたいだった。
*写真は去年。白寿のお祝いで、ひ孫に囲まれる祖母。
速報!山本きもの工房さんで、藤田織物さんを見た!
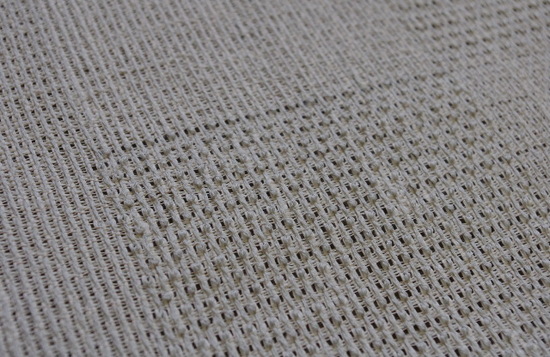
今日は、横浜の山本きもの工房さんで開催中の「こころよきもの展」に伺いました。今回は「立体に織るという世界」というタイトルがついてます。のどから手が出るほど、興味津々の分野です。
それも、京都の藤田織物さんから匠の方がお出でになって、詳しい説明もしてくださるとのこと。おお!!!これは、なにを置いても、ぜひとも拝見したい、ぜひともお話をうかがいたい。そう願って、今日の日を楽しみに待っておりました。
で、伺ってきましたよ。で、お話しもいろいろ詳しく伺いました。物作り魂に火がつく、とっても刺激的なお話でした。織物というのは、経と緯のバランスなのですが、そのひとつの完成形を見た気がします。それも、通り一遍の完成形じゃなくて、糸のことも織りのことも、文化のこともファッションのことも、何でも知り尽くした熟練の方が、それを、一旦こわして、遊んで、もう一度作り上げた新しい完成形です。
曲がりなりにも織りをやってる人間からの、心からのつぶやきですが、「ここまでやるのか、、、、こりゃ大変。。。。」呆然となりますよ、これは。
山本さんが惚れ込んだの、よく分かります。展示会は明日までです。情報はこちら。ご興味の方、急げ!
*写真は、山本きもの工房さんのサイトからいただきました。
きものSalon に載ってる!(ほんのちょっと)

夕刻、ふらふらと本屋へ。いつもの気分転換だ。女性誌のチェックは怠らないように。特に着物関係は。
お、きものSalon 出てますね。
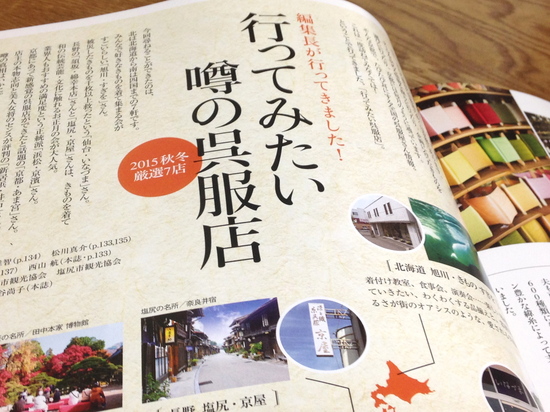
パラパラ見てたら、ひとつの小特集が目についた。「編集長が行ってきました!行ってみたい噂の呉服店 厳選7店」ですって。
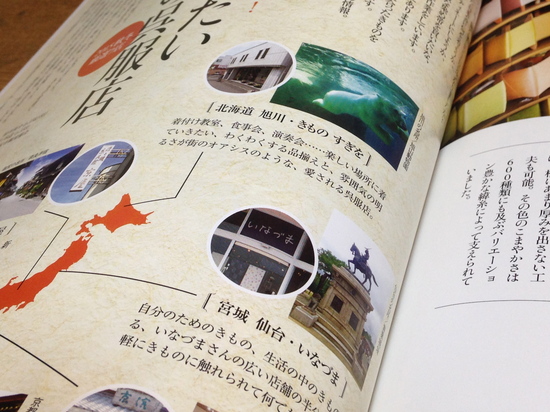
あ、宮城の「いなづま」さんが載ってる!
いなづまさんには、駆け出しの頃、大変お世話になった。特注もたくさんいただいた。呉服屋さんから特注いただいたのははじめてで、ドキマギした。ほんと育てていただいたなあ、、、。
いなづまさんは、先の大震災でご自身も大変な被害にあわれた中、津波で流された簞笥の中のきものを生き返らせて、きもの愛好家の皆さんに大感謝されているよし。すばらしいなあ。
ちょっと目を移すと、ああ! 北海道の「すぎを」さんも載ってる!!
すぎをさんとは、ごく最近のご縁。面識はないのだけど、、、、すぎをさんのページをパラパラ、、、

あああ!!!なんと、「ラブ・ロスコシリーズ、Pink & Green 2」ではないですか!ここで再会するとは!!
拙作載せていただけるとは感無量。雑誌に載せる品として選んで下さったってことは、お店の顔として認めて下さってるってこと?だったら、うれしいです。もっともっとがんばります。
店長の鈴木さんもお顔入りで載ってました。電話でお話しましたね。うふふ。これからも、どうかよろしくお願いします。
クレアを読みに、つきみ野イオンへ。

発売中の雑誌、CREA の巻頭特集が、村上春樹が熊本を旅したことを書いているって知ったので、興味津々、本屋行ってきた。編集部の、世界中どこでもいいから出かけて下さいって申し出に、村上さん、熊本を選んだそうだよ。
目指す本屋は、近くのイオンの3階ね。(上の写真の左側に写ってます。つきみ野イオン)
3階まで、階段駆け上がって、CREA、発見。巻頭は、、、おお、これか。けっこうなボリューム。女性誌なのに、おしゃれじゃないのがいいねえ。(おしゃれじゃないのは、巻頭特集だけで、表紙とか他のページはとってもおしゃれです)

橙書店で、シークレット朗読会&トークが開催されたのが圧巻ね。橙書店、先回の帰省で行って、すっかりファンになったのだ。
しかし、村上さん、我が熊本をまったくほめてない。観光スポットにまったく行ってない。いや、それが面白いんだけど。たんたんと、ひょうひょうと。
人吉では、うなぎを食べただけで、他のどこにも行ってないって。国宝の青井阿蘇神社があるでしょう!!!
阿蘇には行ったみたいだけど、トウモロコシ食べて、ビッグな盆栽(?)見たことしか書いてないし。
熊本城の周りをジョギングして、行き交う人に「おはようございます!」って挨拶されすぎて閉口したって。こんなに挨拶するの、世界中で熊本だけだって。
私、村上さんと同じ、神奈川県民なんだけど、夕方、近くの大和高校の脇を通ると、道を使って練習してる部活動の生徒さんに挨拶されまくって困る。(坂道だから、ダッシュの練習などにいいのかな?)
神奈川県民も挨拶するぞ、村上さん。
夕方、私がそこを通るのは、仕事行き詰まって、いたたまれなくて、逃避行してるのです。精神状態はボロボロなのにキラキラした高校生に、挨拶されると、アジャストできずに困る。
あと、熊本の車は軽ばかりって書いてあったぞ。図星かもだが、神奈川県も軽が多いぞ。(私が住んでる界隈のみか?)

文句ばかり書きましたが、世界中の中から熊本を選んでくださって、ありがとう、村上さん♡
NHKラジオ第2の、「英語で読む村上春樹」愛聴してます。
*写真は、我が家から、つきみ野イオンへの道すがら。緑、あるのよ。熊本には及ばんけど。
坂口恭平トーク&魔よけライブに行った

昨晩は久しぶりに電車に乗って外出。目的地は護国寺の講談社の26階です。ビックリするほどいい眺め。

何に行ったかと申しますと、「坂口恭平トーク&魔よけライブ」。内容、何も知らず、よく分からないまま、とにかく、行きたかったから行ってきました。
実は私、坂口恭平さんの大ファンなのです。ご本人、はじめて。生ライブ、もちろんはじめて。うぉー!

紛れ込んだ天空で、坂口恭平と同じ時間を過ごす。んー、いい。
坂口恭平さん、熊本出身、熊本在住。私、同じ、小学校、中学校の出身です。この日の曲も、熊本つながりが多く。一曲目が牛深ハイヤ、2曲目が石牟礼道子さんがいらっしゃるホームの歌。ラストは、西港って三角(みすみ)西港の歌。トークのイントネーションがなつかしい。
我が地元から、これだけのものを作り出し、勢いよく、あふれるように発信をしている坂口恭平を尊敬している。新政府、賛同してる。

ああ、リフレッシュしたよ。
こんなに生き返ったの、7月中旬に、新宿のベルクに、坂口恭平ドローイング展みに行っていらいかも。ベルクでの展示は、8月いっぱいに延期されたとのこと。また行けるかな。

さあ帰ろう。私もがんばるよ。
坂口恭平氏のtwitterはこちら→☆
午前中の任務完了

今日は朝から、帯2本の仕上げ作業をしました。蒸して、水元して、伸子張りです。
染織の仕事のうちで、やっぱ、水を火を使う段階は、キツいなあ。特にこの季節。室温とか、湿度とか、見ないよ、怖いから。
糸染めと仕上げと言う、はじめと最後の段階で、火と水は必須ですから、毎度のことです。朝はやくはじめるとか、上手くやらないとね。

夏休みのプールのあとのような心地よい疲れです。昼寝したいなー。ノルマを操作すれば、出来るかな、、、、
*写真はたった今、撮りました〜。夏の午前中の我が家です。今日も暑いね。どうか気をつけてね。
あまりの暑さに、、

閉じこもって仕事してますが、、周りは動いているようで、みんなすごいなあ、何よりだわと思ってます。
毎朝、散歩をして、余裕があればちょっとだけ走ります。ちょっとだけね、帰り道だけとか、、、外出はきほんこれだけ。

昨日は、来客がありました。only only のご注文のお客様、来年の今頃、この方にとって、一枚目の着物に取り組むことになりそうです。
こだわりの色がある方で、その色をどう取り入れるかが、課題です。お互い想像力を羽ばたかせて、やり取りを重ねることになるでしょう。楽しみです。

お客様、お二人連れでした。たまたま遠来のご友人が上京されていたのでご一緒に。
このご友人、着物通の方なのですが、着物デビューしようとしているお友達に対し、「(着物の買い物で)失敗させたくない」と言うお気持ちを強くお持ちで、いろいろアドバイスし、ご自分の着物を貸して着る機会をつくってさし上げ、、、、、至れり尽くせり。
なんかホッコリしました。こういうお友達の存在が、着物界に飛び込むハードルをググーッと下げますものね。逆を言うと、こういう方がいないと、けっこう難しいかも。大人になってから新しい世界を開拓するわけですからね。
ご友人同士の信頼関係がすばらしいと思った。着物作るって、どこまで走るか、どこまで無難にするかってこともある。そのさじ加減も、客観的に伝えてくださる。まさに親友って感じですてきでした。
作る方もしっかり寄り添いまっせ!
虹!

夕方、虹を見つけた!

近所に買い物に出て、急いでいたのだけど、虹の方へ吸い寄せられて、どんどん歩いて行った。牛乳が重かった。

なんと、ダブルの虹!

何人もの人が、同じように写メしてた。ずっと空みてたら、蚊にさされた。

この頃お気に入りの、クリスト物件。

虹は東の空だったんだけど、振り返ったら、夕焼け空。

昼間は霧雨ふってたし、こりゃ、虹の出る条件、バッチリね。

ちょっとムンク。

このくらいのおとなし目の空もいい。色もいい。

とてもいい。

いい。
和のランチ会、帯と再会

先週末は、目黒区八雲で、着付け教室をされている、「着付けほのか」さんでの「和のランチ会」に入れていただきました。ほのかさんはお茶の先生でもいらっしゃいます。
この日は、お茶室でのマナーを簡単に教えていただき、お手前をいただき、おいしいランチをいただき、着付け講座も開催していただき、もう盛りだくさん!楽しかったです!

着付け講座のモデルは、一緒に参加したこの方。なんと、締めている帯は、私が織ったものです。以前お求めくださった帯を今回お持ちくださいました。

八寸帯「スモールバード」。なつかしいわー!お似合い。よかった。

お茶室でパチリ。すてきなお茶室でしたわー。

右が先生。いい感じでしょ。額あじさいがお庭に一輪だけ咲いたのを飾ってくださいました。

おまけ画像。つくばいでの清め方を習って、はしゃぐ私。まじめにせーい!
*着付けほのかさんのサイトはこちら→☆
*この着付け講座の様子は、あと2回つづきます。なんと、帯の早変わりなんよ!
築城則子展、ランチデート、堀口度子展

昨日は着物でお出かけしました。まずは築城則子さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんへ。築城則子さんは、小倉織りを復元させ、縞の可能性を大きく大きく広げたすごい方です。
お話しで、心に残っていることのひとつは、織りの制約、縞の制約の中で、クリエイティブの自由度があるのは、色である。色で、自由に羽ばたくってこと。確かに、築城さんの作品は、すっごく自由で洗練されてて、美しい。
それから、2300本の経糸を織るのに、ひと越ひと越に、地響きのような音をさせているってこと。それを3回打ちで打ち込んでいるそうだ。そっか、、、地響きか、、小倉織りは元々は武士の袴で、戦いの装いであるという。地響きを立てて、敵地に切り込む勝負の服なのだなあ。

その後、お友達とランチしました。中華の点心とビール。お友達と言っても、なんとこの日初対面!着物の仕事をしていることと、同じ年であることが共通点。フェイスブックでつながって、なんか、この人、気が合いそうとは思っていた。が、これほど合うとは!不思議なものだ。
狭くなりがちの私の世界をふわっと膨張させてくれた。ありがとう!
それから、お友達も一緒に、南青山のイトノサキさんへ、堀口度子さんの上布の展示会を拝見しに。
実は私、堀口さんに、石垣島で、20数年前にお会いしているのです。数ヶ月前、堀口さんのお名前を偶然耳にしたとき、何とも言えない郷愁にかられました。20数年前、まだ織りをはじめてそんなに時間はたってなく、右往左往していたころ、はじめて行った石垣島でよくしていただいた。忘れられない強烈な思い出です。度子さん、お会いできてよかった。ご本人も、織っているものも、相変わらず、一本気が通ってて、気持ちいいです。
堀口さんの個展は、昨日で終了しましたが、一部の作品は引き続きイトノサキさんで拝見できるそうです。
*写真は、昨日の私の恰好。帯が拙作です。締めたところは着付けが下手すぎてNG(ごめん)。ただいま片付け中でパチリ。
これ、実は巻き取りしているときに大失敗してしまって、商品にならなかった分です。仕立てでカバーしてもらい、締められるようになりました。こんなことでもない限り、新作は自分のものになりません。
昨日は着物の業界人ばかりに会いましたが、まあ評判よしだったかな。(←だったら、もっとちゃんと締めろ!)もとじさんで、帯締めの作家さんに、わざわざ声かけてもらって、ほめられた!やった!
サイ トゥオンブリー、原美術館
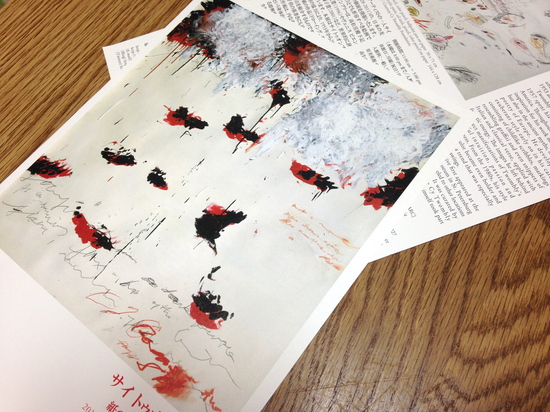
最近のこのブログ、お出かけ記録と化しておりますね。普段は閉じこもりの私、モンモンと悩みつつ、ダーンと壁に激突しながら、モクモクと染織してます。その合間を縫って、「これだけははずせないっ!」とあらば、といそいそと出かけます。
行ってきましたよ、「サイ トゥオンブリー 紙の作品、50年の奇跡」。それも初日に。ものすっごく楽しみにしてました。原美術館も、すごく久しぶりです。(ハラビのサイト→☆、展示会のことはこっちの方が分かりやすい→☆)
サイ トゥオンブリーの本物みるの、いくつ目だろ?過去、2点は見てる。3回目にして、やっとまとまった数見られたわけか。画集は3冊持ってる。
私、サイ トゥオンブリーのこと、知らなかったのだけど、いつだったか、もうずいぶん前、「ヨシダさん、絶対好きだよ」って教えてもらって、日本の美術館では見られないそうだから(のち、数点はあることが判明)、Amazonでカンで画集買った。それが、ものすごーーーく良くて、心酔しまくり。今日にいたる。
で、ドキドキの今回の展示会だったわけです。5つの展示室の、1室目からやられたなあ、、、。1室目は違う年代の作品を組み合わせて展示されてて、2室目からは、年代毎なのだけど、年代、関係ないのです。だんだん構築されてったとかじゃなくて、はじめからいきなりいいのです。独自の自然な世界観。ぜんぶ、いい。いや、天才って言ってしまえばそれまでなんだけどね。
この日は、トークもあり、もちろん申し込んでました。2003年に、エルミタージュでのサイ トゥオンブリー展のキュレーターをした方のお話でして、この方、それ以前にエルミタージュで、ルイーズ ブルジョア展も、開催したのですって。まだ冷戦が終わって、10年くらいの頃だって。すごく受け入れられたらしい。ロシア、すごいな。この展示会も日本巡回してくれ〜〜〜(って、ずーっと昔の話しですね)

今日は話題をもうひとつ。
原美術館は、私にとって、特別な場所です。今は亡き祖父と二人で来たことがあるのです。
もうずーーーっと前、たぶん、10代終わりの頃の美大受験の頃か、、、、。夏期講習やらなんやらで、上京しては母の実家に居候してました。現代アートカブレのクソガキだった私は(今もほとんど変わりませんが)、こと有る毎にアートスポット巡り。原美術館は、大のお気に入りの場所です。
ある日、祖父が、「ミホコ、今日はどこに行く?」「ハラビ?」「三菱の開東閣の近く?」「おじいちゃんも行こうかな」というのです。どうやって行ったか覚えてません。品川から歩いた?五反田からバス?祖父はその頃、70オーバー?
祖父は現代アートなど、まったくの無関係で生きてきた人ですが、タイトルのプレートをひとつひとつじっくり読み、とても満足げな顔をしてました。
その後、うなぎを食べさせてくれました。どこでだったかは、まったく覚えてませんが、東京で食べたはじめてのうなぎだったと思います。
祖父はその、5,6年後に亡くなりました。もう20年くらいになります。
*上の写真は、展示会のリーフレット。下の写真は、原美術館の通用口の前に立つ私。籠から制作ノートが覗くのがいいでしょ。着付けが下手っぴなのと、いつも同じ着物なのは、お見逃しのほど〜〜。
同窓会に行って来た

今年もこのシーズンがやってきました。5月下旬と言えば、我が母校、熊本県立濟々黌高校の同窓会です。
去年は、この東京同窓会、我々62年卒が幹事学年でして、この日のために、一年間かけて苦楽をともにし、準備に奔走したのです。あれから一年たったのか。早いなあ〜。
と言うわけで、今年は一学年下の、63年卒の皆さんが、幹事をやって下さって、我々は楽しむことに専念できたのです。

幹事さんたちの、舞台裏のヒヤヒヤドキドキの記憶が新しいだけに、「今、ドキッとしてるだろうな」とか、「盛り上がってよかったな」とか思ってました。
同窓会の幹事って理不尽なことが多いんだよね。社会とは違うルールやノリがあったりするし。それを乗り越えてこそのこの日なんだよねえ、、、。63の皆様、本当にお疲れさまでした。おかげで同級生や先輩後輩に再会して、また新しくお出会いして、楽しい時間を持てました。ありがとうございました。

写真、下の2枚の中央にいるのは、幹事メンバーのKくん。校黌斉唱を盛り上げてるところ。すごい!私は、彼の勇姿に目が釘付けで、舞台の方を見られなかった!(笑)
鈴木マサル展、Basso conti展、田中昭夫展、ミナペルホネン

昨日は、六本木、青山方面に出かけました。走れ、走れ。大急ぎで、たくさん、展示会を拝見してきました。
まずは「鈴木マサルのテキスタイル 傘とラグとタオルと」。六本木のギャラリールベインです。この方の傘を見たかったのだよ〜。カラフルで楽しくて、晴天でしたのに、雨あめ降れふれ、です。これ、欲しいなあ、、、とあっという間に憧憬のユーザー目線です。会期は5月24日までです。
*写真はすべてこちらの展覧会で撮りました。

それから、歩いて(走ったんじゃないの?笑)(六本木から南青山って歩いて20分くらい)、南青山のイトノサキさんへ。「Basso conti 織物展」、開催中です。きちんとした素直な着やすそうな着尺や帯でした。草木染めの良さ、感じました。こちらも、24日まで。

その後、別件がひとつありまして、気付くと、ぎゃー6時半すぎてる!!!走って、走って、すべり込んだ先は、DEE’S HALL。そうです、「正藍型染師 田中昭夫の布 頒布会」です。ついたのは、6時45分くらいでクローズは7時なのけど、まだまだお客様もたくさんいらして、熱気ムンムン。ああ、この方が田中さんか、、、
ちょっと拝見してすぐ退散するつもりが、動けなくなりました。これは大変なものだ。無理してでも手元に置きたい。相当無理して、ひとつ、分けていただきました。結局、7時20分くらいまで居てしまいました。
こちらは、本日23日が最終日。今日は18時までですよ。

さあ、走ります!次は、ミナペルホネンの20周年「ミナカケル」、目指すはスパイラル。こちらは、20時までですので、これまた滑り込みセーフ。こちらも、大勢の人でにぎわってました。が、すっとミナの精神が通っているようで、人の多さが気にならないと言うか、、、空気感まで作る布、すごいな。こちらは、6月7日まで。
帰りついても、一夜明けても、興奮してる私です。
芭蕉布展、小川待子展、線を聴く

今日は銀座に出かけました。展示会を三つみて、自然と美について考えました。

まずは、もとじさんへ。喜如嘉の芭蕉布展の、平美恵子さんによるギャラリートークでした。
芭蕉布は、ことあるごとに拝見しているので、目新しいことは何もなかったのですが、行ってよかったーーーー!やっぱ、いいですね!迫ってくるものがあります。昔と変らず、受け継がれ、織られている、奇跡のような布。ちょっと怠けたり、我を出したりしたら、あっという間に無くなってしまう。
平美恵子さんが、「芭蕉布は自然といわれるけれど、実は、人手を掛けて、手間ひま掛けて、選別して選別して、バランスをとって作った布だ」っておっしゃってたのが、心に残る。ただ自然にしていただけでは、出来ないのだって。そりゃそうだろうけど、その労力は想像を絶する、、、

それから、思文閣銀座で、小川待子展を拝見しました。迫力あったーー!陶器とガラスが抱き合ったような。すごく好きでした。人の手を感じさせない。まるで、溶岩が自然に冷えて固まったよう。でも確かに人の仕事だ。
掛け花入が欲しかったなあ。そばに置きたい。買えないけど。こんな物作りしたい。

その後、メゾンエルメスで開催中の、「線を聴く」へ伺いました。線に主眼を置いたグループ展ですが、こちらもめちゃくちゃ面白かったです。特に、ロジェ・カイヨワさんの自然石のコレクション。すべてがいいのだ。完璧な自然。お茶室に置きたいような、心がすっとする石でした。
備忘のために、ロジェ・カイヨワさんの言葉を、写し書きしておきます。
「あちこちに石がみずから書き残したしるしは、それにこだまを返す他のしるしの探索と精神を誘う。
私はこうしたしるしの前に佇み、みつめ、記述する。
そのとき、遊びがはじまる、発明であると同時に認識でもある遊びが。」

*写真は今日じゃないよ。以前いった長坂のアフリカンアートミュージアムの庭。iPhoneに残ってた。
I’ve been to the African Art Museum at Yamanashi Prefecture. It has beautiful tiny garden. I saw a gardener who was working hard to keep the garden nice and neat.
国展に行った
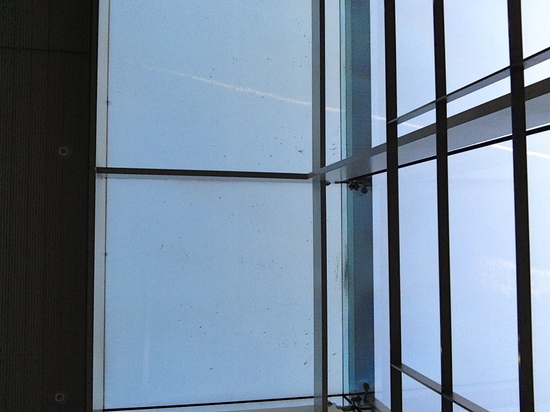
昨夕は、国展に行って来ました。金曜は夜間も開いているので、ねらい目です。地下鉄は、六本木でなく、千代田線に乗って乃木坂で降りる。ささっと入れるので、時間短縮できます。染織しか見ないのだけどね〜。
見たかったのは、小島秀子さん、下地康子さん、川村成さん。それぞれに、すばらしかったです!技術も、センスも、ピカピカに磨かれてるなあ、、、、やりたいことをやり遂げてる感が、ゾクゾクするほどよかったです。
他にも染織部門レベル高くて、「こんなによかったの!」と感激しながら、見てました。手で作ったテキスタイルは、やっぱいいなあ。もっと身につけたり、生活に取り入れるべきだっ!と、ひとり息巻きながら見てましたが、実情は難しいのが、モンモンとするところです。流通しなければ生き残れないというのが、私的な意見ですが、その解決策はなかなかです。
午後8時の閉館ギリギリまで、見ても見ても飽きず、見てました。
*写真は、国立新美術館。乃木坂側の入り口。飛行機雲が登り龍!
ある連休の午後

ゴールデンウィーク後半のある午後、お客様の予定があった。前日になって、「ゴゴイチうちなら、一緒にお昼にしたらいい」と思いたち、お誘いしたら、乗って下さった。

るんるんと準備。献立は、カレーとサラダ。スーパーで、「オトナの方がお見えになるのだから、ビールでも買っとくのが礼儀」と(「酒飲みは理由が必要」とどなたかも書かれてましたね)、缶ビールをゲット。お仕事の打ち合わせだから、軽くね。

その午後、遠くから貴重なお休みを利用してお出で下さったその方と、再会を祝し、お互いの健康と、これからの仕事の成功を祈念し、カンパーイ!
気分は一気に盛り上がり(私だけ?)、楽しくミーティングをすることが出来ました。世間がお休みだと、お昼のビールも許される空気が漂ってるよね。(思い込み?)
気分だけでもお休みモードになりたい私につき合ってくださって、ありがとうございました。ご意向をくみ、いいもの織るよう、がんばります。

写真は伊豆半島。
もちろん、大ウソ。うちの近所。歩いて10分、走って5分のところ。小田急線沿い。このずーーっと先は江ノ島だよー!
ありがとうございます、本日12周年。

今日、5月1日は、染織吉田の設立記念日です。生きてるだけでビックリ状態のまま、なんとか織り続けてきました。本当にどうもありがとうございます。12年間、ずーっと、支えていただき、教えていただき、応援をいただき、おかげさまで生きています。心から、感謝申し上げます。
12年という時間の流れのはやさにビビります。最近、年を取ったせいか、ますます加速してきました。どんどん織らないと、織り尽くせません。焦ります。
私自身は、12年前と今と、ちっとも変わってないようにも思います。自分の表現したいものを、どうにか形にしたいと七転八倒。失敗して転んだりもしましたが、その都度、助けられ、起き上がることが出来ました。ひとつひとつを思い出し、ありがたかったなあと、感謝にたえません。
今日も、普通に仕事してました。明日からもずっとです。ひとつひとつ、丁寧に。元気で仕事が一番です。
染織吉田を、どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。

*写真は、数日前。朝ジョグしてたら、いきなり目に飛び込んできた、満開の藤の花。近所なんだけど、藤が生えてるって認識してなかったら、突然、花のかたまりがボンッと出現して、ビックリした。
この木が生えてる場所は、アパートの横の、ジャリ敷きの駐車場の脇。盆栽をそのまま大きくしたような、カッコいい枝振りの藤には似つかわしくない。ここ、何十年か前までは、お屋敷のお庭だったのかな。相続かなんかで取り壊されて、アパートと駐車場になったけど、藤は残されたと推理します。それは幸なのか不幸なのか。
お茶会へ

昨日は、お茶会にお誘いいただきまして、ウキウキと出かけてきました。鎌倉まで♡ 今年のGW、唯一の、お出かけです。
実は私、お茶席、初参加。ドキドキしまくりでした。お誘いいただいときに、無作法者であることと、紬の着物と帯しか持ってないことを白状しまして、カジュアルな会だから気にしないでって言っていただいてました。その上なんと「私も当日は、ミホコさんの帯しめるつもりだから。」と!!!ビックリ、大光栄です。
一夜明けまして、なんか、いろいろ濃密過ぎて、すご過ぎて、上手く感想書けないけど、お茶っていいですね!それをしみじみ感じました。私の知らない世界を垣間みさせていただきました。
床の間の完璧さに、打たれました。ここまで、一分の隙もないほどの空間に作り上げるって、すごい。余白って美しいなあ。この空間に自分も居させていただくことの不思議さとありがたさ。
風情のあるお庭を眺めながら、お薄を一服いただきました。向こうのお山には、山藤が咲いているのが見えました。
お道具拝見、文化の凝縮だなあ〜。お仕覆は17世紀の印金だとか、、、それを実際に使ってだもんね。お茶はタイムマシンだね。
ご一緒させていただいた方々との出会いも、たいへん貴重で、引き合わせて下さったのも、ご亭主さまのお心遣い。どんだけ準備してくれたんだろうって思うと、ただただ頭が下がります。
お茶席のあとは、酒宴も用意してくださってて、これまたすばらしく、ほろほろ酔いで帰宅しました。
*写真は、お庭の梅の木。ご亭主はこの木の下でお薄を点ててくださった。帯も新緑に映え、ご亭主に寄り添い、うれしかった。
代官山へ
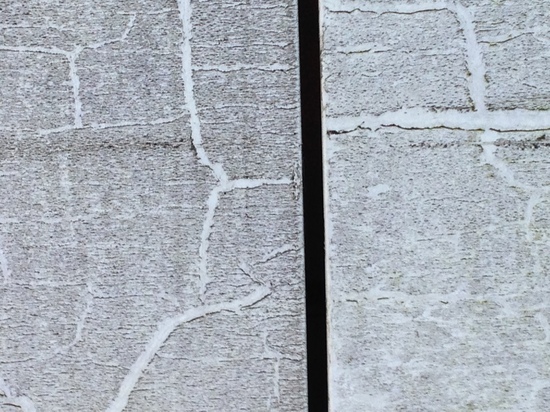
100歳の祖母を見舞いに、母が上京していて、少々時間があるというので、代官山で待ち合わせた。
待ち合わせ場所を指定したのは私。外出したら、用事をハシゴするのは必須です。今、代官山で拝見したい展覧会をやってるのだ。「勝山健史織物展」。
駅で落ち合ったら、ごきげんの母。「代官山、いちど来たかったんだ。若者の街だけん!」ガクッとくる私、、、ちょ、、、
まずは、目的地。ヒルサイドテラスへ。勝山健史さん、いやはや、すばらしかったです。糸もいいのだろうけど(塩蔵繭!)、なんというか、、、、バランス最高。糸や織りのレベルが高く保たれてて、そこに効かせ色がピピピっと来てて、ふわー、すっかり感服、いい気持ちだ。
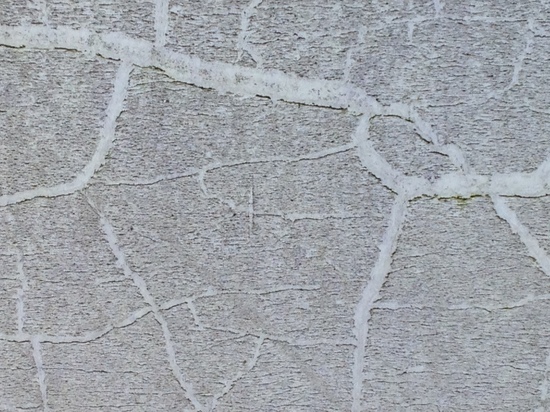
母に「このヒルサイドテラスの裏は、何か知らんけど、すごいお屋敷なんだよ」と言うと、興味をしめす。行ってみようかと言うと、行きたがる。おお、公開されてるじゃん。
旧朝倉家住宅は、渋谷区の持ち物で、一般公開されていた。私は入場料100円、母は60歳以上無料。庭が傾斜地で歩きにくいが、とても立派。お宅もいい材をふんだんに使った大正期の建築。
しかし、母よ。若者の街だから、代官山に来たかったんじゃないの?
まあ、よいです。
代官山らしい、クールなレストランで夕食を食べ、私はビールを4杯飲み(グラスだよ。だんだん味と色が濃くなる)、ほろ酔いかげんで駅まで歩き、実家に帰る母とは東横線内で別れました。
母には、ブログに余計なこと書かないように釘を刺されたので、これ以上のことは書きませんよ。うふふ。
*写真は、オサレな代官山ではありません。神奈川県の端っこの、我が家の近くです。
乗松祥子さん、善林英恵さん

昨日は面白い日でした。友人の帽子作家、善林英恵さんが、展示会のために上京。「この機会に行ってみたい所がある。よかったら、ご一緒に?」というお誘いを受け、等々力の「延楽梅花堂」に行って来きたのです。
「延楽梅花堂」のことも、こちら主宰の「乗松祥子さん」のことも、はたまた乗松さんの御本「百年の梅仕事」についても、今までまったく存じあげず。
つい先週、善林さんが、「久々のヒット本」と評した「百年の梅仕事」を早速取り寄せて読んでみた。読みはじめたら止まらない、引き込ませる本だ。乗松祥子さんに興味津々。生き方、働き方、考え方に心酔する。(善林さんのブログ、この本の紹介のページ→☆)

等々力の高級住宅街の、たいへん分かりづらい所にある「延楽梅花堂」にたどり着き、商品など見せていただいていると、乗松さんご本人が、お茶を入れて、2階から下りてきて下さった。
まあ!ツヤツヤピカピカのエネルギーあるお姿は、まさに神の降臨!って大げさですけど、そんな感じしました。お話できてよかった。ちゃんと生きてきた方には、神様がついてますね。梅の話しはもちろんですが、善林さんや私のことなども、興味を持ってお聞き下さり、とても励まされました。
大きな梅干しをひとつ食べさせて下さいました。たぶん古いものだと思う。大きな種をティッシュにくるんで、大事に持って帰ってきました。帰り着いて、早速、くるみ割りで割って天神さんを取り出して、しげしげ眺め、それから食べました。苦みの中に、年代物の極上ブランデーの味がしました。
善林英恵さんの作品展は、日本橋三越本店5階スペース#5にて、4月28日まで。善林さんのサイト→☆
延楽梅花堂のサイト→☆
*写真は、購入してきた杉田梅の梅干しと「百年の梅仕事」
きるものがたり’15

横浜に出かけてきました。「きるものがたり’15」。山本きもの工房さんの、和裁教室の生徒さんの作品展示会です。何年か前にも伺っている展示会ですが、今年もレベル高かった。きりっとしてるの。それに、楽しく縫った感がありありですてきです。こりゃー、縫うのも着るのも楽しいでしょう。振り袖あり、子どものきものあり。いいな〜。
山本親方の作品も展示されてました。超極細の宮古上布のお着物の美しさに見とれてたら、やはり仕立てに秘密あり。解説いただきうなりました。
「麻の着物の擦れの場所はこことここだから、それを防ぐにはこうする。それでも擦れたら、3mmだけ落とせば、生き返らせられる」とか。
すごいねー、仕立てには、知恵と技が、これでもかってくらい詰まってる。仕立ての奥深さを聞いていると、きものを着ないともったいないって思います。だって、文化の結晶を身につけるのだよ!

着付師の友人と待ち合わせていたので、その後も、ああだこうだと着物談義に花を咲かせました。自分が着物の仕事をするようになるとは、つい15年前まではまったく思っていませんでしたが(着物を織って20年ですが、はじめの頃はまさか本業になるとは、思ってなかったです)、着物のおかげで、日本のすごい文化をほんのちょっとかがせてもらってます。底なしなので怖いですが、あらがいがたいものですな〜。
山本きもの工房の、「きるものがたり’15」の情報はこちらから。4月15日まで。
*写真は横浜じゃありませんよ、うちの近所。朝。
7k fun run!

今日は自分的にはビッグな日で、在日米軍キャンプ座間の桜祭りで、7kファンランに参加してきました。7km走れるのかドキドキ。天気予報もあまりよくない。

朝10時のスタートに、相武台前の駅からてくてく歩いて8時半には基地に着いた。パスポート持参。事前登録としっかり照合された。免許証でもよかったみたいだけど、暗証番号覚えてなかったからね、パスポートで登録したのだ。手荷物検査も、さすが厳しいです。

さあ、スタート、がんばれ、私。目指すは完走。
(リアルな私をご存知の方は、皆さんご承知と思うけど、私は運動全般さっぱりダメ。幼稚園の時から、走るの飛ぶの投げるの泳ぐの、全てダメ。平衡感覚もリズムもまったくダメ)

7kmは、基地の端もコースになってて、そこは米軍のゴルフ場の際なのだ。フェンス一枚向こうは、そこは普通の日本。神奈川県座間市。よく見慣れた普通の住宅やアパートが建ち並ぶ。かたや、ひろーくて気持ちいいゴルフ場。なんだかなぁーー。
誘導や受付していた、軍人のお兄ちゃん達は、命令あれば、シリアでもイランでも飛んで行くのだろうか。優しい気のいい青年に見えたが。なんだかなぁー。
などと思いながら、ときどき写メしながら、完走しました!!!歩かなかったのがえらいぞ、私。42分弱だった。まあまあだ。

イースターのうさぎさんもいましたよ。
I ran 7km today ! It’s really big for me. I think I did good job.
I enrolled the cherry blossom festival at camp Zama US army.
Kanagawa Prefecture where I live has many US bases. I wondered the differences of lives separated just a few inches fences. I saw the young people in the base they may fly to the middle east! I hope they will remember the cherry blossom even in the different continent. And I hope to myself to remember I was here today !
山岸幸一さんのトーク会に行った

山岸幸一さんの個展のトーク会に、銀座もとじさんに伺いました。

やー、すばらしかったです!もう何度も拝見しているのですが、今日初めて対峙したような気がするよ。見るたびに新鮮で、新しい気付きをたくさん与えて下さるお作品です。

織りで出来る最高のこと、追求し切ってらっしゃる。大尊敬です。織りの可能性はとてつもなく広い。ぽやっとしている暇はないぞっ!って思いました。
織りはやっぱ、糸と染めやね。追求の仕方は、いくらでもある!!
山岸先生の展示会は、銀座もとじさんにて明日まで。

写真は展示会とは関係なく、、、、。うちの近所、ジョグの途中。
この一週間

この一週間は、多忙で、めずらしいことに3日も外出しました。それも着物で。ふー。疲れちゃいけないけど、疲れたよー。

金曜の晩は、すごく華やかなパーティーに呼んでいただいて、ありがたかったなあとしみじみしてます。帝国ホテルでのパーティーなんて、滅多なことでは参加できません、私。

尊敬する方々にも、久しぶりにお会いできたし、、、、これを実にできるか、、、切実です。

仕事は、、、、ちょっと大失敗してしまって、大反省して、リカバーして、どうにか進めてます。大失敗は、only only じゃなくて、それだけは本当によかったよ。
*写真は、なんか、基地みたいじゃん?実は、うちの近所のスーパーの駐車場。朝はやく。
Last week made me very busy. So I need to be refreshed.
I ease myself this afternoon, I walk to the shrine close to me, and shop daily things at the Ito-Yokado supermarket.
On my way back home, I drank a tiny bottle of Sake at the park watching the cherry bud.
落語会

昨晩は、落語会に行ってきました。「古今亭菊之丞・春風亭一之輔 二人会」。所は清澄白河。深川江戸資料館の小劇場へ。
落語、久しぶりで、るんるんです♪

前座が終わって、菊之丞師匠が出て来たとたんに、ぷわーっと空気が華やぐ。さっすがだなあ。クリーム色だったか、明るい着物に、濃い青緑の半衿だったかな。座布団に座って、手をついて深くお辞儀するとき、ツヤっぽい首筋にドキッとする。それだけで、持ってかれる。ひと笑いさせてもらって、さあいよいよって、羽織をするっと脱ぐとき、ふたたびドキリ。

お次ぎは、女形っぽい菊之丞師匠に対して、立役ぽい雰囲気むんむんの一之輔師匠。こちらは黒紋付。やーん、かっこいいー♡これまた、お辞儀や、羽織を脱ぐ仕草にドキドキである。それだけでいい気分にさせてもらって、あの笑い。至福でした。

写真は、ブルーボトルコーヒー。清澄白河まで行くなら、偵察してこなっきゃと行ってきました。いまだに行列だったので、その場でコーヒー飲むのはあきらめて、並ばないで買える豆だけゲットしてきました。まだ飲んでないのだけど、すっごくいい香りです。楽しみ〜。
今日の出来事、前半(後半はありません)

朝起きて、寝ぼけ眼で、まず糸の世話。昨日染めた糸が、一晩タンクで、しっかり染液を吸って待っている。おお、いいじゃん、いい色だ。よく染まってる。洗ってベランダに干す。

外に出て、辺りをジョギング。今朝は、南林間方面へ。
あ!あれは!!なんと、クリストが出現してた。

大興奮で写メしまくる私。ミラーに写ってる。

クリスト好きです。でかい現代アートが好き。すっとする。
今朝は寒かったね。水たまりに氷。クリスト、写ってる。(←違うっ!)

ヨチヨチ走りなのに、ヘトヘト汗だく。うちに帰ったら、うまい具合に糸が乾いてた。色を観るためなので、完全に乾かなくてもいいんだ。うん、この色でいこう。そっそく糊付け。緯だからごく軽くね。

干してる間に、朝ご飯。

後片付けなどしていると、おお、糸があらかた乾いた。重量のない糸だと、乾きがはやいね。早速巻いて、すでに試しのブラッシングがほどこされてる経糸を織る。

試し部分は、あっという間に織れる。うーん、もうひと工夫。考え直し。スケッチブックと色鉛筆。
そして第二回の試し。ブラッシングの一色目を染める。乾かないと、染め重ねられないので、この間に、郵便局行っちゃおう。

歩いて行ける郵便局は4つあるのだけど、今日は、南林間へ。あのクリストが気になって仕方ない。日が高くなって、空気がかすむ。花粉が飛んでるのかな?

いやあ、やっぱ、すごいわ。(ご近所現代アート!)行きも帰りも、引き続き大興奮。

帰って、ブラッシングの2色目。乾かしている間に、昼ご飯。

仕事に戻って、そわそわしてきて、ラジオをつける。なんか、一人でいたくなくて。しばし、ラジオに聴き入る。
皆と一緒に黙祷。
新作?

新しい帯、できました!
って大ウソよーん。
これは試し織り。今、傍らで、いろいろな試しを繰り返してます。これから取り組もうとしてるのは、もっと重厚な感じのするものですが、次の次の次くらいには、こういうのもいいかなあ。
どなたか、こんな帯、締めて下さいませんか?
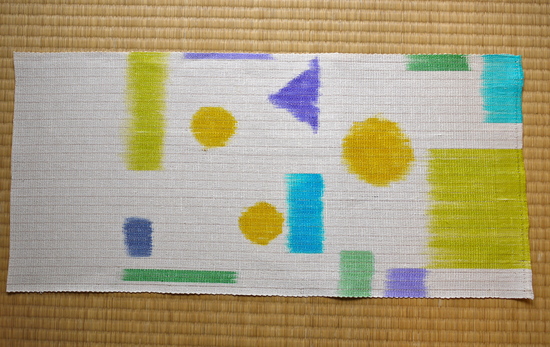
この試し織りは、この位の長さです。本番前にするこういう遊びが、何かを運んでくると思ってます。ま、何より、自分が楽しいしね。
このくらいから、ジリッジリッと完成度あげて行くのが、カイカン。
ジャック・ドゥミの少年期
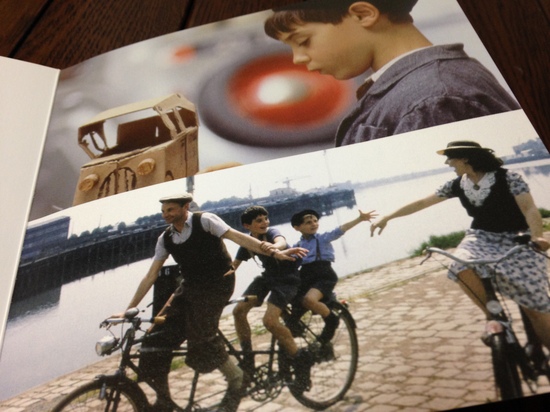
昨日の夕方、ちょろんと抜け出して、映画みてきました。銀座のメゾンエルメスのル・ステュディオで。
「ジャック・ドゥミの少年期」。1991年のフランス映画です。24年前。私、この映画が上映されたの覚えてる。どこに住んでたんだっけ?岐阜かな?情報誌かチラシかなんかでみて、すごく行きたかったけど、行けずじまいだった。
「わたしは残しておきたい 輝くばかりのジャックの少年期と夢見るようなあのまなざしを」っていう、印刷された宣伝文句も覚えてる。
それで、この映画をやると知って、これは行かなきゃって思って予約をいれた。(無料だし!)
本当に「夢見るようなまなざし」だった。「輝くばかりの少年期」なのだ。両親と弟と、周りのみんな。優しいお母さんが印象的。ああこれこそが幸せだ。最高の幸せだ。
が、実はそんないい時代でもないのだ。戦争があり、ドイツ軍が攻めてきて、爆撃があり、疎開を余儀なくされ、貧しいし、直接描かれてないけど人が死ぬ。望む進路には障壁だらけだし、、、
そんな中で、「夢見るまなざし」を頑固なまでにキープするのだ。
ジャック・ドゥミは、夢をかなえて映画監督になった。15本の映画を撮ったんだって。で、59歳で死んだ。その直前に、奥さんのアニエス・ヴァルダがこの映画を撮った。人は何をやっても死ぬんだなあ。生きて死ぬなんてあっという間なんだなあ、などと思った。
なごみに載った!
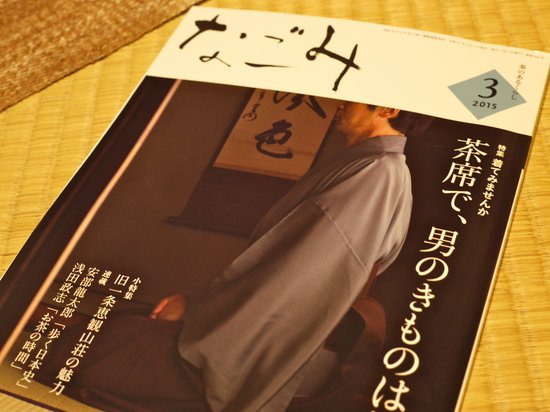
今発売中の、月刊誌「なごみ」に、私の角帯が載ってます!「なごみ」って、裏千家の雑誌で、お茶の方々にはよく読まれているみたい。3月号は、男のきもの特集です。
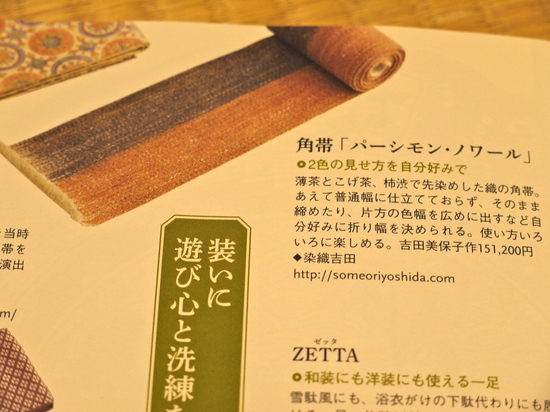
ほら、このページ!23ページです。「小物使いでお洒落なコーディネートを」っていう特集にピックアップしていただきました。
角帯、「パーシモン・ノワール」。ブラッシングカラーズで、柿渋を、明るい茶色の方はそのまま、黒に近い焦げ茶の方は鉄媒染で染めました。経糸はタイ産の絹のキビソです。なかなか存在感のある角帯になったと思っています。
申告してきた

7時半にうちを出て、抜けるような青空のもと、大和市の青色申告会に行ってきました。朝9時からのオープンに、8時10分には着いたのだけど、すでに5名ほどの方が、並んでました。この時点で、私はすでにヨロヨロ。みんなすごいなあ〜。
8時45分に入れてもらえて、ほどなく見てもらえて、一部数字が合ってなくて、担当して下さったお姉さんと、なんだかんだ一時間弱ほどのキンチョーしたやり取りがありましたが、どうにか提出することができました(合わせてもらった)!昨年に引き続き、イッパツ提出です!!!これで無罪放免です!
やれやれ〜。「ほっとされましたでしょう」とお姉さん。「春が来ました♡」と返しました。さあて、春ですよ〜。(夜には祝杯をあげました)
I am proud to tell you I finished my tax return with no pain.
2 year in row, I could do this successfully. It was beautiful blue sky.
itonosaki さんへ伺った

南青山に出かけました。ちょっとウロウロしたけど、やっぱ、おしゃれな街よね〜。たまに行くと、目が覚める。レベル、高いよ。行かなくちゃね。

伺った先は、itonosaki さん。昨年オープンした、かっこいい着物のセレクトショップです。
itonosaki さんでは、「手描き友禅と上田紬の楽しみ」と銘打った展示会を開催中で、今日はそのトーク会でした。私が伺った時には、もうずいぶんたくさんのお客様がお揃いでしたが、まあ、その華やかなこと!
作者の方は〜って見回したら、その輝きの真ん中に、ひときわ輝いてるお二人がいらっしゃいました。わーー、ビックリ、お二人揃って、すっごく美人さん!華があるわあ〜。作者が輝いてるの、いいなあ、、、、
お話の最中もドキドキしてました。まだまだ羽ばたかれるお二人だなあって思いました

写真は、我が家のお姫様、こうめちゃんです。一番下の写真は、お付きのものを従えてるところです。
こうめは今、満開だよん。魅惑的な香りをあたりに発散しております。
Koume-chan who is my lovely plum BONSAI is in full bloom now! She has so beautiful aroma.
今日も良き日

今日もまたすばらしい日でした。九寸帯、クリスタル・ストリーム (crystal stream)に再会できました。締めて下さってるところ、拝見するのは、2回目でしたが、前回とは全く別のお着物に(何と訪問着!)合わせてくださって、大感激。この方の、既成概念の枠がない感じ、いつも、いつも、感服しています。
うふふ、ランチにお誘いいただいたのですよ。代官山で。とんでもなく本格的なフレンチのコースでした。メインのあとにチーズが出てきて、デザートのあと、また小さなお菓子が出てくると言う、、、、こんなの何年ぶりだろう、、、、
ゆっくりお話できたのも、何よりうれしかった。仕事する上でのビジョンも多くの気付きをいただいた。5年ごとに考え直すことが起きるよ、、などと、、、、そっか、留まってちゃダメね。

すてきな方なのだよ〜。
うれしかったのは、今日のお仕度をしてる時の、クリスタル・ストリームの話しで、「畳紙(たとう)を開けたら、私の好きな色が、目に飛び込んできたの」って、満面の笑みで、おっしゃって下さったこと。色の打ち合わせ、細かくしましたものね。やった。よかった。
この帯のことを書いているのは、この辺りです。→1,2,3,4,5
平山八重子展、荒木節子展へ行った。

平山八重子さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。平山さんは、紬織りの大家で、とても美しい着物を織られる方です。すっごく緻密な仕事がしてある完璧な作品です。多色だし、絣だし、計算されまくり。でも、まったくうるさくなく、響き合ってる。すごいな〜。ご本人が、サバサバしている感じなのも、またいいのです。
計画段階の、設計図も拝見できて、頭の中のぞかせてもらった気に。ふぁー、たじたじ。
その後、新宿に移動して「荒木節子 染の風景展」の最終日にすべり込みました。地下一階に、バーンと荒木節子さんの世界が広がってました。
荒木さんは、今、最も売れてるちょう有名な作家さんのお一人。独自の染めの世界を築かれてます。ずっと前から尊敬の念を持ってましたが、まだきちんとご挨拶したことなく、、
今日も、「あ、いらっしゃる」と思いながらも、話しかけられずにいると、、、。荒木先生から、「あら、すてきなバッグですね」っておそれおおくも声をかけていだきました。今日のバックは私の自慢の一品、大ファンの、はやしのりこさん作です。それをきっかけに、私の織りの話しもさせていただき、意気投合。「がんばりましょう!」ってお話しに。
そうなのだよな、、、諸先輩のように、切り開いて行かないと、、、、いろいろありがたい一日でした。
*写真は、我が家のアイドル、こうめちゃん。この写真は3、4日前。今日はもう8輪咲いて、満開まぢか。こうめが我が家に春を告げてくれます。
Koume-chan (my sweet bonsai plum tree) is the symbol of ice-breaking season of my house. She tells me Spring is just around corner.
岩波ホール

金曜の夕方、神田小川町の TEORIYA さんでの、影山工房講座を終わったら、もう真っ暗だった。早めに出たら、観に行こうと思ってた展示会があったのだけど、ちょっとタイムアウトだなあ。
神保町に向かって歩く。スマホにメール。「竜巻だいじょうぶだった?」えっ!検索すると厚木市で午後3時頃。わー、知らんかった。厚木はすぐ隣り。
神保町をウロウロしたかったのだが、この日は、なんせ寒かった。ウロウロなんて不可能だ。さて、どうしよう。神保町で、寒くなくて、何か面白いこと。あ!岩波ホール!ものすっごくご無沙汰してるけど、岩波ホールがあるじゃん!
とりあえずビルの下まで行って、看板を見上げる。上映中なのはポーランドの「幸せのありか」。みようかなあ、、、当日一般1800円が、ちとネック。
そしたら、見知らぬおじさまに声を掛けられた。「失礼ですが、今から映画みられるのですか?もしよかったら、前売りチケット、安く譲りますよ。もう最終日で最終回だからね。1200円でどうでしょう?」

と言うわけで、特別に寒い日の晩、若い頃、憧憬の念を持って足を運んだ映画館で、映画を観た。
映画は、脳性麻痺の男の子が、小さい頃から、成長していく過程。それがみずみずしいこと、美しいこと。実話なのだそうだ。
主人公は、私より、一回りくらい若いんじゃないか?だとしたら、映し出されるポーランドの風景は、私と同時代なのだ。共産圏だったし、庶民の生活は、決して豊かでないけど、とても、とても美しく、心が揺れた。
ああ、私、映画を観ることが好きだったなあ、、、、映画で、世界中に旅して、主人公になりきるのが大好きだった。忘れてたよ。
*写真はうちの近所。遅くに帰ってきたけど、竜巻の影響は一切なかったみたい。
I saw movie at Iwanami Hall at Jinbocho, Tokyo on Friday evening. Iwanami Hall is a very famous film house showing anti-hollywood movies since opening. When I was very young (about 20 years old), I visited there so often.
影山工房公開講座に行った

染織家の影山秀雄さんの、公開講座「織りを伝える」を受講してきました。影山さんは、織り歴40年。染織の家に生まれ、ずっと織りと共に生きて来られた、マエストロです。
私は影山さんのシンパサイザー。すごいと思ってる。その経験に基づく膨大な知識。それを惜しげなく伝えて下さる姿勢。ほんと、ありがたいです。
私が受けた講座は、「私の好きな糸の話」と題されてて、影山さんの実際に使ってられる糸とそれで織った布の実物を見せていただきながらの講座でした。
木綿、絹、野蚕、麻、カシミアやヤク、蓮糸。
糸をどう使いこなして行くかってことが、大変面白かったです。双糸にしたり、追い撚りを掛けたり。この糸を使いたいってことがあって、使いにくい糸だったとしても、目的に合わせ、一手間、二手間掛けることで、経糸にも使えるし、また、唯一無二の布にもなる。これぞ、私が求めていることだ。私の弱いところでもあると思う。まだまだ追求が足りないぞ、私!
講座のほか、影山さん考案の機道具も展示販売されてて、こういう知識の交流、道具の交流、いいなあ〜と思いました。影山さんから教えたいただいたことと、譲っていただいた道具を、しっかり自分のモノとしなくちゃね。がんばろう。
*写真はうちの近所。ブロック塀の一部がガラスでいい感じ。なんだけど、ガラスの向こうは集積所。下半分の緑はカラスよけの網。ちらと見える黄色は、大和市指定有料ゴミ袋。
I have joined into the lecture of weaving by Mr. Kageyama yesterday. He showed the cloth made from the fiber extracted from lotus. It was a soft, savage and beautiful cloth.
濱野太郎展に行った

二子玉川で開催中の、濱野太郎さんの個展に伺いました。よかったなあ。観てると、濱野さんの思いが伝わってくる布でした。素材をどうしたいのか、どう織りたいのか、貫いてる感が半端なくて、すてきです。
そのあと、二子玉川のおしゃれエリアに用事があり、ウロチョロしましたが、心打つものは何もなく。心を振るわせるものこそ、作家が作るものだ。濱野さんの作品は、まさにそうでした。
帰りの電車から、ドラゴン発見。幸先よいぞ!
*濱野太郎展は、二子玉のKOHOROさんのお向かいで、2月1日まで。ネットでもお買い物できるようです。
I saw a rising dragon from train window on the Denentoshi line yesterday. The rising dragon brings good fortune to you and me!
雑感

年末から、いろいろ生活に変化をって思って実行してます。
仕事場の壁一面に棚を作ったのだ。2×4ってお安い材木を使ってね。ホームセンターとうちを20回くらい往復した。自力でやったにしては、大満足。
ベランダに植木鉢が仲間入り。梅とつくばねの植木を育ててる。
毎朝ちょっとだけジョギングしてます。
年が明けてからは、10年以上ぶりで日記を付けはじめた。それも5年連用。はて続くのか?

連日のisisの怖い報道を聞いていて、人質になってるお二方の年齢と私の年齢がそう変わらないのが、気になって仕方ない。我々が生きてきた時代は、ほんのちょっと前までは、総じて平和だったのでは?(ほんのちょっとが10年単位のお年頃だけどね。ほんのちょっとが、10年を2回かな。)
我々、ベトナム戦争とかは記憶ない世代だし。パレスチナはややこし過ぎて理解の範疇こえてたし(私だけ?)。天安門とか湾岸とか確かに怖かったけど。他にもいろいろあったけど、たいした記憶はない(健忘症かつ勉強不足の私です)。
私の中での大きな出来事は、ベルリンの壁崩壊と、ソ連崩壊で、このふたつとも、明るい輝かしい記憶。人間、やるなあって思った。高らかに歌い上げたいような、、、あくまで当時の私の感覚だけど。このふたつで、世界はいい方向に進んでるって思い込んじゃった。9.11までだけど。
一生懸命いきていれば、いい方向に必ずころぶって、少なくても思い込める世の中でありたい。
お二人、日本に帰ってこーい!
*写真は朝のジョギング中に。(←走ってないだろ!)
少年野球場、ばーちゃん、地震の記憶

自分的には、すごく気に入った写真が撮れた。iPhoneで撮ったものだけど、いいでしょ?うちの近所の、少年野球場。朝。

毎朝、ラジオ体操をして、その後外に出ることにしてる。目標としてはジョギング。しかし、ほとんど歩いてる。せいぜいヨチヨチ走り。きれいな風景を見つけたら、すかさずパチリ。

昨日は20年前の大震災を思いながら、、、今日は100歳の誕生日を迎えた祖母を思いながら、、、

午後にはひとつ、織り上がったよ!

My great grandma’s 100th Birthday is today, She has been walking and running this 100 years history of her own. Happy birthday Toshiko Ba-chan!
She knows Great Kanto Earthquake in 1923, also Great Hanshin Earthquake Disaster in 1995. And the Great East earthquake and tsunami in 2011.
Life is not easy, but she is still fine.
おばあちゃん、日本クラフト、白洲千代子展

祖母に会いに行ってきました。昨年末から、介護施設に入ったのです。
蒲田の駅から徒歩15分なのだけど、スマホの地図みながら歩き出したら、冷たく強いビル風に、あえなく降参。駅に舞い戻り、タクシーに。
実はお見舞いは二回目で、先日、帰省先から戻ったときも羽田から直行で行ったのだ。この時は、京急蒲田駅で早々に降参しタクシー。(私は降参しないとタクシーに乗らない。タクシー乗車は屈辱でもある、、、体力なしか、地図よみ能力なしを認めることとなるから。)両日とも帰りは迷いながら歩き。この辺の道は複雑。わからんわー。

今日の祖母は、顔色もよくツヤツヤしてて、私が「みほこだよー」と言うからかもだが、「ああ、みほちゃん」と反応してくれる。
祖母は、あと6日で、100歳なのだ。お祝いにファミリーが次々顔を出すだろうから、寄せ書きができるよう、台紙を作って壁に貼ってきた。折り紙の輪っかをつなげるのも作って飾ってきた。外出できないからね、お部屋をにぎにぎしく!

それから、日本クラフト展を拝見しに、六本木のミッドタウンへ。大賞が織り作品だったので、これは観ておきたいと。大賞を取ったのは、勝知恵美さんとおっしゃる作家さんの5本の八寸帯。これは本当にすばらしかったです。経糸が塩蔵の生糸で、緯糸は手漉き芭蕉麻糸とあった。素材ととことんつき合って、やり切ってらっしゃる。存在感、美しさ、はんぱなかった。
日本クラフトとかの公募展、入賞作などすごいの並ぶのに、イマイチ、人目にふれないのが、もったいないーって思います。こもってる感じがしてしまう。ミッドタウンって言っても、知ってる人しか行かない奥の5階のフロアだったので。

それから、ジュエリー作家の、白洲千代子さんの展示会を拝見しに、茅場町の森岡書店さんに伺いました。白洲さんとは、年末に白洲邸での忘年会に呼んでいただいたご縁です。美しい空間を構築する方だなあと思ったので、お作品を拝見したく。
白洲さんの今回の展示は、「本をイメージした陶器のブローチ」ということで、本そのものの形をしたものもあったし、本の中の挿絵のようだったり、空想が広がるもとだったりするような、すてきな作品が多くありました。色が効いてる。さすが、ジュエリー作家だなあ。かつ、光り物がキラッと効いてて、憎いわあと思いました。

会場の森岡書店さんもいい感じで、白洲さんの陶器との相性ばつぐん。置いてある本も、愛情あふれてました。この前行った熊本の橙書店さんといい、すてきな本屋さんってあるのだなあ。
(橙書店さんのことを書いた拙ブログはここ→☆。開店のときの挨拶文をもらってたのが出て来た。とてもいい文章だから、ご紹介と記憶のために、追記で書き写させていただきました。)
写真は、森岡書店さんが入ってる、第2井上ビル。古くて風格あってすてきだわ〜。でもきっと、うちのおばあちゃんの方がもっと風格あるね。なんてったって、東京駅と同い年よ、おばあちゃん!
村江菊枝展に行った
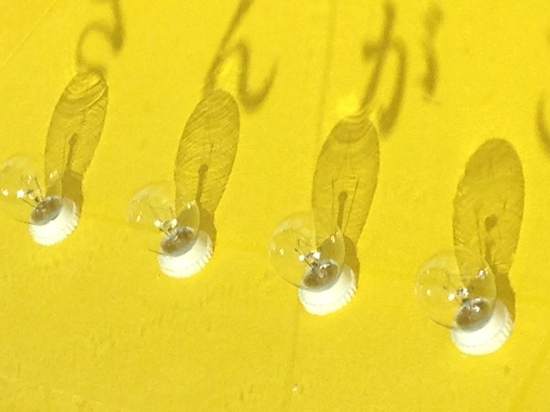
銀座もとじさんで開催中の、村江菊枝さんの個展のギャラリートークに行ってきました。村江さんの作品は、以前別の機会でみせていただいたことあって、そのとき、すごく印象的で、ぜひもう一度観たいって思っていたのです。

拝見し、トークをお聞きして、その美しさの追い方というか、求める美しさに対する一本気でいらっしゃるところとか、とても感銘を受けました。
家庭の中で、家事をするのと同じように、織りと取り組んでいるっておっしゃってたけど、こんなレベルで織ってらっしゃるってことは、どんなに家事も高レベルでらっしゃるのだろうと、憧憬の思いで、ボーッとしました。

写真は、和光のウィンドウです。和光のウィンドウ、四半世紀以上前、私が学生で、世間はバブルだったころ、銀座に出るたびに、ドキドキして観に行ってました。いつも最高に面白かった。いつの頃か、詰まらなくなり、気付くと日本の景気も悪くなってました。
久しぶりに和光のウィンドウが気になったってことは、少し明るいきざしでしょうか?
Today, I had a small excursion to Motoji who is my favorite kimono house in Ginza, to join the live talk show and kimono exhibition of Ms. Kikue Murae. I surprise with her attitude for kimono making that she weave the japanese kimono as same as she do the daily life.
Then, I went Itoya / stationary shop to buy a new file for 2015 works. After that, I went to Matsuya Department store and bought sashimi of GOOD Red Snapper. Clear Blue sky stayed on me today.
雑感・4

1月4日の朝から晩までの雑感です。
1月4日 午前中 熊本ゆかりの染織家展二日目、ギャラリートーク
さあ、いよいよギャラリートーク。この日のために、できるだけの準備をしてきた。早起きして着替えと朝ごはん。自分のことも、アゲてアゲてアゲて。上げないとしゃべれないよ。
トークのテーマは、織りと糸の深い関係について。いかに、糸の生の素材感を布に表現するかってこと。織り作家にしかできない、立体的な反物づくりについて。
お集りの方々に、織物の面白さをお伝えしたい一心だったが、ご満足いただけたか?自分としては、やり切ったのだけど。写真は、和の國さんのブログからお借りしました。必死にトークする私と、お聞きくださってるお客さま。けっこう前のめり?
1月4日 昼
豪華ランチを、高校の先輩がごちそうしてくださった♡がんばったご褒美かな?おいしかった。ペコリ。
1月3日から4日の全日 熊本ゆかりの染織作家展を通して
4日のトークをピークとして、多くのお客様にお越しいただきました。うれしい出会い再会で、感激しました。
昨年、この会で、ラブロスコシリーズの八寸帯、「ピンク&チャコール」をお求めいただいたお客様は、満面の笑みで締めてきてくださった。家が火事になったら、この帯もって、逃げるって!!!えー、ほんとーー!
2歳のかわいいお子さんを連れた若いお母さんに話しかけられ、この子が高校受験をする頃に、自分の着物を作って欲しいと。着物を作るってそういうスパンなんだなあ。この方の、人生の大きなストーリーの伴走者となれるよう、がんばろう。
友達もきてくれたけど、なぜか、私のいない時間帯にきてくれる人ちらほら。会いたかったが、お店の方に伺うと、ひとつひとつの作品を、じっくり丁寧に観てらしたよとのことで、とてもうれしかった。ありがとう。
1月4日 夜
今回の帰省で唯一の宴会。幼稚園の同窓会。42年の付き合いの面々。このリラックス感は何なのだ。ああ、緊張が抜けて行く〜〜〜。
1月4日 深夜
うちに帰って、お風呂に入って、パジャマに着替えて、しばらくしたとき、前のボタンを掛け違えてるのに気付いた。ガーーン、、、これ、42年前、幼稚園で習ったよ。ボタンは身頃の左右を合わせて、下から締めていくと、掛け違えない。。。。
雑感・3

1月3日の続きの雑感です。
1月3日 午後
昼過ぎに和の國さんを辞して、なつかしい上通と下通を端までふらふら。実はずーっと行ってみたいと思ってた本屋さんとカフェがあるのだ。ネット上で見つけて、3回前の帰省時くらいから、行けるチャンスを虎視眈々とねらってた。(←大げさ!)
橙書店と、その隣りのカフェ、orange。ここに行きたかったのだ。
下通のエンドひとつ前で角を右に曲がると、新市街に抜ける小さな路地がある。その角ッコんとこ。行ったこと無くても、地図を見ればすぐ分かる。へーー、こんなとこに、そんなおしゃれな店できたんだー。ま、ちょっと独特な雰囲気ある界隈だったわな。
えーっと、あった!ここだ!ドキドキ。本屋さんを扉を開けると、わー、吸い込まれる思い。思いっきり立ち読みし、選びに選んで2冊買い、orange でコーヒーをゆっくり飲みながら、次の日の「熊本ゆかりの染織家展」でのギャラリートークの草稿を書いた。
すっかり満足して、交通センターに向かう。ここ、もうすぐ無くなるのよね。今は名前が変わってしまったデパート、いにしえの「岩田屋伊勢丹」を目に焼き付けて、バスに乗って家に帰った。
1月3日 夜
夜中、静まり返った居間でギャラリートークの原稿を清書していたら、突如、スイッチが入ったように、ガーガーガーと音がした。ビクっとするも、何か懐かしい音だ。ちなみに旅先での原稿書きは手書きである。だから、ホントに静かな中での出来事。
なんなのだこれは?怪奇現象??宇宙と交信がはじまった???
驚いてそこら辺のざわざわしたものを触ったら(我が家の居間はいつも大変に散らかっている)、今度は、「いらっしゃいませ、100円になります。」と、高い声で機械がしゃべる。近くに住む姪のおもちゃだ。
さっきのガーガーガーは、おもちゃの電車が何かの拍子に接続したらしい。なんだか、おもちゃの国に迷い込んだ気分。他のおもちゃもしゃべり出すかな?もしかして、くるみ割り人形?そっちの国に行ってもいいなと思いながら、原稿を書いた。
*写真は橙書店のサイトからお借りしました。
*1月12日追記
橙書店さんに、「開店のお知らせ」が置いてありました。ちらと読むと、とてもすてきなことが書いてあります。請うてみると、オッケーだったので、いただいてきました。それが、先日買った本とともに、宅急便に入ってやってきました。読み返してみると、ますますいい文章です。覚えておきたいし、ここ読まれてる方にご紹介したいので、書き写させていただきます。
開店のお知らせ
小さな本屋をつくりました。
たとえば、
繊細な切子のグラス
素朴であたたかな焼き物
凛として美しい漆椀
そういった ひとつひとつを選ぶとき
大切に そっと 手に取ります。
心を込めて作られたものですから。
「一冊の本を選ぶときも、そうであってほしい。」
そんな気持ちで、つくりました。
言葉を紡ぐ人。
絵を描く人。
写真を撮る人。
本の顔を作る人。
それを一冊にまとめあげる人たち。
一冊の本もきっと、心を込めて作られてます。
大切に売りたいので、たくさんは置いてありません。
不便な本屋かもしれません。
探している本は見つからないかもしれません。
でも、旅先でふと出会う人や風景のように
本と出会える本屋でありたいと思います。
場所は「orange」の隣、名前は「橙書店」です。
近くにお越しの際は、ふらりとお立ち寄りください。
主人敬白
雑感・2

昨日の続きで、ここ数日の雑感です。
1月3日 熊本ゆかりの染織家展、初日 朝
朝イチで着物を着る。着物は一揃え、宅急便で送ってあるから、着るだけのはず、、、、、
着付けに先立ち、まずは、髪。ひっつめにして、お団子にしたかったのだが、、おー!ピン留めがない。持ってくるの忘れた、、、、、母はショートヘアだから借りられない。ゴムだけで、アップできるのか、、ただでさえ、ぶきっちょな私、、、、ものすごーく苦労して、ごまかした。
髪をやっつけたら、次は化粧。が、ガーン。化粧の道具も忘れた。いつものポーチに入ってるファンデとリップはあるが、目をパッチリに見せる道具は、ごっそり忘れた、、、、特におしゃれしない限り、これらは使わないのだが、ああ、本日はお正月で展示会初日だよ。年のうち一番くらい、おしゃれする日だよ、、、
まあ、それもごまかして、いよいよ着付け。着物と帯、自作でコーディネートして持ってきているのだが、前日の晩、母がうちにあった帯など出してきた。その中で、私の着物に合いそう、かつ、お正月ぽく金が入ってて、シャキッとした八寸帯が一本があったので、急遽、帯はこちらにしてみようという気に。
が、これが、苦労の元だった〜!ひらき仕立ての帯、締めるの初めてで、勝手が違って、四苦八苦。その上、硬くて言うこと聞いてくれないの。。。大変不本意な着付けとなってしまったが、タイムリミットと体力気力のリミット。カッコよさはあきらめる。
あせりとあきらめの、どよーんとした気持ちで、和の國さんに着いたら、そこは、ピシッと整った、凛としたお正月の空気みなぎる空間で、熊本ゆかりの染織家たちの作品がどうどうと並び、ああ、ありがたい、美しい日本の正月と思ったのだった。
写真は、和の國さん「熊本ゆかりの染織作家展」にて。ちょうど、熊本ゆかりの作家のうち、織り作家がコーディネートされてます。手前は、帯が吉田作「チャーミングボックス」。お着物は堀絹子さん作。奥は、着物が吉田作「フィールドオブクリーム」。帯は黒木千穂子さん作。
雑感・1

熊本から戻りました。旅先だと上手く更新できない私。先回のブログ更新後からの、つれづれ雑感を書きます。(たぶん続きは明日。)

1月1日夕方から夜
羽田に着いたら、もう夕暮れで、飛行機に乗ったら、すでに真っ暗だった。羽田発17:40の熊本行き。座席は指定済みで富士山が見えるかと、右の窓側を取っておいた。
なのに、、、、見えるわけないじゃん。暗闇だよ。チケット取った時分は、その時間、ちょうど夕焼け頃だったのか。季節は動くぜよ。自分の、うかつさ、想像力のなさにショック。ガーン。
飛行機は、窓から、元旦の夜景がよく見えた。東京もよく見えたし、途中もよく見えた。熊本上空を旋回した。白川に掛かる橋の名前を思い出した。
家に帰り着くと、9時頃だったか。ひとときの団らん。客間に布団を敷いてくれててありがたい。しかも敷き布団は三枚重ね。過剰ではなかろうと思いつつ、よく寝た。

1月2日朝
寒かったので、母のダウンを借りたら、ポケットに、くしゃくしゃになったちり紙が、入っていて、一瞬自分のダウンかと錯覚した。私の普段着には、いつも、使用済みだが捨てるほどではないティッシュが入っている。ちょっとそこらを拭くのに便利である。洗顔したあと、洗面台をちょっと拭くとかとか。
が、正直、少々情けない。いつもポッケにボロのティッシュ。それを母娘二代で自然にしてる。血は争えないとは、このことか、、、

1月2日 日中
今回の帰省、1日家にいる日を作ったのは、深い訳がある。砧打ちをしたかったのだ。砧打ちとは、織り上がった布を木の棒で何回も打ち付けて、繊維を滑らかに柔らかくするものだ。けっこうな音と振動がするから、街のマンション仕事場では難しい。帰省時は千載一遇のチャンスなのだ。
それで、2日は朝から、倉庫のたたきでがんばりました。タイのキビソ糸で織った八寸帯を二本、ちょっとコワい感じだったので、それをそれぞれ、屏風畳みにして、打つところを送りながら、ドンドンドンドンとたたき続ける。
見かねた父と母と妹が手伝ってくれた。

一番上の写真が砧。二番目が砧打ちする私。三番目が母。四番目は妹。父も手伝ってくれたのだけど、撮り忘れ。五番目の写真はニュー孫をだく父。
(砧打ちと姪のだっこで、私の腕は重症の筋肉痛。未だ治らず。)
あけましておめでとうございます
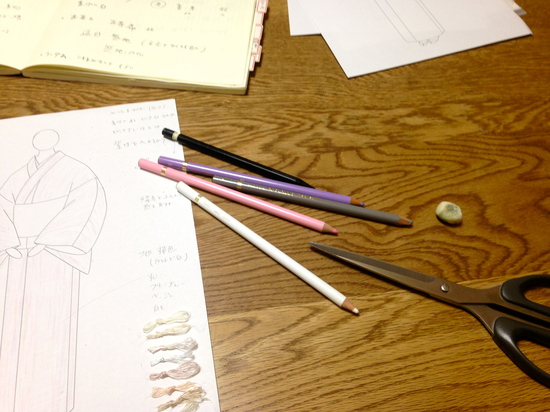
2015年、はじまりましたね!いい1年にいたしましょう。
今日は朝から、only only でご注文いただいているお着物の、打ち合わせ資料を作りました。淡く、はかなげで、芯はしっかりと強い、そんなお着物つくります。
夕方の飛行機で、ふるさとに帰ります。3日から「熊本ゆかりの染織家展」です。4日は11時30分から、ギャラリートークをさせていただきます。その資料もつくらなっきゃ!ぜひ、お越しくださいね→☆
いつものように、バタバタとした年明けですが、元気で仕事できていること、何よりのことと感謝しています。
今年も盛大にバタつく所存です。どうかよろしくお願いします。
(今年のチャレンジのひとつ。以前やろうとして立ち消えてた英語ブログ。復活と立ち消えを繰り返すとは思いますが、できるだけ、、、)
Happy New Year!
This morning, I made sketch of original Kimono for a client. She likes world of Kyoka Izum who is a Japanese writer. Izumi wrote many beautiful novels in late of the Meiji era to the beginning of Showa era.
And then I cooked Ozoni that Japanese soup for New Year day. I tasted them with two mochi.
よいお年を!

大みそかの本日、私は、新春3日から5日に開催される「熊本ゆかりの染織家展」に出品するタブローを作っていました。展示情報はここ→☆。ふぅー、ギリギリ〜。ぜひ観にきて下さいねー。

今日は、この辺りは、いい天気で、穏やかな年の暮れだったのでは?よそではどうだったかな?お宅はどう?
今年も、1年、おつかれさまでした!
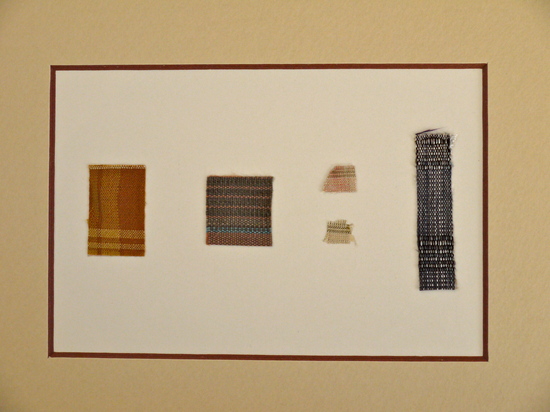
私はこの1年、元気に、せっせと機織りすることができました。そのこと、とても感謝しています。本当にどうもありがとうございました。

しかし、決して満足な1年という訳ではありませんでした。もっと、もっとと思いながらの空回りを感じてました。

じゃあ、どうすれば、手応えある、実のある仕事に繋げられるか、、、、、山にどう杭を打ち込むか。
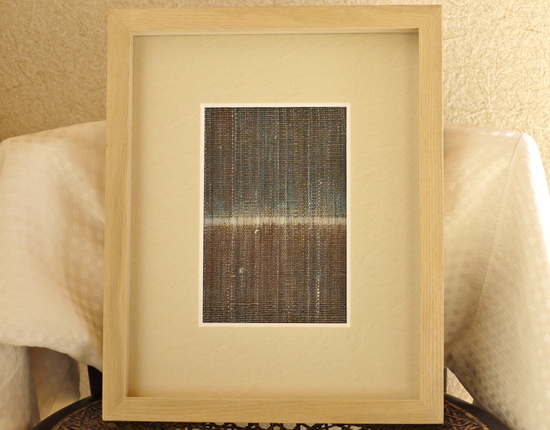
2015は作戦を実行に移す年だ。
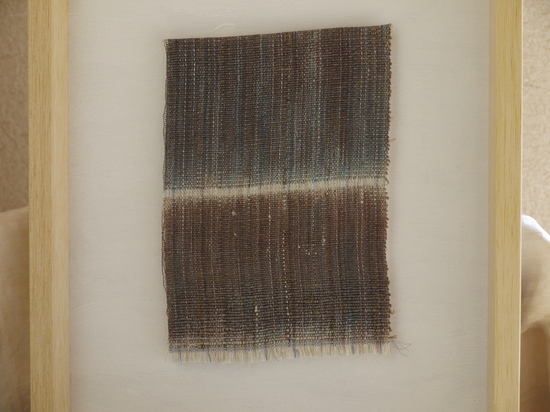
このブログを読んでくださっているあなた様、今年も本当にどうもありがとうございました。
モニターに向こうに、あたたかい応援オーラ、感じております。支えていただいてます。
来る年があなた様にとって、健康でいい1年でありますように。
見惚れました

大好きなブログ「神奈川絵美のえみごのみ」の神奈川絵美さんから、メッセージいただいた。
「久しぶりにシスレーを着たので、写真を送ります」と。おっ!やった!
注)シスレーとは、この写真で絵美さんがお召しのお着物のことです。本名「シスレーの居る風景」。二人でキャッチボールしながら、糸から選んで、染めて織って、作りました。ONLY ONLY の走りです。
私は、その写真を一目見て、惚れてしまった。
「なんて、お似合いなんだろ!このシスレーの幸せ者めっ!」
同時にいろいろ思い出した。「シスレーの居る風景」に取り組んでいたころのこと。走馬灯ってやつですね。もうずいぶんの昔のような気がする。
今、絵美さんのブログの、カテゴリー「シスレーの居る風景」を見せていただいたら、2008年から2010年ですよ!若かったなあ、、、。絵美さんも私も、初々しいような感じするね。私もお誂えさせていただく経験がまだ浅く、手探りでもがきながら進んで行ったものね。
それがこうやって、大事にしてもらって、クリスマス時期の都会の街に連れて行ってもらって、いろいろ出会いが会って、、、幸せだなあ、、、、
じーんとした。きゅんとした。
「神奈川絵美のえみごのみ」は以下のリンクから。すてきなブログよ。ぜひご覧あれ。
トップページ→☆
この日の記事→☆
シスレーの居る風景のカテゴリー→☆
*写真は、絵美さんが送ってくださったもの。ね、光があるでしょう?絵美さんとシスレーが、輝きあってる。
福田喜重の世界、ディオールの世界

青空がきれいな空気が冷たい朝、ちょいと銀座までお出かけしてきました。

まず、「福田喜重の世界展」を拝見しに、銀座もとじさんに伺いました。今日はギャラリートークで、人間国宝、福田喜重先生のお話を直にお聞きできるというありがたい機会でした。
福田喜重先生の作品は、とてもとても美しい正統派の日本刺繍で、ひれ伏したいほど、いいお着物、素晴らしい帯、感服しきりです。
お話の中で心に残ったのは、正倉院御物とクリスマスツリーの意外な共通点でした。両者とも、補色で成り立ってると。そっか、クリスマスは赤と緑だもんね。正倉院の時代も大陸からの文化だから、補色が多いのだとか。それに引き換え、平安以降の日本の文化は、気の文化、水蒸気の文化で、あいまいな色、ぼかしの世界だとか。
なるほどー。福田先生の世界は、水蒸気が立ち上る幽玄な世界を、染めと刺繍で現したものなんだ。まさにその通りだと思った。
「福田喜重の世界」展は、銀座もとじさんにて、12月7日まで。

それから、「エスプリディオール ディオールの世界」展に行きました。ディオールブランドに興味がある訳ではないのだけど、あちこちで評判だったので、こりゃー観とかなくちゃと思って。
で、一歩入るなり、クラクラしました。今日の午前は晴天で、寒いけど太陽さんさんの元から、いきなり、暗幕に仕切られた別世界に迷い込んでしまったものですから。
心をどこに置いたら分からないまま観て回って、ますますクラクラ。すごいレベルの、すごい量のエネルギーです。うわーー。
その上、急いで帰らなくちゃと思って、サクサク観ようと思ったら、そのエネルギーにあてられて、軽くめまい。地下1階から地上3階までの展示を、階段の手すりにつかまりながら行き来しました。そうしないとへたり込みそうだった。
会場もものすごく美しかった。すみずみまで構築されてる。すごい。これが一流ブランドの力か。
「ディオールの世界」展は、銀座のアップルストアの隣りのビルにて、1月4日まで。入場無料。すごいから、まだの方は観てビックリなさるといいかもよ。
*写真はすべて、ディオール展にて。一番上の写真は、フランスからやって来て、製造の実演されてるところ。なんかね、最後の晩餐を想った。神々しかった。
きつつきさん

先日のことだけど、山梨のきつつき工房ご夫妻が、出張のついでに寄って下さいました。きつつきさんは、織機や機道具の製造販売や修理改造などされてる頼りになるご夫妻。私は、織機を改造していただいてから、すっかりファンになってしまいました。
今回は、注文している綛あげ機の相談で、寄って下さいました。私が何を欲しているか、どう使って行きたいのかってことを、もっと分かりたいって思って下さったんだと思う。ありがたいなあ〜〜〜。注文制作の鑑!
綛あげ機は、綛の振り幅とか、落としとか、枠周とか、ちょっとしたことで、使い勝手がまったく違ってきます。今までは、織りをはじめた当初、訳も分からずとりあえず買ったのを使ってました。使いにくいなあって思っていたけど、こんなもんだと思ってた。解決に向けての努力の仕方すら、想像できず、、、。(苦労して当たり前と思ってるのがそもそも間違い!)
夏に改造してもらった織機の方もそうでした。20有余年、悩みながら使ってた。もうダメかもって思った時、ふとよぎったのが、風の噂に聞くきつつき工房。ダメ元だ、ぶつかってみるか。(って電話番号は検索しまくって調べました。)
その電話がつながって、丁寧に話しを聞いてもらえて、「じゃあ今度下見に伺います」って言ってもらったとき、ああ、救世主に出会ったって思ったよ。
私の織機、ほんとーーに使いやすくなりました。それから将来に対する不安も消えた。(きつつきさんは私より一世代くらいお若い。)綛あげ機の方も、心から楽しみにしています。
あまりに感動したので、故郷の酒でも取り寄せて一献さし上げようかと思ったけど、お聞きしたら、きつつきご夫妻、飲まない人種だそうです。あらー。飲んだくれの私とは、元からわけが違うのです!(ってブログは飲みながら書くこと多しです。ですから拙ブログは酔っぱらい口調。)
道具を改良して、素材を吟味して、独自のシステムを開発して、もっともっと、チャレンジします。がんばりまーす♡
*写真は、きつつきさんにいただいた白菜と蕪と柿。きつつきさん、いらっしゃるたびに、自然豊かなお土産をくださるのです。野の花をいただいたこともある。山梨の山麓から、ドンとそこそのものを手渡され、とてもうれしい。こっちには絶対ないものなのよ。
白菜、虫がいて、わあ!なつかしい!!って思った。買う野菜には虫、いないもんね。おいしい食料は誰に取ってもおいしい食料。柿もうまみが濃厚でチョーおいしかった。
やましたの布きれ展に行った
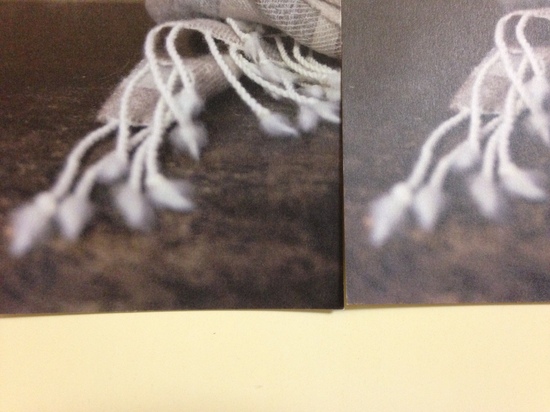
染織家、山下枝梨子さんの個展「とおまわりよふゆ。」に、伺いました。
会場は新高円寺のギャラリー工さん。扉を開けるとそこには、バーン!とやましたワールドが創造されていました。
ご自分が思う世界を、丁寧に、こつこつと、わくわくとクリエイトされてきたんだなあと思いました。
作り手が作りたいものを作り散らかしたのではなくて、山下さんは、使う人を思って、一越一越、積み上げてこられたのだなあ、、、そこに醸される山下さんらしさが、とてもいとおしくすてきでした。
ご案内状には、「主張が少なく、存在感がうすい。わき役な布たちを揃えました。」とあります。これ読んで、ああ、山下さん、勝負に出たなあって思いました。自分の世界をしっかりと確立させた。すばらしいです。やり切ってるし。
しかし、存在感はあると思ったなあ、、、。主張もあるよ!しょっちゅう使いたくなるいい布でした。
やましたの布きれ展「とおまわりよふゆ。」は、新高円寺の GALLERY 工 さんにて、11月28日金曜日まで。山下さんのブログはこちら→☆
*写真は、この展示会のご案内状。うちのドアに貼ってます。
型染め講習と雪の結晶、後篇
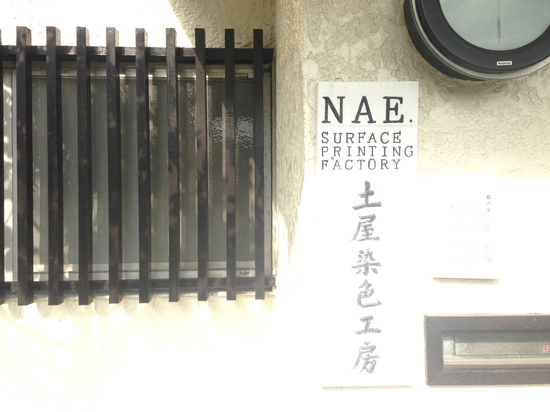
さあ、いよいよ、講習会がやってきました。土屋先生の元にいざ!
藤沢の駅からバスに乗って、スマホを頼りに行き着いたとたん、うっわーーーっ、この工房、完璧!
広さとか、動線とか、道具の配置とか、光の具合とか、水回りとか、熱源とか、電源とか、完全無欠!神経が行き渡ってる、、、、すっごいなあ、、、出来る作家の仕事場って感じがバリバリしました。大切に作り上げてこられたんだなあとも思いました。愛があふれてる♡ここに入れていただけただけでも、参加したかいがあるってもんです。
土屋先生は、にこやかに優しく受け入れてくださったけど、、、実は、めちゃくちゃ大変でボロボロになりました。

一言で言えば、自分の出来なさ具合に凹みまくりました。いろいろデザイン的なことなど考えてきたこと、ぶっ飛びました。だって、カッターが使えない。シャが張れない。次が読めない。糊をこねれば、ふちを汚すし。均等にぬれないし。地白と地染まりの違いもピンとこないし。
あたふたあたふたしっぱなし。ペースがつかめなく、頭がいっぱいで何も入ってきません。ああ、、、
型染めは初めての経験とはいえ、テキスタイルという大きなくくりでは、ずっと携わってきているものだから、私、もうちょっと出来ると思っていた。大いなる間違いだったぜ。凹みまくり。
それに疲れた。体力なしを反省した。一日中織ってるのは出来ても、染めてるのは出来ないんだ。出来なきゃダメじゃんね。

講習会の受講者は二人で、もうお一人がツバキの模様の暖簾を作られた。型彫りしているとき、土屋先生が、「花を彫る時は花の気持ちで、葉っぱを掘る時は葉っぱの気持ちで」って指導してらっしゃるのが心に残った。そっかー。大事なのはそこだよね。私も隣りで、雪のひとひらの、可憐さを思いながら彫った。余裕ないながら。
染めたものの写真は載せないよー。ここには作品レベルまで達しなかったものは、載せないです。

この度は、土屋先生に大変お世話になりました。本当にどうもありがとうございました。型染めに限らず、染め全般について、いろいろと不思議に思っていたことや分からなかったこと、教えていただきました。染めは化学や物理が分かってないと(化学反応をおこして、染料と繊維を物理的にくっつける)、どうしてものみこめないない所があるのだけど、今回、突破口をあけていただきました。あとは実践あるのみ!!!!

*写真は上4枚が土屋工房。本当にきれい。自作も多いとのこと。さすがです。見習わなければ。最後の写真が、涙なしには語れない、私が彫った型紙。
型染め講習と雪の結晶、前篇
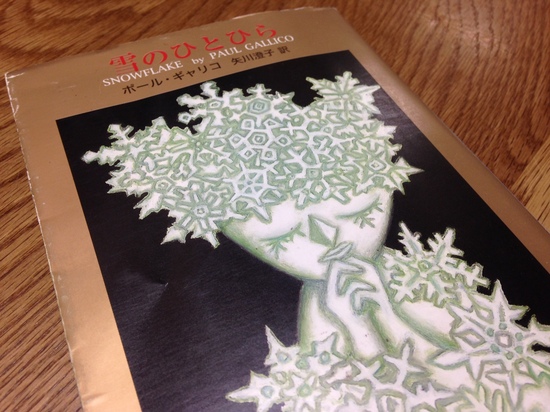
もっと染めを勉強したいって、ずっとずっと切望してました。染めと一体化する感覚が欲しかった。染めながら、「もう一歩、もう一歩」って思ってた。
そう願って、はや、ウン年。絶好の機会を作りました。この三連休、型染め講習を受けに、三日間、土屋直人先生の元に馳せ参じておりました。
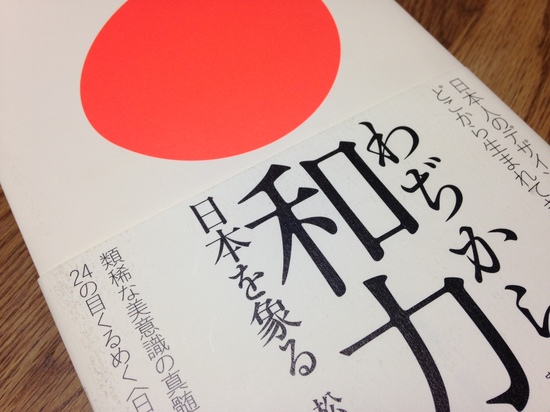
話しは、講習会に申し込んだ一ヶ月ほど前にさかのぼります。土屋先生、染めるものは自由で、デザインなど、メール添付でおくれば、何回か推敲してくださるとのこと。ありがたい。できるだけの準備をしよう。
自作帯に、後染めできないか?染め重ねることで、もう一歩踏み込めないか?
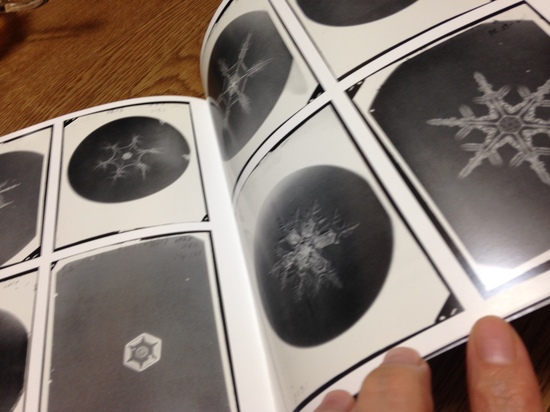
もうずいぶん前に、「雪のひとひら」という帯を作りました。今はとても仲良くなった友人が、初対面のとき、プレゼントしたくれた小説のタイトルです。とても印象的なすてきな本で、この本をモチーフに帯をつくりました。ただ、少々おとなしくなりすぎました。「雪のひとひら」の可愛らしさがもう一歩だった。ここに雪の結晶を染め重ねたら?でも、雪の結晶っていったいどう表現したら???
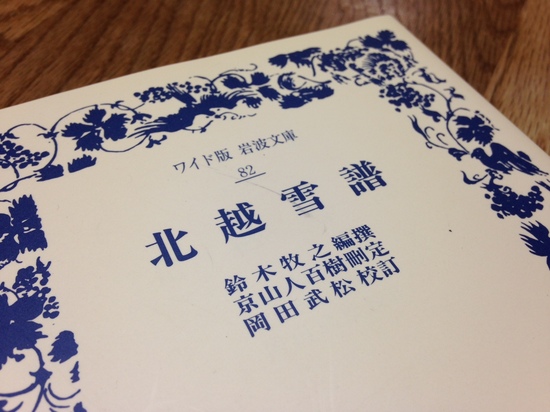
その頃、ちょうど、「和力」って本を読んでました。この本にヒントがあったような、、、、
ありましたよ、雪の結晶についての記述。雪の殿様と言われた土井利位が雪を顕微鏡で観察して結晶図「雪華図説」を発表したことと、人工の雪の結晶をはじめて作ったのは、中谷宇吉郎ってことが分かった。
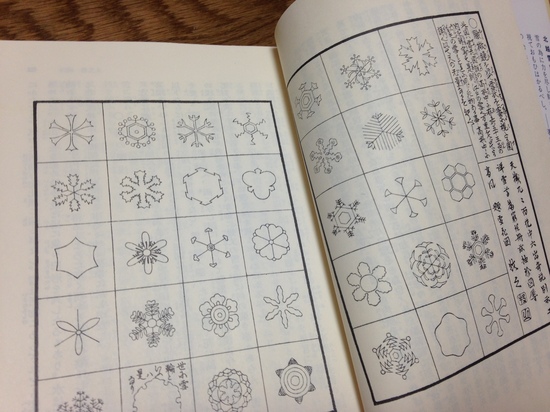
お!中谷宇吉郎!ちょうど買った本の人だ。そっちを読む。それから、雪華図説は、「北越雪譜」に転載させれてるってことが分かった。おお!北越雪譜なら、うちのトイレの本棚にあるよ!
芋づる式に、どんどん見たけど、家紋やらに使われている、意匠化された雪の紋は、すばらしいね。受け継がれてるデザインは最強で完璧なのだなあ。自分の帯に使うかは悩みどころだけど。

それからもうひとつ初めて知ったこと。室町時代、雪のことを「六花(りっか)」と呼んだんだと。六角形だものね。
おおおー!ふっと目線を上げれば、六花亭のお菓子が!ちょうど北海道のお土産をいただいたのだ〜!六花亭、雪国らしく、きれいないい名前ね〜。おいしいし♡
*写真は、話しに出てくる本などだけど、ずれちゃってますね。出てくるタイミングが。申し訳ないです。
ガーン!ショッック!

竹筬研究会の「試作竹筬と織布展」に、横浜のシルク博物館に行ってきました。
竹筬研究会と言うのは、途絶えてしまった竹筬を甦らせようと、竹の調達から、筬羽作り、組み、など一連の流れの復元に取り組んでいるグループです。会長は、下村ねん糸の下村輝さん。下村さんは、絹織物をやってる人なら全員知ってる、チョー有名人です。
下村さんは、私にとっても心の支え。今でも織り続けていられるのは、20代から30代のはじめ頃に、直接教えていただく機会が多くあって、糸とは何ぞやってことを、ドーンと仕込んでいただいたからだってとても感謝しています。
竹筬研究会も設立して、もう10年以上です。と言うことは、竹筬がなくなって、10有余年ってことですね。会場には、復元され、活躍している竹筬と織布が並んでいて、すばらしかったです。
いやはや、この活動が、ここまで実を結んでいることに、目を見張りました。私は、「金筬でもいいんじゃね?」ってクチですから。筬をはじめ、道具も素材も、突き詰めれば、突き詰めるほど、際限がない世界です。

ショックなことがありました。
会場で、10年ぶりくらいでお会いした人がいて、その人、仮にエスさんとします。エスさんは私のこと、とても気にかけて下さっていて、たぶん、私のこと好き。私もエスさん大好き。(女性ですよ!)
エスさんが、私を見るなり、
「うわっーー!ヨシダミホコっ〜〜!!!元気ないね〜!なに、しょぼーんとしてるの〜!あの時の輝きはどこ行ったの〜。ヨシダミホコらしくないっ!」とのたまいました。ええーー!そう????私、いちおう、元気なんだけど、、、、
いとへん関係の人は、スバスバ言う人が多いんです。その場にいた人集まってきて、光を失った(とされる)私に、やれ、「着てる服が地味」(自分では気に入っているネイビーのセーターを着てた)、「化粧をしろ」(いちおー、してたんだよー。ファンデうっすら。口紅はもともとヌーディーな色で、それもコーヒー飲んだら落ちた。目の上は、するとケバくなるんだよね。)「牛肉を食べろ」(はい、お昼に中華街で牛肉粥を食べ、帰りにも切り落としを買って帰りました)、「閉じこもってるんでしょ、それは怠慢よ」(だって、出てたら織れないじゃん。と言ったら、楽しようとしてるって言い返された。閉じこもって織ってる方が楽なのよね、いろいろ交流するより。)等々言われまくりました。
もっと、しょぼーん。
織りの大先輩の小熊素子さんとお話できたので、小熊さんに、泣きついたら、あははーと笑っておられました。小熊さんとも久しぶりにお会いしましたが、とっても輝いておられました。聞けば、水泳に通ったり、活動的にされてて、織りも順調のご様子。小熊さんほど、いろいろ乗り越えてくれば、達見なのでしょうが、私はまだまだです。
ちょっと目線を変えましょうかねえ、、、っって思った一日でした。みなさんの愛に感謝です。こんどは、ヨシダ、光ってんっじゃんって言わせなきゃね♡
*「試作竹筬と織布展」は、11月24日まで、横浜のシルク博物館にて。
写真は横浜じゃありませんよ。うちの近くの地面。
糸のこと

次の帯の糸を準備しています。糸ってまずは買うまでが大変。選ぶのがひと仕事。作りたいもののイメージをどう具体化するかってことなんだけど。守りに入らず、果敢に買うことが大事と思ってるのよね。(それで、糸棚は大変なことになってるのだけど)
決断するまで、お腹が痛くなるほど悩んだけど、買ったよ!そしたら、お湯で洗います。一晩つけ込んでから。

時間をかけて、しっかり洗ったら、けっこう重さが減りました。6%も減ったのがあって、ビックリ。お湯だけで、セリシンが溶けたってことね。精練なしで行こうと思ってたけど、少々落ちて、しなやかさが出て、ちょうどいいか。

さあ、この糸で行きますよ。今回、無染めで行きます。これから糊付けです。
私、精練と糊付けが、染織のかくれた超重要事項だと、思うようになってきた。ここを制御できてこそ。
冨田潤+ホリノウチマヨ展、三嶋りつ惠展、リギョン展、なにNUNOね展

おはよう!今日は5時起き。私としては早起きです。
朝からノルマをバンバンこなして、昼から着物きて、お出かけしました。半衿付け替える間がなく、秋も深まったというのに、単衣のお襦袢。帯もぐちゃっと。しかし締め直してらんない。ひー、堪忍して〜。
今日は冨田潤さん+ホリノウチマヨさんの展示会の初日でした。
冨田さんの作品はもう何回も拝見してますが、見るたびに、「これ、どうやって作ったのだろう?」って思います。じーっと見れば分かる部分もあるのだけど、引き込まれるような感じで、不思議な魅力に満ちてるなあって思います。
ホリノウチさんの作品は初めて拝見したけど、ストレートな感じがとてもすてきでした。おおらかで、あったかくて、色もいいわー。ウールってこんなに面白いんだ。素材が歓喜してるね。
*冨田潤+ホリノウチマヨ展は、11月19日まで、銀座の日々さんにて。
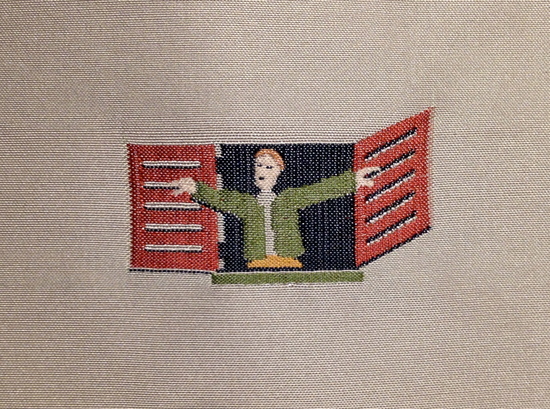
それから、三嶋りつ惠さんのガラスのお椀展に行きました。三嶋さんの作品展に伺うの初めてでした。以前、一点だけ拝見したことがあって、それがとても美しくインパクトあって、ずっと気になる作家さんでした。
ズバッとした存在感がある、背筋が伸びる作品でした。このお茶碗でのお茶席を想像するだけで、空気が凛とする。すばらしかったです。
*三嶋りつ惠展は、思文閣銀座にて、11月16日まで。
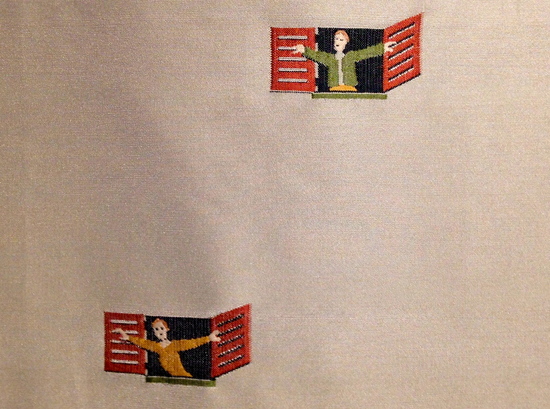
銀座に出ると、必ずチェックするギャラリーが、メゾンエルメスです。開催中の展示は、ソウル在住のアーティスト、リギョンと言う方でした。どんななのかまったく予備知識ありませんが、ここでの展示はまったく裏切られたことがありません。ドキドキしながら8階へ。スタッフの方に履物を脱ぐように、言われます。
ビックリしたー。ガランとした大きな部屋です。ただそれだけ。夕方の日の光が差し込んで美しい。床が白蝶貝を張ったような感じでピカピカ。お腹に響くサウンド。壁に少々のテキスト。それだけなんだけど、この清々しさは何?
もう一部屋は、一組ずつしか入場できないとのことで、入り口でしばらく待ちます。順番がきて、誘導されて、草履を脱いで入ります。おお、、、目がバシバシします。ハレーションをおこして、何がなんだか分からない。こちらはただの白い部屋。そこに強烈な白いライト。床から壁はアールがついてて、境目がありません。見えないけど、たぶん天井もアールがあるね。白い球体に紛れ込んだ感じ。
韓国人の現代アーティスト、数人しか知らないけど、なんか好き。共通点は、極限までやり切った感じがすること。人種でカテゴライズするの詰まらないと思うけど、このエクストリームな感じはコリアンのアートなのではないだろうか?私は大好きだ。
で、うちに帰ってきて、フライヤーを良く見てたら、リギョンさんは、女性みたいだ。1969年生まれ。これまたビックリ。私と同性、同世代。黄色人種というのも同じ。性別、年齢でカテゴライズするのも、これまた詰まらないけど、同じカテゴリーの作り手がここまでやり切っているのを見ると、すごく燃える。
*リギョン展は、銀座エルメスフォーラムにて、1月7日まで。
それから、六本木へ移動。NUNOさんの「なにNUNOね?」展へ。わー!大きな布、迫力です。手仕事と機械仕事のブレンドなのだなあ。会場の壁に、展示作品のエスキースというか、アイディアの元というか、、、コラージュスケッチがあって、それがすごく面白かった。探ってる手の跡、思考のあと。コンセプトをしっかり立たせてて、さすがと思った。
*なにNUNOね?展は、ギャラリール・ベインにて、11月23日まで。
写真は、過日みた、ジオ・ポンティのテキスタイル。今日は撮ってる余裕なかったよ〜。へとへとになって帰ってきました。
織楽浅野展、ジオ・ポンティ展、きものサローネ
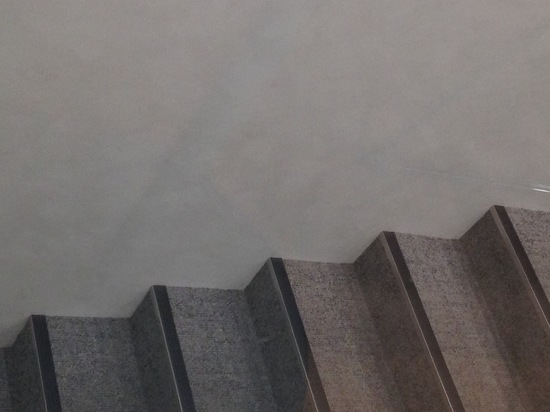
今日はお出かけ日。刺激をいっぱいもらってきました。まずは、、、、
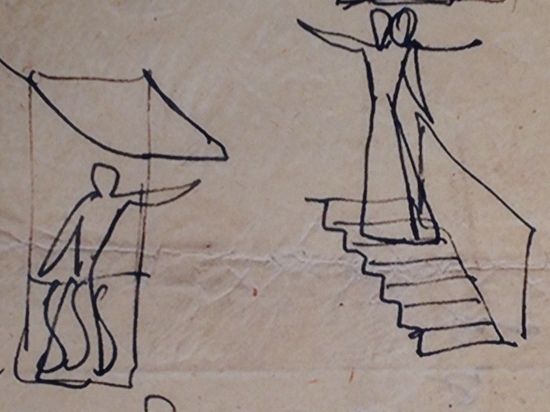
織楽浅野さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。織楽浅野の世界観が、バシッと伝わってきました。美しい世界へ連れて行って下さいます。
個展のタイトルは、「うつす」。いただいた資料に、「天がモデルを示し、聖人がこれに従う」とありました。なるほど、浅野さんは森羅万象から美をみつけ、洗練し、新しく生み出してらっしゃるものね。
浅野さんの生み出す、新鮮な美しさと、力強さと、スピード感に圧倒されました。
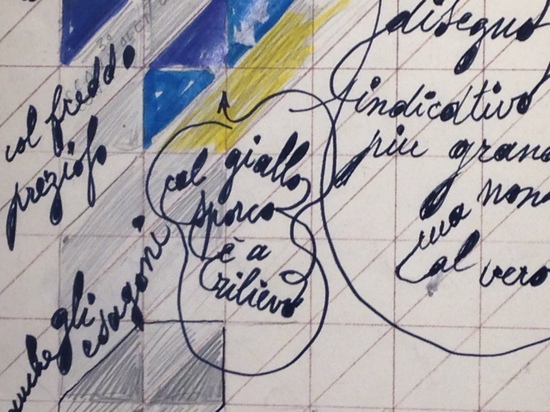
それから、銀座の中央通りを、京橋方面にどんどん歩いて、INAXのギャラリーに行きました。イタリアの建築家でありデザイナーのジオ・ポンティの展覧会を拝見しました。20世紀に活躍した人。
さすがイタリア人。なんだか、楽しい。ちなみに、今日の写真は、すべてINAXで撮りました。ね、楽しそうでしょ?
壁に書いてあった文章から引用。
「建築をつくりましょう!建築をもってする以外にはできないものをつくりましょう!建築は、外では厳格で緊密なもの、内では遊びと驚きに満ちた有機体です。外側は結晶ですが、内側には人生があります!」

さらに中央通りをどんどん、日本橋方面に。めざすは、COREDO 室町、きものサローネです。いろんな業者さんが、一同にドーンと。あわわ、、溺れそう。着物ってこんなに幅広かったのか、、、
自分だけの小さな世界から(それも崖っぷちに居る)、ドンと突き落としてくれました。さあ、はい上がるわよっ!
あ、でもさ、私はやっぱり織り物が好きだと思ったよ。手織りでしかできないものがある。手織りでの表現に掛けて行こう。
hirocoledge, ミナ・ペルホネン、東京スカイツリー

ほら!見て!!太陽がスマイル!

昨日、押上まで行ってきました。
アーティストの高橋理子さんが、新しくアトリエを作られて、エキジビションされてたので。鉄工所をリノベーションした空間で、スッキリシンプルで、なるほど、ここはクリエーションの基地だ、泉を自ら掘って、こんこんとわき出そうとしておられるのだなと思いました。すごく刺激的。遠かったけど、行ってよかった。

こんな遠くまで来ることは滅多にないぞと、スカイツリーも行っちゃいました。
ここの制服、ミナ・ペルホネンのデザインだと聞いていたので、一度見てみたかったのです。
かわいかった。森の妖精みたいでした。スカイツリーという場が、柔らかく不思議な国になった感じ。デザインが場を作る。力がある。
似合う人と似合わない人の差が激しいのが、ちょっとなあ、、と思いました。

高いところに登りたいというのは、人の本能なのでしょうか?人がいっぱいの観光地は苦手の私も、知らないうちに引き込まれ、、、、(制服を見たいだけなら、上まで行く必要ないのにね!)
夕暮れの東京を夢中で見てました。人の数だけクリエイションはあるぞ!!!富士山にだって負けないぞ!
いやはや、一見の価値、大アリの、押上スカイツリー初体験でした。
空とマフラー、温便座

天高く、お寒くなってまいりました。
今、帯と平行して、マフラーも織ってます。マフラー織るの、久しぶり〜。目の前でさくさく進んで行くのが新鮮です。スピード感があるの、いいと思う。新鮮さ、っていいね。忘れてた感覚を思い出す。
首もと寒くなって参りましたしね。あたたかいの織りましょう。
最近、たえられなくなって、トイレの便座をオンにしました。あたたかい〜。出来る限りの節電を旨としてますので、11月まではこらえたかったのですが、負けました。
いやー、あたたかい便座になぐさめられてます。つらいときとか、ちょっとお腹が痛いとき、トイレに座って、癒されるってのは、ちょっと情けない、、、。
写真はうちの近所。撮りたてほやほや、今朝ですよ。写ってないけど、頭を白くした富士山も見えました。
友だちの糸

久しぶりのいい天気。ここぞとばかり、先日やってきた、遠来の糸を外に出して風にあてた。友だちが送ってくれた大事な糸だ。

その人は、2011年に病気になった。治ってまた織る日がくると信じていたが、貴重な糸を送ってきたと言うことは、、、、そういうことか。
2011年はいろんな意味で重い年だ。
健康で仕事ができること、イコール、いいこと、とは限らない。が、気の持ちようで、そうできる。つか、そう言うことにしとこうってのが、普通でしょう。
その反対は、悪いこと、不幸なこと、とも思わない。
そんなこと、分からない。
が、いまだに私は彼女に会いに行けてない。時間とお金は、ぐっと無理すりゃどうにかなるのにな。
トーク会ふたつ

昨日のこと、銀座にお出かけ。
まずは、銀座もとじさんの「久米島紬展」のトーク会におじゃましました。久米島紬の織り手の方三名と、組合長さん、工芸ライターの田中敦子さんのお話です。
久米島紬、元気あるなーーって印象でした。織り手の方が、アグレッシブ。かつ自由。久米島紬は無形文化財に指定されているから、いろいろ制約あるなずなのだけど、なんか、それ感じさせない。カツカツの縛り感がない。いいわー。
トーク会に参加のお客様方も、久米島紬をお召しの方が多くいらしたのだけど、その方々がとても満足げにしてらしたのも印象的。
そのあと、和光ホールで開催中の、「融合する工芸ー出会いがみちびく伝統のミライ」を拝見しに。こちらは、5人の作家のコラボレーションに重きをおいたグループ展と言ってしまえばそうなのだけど、その枠を大きく越えてて、とても刺激的でした。トーク会に参加できて、ラッキーでした。面白かった。
この展示会は、チームで作り上げたものだって、トーク会司会の企画監修の美術史家、前崎信也氏。企画会議の当初から、作家5人に加え、写真家、デザイナー、言葉(発信という意味かな)が加わっていたそう。
だから、どういう思いで、作り手たちがいどんでいったのか、はじめから見て、はじめから知ってる。はじめから発信する。ほぉ〜。工芸のひとつの未来だと。
トーク会の終盤で、蒔絵作家の若宮隆志氏が、「すでにモノの時代ではない。思いを伝えたい」との発言に心が響いた。そうだよなあ、それこそ、工芸の未来だ。
*銀座もとじさんでの、「久米島紬展」は、すでに終了しています。
*和光さんでの、「融合する工芸」展は、10月26日までです。
写真はセルフィー。帰りがけ。地下鉄の駅ってすることなくて、ついiPhoneいじってしまいます。
糊いろいろ

これ、我が家の冷蔵庫。パッと開けたら、中段に糊がオンパレードだったので、面白くてパチリ。扉のポケットの分も入れたら、なんと、八つも入ってた!
あ、糊だけじゃなく、薄め材などもあるけどね。涼しくなってきたから、もう冷蔵庫に入れなくてもいいけど、染料置き場も、空きがない。
占領された冷蔵庫、食料品は遠慮しながら、入ってます。あーあ、専用の冷蔵庫が欲しいなー。(冷蔵庫だけじゃないけどね。)
織りをする人にとって、糸にどう糊をつけるか、またはつけないか、これは大問題です。私は、糸にもよるけど、必要にして充分な量をしっかりつけたいタイプ。がっちりつけると、経糸のチョイスが広がるから。
最後にはとってしまう糊だけど、深いのだ〜。
夜さんぽ

このところ、コンをつめてて、軟禁状態です。もうダメだって思ったら、外に出る。

ドキッとするような美しさを探して。

残業中の工場。

働く人たちを見ると、励まされる。さあ、私ももうひとがんばり。

窓の外はこんな感じ。

歩く道はこんな感じ。
やっと洗濯

台風一過の青空のもと、やっとやっと夏物のきもの周りを洗濯しました。(お風呂場でだから、青空はあまり関係ないけど。ま、気分の問題。)
これは、ソープナッツ。和名はムクロジ。石鹸成分を含む木の実です。

この木の実を、ネットに入れて、浴槽にいれて、勢いよくお湯を出せば、ほらこの通り。

じゃぶじゃぶ洗います。すすぎは一回。簡単です。あとは形をととのえて干すだけ。
ああ、季節は動くなあ。(もうとっくに動いてるって!)
コスモス

先日、友人と話していて、コスモスはなぜコスモスという名前になったんだろうって話題になった。
コスモスって英語?宇宙って意味でしょ。でかいよなあー。でもなぜ宇宙?
このときは、解決しなかったんだけど、後日ググってみると、コスモスは、cosmos で間違いない。で、cosmos には、宇宙や世界って意味もあるけど、秩序や調和って意味もある。
コスモスは、どうも整然と花びらが揃っているらしい。秩序があるのだ。宇宙も壮大な秩序なのだろうか。
上の写真は、我が家の近くのコスモス畑。夜にパチリ。秩序あるか?
我が家の辺りでは無理だけど、空気がきれいなところで新月の晩、夜空を見上げると、星空が蕁麻疹みたいだと、見るたび思う。この写真のコスモス畑も蕁麻疹ちっくじゃない??どちらかというと。。。(星空みたいだと言えなくもないか。だとすれば cosmos ともつながるか、、、)

この写真は、次の帯の試し織り。いまだ苦しみ中。織物も秩序が大事なんだけど、私はいつもカオスにおちいる。はい上がるぞ!
冨田潤先生、講義

冨田潤先生の講義に、東京スピニングパーティーに行ってきました。
私、この講義、本当に楽しみにしていました。数ヶ月前、スピニングパーティーのチラシに冨田先生のお名前発見したときから、エキサイトして、受講する気まんまん。申し込みは、先着順ということで、受付開始日、開始時刻の午前10時の時報と共に、メール送信ボタンを押しました。(後に送られてきた受講票によると、受付番号4番でした。私より早い人が3人も!)
冨田潤先生は、私が織りをはじめた頃からのあこがれです。20数年前、ある本を読みました。そのころ、すでに古い本で立花隆さんだったかが書かれた、青春漂流というタイトルだったか、、、大変うろ覚えですが、若者が情熱を燃やして成長して行くルポで、それに冨田さん登場されてまして、感激したのです。こんな人がいたのか!
拝見できる限りは、展示会にも伺ってます。ずっと前、京都で個展をされたときは、夜行バスで行ったなあ〜。早朝の京都で時間をつぶしたなあ〜。冨田氏の作品は、見ていると心吸い取られる布なのだ。最近作られている八寸帯は、具体的な目標です。
アシスタント志願もしたことある。うまく行かなかったけど。
そんな訳ですので、当日も早起きして出かけ、一番前の席をゲット。講義は、朝10時から16時までという長丁場でしたが、あっという間でした。
スライドの数々とお話の数々、質問とお答えの数々。何でも教えますという副題でしたが、本当に何でも教えて下さいました。乾いた砂漠に水が吸い込むように、習ったつもり。ま、水、いただいても、それで何をどう育てるかですが、、、
制作過程のスライド見てて、一番思ったのは、「ここまでやるんだ」ってこと。あの完成度はここだったのか。私がいままでしてた事は、「やってるつもり」だったな。もっとやれるぞ。
*写真は無関係。東京国立博物館、法隆寺館の階段。
森康次先生

森康次先生の個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。この個展のために作られた新作をぜひ拝見したかった。森先生とお弟子さまの佐藤さんにお会いしたかったです。
30分も前に銀座に到着。森先生の刺繍の美しさを堪能しつつ、トーク会の開演を待ちました。鞠の付け下げ、すてき。こんなの着たら世界観が変わるかも。
待っている間に、森ファン、もとじファンのお客さまがどんどん集まってらっしゃいました。さすがーー!
以前に森先生からメールをいただきました。ものすごくお優しいありがたいメールでした。勝手に引用。(ごめんなさい、森先生)
『私も来年は69歳、もうすぐ70です。
このくらいまで続けると、ちょっと面白くなってきます。
見えなかったものが見えるようになって 、分からなかったものが理解できるようになりますから。
歳を重ねるのもなかなかいいものですよ。
吉田さん、何が何でも続けてください。
そして「ちょっと面白くなってきました。」って、聞かせてください。』
じーん。あ、あ、ありがとうございます。はい、何が何でも続けます。ちょっと面白くなってきたっていう境地は、まだまだまだまだ遠いのだけど。
お弟子さまの佐藤未知さんとも、感激の再会でした。スッキリ美しいご様子に、着実に仕事を重ねてらっしゃるんだなって思いました。別れ際に、小さな包みを下さいました。京都のお土産だと。まあ!
うちに帰って、包みを開けると、かわいい飴が出てきました。色もいいのよ。きれいな黄色と緑。
あ!!!!これは、森先生が私にご用命くださり、佐藤未知さんと何度も何度もやり取りを重ねて作ったPure heart Michi だ!!試し織りをお送りしたことなど、昨日のように思い出す。
佐藤さん、お気持ち、しっかり受け止めたよ。ありがとう。お互い、がんばろう!
スコットランド

住民投票の結果、スコットランドのイギリスからの分離独立はなくなった。そっか、、という気持ちで、ニュースを聞いた。
スコットランドは、私にとって、とても大事な国です。21歳〜22歳の2年間、迷い込むようにして住んでいた国。
大学時代、バブルまっただ中の東京で、居場所が見つけれず、かなぐり捨てるようにして、逃げ出した。その行き着いた先。
ホームステイで一緒になった男の子に、どこから来たのかと聞いたら、「リトアニア」と答えた。「リトアニア?ああ、ソビエト連邦ね」って言ったら、「違う違う。ソ連じゃないよ。リトアニアだ。」「ソ連の中のリトアニアってことでしょ?」「違うよ。リトアニアはリトアニアだ。」
そんな風に主張するのに、なんだか、びっくりした。へえーっと思った。その数年後に、本当にソ連が崩壊したとき、心底自分を思い込みを恥じたけど。
パレスチナからの女の子もいた。どこからの来たのという問いには、もちろん「パレスチナ」だ。国の名前では、イスラエルかもしれないけど、そうじゃないのは、当時の私でも感じていた。印象的な民族のスカーフをしていた。
バスクの男の子もいた。この子も、出身地は「バスク」と答えた。「今はスペインってことになってるけど。」
スコットランドに居た頃は、まだベルリンの壁もあったんだ。昔話だねえ、、、、
地図に書かれた境界線は、たまたまそうなったんだってこと。戦争に勝ったとか負けたとか、政治のいろいろで。民族の気持ちが反映されている訳じゃない。民族の気持ちは、勝った負けたでは覆らない。政治が決めた線は、いつもで変わり得るんだって事を、若いくせに頭が固かった無知な私は、教えられた。
写真はスコットランドじゃないよ。うちの近所。また行きたいなーー。
初公開の法隆寺裂をみた
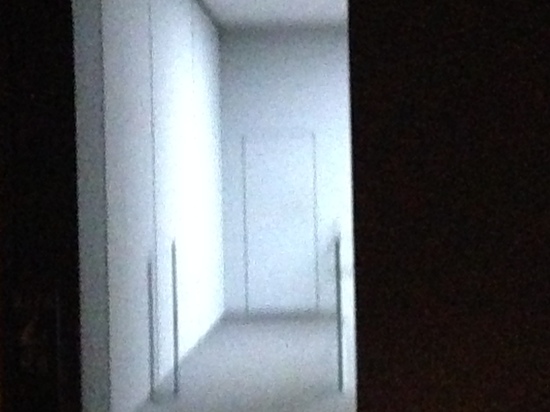
昨日の続きです。
新橋から山手線に乗って、上野で降りる。蚊におびえながら公園を抜け、向かうは、東京国立博物館、法隆寺宝物館。ここの2階の奥の部屋は、幡や袈裟の残欠がいつも展示されてて、私的チェックポイントなんだけど、今回、今まで展示されてなかった分が、修理を終え、初お目見えしてたのです!(展示は15日で終了しています)
展示されている布たちは、聖徳太子が亡くなった時に作られたものなど。昭和12年からガラスにはさんで保管してたんだって。修復されたとは言え、1200年前のだもん、ボロボロです。しかし、その鮮やかなこと。イキイキしていること。最高のアートだ。
かなわんわ。最先端を切り拓いてる人たちが作った作品のみが持つ、パワーがある。技法もすごい。ものすごく精緻。糸もそろってるし。金糸もあったよ。びっくり。
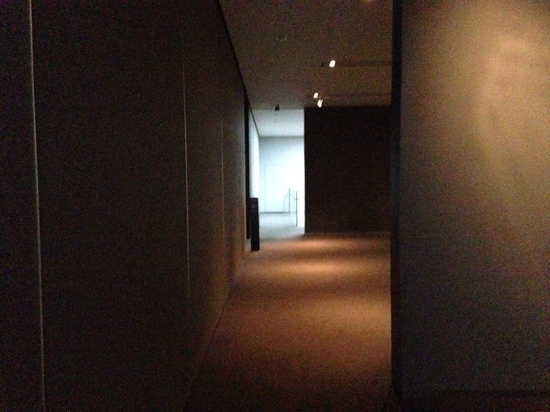
ミュージアムショップの本屋を覗いたら、つい2冊も買っちゃって、金欠に。帰りに中華屋にでも入りたかったのだけど、すごすご帰った。
写真は、法隆寺館。現代アートのギャラリーのよう。
北村武資展、資生堂、ピエール・シャロー

先日、北村武資さんのギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。織りの世界では知らない人は居ない、人間国宝です。
「自分流のものを作るしか道はない。」「織物は、色や模様以前に、織りそのものが大事。」「織の構造美を創造する。」「寂びを入れず、出来るだけ透明のまま織る」などなど、面白く、ズキッとくるお話をたくさんお聞きできました。新しい構造の作品も出品されてて、どんどん開拓されて行くさまに感服。ひれ伏す思い。
思ったのだけど、人間国宝って、伝統文化の継承者ってイメージしちゃうけど、最先端の開拓者であり、チョー売れっ子の作家であり、成功している機屋の経営者なんだ。売れてないと、継承はおろか、開拓もチャレンジもできないし。

その後、資生堂ギャラリーで開催されていた、「せいのもとで」展を拝見しました。
資生堂の社名は、中国の「易経」の一節「至哉坤元 万物資生」から採ったんだって。「すべてのものは大地の恵みから生まれる」という意味らしいよ。さすが、いい社名だなあ〜。
で、この展示会は、その「万物資生」を表現しているらしい。
志村ふくみさん、洋子さんの、草木染めの糸のインスタレーションもありました。茜で染めた白から赤のグラデーション。うん、染織は「万物資生」だわ。

それから、汐留ミュージアムへ、「ピエール・シャローとガラスの家」展を観に行きました。ピエール・シャローとは、アールデコ時代の、フランスの建築家です。知らない分野なのだけど、チケットいただいた事もあり、興味津々で足を伸ばしました。
20世紀の初頭の一時期、パッと才能と時代がぶつかって花ひらいた。ドキドキ感があった。高揚する。きっと、寝る間を削って、線を引いたのではないか。
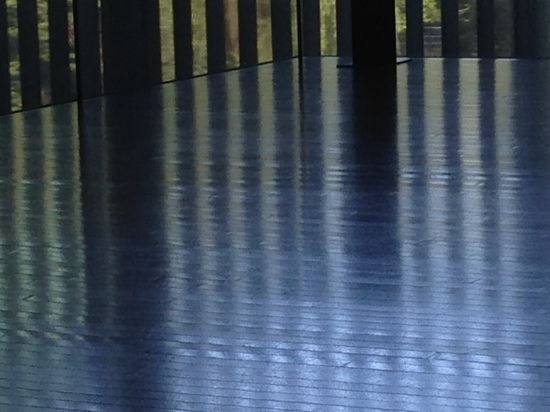
その後、もう一件いったのだけど、長くなったからまた書きます。写真は、シャローのガラスの家。じゃなくて、東京国立博物館の法隆寺館。
花ト囮

ダンスを観てきました。DAZZLE ってダンスカンパニーの「花ト囮」(はなとおとり)です。とても怖くておどろおどろしく面白かった。
その圧倒的なダンスに、もっと近くで観たい、もっと小さな劇場だったらよかったのにと思いました。アングラっぽい所でも良かっただろうな、、、、、、会場は、東京国際フォーラムのホールCでした。
が、音響とか照明もすばらしかったので、それが理由でのこの会場だったのか、などとも思いました。こんだけ完成度高いと、会場も選ぶんだろうな。

実は私、ダンス、まったく縁がなく、今回チケットいただいたのです。うわーい、チョーラッキー!予備知識がなくて、すごいもの観るの、何よりありがたい。非日常にいきなり連れて来られた感じ。道中のそぼ降る雨がまた良かった。
写真は帰り道。
森田空美先生!
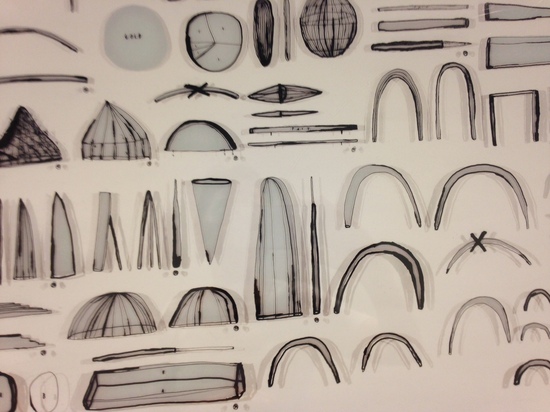
大感激な出来事がありました。なんと、あの森田空美先生に一対一でお会いして、作品を観ていただき、アドバイスをいただくという光栄に浴して参りました。
今の着物界をリードと言うか、、、、大転換させた方ですので、雲の上の方だと思っています。いやーー緊張したよ!
ずっと帯の風合いに付いて悩んでました。締めやすく、美しく。ブレイクスルーめざして、七転八倒してました。暗中模索で、もうこれ以上は堂々巡りかと落ち込んでた頃に、ご縁があり、森田先生につないでいただきました。
青山のオフィスは、ドアを入ると、そこは異空間。キリッと整い、空気が違う。先生はにこやかでお優しく、丁寧で、着物に対する深い愛と責任をもたれた方でした。
参りました。見ていただいた拙作、自信作がそうでもなかったり、イマイチかと思ってたのほめられたり、目から鱗のご意見いただいたり、、、
糸に対する執着も、湯のしに対するこだわりも足りないな、私。結構しつこい方だと思っていたけど、それは自己判断だった。基準が低いよ。もっともっと上げねばだ。
色やデザインへのセンスをほめられたのは、うれしかった。お見せした九寸帯、「あら、もう少し前に拝見してたら撮影に使わせてもらったのに、、」とおっしゃられたのは、にんまりした。
森田空美先生、本当にどうもありがとうございました。お話いただいとことを、しっかり布に反映させます。
写真はたまたま見かけたポスターをパチリ。ちょっと森田先生の世界観ぽいと思った。トーキョーワンダーサイトってところの。カッコいいよね。
被せ綿、お納め

ずっと取り組んでいた菊の被せ綿の染めですが、黄色も染まりました!福木に茜を少々まぜて染めまして、その上に、酸性染料で補強しています。福々しくと思ったので、福木を使いましたが、めざす色は鬱金(ウコン)色です。

ほら!赤と黄色がそろいました。重陽のお節句に使うものなので、思い切り濃く染めています。赤は緋毛氈(ひもうせん)とか陣羽織とか、ああいう意味ある真っ赤をめざしました。昔から特別に尊ばれている色なんだなあと思いました。
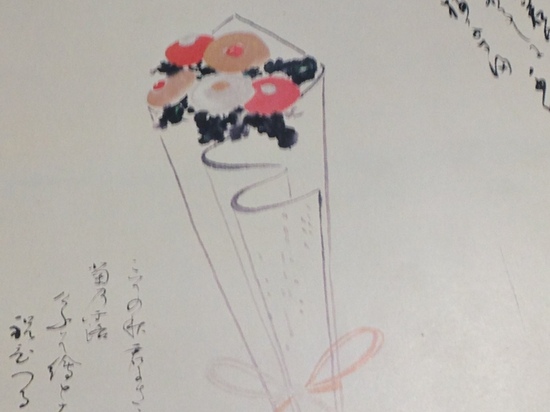
これらを抱えて、お納めもしてきましたよ。遠州流のお茶のお家元さまです。飯田橋の駅を降りて地図通りに伺ったけど、なんだか江戸をすぐそこに感じたよ。別世界に迷い込んだような感じだった。
この絵は、先代さまがお描きになった被せ綿を被せた菊。うわー。なるほどなあ。昔からこうやって、菊にこの被せ綿をして、長寿を願って、差し上げたりしたそうです。
ものすごくおいしいお抹茶もいただきました。無作法なのに、ひゃー、どうしましょう。
すばらしい体験をさせていただきました。昔からの行事の一端を担えたとしたら、大変光栄です。
田中直染料店へ

今日は、渋谷にある染料屋さんに行ってきました。京都の本社から専門の方が見えると聞きつけていたので。
前々から酸性染料の使い方で、どうしても解決できない点があり、試行錯誤を繰り返すも、成功と失敗が交互にきて、いったい何がいいのか悪いのか糸口さえ見つからず、悶絶していたのです。とうとう京都まで相談に行くしかないかと思っていたところに、あちらから東京にお越しになるとは!!!なんという幸運!(こういうの鴨ネギって言う??言わないね)
その方を独り占め(笑)するために、開店直後を狙って行きましたが、何と先客がお二人も。みなさん、情報通、かつ情熱的ですな。

それで、今までの失敗資料など持って行きましたら、すっごく興味を示して下さり、たっぷり相談に乗って下さいました。さあ、これを制作にどう反映させるか。やるしかありませんな。がんばります。
田中直染料店さん、いつも、どうもありがとうございます。その的確な判断に感服です。染めは化学やなあ、、、化学と愛情ね。(ちなみに織りは、算数と愛情。)
染料屋さん、糸屋さん、道具屋さんに「あいつはなかなかやるな」って思っていただくの、ひとつの目標だったりします。
*写真はうちの近所。散歩の途中で見かけたガレージ。
菊の被せ綿

このところ、通常業務の帯を織るのと、飛び込んできた「菊の被せ綿(きせわた)」を染めるので、大わらわ。
これは、茜を煮出しているところ。

ほら、こんなに立派な染液が取れました。染料となった茜は、被せ綿を頼まれた先から送られてきたもの。とても古かったし、色が出るか心配だったけど、何度も洗ってきれいにして煮出したら、がんばってくれました。茜、すごいぞ!

真綿をこのように染めています。まだまだ試し染めです。

濃度を変えて、何度も試しをしました。見本をいただいているので、その色に近づけようと必死です。めざすは、真っ赤と真っ黄です。

染め直し。酸性染料の力も借ります。

これでどうだ!(って実はこのあとも、色味を近づけるため、染めは繰り返されるのでした。悪戦苦闘の最中です。)
水戸岡鋭治さんの展示会。本も読んだよ。

熊本からこっちに戻り、はや、一週間。すっかり通常業務なのだけど、今頃、疲れがどっと出ているのは、これはやはり、寄る年並ってことでしょうか?
この一週間で、本を2冊読みました。熊本の現代美術館で買い求めたものです。
熊本市現代美術館では、「水戸岡鋭治からのプレゼントーまちと人を幸福にするデザイン展」を開催してました。水戸岡氏は、JR九州の新幹線とか、ななつ星とか、とても有名なデザイナーです。
帰省時にこれをやってるってことは、知っていた。しかし、行けるか?つか、行くか?私、乗り物とか、ほとんど興味ないし、、、

でですねーー、実は短時間ながら2回も行っちゃいました。1回行って、もったいなさ過ぎて、時間を見つけてもう一度。本当にこれは、水戸岡氏から全ての人に向けた「プレゼント」でした。
子どもたちは、ただただ楽しく目を輝かせているし、大人は、ここまでの仕事をひたむきにやり遂げる、仕事哲学とロマンに打ちのめされたのでは、、、、私はほれたよ。仕事とは、こうあるべし。買ってきた本にも、書いてあったよ。
「あと1%だけやってみよう」とか、「それが出来ない理由はどこにもない」とか、「次世代が幸せになる仕事でなければ意味がない」とか。
もいっちょ、氏の真骨頂、「とことん試行錯誤すれば見えてくる」「デザイナーは公僕であれ」「経済は文化の僕である」などなどなど。

うーーん、私もがんばります。水戸岡氏の数万分の一でも、一歩一歩やっていきます。
写真は、今回までは、内輪のお祝い事で失礼します。私が撮ったベストショット。やっぱ、りょうくんに負けてるわ。
ベストショット





今回の帰省中、デジカメでバシバシ写真を撮りました。家族にも、勝手に撮ってよと言ってカメラ渡してたら、知らぬ間に1000枚近く撮れてた。で、ベストショットを選ぼうと思ってつらつら見る。以上の5枚が候補だなあ、、、と。
ショック!これら、すべて、私が撮ったんじゃない!それもカメラマンは同一人物!

ジャーン!撮ったのは、甥のりょうくん、7歳です。いやあ、いい写真撮りますねえ、おばちゃん、完敗です。
りょうくんは、いとこのひなちゃんのエスコートもこなすジェントルマンです。

ほら、ここでも、りょうくんは、ひなちゃんのことをしっかりエスコートしています。
あ、ついでながら、私の髪型にもご注目ください!生まれてはじめて、夜会巻きしてます!!!あげてくれたのは、幼なじみのチャコちゃんです!
帰省してました

ちょいと熊本に帰ってきました。ここは羽田空港。空港っていいよね。好きだわー。
さあ、これからフライト。いつもの通り、さっぱり気ままな一人旅です。

が、帰った先は、ちっとも気ままじゃなかったよーーー。カオスでした。ちょー久しぶりに大家族が結集です。
おかげさまで、両親が金婚式、父が喜寿のお祝いを迎えました。そのお祝いに、四人姉妹と、婿たちと、孫四人が駆けつけました。みんなそれぞれの事情と台風を乗り越え。
義弟の一人は飛行機が欠航、宴席には電話で出席。これがただひとつの残念事項でした。
ふるさとはいいなーー、家族はいいなーーって思った数日間でした。
真綿を染める

ちょいと頼まれまして、草木染めで真綿を染めました。ふわふわしてて、かわいいです。さすが、真綿。

何にするかと申しますと、重陽のお節句に、菊の花にかぶせて、夜露をとるのですって。その綿で体を清めると長生きするのですって。
おお、そんな故事があったとは、知らなかったぜ。
染料は、写真の左下から右に向けて、エンジュ、アカネ、スオウ、左上から、フクギ、アカネの薄め、ヤマモモ。
現在の経糸

これ、今、張ってる経糸です。全部、きびそ糸。太細の差が激しくて、ももけて、ももけて、ものすっごく織りにくい。織りにくいのは分かってたから、糊の付け方をそうとう工夫したんだけどな。およばず、、、
これをどう御するか。糸の良さと特性を、もっともっと、バーンと表現したい。
これを、八寸帯、半幅帯、角帯に発展させたいのです。もうひと工夫だ。
生まれ変わった織機

じゃーん!これが私の生まれ変わった織機です。座板と杼箱と小ろくろが新しくなりました。写ってないけど、ペダルのガイドの柵も固定されました。親ろくろもコードを固定できるよう、穴をあけてもらったんだよ!

ほら、一番の懸念の座板はこのようになったよ。織機の材に、ボルトを入れて、押さえをつけてもらったの。座板そのものの欠けも大きくなり遊びが出来ました。今まではいつ落ちるかとビクビクして織ってたけど、それは激減すると思う。安心して織りに打ち込めるね。

これは小ろくろ。幅を伸ばしてもらいました。今までの左右からコードが落ち、ストレスだったんだ。固定しようと釘を打ったりしてたんだけど、釘の頭がコードを切ったりして、これまたストレス。
今回、きつつき工房さんにお願いして、長年の願いが理想的な形でかないました。とってもうれしいです。
今までも出来る範囲で織機の改造してきました。ペダルも入れ替えたし、筬柄も変えたし、杼箱も自作してたし。ろくろもどんだけいじったか、、、、座板も何枚も変えたよ。角度をつけたり、ストッパーつけたりもした。
織機を改造することは、染織をしていれば当たり前のことなのですが、、、今回は目から鱗でした。自分では想像もできなかったことを提案いただいたりして、、、、。
きつつき工房さんが、私の織機の問題を聞いて下さり、一緒に考えて下さり、寸法を測り、最適な材を調達して、加工して、そして実際に装着して、、、、、願いがかなった!うーーん、すてき!
これって、私が取り組んでいる着物や帯の完全注文制作 ONLY ONLY と同じだね。私はここまで出来ているのか???悶々、、、自問自答です。
今回の私のこの深い満足を、私にご注文くださる方にも、味わっていただけるよう、新しい織機と一緒にがんばります。
きつつき工房さん、本当にどうもありがとうございました。
織機改造!

本日は長年の夢だった織機改造の日です!山梨からきつつき工房さんが、お越しくださってます。私、仕事の手をとめて、ドキドキしながら(じゃまにならないように控えめに)見守ってます。
私は織機を2台持っていて、一号機とは、20年以上の付き合いの頼れるヤツなんですが、座面とかろくろとかに、いろいろ使いづらい点を抱えてて、どうしたものかと悩んでました。今後も一生このままつき合っていくのは厳しいなあと。
一度、座面の板から落ちて頭を打ったのが決定打で、何とかしなければならないと決心しました。
そこで思い切って、評判を聞いていた、きつつき工房さんに電話して相談したら(まさに「悩みを打ち明けた」状態)、一度見てみましょうということになり、この3月に下見にお越しくださっていたのです。
そして、晴れて本日!私の織機は生まれ変わります!(←大げさ!ちょっと手が加わるだけ。でもそれを切望していたのです〜)
写真は、お仕事中のきつつきご夫妻。お世話になります。
以上、ライブ中継でした!
仁平幸春展、夏の景

仁平幸春さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。仁平さんの世界観が会場に満ちていて、とてもすてきでした。作品はすでに縁があって、もう会場には無いものもたくさんあったようで、それがちょっと残念ですが、全部見たいなら初日に行かないとダメですね。
トークも白熱してました。仁平さんのお話で、特に心に残ってフレーズは、「ご注文で作るものと、自分でインスピレーションで作るものは同じだ」「よろこんでいただくことは、妥協とか迎合とかでは決してない」「シンプルと言うのは、同じ方向に波長を整えてあげることだ」などなどでした。
自分のやってることを省みるのに、仁平さんの作品を拝見したり、お話を聞いたりするのは、とてもいいです。「ここまでやってる人が今、私の目の前にいる」って現実を突きつけて、一回奈落に落ちるのです。
さあ、はい上がりますわよ。
仁平幸春展は、銀座もとじさんにて、明日まで。
それから、「夏の景」と銘打たれた展示会を拝見してきました。とてもすてきな工芸作家さんたちのグループ展です。以前、上野の都美館で、大きな展示会を拝見して、いいな〜って思っていたものですから。
今回は、こじんまりとしたギャラリーで、規模は小さいのですが、こんなモノと一緒に暮らせたらなって思うもの、たくさんありました。分野が違う作家さんが、いい意味でぶつかりあって、その刺激を観るものにも、分けてくれるような展示会でした。
この展示会は、今日で終了しています。
写真はうちの仕事場風景。すみません、文章にあう写真がなかった。銀座もギラギラ暑かった。
青い空

今日は、カリフォルニアかってくらいの(行ったことはありませんが)、完璧な青空でしたね。湿度は、多湿で有名な故郷熊本もまっつぁおって程で、くらくらになりました。(こちらはモンスーンアジア)
暑さと湿度で、関東一円、もしかしたら日本全国、なかなかしんどい一日だったと推察します。

そんな中、私は蒸し作業と、染め作業をしておりまして、日付が変わった今頃、やっとエアコン入れて、人心地ついております。
糸染めって、時間が染めてくれるところあるから、夜ご飯食べながらも、お風呂はいりながらも、続行するのです。そうすると一日で終わったりもできる。ある意味、効率的とも言えましょう。
大きなタンクに一日中、お湯が沸点をキープ。梅干しなめながらがんばりました。
(アイス食べたかった〜。でも暑くて買いにいけなかった。ご褒美にやせればいいけど、そうはいかない。)
着物でおでかけ

チャンスがあれば、出来るだけ着物でお出かけしようと思ってる。なかなか出来ない現実もあるけど。
駅でも電車でも、着物の人がいたら、目線だけで追う。目的地にはたいてい着物の人がいる。
目的地がパリッとした場なら、パリッとした着物姿の人が多いし、くだけた場なら、それぞれ自由な着姿となる。道行く人は、もちろんそれぞれ。私は持ってる数が少ないから、季節で変えるのが精一杯。どこにでも同じ着物で行っちゃうんだけど。
で、最近思ったのは、必ずしもパリッとした着物がいいって訳でもないね。パリって言うのは、新調してすぐだったり、格式があったりってことだけど。
年期の入った感じもよいなあ。前帯の下のところが少々すり切れたりしているのをみると愛おしくなる。何回も何回も締められ、いろいろにお出かけし、もしかしたら前の主との思い出が。
帯揚げがちょっと汚れていたりするのもまた良い。生活に溶け込んでいる。特別じゃないんだって思う。
着物と一緒に自分も育っていければなお良い。そうありたいものだ。
*写真と文章は特にリンクしてません。着物きて写ってるのがこれしかなかった。左はいつも同じ着物の人。右はたくさんお持ちで豊かな着物ライフの人。
昨晩のこと
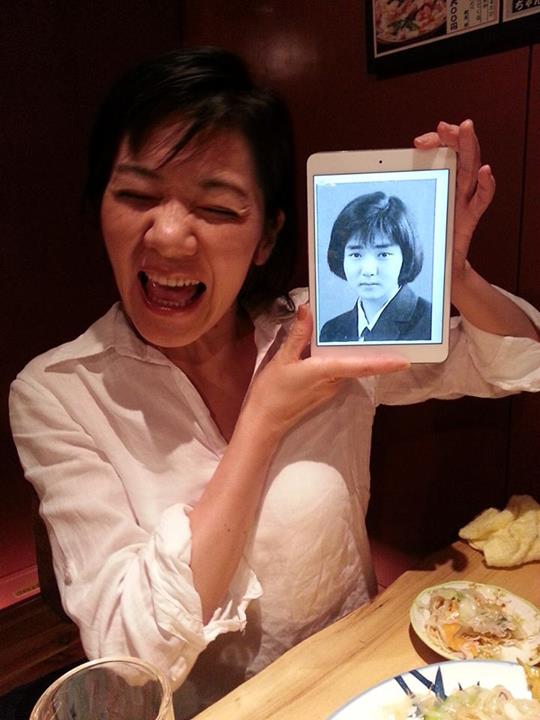
とつぜん、はっちゃけてる自分の写真で、失礼します。面白い写真、撮ってもらったので、ついつい、こちらにもアップ。
昨日は、同窓会の会員PR班の打ち上げでした。楽しかったー。リラックスしたーー。28年ぶりに再結集して、みんなで苦労して作り上げた同窓会。ひと仕事成し遂げたよね、私たち。がんばりました。
同窓会の仕事、やったこと、ちゃんと評価してもらっててうれしかった。それ、聞けてよかった。「もっと出来たはず」ってついつい思っちゃうのだけど、救われた思いしました。やるだけやった。幹事の仲間にしてもらって、本当によかったよ。
この28年、みんなそれぞれ、いろいろありました。そんな話しもやっとしました。それぞれのタイミングで、熊本を出てこっちに来て、それぞれに乗り越えて来たよね。いいことばっかりじゃなかったよね。これからだって、不安だよね。それでも、一歩一歩、がんばりましょうぜよ。人生ってそんなもんかな。それがやっと分かって来たお年頃か。
来し方行く末に思いを馳せながら、みんなそれぞれ、飲み過ぎました。大酔っぱらいして、終電近くで帰ってきました。
写真は、卒業写真の私と昨日の私です。すごいでしょ、卒業アルバムをスキャンして、アップしてくれてるのです。びっくりね。おはずかしー。
わらわらと、

7月になってしまいました。
最近は、落ち着かない日々を過ごしています。いろいろ物品購入の手配したり、試しをしたり、仕上げをしたり。わらわらです。
上は栗染め。試し染め。

これは、アップし忘れてた。くりさま、ご入浴中(湯通し)です。これ、本日、湯のしから帰ってきました。

悩みながら取り組んでた帯。これも入浴中。

悩みながらの試し。ご注文いただいている八寸帯に発展させたいのだけど、模索中です。

これは到来もの!!ありがとう!!!
池袋な夜

池袋に行ってきた。先日の大同窓会の、引き継ぎ準備のため。集合場所は、同窓の後輩がやってる居酒屋さんで、池袋の西口からちょっとの所。
私、5年前まで、この辺り、生活圏だった。このまま、この道を自転車で15分走って、右にちょろっと入った所の小さなアパート。10年住んでた。
何か必要なものがあるとか、ちょっと気分転換に、この辺りは良く来た。ここからちょっとの所に、おいしい豆腐屋さんがある。パン屋さんもある。
引っ越してから、はじめてだ。池袋、ウェストゲート。猥雑な所もなつかしい。

先日の、脱法ハーブの自動車事故の現場があった。花やペットボトルがたくさん供えられてた。被害者は中国人の方だったな。この辺、外国人も多いのだ。外国で事故に巻き込まれるなんて、さぞ無念だろう。悔やんでも悔やみきれない。
同窓会の集まりでは、私、リラックスしてよくしゃべり、飲み過ぎました。みんないいやつ。同窓生はいいもんだね。酔っぱらって夜中に帰ってきました。
バルテュスの写真展へ行った

バルテュスの最晩年の写真が展示されていると言うので、三菱一号館美術館に行ってきた。
メイン会場から離れた、小さなの展示室。ポラロイドで撮った写真がたくさん。同じモデル。似たようなポーズ。例の、あの、バルテュス特有の、少女の肢体。ピンぼけがまた良し。
そのたくさんの写真、少しだけアングルを変えたり、影の出方を変えたり、モデルの手の位置を変えたり、、、、ごくごく微妙に変えて、何枚も何枚も。空気を変えて、撮ったのかな。
バルテュスの絵は、1940年代とか50年代とかのビンビンな緊張感のある作品に惹かれてて、やはり最盛期ってもんがあるのかなって思ってたけど、ところがどっこい、最後の最後まで、この執着。少女に魅せられ続けた。執着し、形にして行った。すごいぜ、バルテュス。
「バルテュス最後の写真」展は、9月7日まで、三菱一号館美術館にて。
写真は私。美術館にて。着物を誂えたのがうれしくて、何かと言うと着てまわってます。単衣の季節が終わっちゃう〜。
グランド・ブダペスト・ホテル

映画みてきた。グランド・ブダペスト・ホテル。いやーー、面白かったです!映画を観ることの最大の魅力は、異世界に連れて行ってもらえることだと思ってんだけど、そう言う意味では、最高に面白かったです。持ってかれました。
ヨーロッパの東側の、山の保養地の高級ホテル。時代は1932年。(1960年代と現代も、入れ子になってるんだけど、きらびやかで、次々事件が起こる1932年がメイン)
古き良き、おしゃれで、贅沢で、退廃的で、シニカルで、ブラックで、暴力的で、非合法なヨーロッパ。(あら?褒め言葉になってない?)
登場人物が、それぞれ魅力的。でも結局、誰も幸せじゃない。そのどうしようもなさも好き。人生に意味はないって思ったよ。あはは。
すばらしく、きれいな映像です。すべてのシーンが決まってる。色もきれい。おすすめ!!!

サイトはこちら→☆。 私が行った回は、すごく混んでた。行かれる方は、空いてそうな劇場と日時を狙われるとよろしいかと。
写真は、表参道駅の千代田線の地下鉄のホーム。日比谷に向かうのに乗り換えた。
トライ、柿染め

先日、染液をとった柿の試し染めで、布をいくつか染めてみました。ああ、面白かった!草木染めは、最後の最後まで、どんな色になるのか手探りで、そこにやっぱり引き込まれるね!
さあ、この試しを、どう発展させるかだ。(次は楽しかったではすまされないぞっ。)
ちなみに、上の写真は、手前から、チタン媒染、銅媒染、アルミ媒染です。他に、錫媒染と、鉄媒染もデータ取りました。
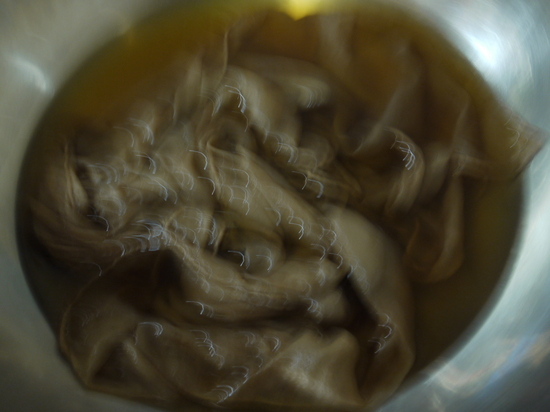
おお、写真に蛍が飛んでる!これは、染液で布を煮込んでいるところ。

これは、トップの写真の手前に写ってるチタン媒染の布を染めているところ。今日は簡易的に割り箸で押えて、染まらない部分を作っています。
ま、カッコよく言うと、夾纈(きょうけち)ですな。浸染の三大技法(これもカッコよく言うと三纈(さんけち))のうちのひとつ。板で強く押え、そこだけ染まらない部分を作って染めるってことで、思わぬ効果が出て面白いんだー。効果的にカッコよくやるには、ひねりが相当必要なんだけどね。
柿の木

我が家のベランダのすぐ前に、柿の木がある。大きくはないが、なかなか風情のある木だ。私は毎日この木を見て生活している。

先日、朝からガヤガヤ聞こえた。あ、植木屋さん!私の住んでる集合住宅は大家さんが、とても大事にメンテをしておられ、ときどきこうやって手入れの方がやってくる。

うちの目の前の柿の木にも、ハサミが。お休み時間を見計らって、出て行ったら、ちょうど大家さんご夫妻も出ておられ、切った枝葉をいただきたいとお願いすると、こころよくオッケー。
ほら、こんなかわいい実もなってた。

いただいた枝葉を早速解体。小さく、小さく。

煮出します。実は、柿の染めをやりたいと思ってたの。栗染めに続けてね。
猫のぱんだちゃん

最近知り合った一人暮らしの女の人に、出張中、お宅に通って猫のお世話をしてくれないかと頼まれた。えーー、私、親の家を出てからは、めだかしか飼ったことことないよ〜。大丈夫かしら〜。
それでも、一人暮らしは助け合わないとと思っているので、引き受けた。それで、先日から、彼女のお宅へ通っている。片道徒歩20分くらい。一時間くらいのボランティア。下見も入れて、全部で3回だから、何てことない。
下見に行った日は猛暑日かってくらいのギラギラの日で(先々週の週末ですよ。それも約束の時間は午後一時!)、一回目行った日は大雨で、二回目の今日は、午後は忙しいし、暑くなりそうだったから早朝に行こうとしたら、貸してくれた自転車がパンクしてた。で、お店が開く10時を待って出かけたら、真夏の太陽がジリジリでした。
ああ、なんだか艱難辛苦(←大げさ!笑)。
それでも、猫のぱんだちゃんが、はじめは知らんぷりしてたのに、今日などは近づいてきて、なでなでさせてくれたりすると、守る相手がいるのはいいことだなあと思ったり。
今朝、ラジオで、やはり一人暮らしの女性が入院することになり、飼い猫に10日間分のエサとトイレの準備をした。10日後感激の再会だったみたいな話し、流れてた。
一人暮らしだからこそ、動物がいるといいのにね。難しいね。

写真はうちの近所。帽子に黄線。これって、知る人ぞ知る、某高校の制帽のごたる。笑。
私の単衣・2

私の単衣をつくるのに、山本きもの工房の山本さんには、とーってもお世話になりました。全身自作の夢をかなえて下さいました。
実はお襦袢もつくりましたのよ、おほほ。こちらは裁断済みの白生地の状態で送っていただいて、うすーい緑に自分で染めた。日本語でいうとひわ色かな?ミントグリーンにちょっと黄色を溶かしたような色。透き通った羽衣系の布になった。
着物の裏につける居敷宛てなども、裁断済みを自分で染めた。こちらは薄めの菜の花色というか、カナリーイエローというか。かわいい色になりました。
帯もね、手元にあった一本をおろしたのだけど(こちらは、1丈5尺と長過ぎ。切ればよかったのだけど、どこを出すかを自分で決めていいものやらと思い悩み、切れずにいた。)(自分のものにすると決めてから、人が変わったようにバシバシ決めてった。あはは)、「タイコの幅はこの縞からこの縞までの八寸で」「前帯はそれに限らず」「タレ先はこのポイント」「長さは私サイズで切って下さい」と指定して、思い通りの帯にしてもらった。
いやーー、仕立師さんって本当にすごいね!山本さんと話してて、実感しました。
着物の反物の長さが足りないの、単に形にしてくれただけじゃないんだよ。着物としてカッコいいの。格子のリズムも抜群なのだ。縫い方も必要に応じて変えてあって、力が掛かるお尻あたりの背縫いは鬼のように細かいのだ。
今回しみじみ思ったのだけど、仕立師さんと組んで助けてもらうことで、織り手はもっと自由に羽ばたけるのではないか。仕立師さんのすごさを知ってれば、「ねばならない」の強迫観念に押しつぶされそうになることから、ちょっとだけ解き放たれるんじゃないか。もしかしたら、織ること自体にもっともっと集中して、愛撫するように織れるんじゃないか。
山本きもの工房さんのサイトはこちら→☆
私の単衣

この春の私的一大イベントは、清水の舞台からダイブして、単衣の着物を誂えたことでした。やったーー!
頼もうって決めた時から、いろいろあって、仕立て上がって、何回か着るまで、ずーっとドキドキしてました。やっとやっと落ち着いてきましたので、ここにも書きますね。
長年、単衣の時期に自作を着ていないことを残念に思っていたのですが、やっと思い切りました。といっても、自分用に織れる訳ではありません。手持ちの自作反物の中から、売れないかもなってのをおろすのです。実は長さが足りない反物を作ってしまってたのでそれが候補。本来3丈3尺なければならない反物が、2丈8尺7寸6分しかありません。
糸とか染めはすっごくいいの。国産座繰りの無撚り糸や、石垣島産の手引き糸など使ってます。
これ、着物になるだろうか?
横浜の、山本きもの工房の山本さんにおそるおそる相談してみると、大丈夫だよ、と!下前の衿と衽に別布を入れこむことで、見た目は全く遜色ない着物になるとのこと。すごい!山本さん!
別布も、自作布。以前織った単衣にも抜群の着物の余り分を使っていただくことに。
それで、いろいろ相談させてもらって、襦袢と着物の裏地(居敷宛てと衿裏、袖口のすべり)の布も、自分で染めることに。
ひゃー、自分のことなので、一回で書ききろうって思ってましたが、長くなりそうなので、今日はここまでです。続き、もちょっと、書かせてね。
今回、着物を誂える側の気持ち、よーーく分かりました。その気持ちに添えるように、私もがんばります。
平山ふさえさん、下地康子さん

染織家の平山ふさえさんと、下地康子さんが、我が家を訪ねて下さった。平山さんは、芭蕉布の聖地、沖縄本島の喜如嘉在住の作家さんです。下地さんは、関東在住ですが、ご出身は沖縄。
我が家に沖縄の風が吹きました。暑くなりましたし、沖縄からの風、心地よかったです。
三人で、アツく染織を語りました。いやはや〜。
織りを専業で続けていくことの大変さは暗黙の了解なのですが、お二人ともそれを自然に引き受けてらっしゃると言うか、、、覚悟と心意気を感じました。
すてきな作り手仲間です。お互い、がんばろう!
平山ふさえさんのブログはこちら。ぬぬぬパナパナ展に出展されてます。東京展は終わってしまいましたが、大阪はこれから。行ける方、ぜひ。
下地康子さんのサイトはこちら。国展で展示されてましたが、会期終了。あー、観に行きたかったなあ〜。
写真は天野志穂実さん撮影。このライトの下で、おおいに語り合いました。お酒も少々飲み過ぎました。
同窓会でした!

昨晩は、我々、昭和62年卒が幹事をつとめさていただいた、済々黌東京同窓会2014でした。高校の同窓会。ものすごく本格的なヤツ。昭和17年卒の大先輩から平成26年卒の若者までが一同に集う一大イベントです。
大にぎわいで、まあ、成功と言えるのでは、、、というか、これ以上は出来ないよってくらい、がんばったよね、私たち。
丸1年、これに携わってきました。なんで、こんなに時間とエネルギーを取られるのだと思いながらも、リーダーに引っ張られる形で、コツコツ出来ることを、、、
みんな、すごいです。「ここまでするの?」ってことをやり切ったことの結集だったよね。ひー。
私は、ユニオン(団結)がどうも苦手で、今も昔も、なかなか上手く溶け込めないのですが、今回は仲間に入れてもらって面白かった。リユニオン、バンザイ!

当日は5時45分起き!お着物ですよ。うふふふー。
この日、私は生まれてはじめて、ヘアメークというのをやってもらいました。えへへ。中途半端な長さの髪を無理やり上げてもらってます。
私、今まで、一度もきちんとした恰好ってしたことないんです。成人式もしてませんし、大学は中退ですので卒業式もありませんし、残念ながら結婚式も経験してませんしね。あ、私、受験で、高校の卒業式も出てないんだ。式典は得意でないから、別に望まなかったけど、なんだかやり残した感、あります。
今回、そういう意味でも、同窓会の幹事をやりながら、なんだか卒業式みたいだなあと感じてました。
仲宗根みちこさん、新里玲子さんのトーク会

昨日、一昨日と、二日続けて、銀座もとじさんに伺いました。開催中だった宮古上布展のギャラリートークで、仲宗根みちこさんと、新里玲子さんが、お話される由、これは聞き逃せないぞ。
で、お二方とも、すっごくよかったです。引き込まれて拝聴していました。いやはや、苧麻を糸にして、それを布にするってやはりすごいなあ〜。伝統があって、その上で、ご自身独自の織物に昇華されてるし。いやはやー。
仲宗根みちこさんは、はじめの方で「私が織りたいものを織る」とおっしゃってた。で、終わりの方では、常にバランスを気にしながら仕事を進めて行くことや、ひとつひとつの作業をいかに慎重に丁寧に失敗せずにこなして行くかを話された。なるほど、自由にのびのびと織りたいものを織るには、同時に、厳しく締める所は締めないとね。
苧麻で太い細いをまぜたり、経に絣糸をまぜ込むときの、テンションの狂いを、機から降りて、後ろにまわって、直しながら織ってるって。その大変さ、分かります。大変だけど、それこそ、織りたい布なんだろうなあ。
新里玲子さんのトークも、面白かった〜。会場全体を引き込んでくれました。100歳で手績みをしているおばあの話しなど。苧麻の糸と宮古の女性がオーバーラップ。若いときは細い糸を績むけど、年を取ると太い糸しか績めなくなるんだって。それがまたいいんだった。八寸帯の糸に最高らしい。
「糸をいれて行くとき、ぜんぜん違う色を隣に持ってくると輝いたりするのよ。関係性ね。人間と同じ。」そんな話しもしてくれました。
「あこがれの宮古上布展」は、銀座もとじさんで開催されてましたが、18日で終了しています。
写真は我が家の近所。
バルテュス、観ました。

先日、上野に、バルテュス展を観に行ってきた。バルテュスは、どうしても惹きつけられてしまう画家のひとり。会期後半は混むと思って、連休の合間の平日に行ってきました。
見終わって、ああ、この人は絵描きそのものだなあと思った。絵描きという職業じゃなくて、絵描きそのもの。全人生、全人格で絵描きなんだなあ。
ま、個人的には、有名な少女の絵より、少年時代のバルテュスが、飼い猫のミツの物語を描いた連載挿絵がストレートに心を打つなあ、などとも思った。
バルテュス、はじめから最後まで(幼少期から死ぬまで)、上手い。さすが。
で、数日後のさっき、アーリュブリュット(インサイダーアート/知的障がいがある人がつくるアートをさすことも多い)を取り上げたNHKの番組をネットで観たのだけど、あー、なんだか、ちょっとだけバルテュスに似てるぞーって思った。全身全霊でアートに向かってるところが。
バルテュスは、特にそのデビューの頃とか、すごく戦略的だし、確信犯的な絵だし、無垢のアートのアールブリュットとは、真反対のような感じだけど、作品から発するものは、なんだか似てたよ。ベクトルの向け先がはっきりしてて、そこに向かって、進んで進んで進んで、やり切るってところが。
すごいー。とにかくやり切らないことには、話しが始まらんな。
バルテュス展は、上野の東京都立美術館にて、6月22日まで。その後、京都に巡回とのこと。
NHKの番組は、news web。今なら、ここの真ん中辺に動画があります。
写真は、整経後の糸をはずして、静寂に戻った、私の整経機。天野志穂実さん撮影。
染織吉田、11周年です!大感謝です!

本日5月1日、労働者の日、染織吉田は、独立11周年を迎えさせていただきました。これも支えて下さる、あなたさまのおかげです。本当にいつも、どうもありがとうございます。
好きなことを仕事にしていることの、ありがたさと大変さは、日々、感じておりますが、私はやっぱり織りを仕事にしてよかったなあと思うのです。全ての軸を織りに合わせられのですから!
今取り組んでいるくりさまのお着物だって、仕事でなかったら、織らなかったかもしれません。しかし、取り組んでみて、ものすっごく面白く、夢中です。織りって面白いわ〜って感嘆しながら進めてます。それが仕事になるのですから、ありがたいったらありゃしません。(しかし、体はボロボロね。)
いつもいつも、おかげさまです。感謝、感謝。
去年の10周年は、節目でしたので、騒ぎ立てましたが、今年は特別なことは何もなく、ただ普通に仕事してます。普通が一番かなー。
これからも、いいもの、織ります。どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。
写真は我が家の某所。天野志穂実さん撮影。
フリンジさんは本屋さん

今日のオヤツはこれ!おいしいコーヒーとクッキー、昨日、二子玉川の Fringe(フリンジ)さんでいただいてきたのです。
フリンジさんは、ただいま、本屋さんを開店されてます。店主麻子さんとその友人たちの愛蔵本が、読めたり、一部は買えたり。交換もできる。その場でコーヒーとクッキーも注文できる。極楽〜〜。
昨日、たどり着くのがけっこう遅くて、あまり長っ尻できなかったのだけど、それ、よかったかも。タイムリミットなかったら、いつもで居着けそうなくらい居心地いいです。半日は軽く居るね。リミットがなければ、エンドレス。
買ってきた焼き菓子、びっくりするくらいおいしかった。麻子さんのチョイスは、本当にすごい。
4月のフリンジさんのことは、こちらに載ってます。
私も本を出品させてもらってます。ブログに書いてくれてる〜。一部、タブローも置いてます。それも見てね!
熊本県立濟々黌高校、東京同窓会のお知らせです

実は私、今年の前半は忙しいんです。高校の、東京同窓会の幹事の年が廻ってきているのです。私が通っていた高校は、卒業してからも、なんだかんだと繋がってられる、ちょっと特異な高校なのよ。実は自慢。
故郷熊本から、こっちに出てきて、四半世紀は過ぎてるよね。去年の夏頃から、何だかんだと、集まりを持ち、旧交を温めつつ、準備が進んでます。私は、当時から、あまり人と仲良くすることが得意でなかったのだけど、なんか、仲間に入れてもらえてて、今さらながら、濟々黌でよかったなーって思ってる。役には立たないタイプなんだけどね。
で、今夜も会員PR班のミーティングに参加してきました。パンフ・渉外班も集まってたはず。協賛広告のお願いに、出向いていた人もいたはず。みんなすごいなあ。
私はいつも、原則ひとり行動なので、力を結集させたり、人を動かしたりするの見てて、ほれぼれしています。かつ、やっぱ、私は、一人でやって行くタイプの仕事しか出来なかったかなと思ったり。
いやはや、人生は面白いと思います。
ここ読んで下さってる、同窓生の皆さま、昭和11年卒の大先輩(昨年参加の最長老)から、平成25年卒のピチピチまで、5月24日土曜日は、ぜひ、濟々黌の東京同窓会にご参集ください。下のバナーからサイトに飛んでね。

*ロゴ、カッコいいでしょ。同窓生のデザイナー、渡邉善文くん作です。
*サイトを作ってくれたのは、同窓生の河瀬徹くんです。
秋桜きもの塾に行った。

先日のこと、中谷比佐子先生の、「秋桜きもの塾」に出かけてきた。
いつも秋桜舎からいただくお便りに、「きもの塾」のご案内を見た時に、「これは!」と思いました。まず、お習いすることは、「自分の体を知る。それぞれの骨と筋肉の動き」とあるのです。
白状しましょう。私、今まで、いつもいつも、「ちょっと違うんだよな」って思いながら着ていました。着物の本など読むと、着物は体の調子を整える、など書いてありますが、ちっともピンと来ていなかったのです。腑に落ちてない感じを持ったまま、うー苦しいーと思いながら着たり、はじめはきれいに着ても、あとで衿がパカパカになったりしていたのです。

でね、思い切って行って、すごく良かったです。
「きものを着るということは、自分の身体を知ること」「着付けの基本は、骨を美しく動かすこと」
テキストからの引用ですが、そうなのよ、そう言うことを本当に体得したいのよ。
それでね、衿がパカパカいってた訳も分かりました。私の鎖骨がそういう形をしているのだって。ひとりひとり骨が違うんだから、着付けも違って当たり前。私のような鎖骨の人は、衿が広がりやすいから、それをどうカバーするかが着付けの力。それは私だけの着方だし、他の鎖骨には必要ないのだ。そっかーー。
身体を知り、骨に聞けば、中谷先生おっしゃるところの、「身体が喜ぶ着付け」ができるかな。がんばろう。

全体図。
影山秀雄展、中国少数民族のデザイン展。

展示会ふたつ観てきた。出る用事の合間に、パパパッとだったけど、観てよかった。いい布見ると、リセットされるもんね。
まずは、「影山秀雄展」。織りの見本のような展示会で、ああやっぱり手織りの物はいいなあとしみじみ思いました。影山さん、伺うと、丁寧に何でも教えて下さるんです。織物への大きな愛を感じます。
ギャラリーを出て、銀座の街を歩きはじめたら、向こうから、着物姿のすてきなご婦人が歩いてくる。えっと、どこかでお会いしたような。思い出せないけど、、、藍の織りの着物に織りの八寸を銀座結び。さりげなくてカッコいいなあ。すれ違って、あ!影山さんの奥様だ!さすがの自然な着こなし。愛あふれる着物姿でした。
「影山秀雄展」は、銀座一穂堂にて、明日13日まで。
それから、自由が丘の、岩立フォークテキスタイルミュージアムで、中国少数民族の布を観ました。ここは、本当に布好きの聖地ね。すごいなあ。人間が布に出来るすべてのことが、本当にやりつくされてるもんね。民族衣装はエネルギーのかたまりだ。
たまに、見ないとダメね。人間がなぜ布を作ってきたかというに、戻れる。
「中国少数民族のデザイン」展は、4月19日まで。木金土のみ開館。
*写真は我が家。染め場兼台所。撮影は、天野志穂実さん。
山本秀司さんの「新・和裁入門」一気読み!
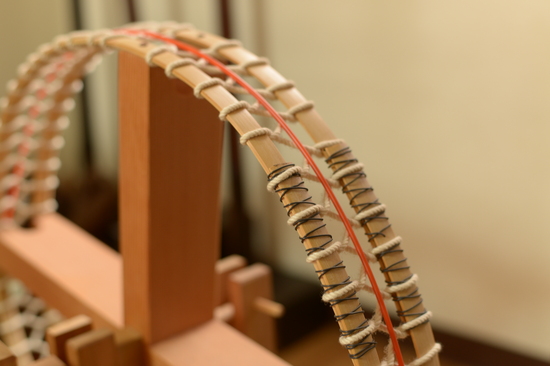
山本きもの工房の山本秀司さんが出された「新・和裁入門」をアマゾンで取り寄せました。面白くて、目から鱗で、引き込まれて、一気読みしました。考え方や基礎が丁寧に分かりやすく書いてあるし、シチュエーションに合わせた離れ業がすごい。仕立てでこんなことまで出来るのね!技術が完璧であるからこその離れ業だって思った。
布を本当に生かして下さる。ご本の「はじめに」に、仕立てる人は「超能力者」「2次元である布を、着る物という3次元の物に作り変える次元操者」とありましたが、本当にそうだわ。仕立てに対する尊敬の念が倍増です。
第一章にとても自然で普通のことが書いてあって、心に残ってる。以下、引用させてください。
「きものを仕立てるーーひと口にそう言っても、マニュアル通りに作ればお客様にとって着心地の良いきものに仕上がるわけではありません。
一反の反物をお客様仕様のきものに誂える。そのためには、確かな技術と知識、知恵、そして感性とコミュニケーション力が求められます。」
織りも全く同じです。自省です。
はじめてきものを織ってから、はや20年が経とうとしてます。しかし、いったい私はどこまでできているのか?
山本さんの本を何回も読み返して、着心地のいいきものを織りの観点から、考えて行きたいと思います。
山本きもの工房のサイトはこちら→☆
「新・和裁入門」のアマゾンページはこちら→☆
写真は我が家。天野志穂実さん撮影。
熊本ゆかり便りに載った!!!みかんだぜー!
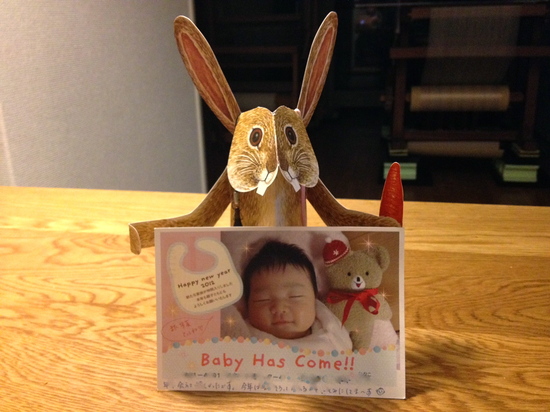
わー!「熊本ゆかり便り」に載ってる〜!
「熊本ゆかり便り」は、熊本から世界に着物愛を発信する着物サロン和の國さんのブログに、月に一度掲載される、着物ライター安達絵里子さんによるエッセーです。
この1月に開催された「熊本ゆかりの染織家展」に、みかんを題材にした着物や帯をださせていただきました。そのことを書いて下さってます。ぜひお読みくださいね。→こちらです!
話の中心は、みかん〜!私は3年程前、みかん色のONLY ONLYのお着物をご注文いただいたのをきっかけにはまりました。返す返すありがたいご注文でした。

故郷熊本は、柑橘のくだものの宝庫です。今はちょうどデコポンがおいしいですね。あのすっぱさと甘さのバランスはたまりません。まん丸の黄金色が、濃い緑の木にたわわになっている所を見るとそれだけで幸せになりますね。(デコポンはまん丸とは言い難いけど。) 色もいいんです。濃い緑、緑、黄緑、若草色、青竹色、黄色、山吹色、橙色、杏色、蜜柑色、菜の花色、タンポポ色、向日葵色、、、、みかんから広がるいろいろいろ。
みかんは表情豊かです。考えるだけでにっこり。そんな着物や帯を織って行きたいです。

写真は熊本のみかん娘、ひなちゃん。おばばかなもので〜。
花盛り

昨日撮った写真だけど、満開の桜です。のびのび。青空が気持ちよい。

誰もいない、近くの児童公園。なかなかいい桜の木があるので、チェックポイントなのだ。

友達が芍薬をくれた。さすが姿がいいね。友達曰く、花が開いたときの手触りがいいんだって。ぜひ触ってって。楽しみ。さわさわした感じかな。盛りを過ぎた、熟れ切った花もいいねって。そうね、それも楽しみ。

これは次の次の次くらいに織る帯の試し染め。いい具合に雰囲気とらえられたかなと思ってる。試しがいいと、結果も必ずいいから、織るのが楽しみ。
たたり
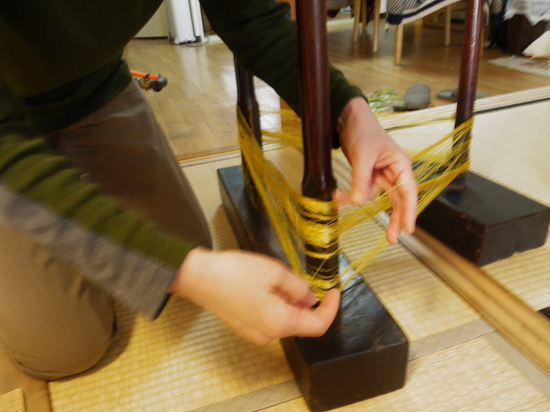
織りの道具で、「たたり」というのがあります。久しぶりに使ったので、ご紹介。ただの三本の棒なんだけどね。

糸と言うのは、綾が取れてなければ、扱えません。しかし、ごくたまに、綾が全くなかったり、崩れていたりする綛があるのです。そういう糸を棒綛と言います。棒綛を繰る道具が「たたり」です。

「たたり」は万葉集にも歌われているのですよ。織りは、人類の歴史とともにあるのです。

辛抱強く、解いて行きます。ヨシダ、ヘロヘロ。
これは、ヘロヘロになるよねー!
水流さんに載った!と思ったら、

あ!ピンクサーキットスクエアが、水流さんのサイトに載ってる!!わーー!!!
と昼間に気付き、ちょっと手が離せなかったから、今、ようやくじっくり読みました。こんなに良く書いて下さってて、しみじみうれしい。水流さんは、本当に染織品を愛して下さる方だなあ、、、そしてその愛を連鎖させて下さる方だ。ああ、この子がここで扱っていただくことになってよかったなあ。
と、読み進めておりましたら、ん?なんだか赤っぽい文字が目に入った。へ?は?
『SOLD OUT』!!!えーーー!!!これ、今日載ったよね?えーーーーーーー!!!本当なの??ほっぺをつねる。
大光栄でございます。水流さま、水流さまのお客様、本当にどうもありがとうございます。大切に作ったものが、大切に扱っていただけて、早速ご縁を結んでいただけて。大切にしてもらうんだよ。
とてもうれしいです。これぞ本望。この子をどうかよろしくお願い申し上げます。
写真は、水流さまのサイトから拝借しました。もう一回リンクしちゃう。じーんとくる文章書いて下さってるからぜひ読んで。
山下枝梨子展に行った

染織家、山下枝梨子さんの展示会を拝見しに、表参道の桃林堂に伺いました。木と陶の方々との三人展でした。
山下さんの作品はチャンスがあるときは拝見しているのですが、今回、なんと言うか、、、「ああ、彼女らしく上ってきたなあ」などと、僭越ながら思いました。
山下さんは、きちんと整った、出しゃばらない、控えめな布を織っておられて、それで自分の特徴を出したり、見る方の印象に残したりするのはなかなか大変と思っていたのです。が、今、とても印象に残ってます。いい布だったな〜。
小さい布を今回たくさん作られてましたが、ひとつひとつが愛らしくて、思わずなでなでしたくなりました。何気ないけど、いいのです。山下さんらしい布でした。
山下さんのブログはこちら。展示会は、本日最終日でした。
*写真は我が家。撮影は天野志穂実さん。
高円寺の夜

夕方に高円寺に行きました。友人と待ち合わせて。楽しい夜となりました。
まず、カメラマン武藤奈緒美さんの個展「気になる樹」を拝見にノラやさんへ。武藤さんの写真は、着物関係の雑誌に載ってるのなどはよく見ているけど、個展という形で拝見するのははじめて。
どっしりと息づいている樹が、武藤さんが覗くカメラのファインダーに切り取られて、それが額装されて、中央線の高架下のなかなかおしゃれなバール(?)の壁にある。その不思議さがいい。見ているとその生命力に深呼吸したくなる。
若い樹もいいけど、年月のたったドーンとした樹がいいねえ。森林浴した感じになるのはドーンとした樹が年月も刷新してくれるからか。
武藤奈緒美展は、4月5日まで開催中。
さて、次、我々は、メキシコ料理の店に行きました。友人は大の美食家で、この人にくっつとけば、おいしいものが、目の前につぎつぎ現れるのです。今までに食べたことないおいしいもの、たくさんいただきました。彼女は、このメキシコ料理をきっと、近々自分でも作るに違いない。すごい才能だ。テキーラも飲んで大満足。
一件だけでは済まない我々は、メキシコ料理の店で勧められた、大一市場を探し当てました。うひゃー、ここいいわ!屋台というか、もうちょっと立ってる感じだけど、簡易的な作り。アジアっぽい感じがいいです。我々が落ち着いた店、すごくレベルが高かった。自家製の分厚いベーコンがお通し。ここはどこなんだ。無国籍な感じです。ワインもおいしゅうございました。
高円寺、楽しいねー!我が家から、ちと遠いのが難と言えば難ですなあ〜。通いたいわあ。
*写真はメキシコ料理の、テキーラハウス
はやしのりこ展に行った

「はやしのりこのかたち」展に行ってきました。私ははやしさんのファンなので、行ける範囲で個展される時は、出かけることにしています。
はやしさんの作品は、とことん作り込んである。作品数も多くて圧倒させられる。今回もすごかったよ。ここまでやるかってくらい。迫力なのだ。
昨今は、なんにつけ、あっさり控えめ淡白が好まれてるけど、はやし作品には、潮流とか流行りとか、そんなの関係ないのだ。

今回は、障害がある人たちがテント地にペイントしたのを、はやしさんが形にしたバッグも出来てた。彼らとはやしさんのパワーとパワーのぶつかり合いって感じで、すごくよかった。
実は私、障害者の作業所など、今まで結構ご縁があって、彼らが作ったものとか、それを生かしたものとか、ずいぶん見てきたのだ。ここまで面白く昇華させてるの、はじめて見た。彼らとはやしさん、両方が生きてて、すごくよかった。
「はやしのりこのかたち」展は、南青山のギャルリーワッツにて、3月29日まで。
*写真は私んち。天野志穂実さん撮影。
祝・オープン!岩崎さんの増孝商店!

岩崎訓久さん悦子さんご夫妻が、この度、蔵前にオープンされたショップ、増孝商店におじゃましてきました!!!笑顔いっぱいのお二人がお出迎え。久しぶりにお会いできてうれしかった。

岩崎さんご夫妻は、力強い織り仲間で、いい布をどんどん織り出していらっしゃいます。それが一同に並んでて感激しました。見てて、このお二人は、心底糸が好きなんだなあと思ったよ。糸から愛があふれてるのだもの。
よかったね、糸たち、岩崎さんとこの糸になって、愛情いっぱいの布にしてもらえて。あんたたちはラッキーよ。

このお二人、いいのだよー。増孝商店の詳細はこちらから!
もとじさん、メゾンエルメス

銀座もとじさんに、プラチナボーイ新作展のトーク会に伺いました。作家さん8名だったから、お一人お一人の時間が短くてもったいなかったけど、一言の中に含蓄があったなあ。着物に合いやすい帯をどう作るかなど参考になった。
あわせて、織三蹟展、帯留め展も開催中で拝見してきた。盛りだくさん!
織三蹟展は代官山ヒルズでも拝見したけど、私のハートがちょっとは磨かれたのか(曇ってることが多いですので、、、)今日の方が響いたな。西陣のすごさを改めて見た思い。
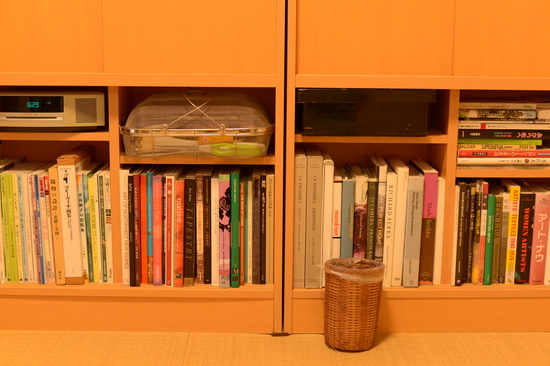
それから、メゾンエルメスに、「コンダンサシオン:アーティスト・イン・レジデンス」という展覧会を観に行きました。これは、エルメス財団が、若いアーティストをエルメスの工房に住まわせながら仕事の場所を与え、エルメスの職人がヘルプもし、新しいアートの創造を応援するというものです。超一流の仕事場に入り込めるのだから、うらやましい限り。
今まで16人のアーティストが参加したそうで、そうやってできた作品たちが展示されていたわけです。ここは会場もすごくよくて、光の入り具合とか、ライトのあて方とか、影の出来具合などが、最高だったなあ。ここにこうあることがアートなのだなあと思った。
一番好きだったのは、マリー=アンヌ・フランクヴィルという方の作品。1981年生まれだって。若っ!クリスタルの作品がメタルの台に乗ってて、壁に写る影が最高によかった。
6月30日まで。銀座に出たら、また寄ろう!
写真は我が家。撮影は天野志穂実さん。
バケットで舌を突き刺す。

うちから一番近いおいしいパン屋さんは、相模大野のメゾンカイザーだと思っている。そこのバケットモンジュは、皮がぱりっとして、大変美味。が、大変にかたい。その日に食べ切らない分は冷凍する。後日、オーブンで焼くと遜色無くおいしい。が、皮のかたさは倍増している。

気をつけて食べればいいのだろうが、おいしくて夢中で食べる。で、気がつくとバケットの鋭くかたい皮で、グサリと舌を突き刺している。しょっちゅうだ。
舌が傷ついてると、痛いし、大変わずらわしい。それをなぐさめるには、強い酒を飲むといいと気付いた。ウィスキーがいいね。ロックでいただくと、冷たさも相まって、舌がしびれて、しばしわずらわしさを忘れられる。その上おいしい。
強い酒を飲むとその後動けないので、日中は晩酌を楽しみにせっせと働く。なかなかの好循環だ。
写真は、ふふさまの緯糸。ビス糸(蚕が自分に一番近いところに吐く、柔らかくて繊細な糸)です。天野志穂実さん撮影。
大和骨董市へ

今日は第三土曜日。朝から、大和駅前で開催されている骨董市に行きました。いい天気で、ものすっごくにぎわってました。売る方も、買う方も、冷やかす方も、多種多様のタイプの人が集まってて、面白いわ〜。私は地元民で、電車ですぐなのだけど、ここは月に一度、突如現れるカオス。ひとくせも、ふたくせもある骨董屋の親父さんたちと、やり合えるもの面白いです。
私は、ロバート・フランクの写真集 PERU と、木でできたものと、古い藤布や麻布の蚊帳を買いました。糸がいい。最高だ。
帰ってきたら、なんだかここの所の疲れが出たのか、昼寝をしてしまいました。よい休日でした。
311を前に

先日のことだけど、半蔵門で行なわれた、東北の観光のシンポジウムというのに、顔を出してきた。友人が参加すると言うので賑やかしに。
それで思ったことは、東北と関わり続けるには、何か必要だってこと。仕事絡みでもいいし、友人絡みでもいい。旅行絡み、ボランティア絡み。何でもいいから、何かないと、関われない。
だからきっかけが必要で、そのきっかけ作りに、いろんな仕掛けがあってよい。
学生さんが「きっかけバス」というので、東北に行くツアーというのがあって、その資金が寄付でまかなわれているから、彼らは一円も使ってない。それを悪く言う人もあるそうだけど、私はいいと思った。だって、「きっかけ」なんだから。きっかけないと、つながれないんだから。
はじめのきっかけ、タダでもいいじゃん。
今の学生は、10年後には社会人バリバリだし。10年なんてあっという間だってこと、よく知ってるし。
東北の観光業、苦戦しているとのことだったけど、きっかけをうまく投げかけられたところは、イケてそうだった。なんでもそうなのかもなと思った。
*写真は、天野志穂実さん撮影
釜我敏子さん、飯田みちるさん、石嶋眞理さん、浅野裕尚さん

一昨日のこと。朝からとても充実していました。
まず釜我敏子さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。釜我さんは、型絵染めの大家。何度も作品拝見してるけど、みればみる程、あたらしい気付きがある。
型絵染めって、型紙一枚を繰り返し置いて染めるのだけど、釜我さん、その組み合わせがすごいのだ。優雅な動きがあって、一枚の繰り返しとはとても思えない。
その上、着物になった時の柄合わせが、背縫いはもちろん、身頃と衽の線、脇の線も、ピターッと合っているのだ。だからこそ、清楚な中にも堂々とした感じが出るんだな。これって、着物を作ったことが無いと、すごさが分からないかも。(私が絵羽を織る時は、脳みそがねじれる程悩みます。それでも解決せず、ねじれた脳がプツンと切れることも、、とほほ)
トークは檀ふみさんとの対談形式だったので、大変はなやかでした。お客様もきれいな方ばかり。しかし一番の花は、釜我さんご自身だったなあ。
「釜我敏子展」は銀座もとじさんにて。3月9日で終了しています。

それから、新宿に出て、もじり織りのグループ展を拝見しました。飯田みちるさんのお作品を拝見したいと思っていたし、この日は飯田さんが在廊されると聞いていたから。もじり織りって、私にとってまったく未知の世界です。うわー!自由だー。自分の世界ができるんだなあ。
飯田さんといろいろお話できてよかったです。織りの仲間はどんどん広げたいものです。
「しゃららーそれぞれの一日」は新宿クリスタルスポットにて。3月9日で終了しています。
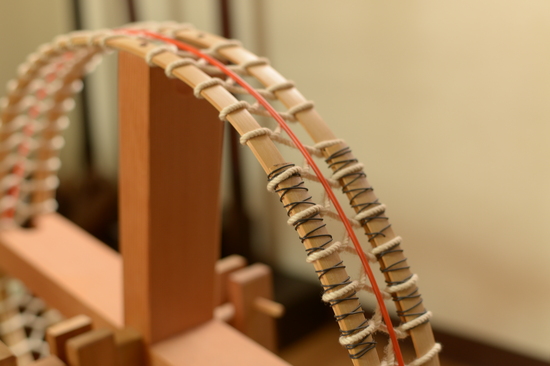
その後は、表参道です。結城紬のリユースを扱ってらっしゃる石嶋眞理さんが、展示をされるとのことで出かけました。石嶋さんの著書も以前に読んで、賛同すること多かったので。結城はすごいね、今も昔も。本当に尊敬する。石嶋さんとお話させてもらってうれしかった。名刺お渡ししたら、名前を見て、「もしかして、1年くらい前に、サイトを作りませんでしたか?」って。えーー!びっくり。見てて下さる方がいる。
「結城紬 逍遥」はラパン・エアロにて。3月10日で終了しています。
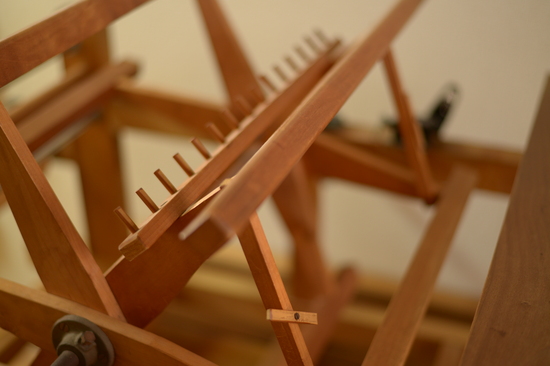
さあ、真打ち、「織三蹟」、代官山です。
織三蹟は、西陣の織元さん、3者の展覧会です。西陣すごすぎ。私などの織とは、同じ織と言っても別世界です。こちら最高峰です。
織楽浅野の浅野さんとお話できてうれしかった。浅野さんがお作りになるものは陰影や存在が、じわっと伝わってきてすごいのだ。それには、ひとつひとつにストーリーがある。
浅野さん、私が織るものなども、見ていて下さって、「もっとできるんちゃうの」とアドバイスくださる。そっか、もっとやっていいのか。そっか、そっか、やらなっきゃな、、、ありがたいこと。よっしゃ、もっとやったるでー!
「織三蹟」展は、代官山ヒルズにて。3月11日まで。
*写真は、すべて私の仕事場、天野志穂実さん撮影です。
青色申告おわった。

青色申告会に行ってきました。毎年思うけど、これはやっぱ、ある種の祭りですね。年に一度の異様な盛り上がり。いやはや、人がいっぱいいる所はなじめません。
とはいえ、何とか無事に受け付けてもらえました。今年もイッパツ合格です。数字はふがいないものですが。やれやれです。
写真は先日、我が家においで下さった、カメラマンの卵、天野志穂実さんが撮影くださったもの。写真の学校の学生さんで、学校の課題を撮らせて欲しいと頼まれたのです。朝の10時に来られて、夕方遅くまで撮り続けられました。私はもくもくと仕事してけど、750枚くらい撮ってかれました。
自分の生き方、ちゃんと見据えてる人で感心しました。人生、羽ばたいて下さいね。いろいろお話できて、楽しかった。好きな写真家はと聞いたら、植田正治だそうです。ああ、鳥取砂丘のあの人かー。去年、新美術館で観た写真展が面白かったと言うと、すぐ、「アンドレアス・グルスキーですね」って返されました。さすが。私、この名前、覚えられないわ。新しい写真の概念はすごく印象的だったけど。
この写ってる机は、熊本のうちから持ってきたもの。姉が勉強机を買ってもらったとき、妹の私がひがまないように、納屋の中から引っ張り出してきて与えられた年代物の机です。
貼ってあるパンダのシール、お若い天野さん、ご存知なかったです。「カンカンランランよ。ほら、日中国交回復の。田中角栄よ」って言ってもきょとん。そうよねえ、、、パンダ来日騒ぎを知っているというのは、年代物の人間ですなあ。
楽しい時間をありがとうございました。写真家 天野志穂実の誕生を楽しみにしていますね。
フリンジさんの2月

二子玉川のすてきな空間、フリンジさんに行ってきました。うすく伸ばした銅でつくった一輪挿しを中心に、フリンジ店主、福永麻子さんが選んだ美しいものがあふれていました。

銅の一輪挿しは、とても丁寧に大切に作られていて、これを作った作り手と、これを紹介しようと選んだ福永さんの、両方の愛が込められていたようでした。
ちなみに、写真は3枚とも、この銅の一輪挿しです。いろいろに生けられるのがいいのよね。

実は私の新作タブローも置かせていただいてます。おってご紹介させていただきますね。
今回の展示は、3月5日まで。(2/27は休み)13:00〜20:00
フリンジさんのフェイスブックはこちら。サイトはこちら。
帰りの話。

帰りは、2月14日金曜日、お昼にチェンマイを発って、バンコクでの乗り継ぎが一時間あって、午後10時半に羽田に到着予定です。
14日朝はゆっくりめ。散歩して、朝ご飯食べて、ゆうゆうと空港に向かいました。が、バンコク行きのタイ航空、遅れてる。ええーー、乗り継ぎなんですけど、、、大丈夫?地上係員さんに聞くと、羽田行きに乗り継ぐ人が20人以上いるから、出発を待たせるとのこと。

バンコクについて、どこのゲートにつくかと思っていたら、なんと、一番はじっこ。こりゃ、国際線まで距離あるわ〜。空港の建物に入ったら、「TO HANEDA」というカードを持った地上係員さんが待ち構えていた。
「我々は急がなくてはなりません。搭乗口は一番先です。走りますよ。」
20数名の我々は、バンコク・スワンナプーム国際空港の端っこから端っこを、隊列を組み、えっさほいさと走り抜けました。中学校の部活のようです。

ほうほうの体で乗り込んだ羽田行き、飛行機は順調に飛び、予定どおりだとのアナウンスあり。ただ、「羽田の天候は雪。視界は前方2メートルとの連絡を受けております」と。えっと、、視界2メートル?
窓側の席だったので、着陸の体勢がとられてから、ずっと外を見ていました。いくらたっても何も見えません。と、突然、すぐそこにライトの光が見えました。え!?その1秒後にランディングしました。見えたライトは、滑走路の埋め込みライトです。1秒前まで何も見えず。目が慣れてくると、外が吹雪なのが分かります。吹雪の中でも飛行機って着陸するんだ。はじめて知ったよ。すごいなあ。
降りた時間は予定通りでしたが、羽田混雑とのことで、1時間くらいは飛行機内に留め置かれ、吹雪の中、飛行機につけるちゃちな階段(それも凍った!)を使って、外に出され(ジャケット、預けた荷物の中よ!)、バスで建物へ。

経験者の私はこの日はもう帰れないってことは、覚悟済み。できれば居心地いいところで。
イミグレの前のスペースはカーペットで、暖かそう。そこにいた係の人に「もう帰れないからここにいちゃダメ?」って聞いたら、「いやー、申し訳ないです。」
荷物が出てくるターンテーブルのところも広くてよさそう。ここで夜明かししちゃダメ?「いやー、申し訳ないです。」
ま、そういうもんかな。外に出された私は、一路、空港5階のショップ前、つい一週間前にも一晩過ごした、懐かしい場所へ舞い戻ったのです。
学習済みですので、私は飛行機降りるとき、読んだ後の新聞もらってきたんだ。バンコク・ポストとか。それを敷いて、全く同じ場所にまた転がる。ああ、人生は面白いネ!
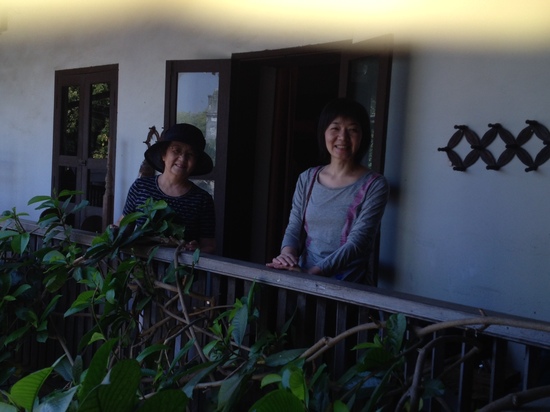
旅にスマホは、必要ですね。一晩あけて、電車の運転状況調べます。モノレール、強いなあ。他のが軒並み「運転見合わせ」なのに、動いてる。浜松町から大門に出れば、地下鉄乗れるな、、、しかし外は雨。うーん、この荷物、動きを鈍らせるなあ。
ふと見ると、お掃除の方が、もう働いてらっしゃいます。「宅配便、この時間に出せるところありませんか?」「ありますよ。24時間営業です」
それで、荷物を預け、うんと身軽にして羽田を後にしました。15日土曜日の早朝です。モノレールに乗りながら、この日のスケジュールをおさらい。朝10時から、銀座もとじさんで、山岸幸一さんのギャラリートーク申し込んでる。これは聞きたいのだ。うーむ、3時間半ほど時間つぶせばいい訳か、、、
それで、動き始めた山手線でくるくる廻ってることにしました。暖かいし座ってられるし、快適です。生まれてはじめて、山手線周回しました。

なかなか大変な思いをしてたどり着いた、銀座もとじさんですが、本当に行ってよかったです。山岸さんの織物は、本当にすばらしい。何をしたいか、何を求めているかが明確で、それを追い求めて、動いて、ゲットしてられる。感服です。
外に出たら青空。いい天気になりそうねーー!
*写真は、チェンマイでのショット。今回の旅行、現地集合で両親と一緒でした。長期滞在の彼らに途中から参加する形です。帰りは同じ日でしたが、彼らは福岡行きで本当によかったです。
行きのこと。

2月8日、昼間から外は大雪。飛行機、飛ぶのかしらん?
旅行会社など電話できるところ、掛けまくる。それで分かったことは、飛行機と言うのは、向こうを出たら(今回の場合はタイのバンコク)、どうにか着陸させて、お客を降ろして、また乗せて、ノルマをこなして行くってこと。
まあ、もしもチケットが正規のものだったら、振り替えてもらえるのでしょうが、もちろん格安航空券。この便、逃せばチケット、パア。
で、8日午後5時すぎに、私の乗る便が、バンコクを飛んだってことが分かった。こりゃ、行くしか無い。羽田にゴー。

完全防備の冬服で出発。雪に足を取られながら、駅まで強行軍。小田急、止まってる。じゃあ東急で行きましょう。渋谷で山手線、品川へ。京急に。ホームまではスムーズ。しかし、電車こない。人があふれてくる。放送があり、たった今から運休です。
がーん。もうダメだと一瞬思ったが、iPhoneで調べたら、なんと、モノレールは生きていた。浜松町へ。ああ、あこがれの羽田空港、国際線。たどり着いたよ。

が、滑走路封鎖。私の乗る飛行機、ランディングできず、名古屋に降りちゃった。その機体が羽田に飛んでくるのが何時になるのか不明。床で一晩を過ごすこと決定。(椅子はもちろん空いてない)

とにかく、少しでも居心地がいい床を探さねば。空港の5階のショップ前に転がってました。
「いい経験だよ、こんなこと、一生に一回だもん。思えば、避難所などにも寝るなんてこと無く生きてきた。ラッキーだったな。あ、しいて言えば、大阪から四国にフェリーで行った時の、三等船室にゴロゴロ寝たのに似てるなあ。あれも面白かったな。もうあれから20年か」などと思っておりました。

はじめの説明では、早ければ午前4時出発とのこと。しかし、それが6時になり、8時になり、、、、、、結局飛んだの、10時すぎだったよ。10時間の遅れだね。でも、搭乗手続きの締め切りは、午前3時だったから、この飛行機に乗ったのは、あの雪の中羽田にたどり着き、そこで一晩過ごした人だけってことで。みんなツワモノだなあ。ご老人、お子様連れ、さぞかし大変だったでしょう。日本語できない外国の方も不安だったね。私ごときが文句言っちゃいけないな。
と言う訳で、ボロボロに疲れて、9日の朝つくはずチェンマイに、夕方遅くにたどり着きました。

後日談。
次の日、まずはマッサージだと、評判の高い本格マッサージ屋に行き、一番高いコースを頼みました。このくらいしないと、前日のダメージ、リカバーできない。
ベテランぽい、にこやかな女性が、とても熱心に、力を込めて、グイグイもんでくださいました。痛かったけど、これで昨日のコリが消えるのならがまんです。
で、その晩、体がほてって眠れず。次の日コリ返しがきて、体中がもっと痛い、、、ああ、人生は過酷だなあ。

写真は、「美しい竹の村」。チェンマイ郊外で、木綿を紡いで、草木染め、手織りをしています。
染織吉田、通常業務再開しました!

ただいま戻りました!
染織吉田、通常どおりにしております。充電してまいりましたので、ますますがんばります。
以上、よろしくお願いいたします。
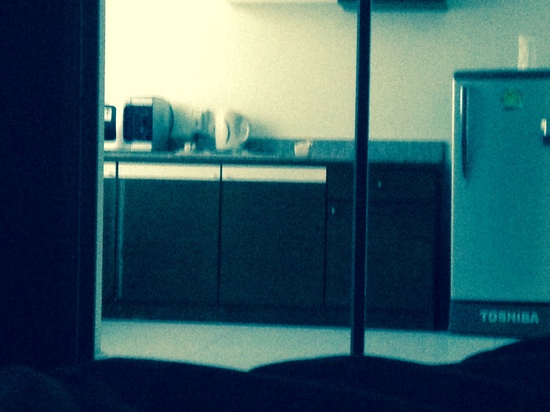
この一週間、特にはじめと終わり、大変に面白い体験をしました。(ま、ひどい目にあったと書いてもいいでしょう)
どんな体験だったかは、関東在住の方には、日付を言えば、推測していただけるかな。
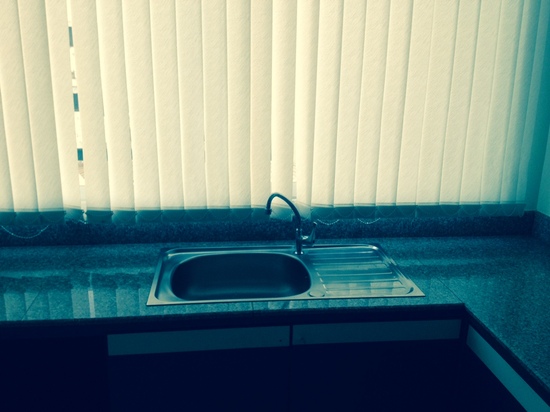
予定では、8日の夜にうちを出て、9日日付変わってすぐのフライト、帰りは、予定では14日の午後10時すぎにランディングして、我が家に夜中に帰り着いているはずでした。

その日は、関東地方、45年ぶりの大雪、交通機関大混乱の日です。
よりによって、行きも帰りも、大当たりです。
今、窓から外の光が、雪に反射してさんさんと降り注いでいます。あーあ、今日、帰ってくればなあ。。。
写真は、滞在先のチェンマイのホテル。
神ノ川智早展に行った
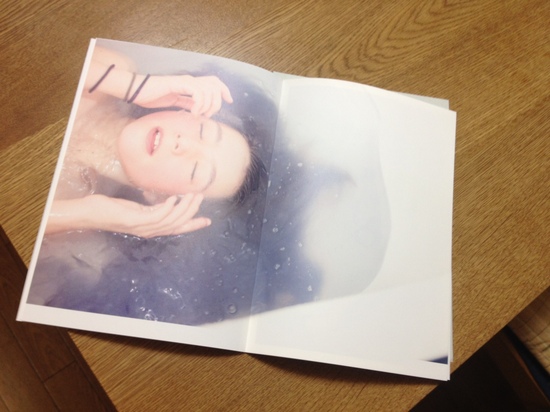
週末に、写真家の神ノ川智早さんの個展に伺った。渋谷の雰囲気のある古いビルの2階だ。
写っているのは、ウェールズの田舎の風景の中の少女。神ノ川さん、こういう世界を撮りたかったのかー。被写体がのびのびしているのが、神ノ川さんご自身がのびのびされているようで、とてもよかったです。
神ノ川さんとのご縁は、5年半前。七緒の取材を受けた時のフォトグラファーが彼女だったのです。撮影のとき、彼女がすっごく乗って撮ってくれてるのが、よく分かり、これはいい写真が撮れているんだろうなあと思っていたら、やはりすごくよかった。今回、その時のことをお話したら、とてもよく覚えていてくれて、うれしかった。お互い、撮り続け、織り続け、そして発表し続けましょうぜよ。
掲載された号の七緒は、こちらのページ中程に載せてます。写真をクリックすると記事全体をお読みいただけます。
写真は、求めてきた神ノ川さんの冊子です。神ノ川さんのサイトはこちら。展示会は終了しています。
和楽と老眼鏡

2月1日のこと、生まれてはじめて、メガネ屋さんに行った。そう、この45年の人生ではじめてのことだ。私、目がいいだけが自慢の人生を送ってきた。何の苦もなく、何でも見えた。それがこの数年、かすむし、疲れるし、辛くて辛くて、しょうがない。ショックだ、、、、、だが、仕方ない、、、

で、メガネ屋さんでひととおり、検査や説明を受け、一段落ついたとき、携帯電話が鳴った。めずらしいことだ。着信見ると、あらうれしい、仲良くして下さってる方。すごく久しぶり。メガネ技師さんに断って出る。
「本屋さんで、和楽を見たら、ヨシダさん、載ってたから思わず電話しちゃった」と。
「あーーー!そうだったーーー!!忘れてたーーー!!!」

そうなんです、私が織った帯、今日発売の「和楽 三月号」に載ったんです!実は、事前に知ってたんだけど、うっかりしてた。(載るよって知らされた時はエキサイトしましたが、、、)
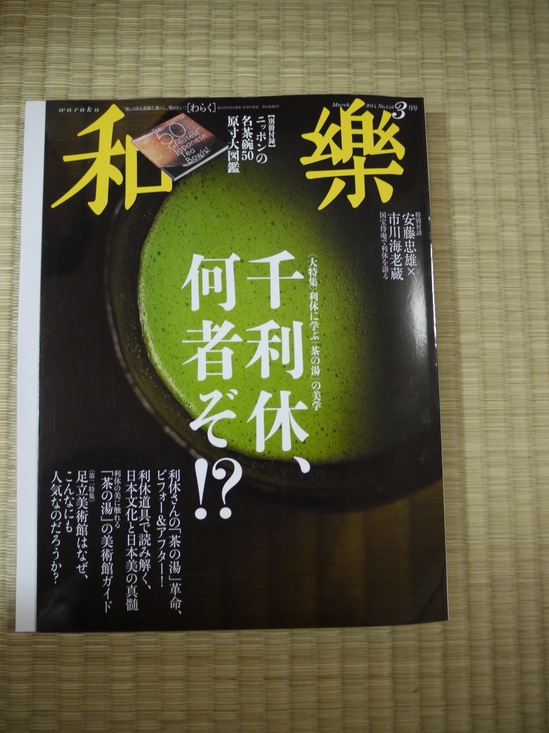
この表紙です。「森田空美の、きものでお出かけしませんか?」というページ。238ページと、241ページに載ってます。ぜひぜひ、チェックして下さいね。(白地に、黄色や緑の春色ブラッシングカラーズの八寸帯がヨシダ作です。)
ヴィトンで鳩小屋、岡田知子展、吉田喜彦展、ヒカリエの47テキスタイル

お出かけしました。時系列順にご紹介。
まず、Traces of Disappearance(消失の痕跡)という展覧会みました。4名の国籍もバラバラな作家による展示会です。ルイ・ヴィトンのピカピカのビルの7階に、鳩小屋できてました。白い鳩が、糞をぽとり。
大きなガラス面にグミみたいなキャンディーが無数に張り付いてました。ちょっとね、教会のステンドグラスみたい。不思議で不安な感じがした。写真はすべて、このキャンディーのアートです。
Traces of Disappearanceは、4月13日まで、表参道のエスパス・ルイ・ヴィトンにて。

それから、イラストレーターの岡田知子さんの個展『和服女性(にょしょう)』へ。壁一面にたくさんの作品が飾られてました。ということは、たくさんの女の人たちに、岡田さんがそれぞれ対峙したということで。それぞれの生き様みたいなものを感じました。岡田さんは、女の人の内面を描きたいんだろうなあ。
岡田知子個展『和服女性(にょしょう)』は、1月28日まで、青山ゑり華さんにて 詳細は岡田さんのブログにて。

日本橋に移動して、壷中居で開催中の、吉田喜彦さんの個展に伺いました。吉田さんは、美濃の陶芸家の大家です。私、こっそりファンなの。吉田氏が作られるもの、手元に置いて、自分の織る物と対話させたいというのが夢ですが、今回もゲットすることは出来ず。自分がそこまで出来てないんでしょう。精進します。
吉田喜彦展は、25日で終了しました。

それから、渋谷ヒカリエ8階で開催中の、47 textiles today で、47都道府県から出品された「繊維製品」を見てきました。これ、すっごく楽しかったです。みんなそれぞれすごいなあーー。日本の繊維業界のレベル、相当高いと思います。見せ方も考えてるよ。繊維ってくくりで、何でもありなのが楽しさの秘密か。
我が熊本からの出品は、「nonocima」でした。野々島学園って知的障害者の施設が生み出したブランド。私、熊本にいるとき、野々島学園にちょっとだけ関係してたのです。その時は、こんなブランドなかったよ。進んだな。
私の織りのスタート地点に、障害を持つ方の、開放感された自由な織物があります。今も大好きです。
渋谷ヒカリエでの 47 textiles today は、2月2日まで。
梅、ほころぶ

今日は大寒。が、我が家のベランダ BONSAI の小梅ちゃんが、ほころんだ。朝、洗濯物を干した時は、今にも咲きそうだったけどまだだった。午後いちに気付いた。やった!

やっと、いただいた年賀状の整理など。染織家の大先輩からいただいた賀状に、何やら見たことない四字熟語が。いただいた時から気になってたけど、やっと調べた。

「歳寒松柏」
さいかんしょうはくって読むんだって。
寒い季節になってから、はじめて松や栢(このてがしわ)が散らないで葉が残っていることが分かるように、人も苦難のときになってはじめて、その人の実力、真価がわかるものであると言う意味なんだって。逆境で苦しい状況でも、信念や志など変えないことのたとえとのこと。孔子さまのお言葉〜。
いやはや、年の初めに、このようなお言葉いただいてたのね。このお正月は暖かだったからね。大寒の日に響くお言葉。
藤山千春展、白寿のお祝い、椎葉聡子さんのグループ展

朝から着物を着た。早起きはしたのだけど、エンジン掛けるの遅くなり、バタバタで不本意な着付け。
まず目指すは、銀座もとじさん。藤山千春さんの個展のギャラリートークでした。染織をはじめて40年だそうです。長く続けたからこそ、分かったこと、気付いたこと多々ある、失敗から得たこともいっぱいあるとお話しされて、心に響いた。
私、まだまだ20年。励まされた思い。がんばろう。
藤山千春展は、銀座もとじさんにて、明日まで。
写真は次の話題の関連です。

はい、今日の主役。私の祖母です。なんと白寿のお祝いです。すごいね〜。99歳、おめでとう!もうすぐ100歳。集まった最年長は私の母、74歳。最年少はいとこの子で2歳。みんな、それぞれ、おばあちゃんとの思い出あるんだなあ。
下の写真、なんとなくずっこけの、私の親戚たち。

その後、フレスコ画家の椎葉聡子さんのグループ展に伺った。椎葉さんの美しいブルー、印象的です。
ちょうど、作品の撮影をカメラマンさんがされてて、プロの仕事、じーっと見てきた。納得いくまで、微調整するのは、どの世界でも同じなのだなあ。
グループ展「春韻」は、広尾の工房親にて、2月1日まで。
「仁平幸春の油彩画と布展」に伺った

染色家の、仁平幸春さんの個展「仁平幸春の油彩画と布展」に伺いました。会場は井の頭の、古道具 素希商店さんです。
写真は、入り口のところ。今回は、手前のお店スペースで布物の展示と、その隣のギャラリースペースで、油彩が展示されてました。ドキドキ。

この何気ない感じがたまらんです。中に入ると、布小物などが展示され、そのまた奥に、帯など呉服系の作品がありました。壁には、油絵が。仁平さんの作品の風格と、古道具の何気ない存在感とが、合うんですよ。気持ちよい空間でした。
帯のお作品、ちょうどいらしていた結城の織元の方が、つぶさに観てらっしゃって、仁平さんが丁寧に解説されていたので、ご相伴で私も拝見できました。いやー眼福、眼福。観られて得した〜。

ここが、ギャラリースペースの入り口。この厚い木の扉の向こうが異次元空間になってました。

中に入って、この扉を締めると、四角い閉ざされた空間になります。とても特別な空間です。仁平さんの作品に囲まれると、内省的な、じっと自分と対峙するような気持ちになります。作品と会話することで、凛とした気持ちになっている。
禅の境地とか知らないけど、たぶんこんな感じだと思います。
「仁平幸春の油彩画と布展」は、本日、15日まで。
展示会の詳細も載っている仁平さんのブログは、こちら。
帰ってきました!

「熊本ゆかりの染織家展」、盛況のうちに無事終了いたしました。お越しくださったお客樣方、ここを読んで応援して下さった皆様、和の國さん、企画の安達絵里子さん、本当にどうもありがとうございました。
今回4回目を迎えたこの展示会、お客樣方に応援していただけるように成長してきたようです。熊本の地に根付いてきたのかな。私の織ったものが、熊本の街を、どなたかにお召しいただいて歩くと言うのは、何にも代え難い、ありがたさです。
トークにもたくさんの方々にお越しいただけました。行きの飛行機の中で原稿書きまくったかいがありました。相変わらず、つたなくはあるんですが、伝わったかなあと、思ったり。
また、今日から心機一転、がんばろう。今年は馬車馬のように働くんです。どうか今年もよろしくお願いいたします。

熊本と言えば、こちら。空港にもいましたよ〜。
今回の帰省は同級生にもいっぱい会えてうれしかったです。ありがたいなあ。熊本の欠点は、居心地よすぎて、幸せすぎて、ちょっとゆるんじゃうことだね。
さあ、熊本ゆかりの染織家展へ!
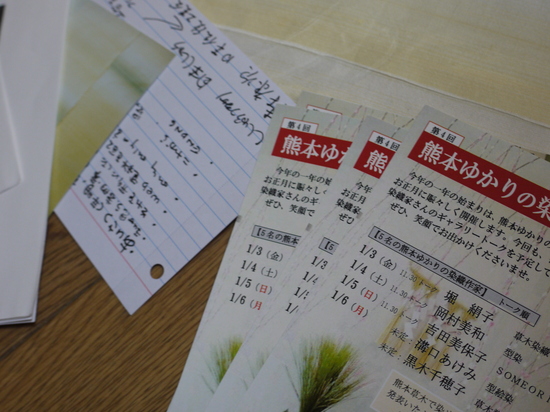
「熊本ゆかりの染織家展」、1月3日より、にぎにぎしく開催されております。
私は、本日より駆けつけます。明日、1月5日には、トークもしますの。11:30より。ぜひぜひ、お出かけくださいね。
上の写真は、旅支度。トークの資料など揃えてるところ。話べたな私ですが、ONLY ONLY(お誂え)のことなどお話します。

これは、新作タブロー。お正月に作ってました。ブラッシングカラーの色見本です。自分でも気に入った一品ができました。これも和の國さんに持って行くよ。
「熊本ゆかりの染織家展」、会期は、1月3日(金)から、1月6日(月)、時間は、11時から19時。会場は、ご存知和の國さんです。
お待ちしております!
*本日より、しばらくブログの更新おやすみします。では、行ってきまーーす!
The weaving artists related Kumamoto (town in Kyushu island japan where i was born) starts exhibition from jan 3 to 6 at Kimono shop “wanokuni” in kumamoto. i will have a talk show at jan 5.
this blog will be closed until jan 8.
あけましておめでとうございます。
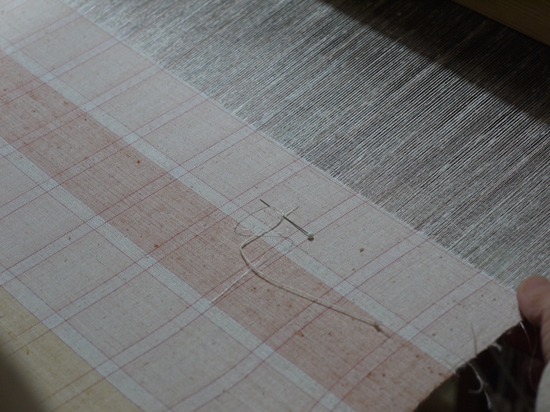
あたらしい年 はじまるよ。
太陽 あがるよ。
ちょっと、うれしいね。
ことし いいとしに しますよ。
さあ、行くよ。
*写真はめとさま。織ってます。
new year is born.
sunshine tells you hello.
i feel nice.
this year will go along with you and me.
Yes ! Sail on.
kozue さん、19歳

大学一年生で、19歳の kozueさんが、我が家に手伝いにきてくれました。写真は糸巻きをしてくれてる kozueさん。いやー、ピカピカしてらっしゃいました。若いねー。
実際には、手伝いと言うより、将来の仕事としての染織の可能性をお話する、という感じになりました。

私は、若い人に、染織を仕事として取り組むの、残念ながら、勧めません。生業として、不確実すぎます。それによっての不安、ストレス、計り知れません。それが、ずーーーっと続くんです。染織を仕事としている限り、一生不安定です。それでもやるか、すべてをひっくり返す覚悟でやるか。私も未だに不安に押しつぶされそうになって、それを蹴り上げている日々。
私としての最大のアドバイスは、まずは出来るだけ関連している会社に就職せよと言うものです。着物のメーカーとかね。呉服屋さんもいいかも。働きながら学べること、無限大にあると思う。それで精一杯働いて、いい所も悪い所もたくさん学ばせてもらえばいいと思います。それから、どうしても自分が手を動かしたいと思えば、作り手に転身もいいかもです。
作り手になるには若くはじめた方が有利とはいえ、つける師匠を見つけるのが大変難しいと思われます。後進を育てる力のある作り手は、今は皆無に近いのではないか、、、(そんな方についてる人は大変ラッキー!)
関連していない会社からの転身の方も、覚悟が決まってると言う意味でいいかもです。染織以外の世界を知ってるし、背水の陣は強いです。
kozueさん、お互いがんばろう!!!未来は、自分で明るくしなきゃね。これはいつも自分で自分に言ってること。
光

午前中、来客あり。仲良くさせてもらってるけど、この業界のプロの方。自分が着るためでなく、クライアントのために、という目線で着物を見る方。
戻られてからメールいただく。
「着物を選ぶ時の私のテーマは、光で、被写体の内にある光を探すのが、クセになってます。ヨシダさんの織りなす光は若々しい眩しいほどピュアな光。あの着物は、着ると不思議に正義に満ちそうと思いました。」
うっわーー。光ですか、ピュアですか、、、私自身はピュアじゃないけど、織ったものがもしもそうなら、本望です。
着る方を正義に満ちさせる着物かーーー。そうなのかなあ。よく分からないけど、そうだったら、うれしいな。
がんばって織り続けよう。
どうもありがとうございました。
*写真は、めとさまのお着物の緯糸。
メリークリスマス!

クリスマスですね。
ほとんど関係ない生活をしていますが、何枚かのカードを贈り、鶏肉を食べ、ワインを飲みました。野菜ももりもり食べました。年末を乗り切る起爆剤でしょうか。
どなたさまもお風邪など召されますな。
写真は、めとさまのお着物の緯糸。糊をつけ直し、真綿も扱いやすくなりました。
Dear Friends
Merry Christmas!
Hi.How have you been? Busy? I hope you and your family are very well and nice.
Do take care. See you soon.
xxx mihoko
フリンジさんに行ってきた

二子玉川に新しくできた素敵なスペース、「fringe フリンジ」さんに行ってきました。店主の福永麻子さんの「!」ピンと来たものがいっぱい。さすがでした。これからますます楽しみな空間です。
写真とらせてもらったので、ちょっとだけ〜。(ごくごく一部、それも周辺狙いで撮ってますので実際は観に行ってね)
上の写真は、私のタブローやミニ巾着などです。うふふ。

こーんなかわいい小動物さんたちもいましたよ。

鏡の中にもご注目あれ〜。

これは開店のお祝いかな。お店にすっごく似合ってた。

店主の事務空間。
フリンジさんのお披露目プレオープンは、12月27日(金)まで。25日はお休みとのこと。詳細は、フェイスブックの「私のフリンジ日記」にて。
打ち合わせで。

昨晩は、とある打ち合わせでした。それで私、すっごく勇気づけられた。
それは、その方が、すごく楽しそうに、夢中になられてたってこと。そっか、私が作るものは、こんなにも、人によろこんでいただくことができるのか。
私が真剣勝負で作ったものを、これまた真剣に受け止めてくれ、精一杯打ち返してくださる。

よかった。もっとがんばろう。
*写真は散歩の途中。朝の光の中で。
fringeさん、もうすぐ開店!

とーっても素敵なお友達がいます。こんなカッコよくてチャーミングな方に近しくしてもらって、光栄だわーっていつも思う。素敵な人や物をひきつけ媒介する、その感度が抜群の人なのだ。
その名は、福永麻子さん。もうすぐ、彼女のお店がオープンします。麻子さんの「好き」を集めた空間になるとのことよ。お店の名前は、「fringe (フリンジ)」at 二子玉川。
私の新作タブローたちは、このフリンジさんに居りますの。どうか観に行って下さいね。フリンジの空間でどう存在しているか、とても楽しみです。
そもそも、私がタブロー作るぞって思い立ったのも、ひとつには、麻子さんとの会話がきっかけです。
「美保子さんの作品見たとき、これは絵画だなって思ったの。壁に飾って観ていたいなって。」
びびびー!絵は、織りをはじめる20年も前からやってます。元々はそっちの人間です。よっし!融合させるっぞ!
フリンジさんは、12月14日がスタートです。12月中はプレオープンの形をとって、麻子さんが好きなものが、いろいろ取り揃えられてるみたいです。むふっ。
写真は、先日オープン準備で忙しくしてらっしゃる中おじゃました時パチリ。お出かけの皆さん、ビルの3階ですからね、右斜め上を見ながら歩くとすぐ分かります〜。
詳しいことは、麻子さんのフェイスブックの「私のフリンジ日記」をご覧下さい。
展示会たくさん

展示会にたっくさん行ってきました。駆け足になりますが、ご紹介させてください。
まず、山下枝梨子さんの「やましたの布きれ展 とおまわりみふゆ」。会場がすっかり山下さんの世界になってました。山下さんは、威張らない普通の布を丁寧に作る人です。布と人は一緒なんだなあと思いました。とてもよかったです。
やましたの布きれ展は、新高円寺のギャラリー工さんで、12日まで。

それから、影山秀雄さんの「影山工房展示会」。織りは深いわーっとまたまた思い知りました。影山さんお手製の道具の展示販売もあり、講座もありで、刺激受けまくって、帰ってきました。影山さんの、培ってこられたものを分けようとされる姿勢、感銘です。
影山工房展は、終了してます。

お次は、「布ノ美 村穂久美雄マフラー展」。村穂さんは、山陰の木綿の第一級のコレクターで、もうずっとずっと以前にコレクションを見せていただいたことがあるのです。10年以上は前かな?今回、ご自身で織られた布は初めて拝見したけど、布への愛が、作品からもにじみ出てました。もう90歳近いのお年らしいけど、いまだ現役の織り手でらっしゃる。生き様がアートだなあ。
村穂久美雄マフラー展は終了してます。
染織関係は以上ね。

次は、「山之口貘展」。沖縄出身の、もうずっと前に亡くなった詩人の展示会です。この展示会の案内見たとき、とっさに「行きたい」って思った。私、山之口貘の詩集、一冊だけ持ってた。ずっと以前に誰かが紹介してて、それが熱くて、惹かれて買った。それ、探したけど、見つからないんだよなー。で、この展示は見とかなきゃってソワソワさせるものがあり。
で、行ってよかったです。愛されて、アートに正直に生きた人だなあと思ったよ。生きることがアートそのもの。
「貘展」は、12月16日まで、書肆サイコロにて。

さあ、真打ち、「椎葉聡子展 -IL SENSO BLU-」展。椎葉さんはフレスコ画のアーティストです。水彩画などもあり、乾いた心(?)にしみ入りました。平面作品観に行くと、心がよろこびますな。いいものです。
椎葉さんは、お年が近いこともあり、作り続けること、発表し続けること、そんなことも学ばせてもらってます。ああ、この人やってるから私もって思う。
椎葉聡子展は、京橋のギャラリーモーツァルトにて、12月14日まで。
*写真もいろいろ。
鈴田滋人さんの個展へ

鈴田滋人さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。
鈴田氏と言えば、言わずとしれた、木版摺り更紗の人間国宝。端正で静謐なイメージで、どんなお話をなさるか想像できないわーって思っていたのだけど、、、、、ものすっごく面白かったです!!!鈴田氏の、美を創造する力に、吸い込まれました。

印象に残ったお話をひとつ。(私の脳内変換があるかもです〜)
工芸は現代美術だ。人に近い美術だ。人を思って美を作るとき、新たな美が生まれる。現代美術の要素の、コラボレーションは、人と着物はスーパーコラボだし、インスタレーションは、まさに状況や空間を作るし、インプロビゼーション(即興)の美術でもある。面倒なことをしないとダメだ。欲をコントロールするのが作業。
深くうなずきつつ傾聴。すばらしかった。
鈴田滋人展は、銀座もとじさんにて、明日まで。
写真は、ちょっと前の銀杏。絵画館前。今はきっとまっきっきでしょうな。
栗の染め、アゲイン。柿もね。

筑波のご夫妻から託されたもの。栗です。今回は鬼皮に加え、イガと枝も。草木染めの染材です。さあ、早速染料にしてしまいましょう。

枝をカットしました。細かく、細かく。色がたっぷり出ますように。なかなか固かったよー。

さあ、取れましたよ。しっかりしたいい色だ〜。立派に取れたので、二染までいただきました。
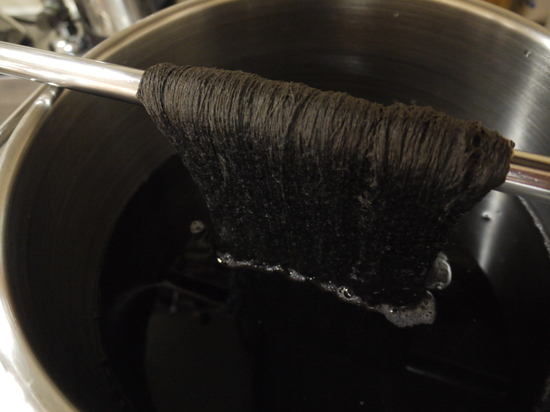
お着物を織るための染料なのですが、本格的に取りかかるのはまだ先です。取りかかる前に、コンセンサス、大事だと思っているのですが、とにかくこの段階で、一度染めてしまいます。やってみないと、提案もできないしね。
うんうん、こんな感じを望まれているのではないか。

そうだ!柿渋染めもやってみよう。ご夫妻は、栗のみならず、柿にも特別の思い入れがお有りなのだ。ふむーー。柿渋染めは、固くなるので、着物には使いづらいけど、帯ならどうだろう。
初・結城に行った!

今回、お世話になったご夫妻。

ご一家。

蚕影神社のあと、結城に連れて行って下さいました。あの結城紬の結城です。私、結城に行くのも初めてでした。結城紬に対する畏敬の念は強く強くあるのですが、なんだか腰が上がらなかった。
結城に行って、ぷらぷら歩いて、北関東の古い城下町の文化の力を感じました。品のある、人がいきいき生きてる街でした。長い長い蓄積があるのだよ、街にも、織物にも。
奥順さんがされてる「つむぎの館」を見学しました。結城紬って名前に安穏してない(安穏のところはすでに無くなったのだろうけど)。いろいろ商品みせていただいて、本来の結城紬と、半分動織機が入ってる反物があったけど、本場のすごさ目の当たり〜。撚りが掛かってない真綿ってのは、織りをやってる者からみると、夢のような糸です。むーーー。むーーー。糸はすごいよ。蚕はすごいよ。
どうすりゃいいんだ。むーーー。
Beautiful holiday

ワンダフルなことがありました。

先日、仕事の打ち合わせに、あるご夫妻の元に行きました。ら、それは、完璧なビューティフル ホリデーとなりました!!!わーい!仕事そっちのけで、すっかり遊んでいただきました。きれいな広い青空で、紅葉してて、ああ、なんてすてきなの。

ここは蚕影(こかげ)神社。お蚕さまの総本山!
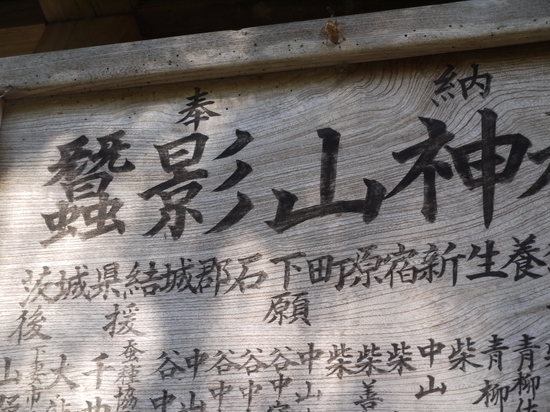
ひなびた里山の高いところに、ひっそりとたたずんでました。養蚕が盛んな頃は、桑畑が見渡せたのかな。

ここは、私はその存在を知らなかったのだけど、今回遊んでくださった方とメールのやり取りをするたびに、「ひなびた蚕の神社があって、いつかヨシダさんをお連れしたい」ってずっと言って下さってたんです。ボロボロだけど、いいんだって。で、ずっと憧れてたのだ。どんなところなんだろう???
行けて本当によかったです。
おみくじ引いたら、大吉でした!!!!
My friend and her husband took me to the shrine called Kokage Jinjya near Mt.Tukuba. The Kokage shrine is dedicated to silk worm and weaving.
Many shrines are dedicated to silk worm in Japan. But the Kokage shrine is the head of them.
森万里子展へ行った

ちょいと抜け出す。表参道とその界隈へ。

表参道で、森万里子展を見た。
正直言うと、私、あまり森万里子、ピンとこないんだ。タイプでないアーティスト。そのくせ、けっこう見てるのよね。10年くらい前の、東京現代美術館でも見たし、これもずいぶん前だけど、豊島(てしま)で沼の中ににょきっとしてるのも見たよ。
で毎度、うーん、アジャストできんわぁ、と思いつつ、ガン見。

タイプでなくても、人を吸い込むのだよ。それに、うなづかせる。目が離せなくなる。たいしたもんだと思う。
森万里子展は、表参道のエスパス・ルイ・ヴィトンにて、来年の1月5日まで。
写真は森作品です。撮影可なのよね、ここ。
友達がきた

先々日、先日と二日続けて、友達がきた。付き合いべたな気がある私としては珍しいことだ。
二人とも、ちょっと年上のすてきなお姉さん。それぞれご多忙の中を縫って、お越しくださった。

一日目にきてくれた人は、この2年くらいのうちにとても仲良くなった方。新しい視点から、私の制作に大きなサジェスチョンをくれた。よし、動くぞ!
二日目にきてくれた人は、もう15年くらいの付き合いか?板橋区時代のご近所さん。オーストラリアの方。3年ぶりくらいだよ。変わらないなあ。アートな人だ。10周年の挨拶状を出したのに応える形でお越しくださったのだけど、それは5月の話。自分のペースで祝ってくれる。うれしかった。
写真はお二人にいただいたもの。場所を変えて撮ってみた。Thank you!
フォトショップ講座、その後
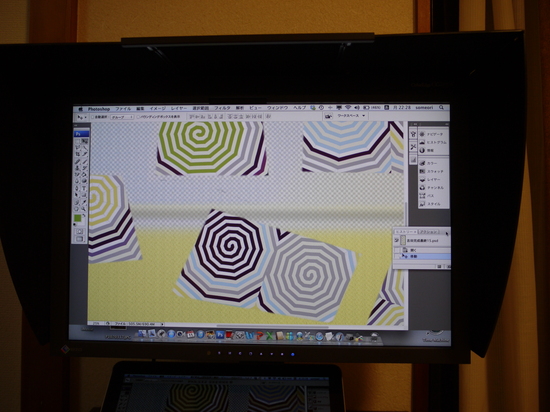
フォトショップ講座、すすみました。
やるだけやったよ、もうフラフラ。パソコン仕事の疲れは独特ですね。脳みその芯のところが疲弊し切った感じです。
あーあ、私はやっぱりガテン系かな。手でつくる方が向いてるね。脳で作り上げるのではなく、手を動かし、体を動かし、全身をふりしぼって作る方が向いてる感じです。
とは言え、今回の講座はデジタルで羽裏を作ることが目的ですから、そこに向かって走りました。自家用とはいえ、実際に使えるものを作りたかった。
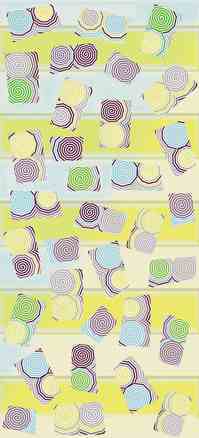
最終完成形はこんな感じ。縮尺不明ですよね。幅は114cmあります。反物の幅の3倍です。長さは250cm。
インスピレーションは現代アートからなのだけど、いじっていたら、現代着物風になりました。私っぽくもなったな。あはは。
制作がすすんで行くうちに、銘仙とか、街着の着物に、カルタや花札やトランプの模様があったなあと思い出した。そんなつもりは毛頭なかったけど、四角が飛んでるとそうなるのかもね。
これって、着物の柄って出尽くしているってことか?それを今の空気に合うようにリニューアルさせているのか?織りも同じか??
物作りなんてそんなものかもなあと思った次第。
フォトショップの講座
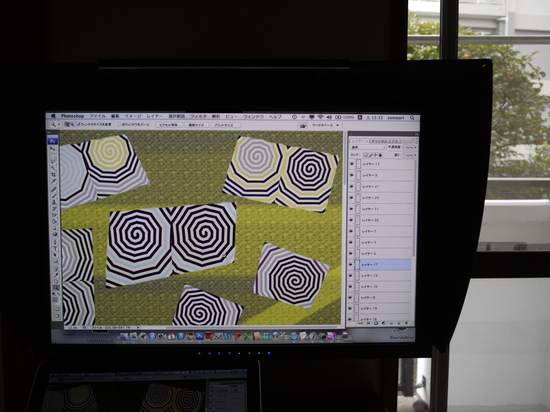
この秋は、フォトショップのクラスを受講しています。講座名は「羽織の裏地ーデジタルの布地作り」。
デジタルで布を作るというのにひかれました。いつも、「これでもかっ!」ってくらいの手作業で布作りをしていますので。
デジタルでものを作ること、手で作ること、いったい何が違うのか?
で、発見したことは、手で作った方が(「体動かした方が」とも言い換えられますが、)すっきりします。ある種、諦観もあります。「やるだけやった、やり切った」と言える。
デジタルだと、際限なく、いくらでもやれるんだなあ〜。やっぱ、やればやるだけ面白くもなるし。フラストレーションはたまりますな。もっともっとを望んでるのに、スキルがついて行かない。「よっしゃ!来たぜ」って感覚はあります。これは、手でやってても一緒ですね。
手で布を作ることを仕事としていますが、何より大事は、手を使うってことじゃなくて、いいものを作ること。その方法が自分の手なんだよね、今のとこ。まあ、たぶん、これからも。ただ、固定化せず、外界から取り入れられるもの、どんどん入れて、ボーダーレスな手仕事を目指したいのだよなあ。
写真は、作業中の私の羽裏。講座内の時間ではとても間に合わないので、おうちでせっせと進めてます。まだまだー!
イメージソースに使わせてもらったのは、アーティストのルイーズ・ブルジョアのタブローです。ルイーズ・ブルジョアって、彫刻家とカテゴライズされるし、有名なのは、六本木ヒルズの巨大な蜘蛛のオブジェだと思うけど、平面もいいのだ。大尊敬。
一衣舎さん、楽艸さんの展示会

一衣舎さんと、お草履の楽艸さんの展示会に、浅草に行ってきました。一衣舎さんには、私の作品も出品させていただいてます。
雨模様、気温も低くて、ちょっと外に出るのを躊躇するような日でしたが、いい展示会でした。面白いものたっぷりありましたよ。ウールの帯とか!ハロウィンのバッグとか!普通じゃ飽き足りない方には、恰好の展示会だと思います。面白くて独自路線で、丈夫で着やすいお着物など探している方、ぜひお運び下さい。
一衣舎の木村さんは、布に対する愛にあふれている方なので、着物全般の相談事などもされてみるのも、いいかもです。私も、いつか欲しいと思ってる羽織のことなどお聞きしましたら、抜群の反物、教えていただきました。ああ、そうか、この布だと、こういうシルエットになるのねえ。想像してウットリです。いつの日にかゲットできるよう、がんばりましょう。
「一衣舎・楽艸 秋の二人展」は、明日まで、浅草のギャラリー丸美京屋にて。ぜひ!
写真は、関係ないですよ。木の肌です。こんな織物、織りたい。
田園都市線から大井町線

二子玉川で開催中の、「濱野太郎展」を拝見してきました。濱野さん独自のアートで世界ができてて本当にすごいです。
濱野さんの作品を観ていたら、Real artists ship. って言葉を思い出した。スティーブ・ジョブズの言葉とのことで、茂木健一郎さんが紹介してたけど、本当のアーティストは出荷するもんなんだと。ただ作るだけじゃなくて、外に出して、作品を手放してこそ、アートだと。それが新たな世界を切り拓くと。
濱野さんは作品をどんどん作って、どんどん出荷して、大きく外で羽ばたいててるなあと思いました。
「濱野太郎展」は、10月20日まで。二子玉の kohoro にて。

その後、デパ地下でお買い物。二子玉、さすがオシャレです。都会〜。
スパークリングワインと、食べるものいろいろと、ケーキを買って、いざ、祖母のうちへ。おばあちゃん、数えで白寿!すごいねーー。ワインは、岐阜から出てきた叔母と私が飲むんだけどね。
祖母や叔母ふたりといろいろ話す。死んでしまった人たちのことなど。親戚付き合いと言うのは、死者の思い出話をする場かも。いいと思う。彼らが生きた証だもんね。せっせと話そう。

写真は祖母のうちの猫。まっちゃん。17歳。こちらも長寿。おばあちゃんもまっちゃんも、ひところより、ぐっと痩せました。一緒に東京オリンピック見ようねって言うのが、合い言葉。オリンピックが決まったこと、良いのか良くないのか分からないけど、「オリンピック一緒に見ようね」と言い合えるのはいいなと思った。
甚五右ヱ門芋がきた!

半年も前に注文して、心待ちにしていた、芋がきた。その名も、甚五右ヱ門芋。山形の真室川の、森の家さんが育ててる特別なお芋です。うーん、ぷりぷり。うれしい。

さあ、作って食べましょう。早速、同封されてたレシピ「佐藤家に伝わるおばぁの芋煮」どおりにチャレンジ。いっただきまーす♡

実は、森の家の佐藤さんご夫婦に、気仙沼さんま寄席でお会いできたのです。佐藤さんご夫妻は新婚さん。すてきなカップルでした。これからますます森の家は、わいわい楽しく盛り上がるなあ。
明日は、甚五右ヱ門芋の収穫祭り「芋祭」なんです。秋の実りっていいなあ。行きたいよ〜。
These are the special yummy & yummy Taros potatos [Jingoemon imo], from Mamurogawa, Yamagata located at east-north japan.
Tanto Tanto Mangiare !
小熊素子さんを訪ねた

とても久しぶりに、染織家の大先輩の、小熊素子さんを訪ねました。石神井公園を突っ切って歩いていくのが、気持ちよかった。久しぶりだけど、よく知ってる道。私、神奈川に引っ越す前は、よくおじゃまさせてもらって、染織の仕事のことや、いろんなこと、教えてもらったんだ。

久しぶりの小熊さんは、染織も、生き方も、前にも増して、孤高の感じ。自分の道を歩かれてた。機にかかってた着尺は、織りづらそうな真綿の経糸だったけど、風格あって、すてきだった。これが織りたいってことなんだろう。織りやすいとか、流行りとか、売れやすいとか、関係ないのだ。

それでいてこの方は、甘ったらしくない優しさがあるのだ。それは、作品にもにじみ出てるのだけど。

小熊さんの仕事場にお邪魔すると、私はなぜかリラックスして、長居しすぎてしまう。いろいろ話せてよかったです。仕事やってく上で、同業者の先輩の存在は、何よりありがたい。
ありがとう!小熊さん!!
写真は石神井公園。
気仙沼のこと、もう一度

すっかり日常に戻っているのだけど、(今日は、胃がん検診でバリウム飲んできたし)気仙沼のこと、もう一度だけ。

私、気仙沼は二回目で、2012年の3月にも行ったんだ。この時も志の輔師匠のさんま寄席で。
で、一年半後の今回、何が変わったか。私にとっての1番の違いは、じゃーん、「レンタサイクルできた」です!

前回も今回も、現地で特に予定を立てていたわけでなし、行き当たりバッタリな旅だった私。
前回は、レンタサイクルなんてなかったと思う。確証はないけど。道を歩くのが精一杯だったから。アスファルトがあちこち波打ったまま放置されてた。歩きやすいスニーカーを履いてたけど油断すると転んで大けがしそうで、緊張して歩いた。それで気仙沼市内散策を断念して、目の前の大島にフェリーで渡って山歩きした。のどかだったけど、森の木の下の方が焦げていて、あの日の火災が、まざまざだった。

今回、ホテルについてふと見ると、「レンタサイクル1日500円」貼り紙。それも電動アシスト付き。こりゃ借りるでしょう。
アスファルト道路は、まだまだとは言え、自転車こぐのくらいは大丈夫までに整備が進んでた。ただ粉じんは舞ってます。リュックのポケットさぐったら、去年の冬のマスクが、買ったままの状態で発掘され。ビバ!ずぼらな私!
レンタサイクルで、マスクと帽子と日焼け止めで、気仙沼を走りまわった。川辺がのどか。ああ、この川を津波がさかのぼったのか。
更地になっている所は津波に持って行かれた所。そこに立ち始めてる急ごしらえの建物。

学校の運動場の隅とか、児童公園とかに、小さなプレハブが連なって立っていた。
なんだこれ?用具倉庫?って思った瞬間、あ、これ仮設住宅だ!
ガーンときました。失礼なこと、思ってしまいました。ネットなんかで、機能的でデザインされてる現代的な仮設住宅の紹介を見てたから。現実は違いました。知らないことを恥じ入りました。

ま、こんなことを感じてたから、その後の、市場で朝飯や着物ワークショップやさんま寄席が、いっそうジーンとくるものであったわけです。よい集まりでした。参加できたことを誇りに思います。
写真は旅の風景。
一番上と二番目は、解体中の、第18共徳丸です。ほら、津波で800m流されたってよくニュースになってた船です。一番下の写真は、市場で出船送りをさせてもらった時のです。楽しかった!左は着物ワークショップでお友達になった方。いいお出会いでした。
気仙沼

宮城県の気仙沼に、立川志の輔師匠のさんま寄席に行ってきました。ほぼ日さんのイベントです。いろいろ盛りだくさんでお腹いっぱい。今はもう帰ってきちゃってるんですが、、、心はまだ気仙沼にあるよ。ぼーっとしてる。

志の輔師匠の落語もそれはそれは熱気を帯びたものでした。中入り後の一席は、「大河への道」っていう伊能忠敬を大河ドラマの主人公しようと画策する話でした。迫真でした。
伊能忠敬が全国の海岸線を歩いて測量していったというとこで、ああ、ここも歩いたんだって思った。たぶん会場の観客みんなが、チーム伊能一行が、三陸海岸を歩き、測量し、ときにその美しさをため息したって様子など、思い描いたと思います。
三陸は美しいぞ!日本は美しいぞ!

今回、旅先で着物で落語が実現しました。会場を賑やかにできますものね。うふふでした。
ほぼ日さんで着付けのワークショップがありましたので、申し込んだんです。自分で着るのと全く違うってのが何とも情けないのですが、、、、、ちょこっと補正してもらいました。タオル二枚、ウェストに巻くのです。カッコよく着たい、自分の着姿をつくりたいと思えば、それなりに意識と努力は必要ですな。私、まだまだです。
なななんと、ほぼ日さんのテキスト中継のページに載ったのですよ。ありゃー。こっぱずかしいけど、うれしいです。こちらのページの一番下に載ってるよ〜。
写真は旅の空。
ホリデイ

うふふ、ホリデーです。気仙沼に来ています。
命の洗濯しております。
Hey! I am escaping from Kanagawa and enjoying my holiday!
I am in Kesennuma where is North-East Japan. Here was get horrible earthquake and tsunami at March 11th 2011.
I have been here one and a half years ago also. And now I am came back.
いい日、いい糸

今日は穏やかないい日でした。お客様もみえて、お話できて楽しかったです。話していると、思わずニッコリ。笑顔を分けてくれる人でした。

今日の仕事場。糸の準備が進んでいます。真綿の糸です。ふっくら。

こっちはきびそ糸。軽く撚りがかかっています。いい感じです。
ムクロジで洗濯、中秋

このところの晴天で、予定を変更してでも、大掃除、大洗濯って方も多いのではないでしょうか?かく言う私も。
大掃除もして、大洗濯も。もう一度着るかもって思ってた、夏の着物をザブザブ洗った。昼間は暑くても、朝晩、こう冷えちゃうと、夏物はもうおしまいだ。
写真はムクロジ。ソープナッツとも言います。今日はこれで洗おう。

ムクロジを洗濯ネットに入れて、風呂桶に投入。その上から、ガーーッとぬるま湯を入れると泡がムクムクです。まさにバブルバス。そこに夏着物を投入し、ゆるゆる泳がせるってわけです。
晴れの日は、乾きもいいし、まさに洗濯日和。

私も観ました。名月や。
台風が去って間もないからか、清々しさひとしお。
アメリカン・ポップアート、カラーハンティング、タレル

台風の前日、派手なポンチョをかぶり、完全防備で出かけた。行き先は、六本木。
国立新美術館で、アメリカン・ポップアート展を観た。
ラウシェンバーグの本物なんて、すごく久しぶりで、うわーーーやっぱ、私、ラウシェンバーグ、大好きだって思った。ジャスパー・ジョーンズも好き。
で、この展覧会のコンセプト、アメリカン・ポップアートは、1960年代のアメリカ。私、1968年生まれ。生まれた頃の、太平洋の向こう側のビンビンのアート。
私が、現代美術かぶれだった(今もだけど)のは、1980後半からだから、その時すでに主流でないのだ。今ではすでに古典か、、、、うーん、ノスタルジック、、、ま、それでも好きです。ひきつけられる。好きなものは、好きなんです。
アメリカン・ポップ・アート展は、10月21日まで、国立新美術館にて。
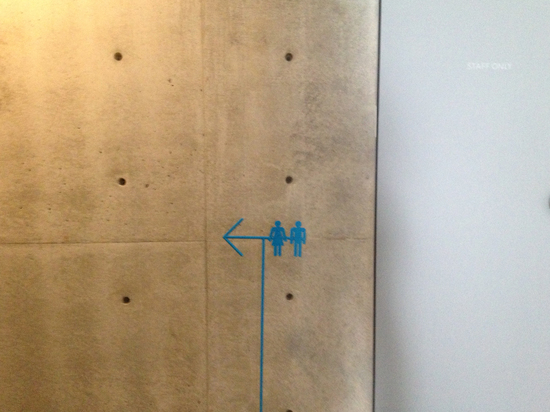
それから、ミッドタウンの 21_21デザインサイトに、カラーハンティング展に行った。これ、ものすっごくよかったです。すかーっとした。
色をきっかけに広がる、広がる。こういうコンセプトありきの展覧会、これから主流になるかもなあ。企業や学校やたくさんの人を巻き込んで作りあげる。
アートとはなんぞやってこと、考える。そこらに無限に広がるもの(例えば「色」)、どう切り取るかなのか?ディレクションがアートなのか?よくわからん。
カラーハンティング展は、10月6日まで、東京ミッドタウンの 21_21 DESIGN SIGHT にて。
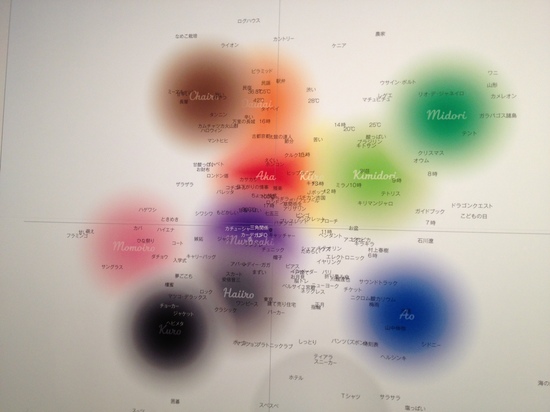
帰りは晴れてて拍子抜け。お家に帰って、評判を聞きつけてた、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催中のジェームズ・タレル展の動画をネットで観た。英語、分かんないけど。
ドギモ抜かされるほど、よかった。タレルにハート、持ってかれた。まいった。動画みてるだけで敬虔な気持ちになる。これがアートの本質か?ニューヨーク、行きたいなあ。
ジェームズ・タレル展は、グッゲンハイム美術館にて、9月25日まで。くだんの動画はこのページ。大おすすめ。
写真は3枚とも、21_21デザインサイトにて。
コマラさんと、ロニーさん

先日のことだけど、ビンハウス展の初日に、沼袋のシルクラブさんに行ってきた。この日だけ、インドネシアから、ジョセフィーヌ・ビン・コマラさんが来日されるとご連絡いただいたから。
今回の展示会、コマラさんのご主人の、ロニー・シスワンディさんの追悼と言うことで、コマラさんにひとことお悔やみ伝えたかった。
10年以上ぶりのコマラさん、深いまなざしは変わらないね。I am so sorry. って伝えられてよかった。
ロニーのこと、いろいろ思い出した。
私は勤めていた会社の関係で、けっこうご縁があったんだ。ここにちょっと書いてる。ロニーが来日したとき、染料が欲しいと言うから、藍熊染料さんにお連れしたな。私がちょっと値切ったら感心された。
シルクラブさんには、いろんな方が見えてて、私のもとのボスの今井さんご一家とも久しぶりにお会いできた。
今井夫人の紅子さんと話した。
「ロニーがゆうどに来た時、紅子さん、着物でいらしたでしょう。ロニーがすごくうれしそうな顔したのよく覚えてます。」
「そうそう、今着てるこれ、あのときのこと覚えてて、ロニーが着物の上に着るようにって作ってくれたの」
紅子さんは、きれいな紫の、道行きのようにも使える、軽いコートを羽織ってらした。
私は、あの時、人にウェルカムの気持ちや敬意を表すのに、丁寧に着物を着るってことを覚えた。
元の職場のゆうどに対する感謝も伝えられてよかったな。私が辞めたときは、まだ仕事も多かったから、せっかく育てた社員が抜けたのは、一年も前に申し出たにせよ、今思えば申し訳なかった。
今回のこの場も、ロニーが作ってくれたね。
コマラさんが、地下の会場に、ロニーの写真を持ってくるように言ったのと、今井さんが、ロニーとの思い出のデカンショ節をうなったのもよかった。
ビンハウス展は、シルクラブにて、9月20日(金)まで。
写真は、うちの近所。夜の散歩より。
久保原由佳理展とスピニングパーティー

久保原由佳理さんの個展のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。ずっと拝見したいなあと思っていた作家さんです。
すばらしいお仕事でした。すごく真っ直ぐに染織に向き合われてる様子がありありと伝わってきて、なんだか泣きそうになりました。
久保原由佳理展は、銀座もとじさんにて、明日までです。

その後、銀座4丁目のバス停からバスに乗って、晴海埠頭に向かいました。スピニングパーティーです。もう何年も前に2回ほど行ったきりで、チョー久しぶりでした。(6,7年前か?)
私は糸を探しに行くわけですが、今回は獲物をゲットできた感があります。今までは、自分がどんな糸を求めているのか、ピントを合わせ切れてなかったなあ。無駄に歩き回り、無駄な買い物をし、それが今も糸棚の奥底にあったり。やっと、自分の求めているものが分かり、そのために何をどう準備すべきか分かりはじめたってことか。←遅い!
スピニングパーティーのような、染織に関わる人が集う場所に行くと、会いたいなあと思っていた人に会えたりするのがいいね。決して人付き合いが多い方ではありませんが、いくつかのうれしい再会もあり。
新しくお会いできてうれしかったのが、福岡で翔工房を主宰されている田篭みつえさん。思ってたとおり、とってもすてきな方でした。染織を愛されてるなあ〜〜。
写真はうちの近所。夜の散歩。
異常気象、とうとう。

この夏は自然が厳しく、しんどかった。めちゃくちゃ暑かった。私のところは大丈夫だったけど、渇水したり、洪水だったり、竜巻がきたり。地震もありましたね。実害なくてももうヘトヘト。ラジオのニュース聞いてるだけでソワソワの日々でした。
あなた様におかれましては、いかが過ごされましたでしょうか?大丈夫でしたか?
私と言えば、夏の間もわりと平穏に暮らしていました。
閉じこもってやる仕事なので、一歩も出なくて、せっせっせっせとやるのみ。バテそうになると、エアコンつけたり強めたり。自然にリンクしていないって詰まらなくもあるけど、この夏だけは助かった。
が、昨日とうとう我が家も異常事態が!
お昼前、奥の和室で、検反してますと、いきなり天井からボタボタッと水!
一瞬、頭が真っ白。何が起きたか分からない。とにかく身を挺して布を守る。助かった、布までには1mほど距離があった。大丈夫、ハネもきてない。布の無事を確保してから、バケツと洗面器を持ってきて、水を受ける。
ひぃー!まるでドリフだ。これはドリフだ。
おさまってから、大家さんに電話したら、すぐ来て下さって、上の方がミスト扇風機のタンクの水をこぼされたと判明(うちは集合住宅の一階)。ああ。
しかし、この一件で、予期せぬ異常気象に遭遇したときの、一瞬の火事場の馬鹿力とその後の茫然自失になるさまが、よく分かった。この程度のことで実害なしでも、心のゼイゼイ、バクバクがしばらくおさまらなかったもんね。
この夏、さまざまな被害にあわれた方、少しは楽になられたでしょうか?まだまだ大変なさなかにおられるかも。大変でしたね。心からお見舞い申し上げます。
写真はうちの近所の駐輪場から夕日を見上げる。
アンドレアス・グルスキー展に行った。

先日、都心に出たついでに、気になっていた「アンドレアス・グルスキー展」を観た。もう見逃しちゃうかと思っていたのでラッキーだった。
アンドレアス・グルスキーのことは、まったく知らなかった。ドイツの写真家だということだが、ネットのプレビューなどで観る限り、写真ぽくなく、「?」「よく分からん」と言うのが本音だったが、だからこそ観たかった。
で、度肝を抜かされました。ドびっくり。
でかい!世界観も何もかも極度に作り込まれてる!極限に限りなく近い完成度!
ドびっくりというのが、アートなのか?
そうだとは言い切りたくないのだけど、ドびっくりしちゃうのよね。(あー、そうなのか)???
すごかったです。観てよかった。
「アンドレアス・グルスキー展」は、六本木の国立新美術館にて、9月16日まで。
写真はうちの近くで空を見上げる。iPhoneでパチり。こんなビンビンの写真作品を観た記事の写真としては、合いませんなあ。
青田五良の掛け軸、見参かなう
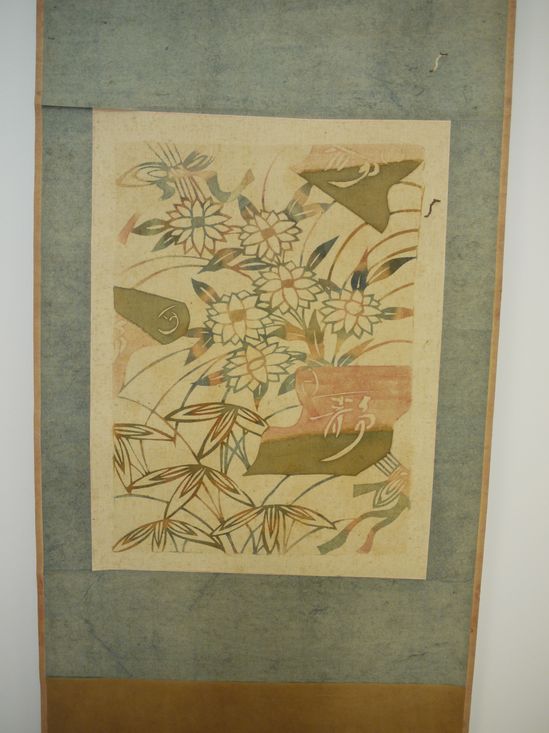
この掛け軸、青田五良の作品です。いいでしょ、いいでしょ。
とっても不思議なご縁に導かれて、拝見して参りました。伸びやかで繊細な、青田の息吹に触れたように思いました。掛け軸の表装に使っている紙も青田の染めだそうです。昭和のごく初期の、熱い文化を感じました。
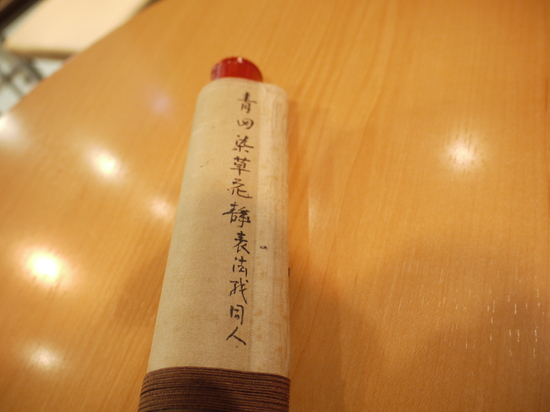
くるくる巻くとこんな感じ。宝物ですね。

この宝物を持っていらっしゃるのが左のお方。青田五良でネット検索して、私を探し出して下さったのです。銀座もとじさん経由で、電話でお話して、とことんお優しい方だなあと思いました。青田がつなげてくれたご縁だなあ。
本当にどうもありがとうございました。
さえりさん、きたる。
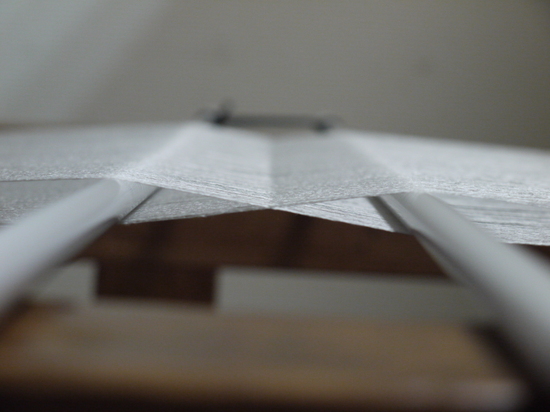
旧い友達のさえりさんが、我が家を訪ねてくれた。遠くから、暑い中。
さえりさんと私は、かれこれ、25年の付き合いではなかろうか?若気の至りで大学を中退して、エジンバラの語学学校で会ったのが、出会いだから。
初めて会ったときから、インパクトの強い人だ。自然と医療とアートを融合する人なんだなあ。さえりさんが来てくれるんならと、「bass」を買っておいたよ。イギリスのビール。
しゃべってて、ここんとこの、私の「10周年&サイトオープン」関連の話となり、
「なんで、ロゴをレムニスケートにしたん?」と聞かれ、「?」となる。えっと、ロゴはね、織りで一番大事な綾を表してるんよ。無限大のお印でもあるし。
ところで、レムニスケートって何?はじめて聞いた。
で、「レムニスケート」について教えてもらった。
レムニスケートって、海が凪いでいるときから、だんだん波が出てきて、その波がどんどん大きくなり、連なって打ち寄せる、その連続する波動のことみたい。(ちと違うかも)
内と外が、連なる。過去と未来が連なる。宇宙からも、自然からも。
うーむ。染織吉田のロゴ、よかったみたい。
織りって、すごく神秘なのだ。ただ、私は、そこをあまり追求しないようにしてる。普通に毎日機織りしてて、いつか体得したいと思ってる。
写真は、綾。織りの要。今織ってる、アトリエ森繍の佐藤さんのお着物の。
熊本ゆかりの染織家展、打ち合わせでした
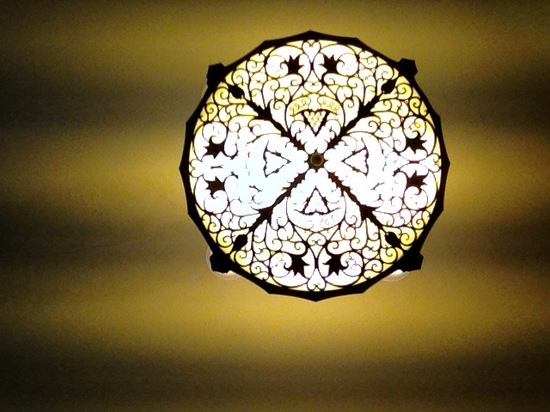
本日は、「熊本ゆかりの染織家展」の企画者で着物ライターの、安達絵里子さんと打ち合わせ(という名のデート)でした♡。(って唯一の夏休みです)(打ち合わせだけど)
場所は、東京国立博物館。法隆寺館で待ち合わせだったのだけど、その前に観ちゃおうと早めに出かけた、「和様の書」展でばったりお会いしました。
(写真は本館の天井)

「和様の書」、書道はさっぱりの私ですが、1000年前の書の美しいこと!力強いこと!
書は教養だったのだろうか?
いや、、教養とか、文化とか、芸術とか、、そんな安易なカテゴリーを超えた、生きることそのものみたいな力を感じました。
(写真は本館の内線電話。展示物じゃないと思うよ)

東博に7時間くらい居ました。そのうち3時間は、打ち合わせだったにせよ。東博いいねえ、満喫しました。
その後、不忍池のほとりを歩いてアメ横へ。伊勢音って鰹節屋さんに。ここの鰹節削りを使ってて、かんな研ぎのサービスしてくれるのです。待ってる間に一本買って、地下鉄の駅に歩いてたら、雨が降り出した。
ありがとう、アカオニさん

この染織吉田のウェブサイト、作ってくださったのは、山形のデザイン会社の、アカオニさんです! Bravo!
いやはや、ほんとーーーにお世話になりました。おかげさまで、夢に描いた通りのサイトができました。
たぶん、ものすごく七面倒なクライアントであったと思います。(私、前世は校正者だったんではないかと言うくらいうるさいんです。半角開けてとか、句点の打ち方変えてとか、、、自分の原稿がなってなかったのにも関わらず)
うざい私によくお付き合いくださり、よくご辛抱いただきました。的確なアドバイスもいただきました。
私も注文制作で物作りをやっておりますので、お客様のご希望をかなえるってことは、一緒です。参考になること多々でした。異業種に学べです。
心から、本当にどうもありがとうございました。
山形とご縁ができたのもうれしいです。
(どうして山形かと申しますと、私の大好きなサイトがありまして、そちらに「大変申し訳ありませんが、お宅様のサイトの作ったデザイナーの方を紹介していただけないでしょうか?」とメールしましたら、こころよく教えてくださったのですが、それが何と、山形の会社だったのです。えっ、関東じゃないの、、、一瞬くらっときました)
お話が始まったのが、今年の2月ですから、半年ですねえ。あっと言う間だったし、長かったなあとも思います。
サイトが完全に完成しました。さあ、バリバリがんばろう!
お世話になった、アカオニデザインさんのサイトはこちら。
作ってくれたのは小板橋基希さん、写真は志鎌康平さん、お会いはできなかったけど、後藤ノブさんと阿部衣利子さんが、支えてくださってたの知ってます。どうもありがとうございました。
大好きなサイトというのは、こちら、森の家さん。
今日の写真は志鎌康平さん撮影。撮影は4月3日でしたねえ、、、今となっては楽しい思い出。
梶の葉

郵便受けに、大きな封筒。差出人は、ライターの雨宮みずほさん。2011年に出された「東京きもの案内」が有名だ。
雨宮さんが私に大きな封筒?それも速達。何だろう?
開けてビックリ!湿らせたキッチンペーパーとクリアファイルの間から、大きな葉っぱ!!!
添えられていたお手紙拝読。
この葉っぱは、梶の葉っぱで、昔、短冊の代わりに、七夕の日、梶の葉に願い事を書いて笹に吊るしたそう。もともとは、布や紙に使われていた原料でもあるそう。
へーーーーー!知らなかったよ!
すごいなあ、雨宮さん。さすがの知識と、それを分けて下さる優しさ。普段から、ここにこの木が生えてるとか、気にしてらっしゃるんだろうなあ。きれいな葉っぱを選んで、枯れないように水で湿らせて。包みながら、私の機織り姿とか思って下さったのかなあ。うれしいです。ありがとうございます。
もうすぐ、旧暦の七夕ね(今年は8月13日だそうですぜ)。心に涼風。
雨宮みずほさんのブログ、トップページはこちら。季節の風、感じます。すてきなブログ。
梶の葉のことを書かれたページは、こちら。
夏の晩

暑かった日の晩、窓を開け放って、扇風機を回す。細く開けた玄関から蚊取り線香の煙。氷をいっぱい入れた芋焼酎のロックを飲みながら、焼いた海苔に梅干しを崩しつつ。納豆を巻いたり。古いジャズのCD。
ああ、夏の晩。
夏だぜ

夏だからといって、特に予定もなく、普段と変わらず、どうってことない日々を送っている私ですが、夏は夏ですね。ちょっとした散歩でヘトヘトになったりするとき感じます。夏だなあ。
いただいた暑中見舞いに「夏を乗り切りましょう」って書いてあって、そうだ、そうだ、どうにか知恵と工夫で体力温存して乗り切るぞって思う。この感覚、やっと分かった。昔は、「乗り切るって何?ほっとけば過ぎてくじゃん」って思ってた。
違うのよ、過去の私よ。夏は乗り切るものなのよ。
写真はうちの近所。夏っぽいでしょ。
空にドラゴン

所用あって大荷物を持って、銀座まで。(はじめは両手に風呂敷の予定だったが、突然の雨を恐れて、ひとつはリュックで背負うことにした)
暑くて荷物が多いのは、なかなか大変。でも一瞬、バックパックで遠出する夏休みの感覚に似てるなあと思ったり。ああ、目的地が空港だったら、、、、
用事がぶじ終わって、銀座熊本館(物産館ね)に足を伸ばし、くまモングッズを買う。遠くに住む大切な友達にプレゼント。お誕生日おめでとう。
ほら、吉兆。空にドラゴン。
お祝いのメッセージ
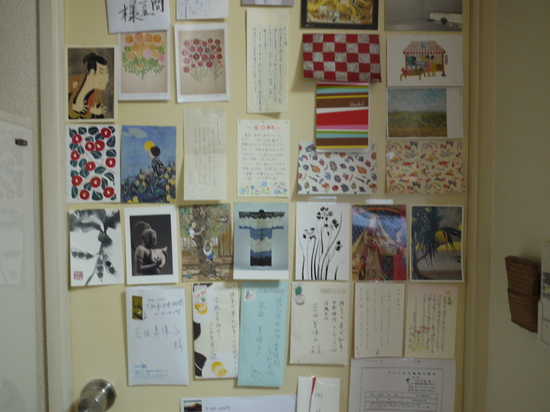
写真は、我が仕事場のドアです。10周年のお祝いで、いただいたお手紙やお葉書やファックスを貼って、毎日眺めてます。最高にありがたいです。これらは永久保存。メールいただいのも、プリントアウトしましたので、それらも永久保存です。
10周年は、同じ仕事をしていれば誰にでも訪れることで、特に騒ぐことでもないと思いつつも、盛大に騒いだこの2ヶ月間。(いえ、その準備から数えると4ヶ月間)(いつもと違う多忙さにボロボロに疲れたこともありました)
いただいた一通一通のお手紙読んでいると、じーんとします。
開業当初にお世話になった税理士の先生もお手紙くださったのだよ!覚えていて下さったとは。大感激!
もちろん、開業当初はもちろん、今も税理士さんなどお願いできる身分ではありませんが、10年前、板橋税務署のサービスなのか、新規事業者は記帳指導がお願いできたのだ。
で、おそれおおくも、税理士の先生が、我が家(オンボロアパート)まで来て下さって、現金出納帳とか、事業主貸とか借りとか、記帳の仕方を一から手を取るように教えてくださったのだった。
二ヶ月に一回だったかなあ、2年間来て下さった。このお方のおかげで、私は今でも、曲がりなりにも、複式簿記の仕組みが分かり、青色申告できるのだ。
このときは、開業資金も区の融資を利用して借金してた。300万だったかな?よく返せたな〜。
あーあ、いろいろ思い出しますなあ。いろんな人に助けてもらって、やってきた。それを思うと泣けてくる。
デート目撃

今朝、うちを出て歩きはじめたら、遠く前方からこちらに歩いてくる老夫婦あり。
奥様が日傘をさし、手をつないであいあい傘。いいなあと思うも、すれ違う前に私は右折。
用事をすませ、帰路、先ほどのカップルとすれ違う。どうやら、目的地は私と同じだな。まだあと300メートルくらいあるよ。道中には休めるところもないし、大変ね。
このご夫婦、思ったより高齢だった。ご主人は90近いと推察。奥様も80は下らないのでは。
年を取ると投票するのも大変なんだたあ。でもすごいや。
それに、二人で、手を取り合ってのデートだったよ。うらやましい。
写真はうちの近所。すてきなおたく。投票所とは反対方向。
— iPhoneから送信
福本潮子展へ、下地康子展へ

福本潮子さんの展示会のギャラリートークに、銀座もとじさんに伺いました。福本さんは、言わずと知れた、藍染めの大家です。お話の中で、「基本は几帳面です。計算できるところまではきちんとやります。それ以上のことは自然に任せます」とおっしゃってたのが心に残る。あの美しく冴えた白の秘密は、緻密な計算だったのね。
その後、染織家の下地康子さんの個展を拝見しに、南青山の como さんに伺いました。色とテクスチャーの妙、すばらしかったです。下地さんの表現したい世界観と、作った作品がピタリと合ってる感じがしました。それってすごい。
染色家・福本潮子展は、銀座もとじさんにて、15日(月/祝)まで。
真東風 織工房URIZUN 下地康子展は、como さんにて、17日(水)まで。
というふうに、今日はおしゃれな場所に行ったのに、写真はうちの近所。工場の壁。
利根山光人展

先日のことだけど、町田市立国際版画美術館に、利根山光人展を観に行ってきた。不勉強でこのアーティストのこと、存じ上げず。ただ、近場で、流行りものでない、ガッツリしたアート、観たかったから行ってきた。
で、ものすごく、よかったです。
油絵などの作品多く残した作家なので、回顧展と言えるのかどうかわからないが(この展示では版画にフォーカスされてたので)、この作家の生き様を観たような気がしたのだ。
1921年生まれ。1945年に召集。外地に向かう途中に終戦。その後アートの道へ。終戦後のダム建設現場の絵とか、ものすごくよかった。その後のメキシコ体験がターニングポイントだったらしく、如実に絵がかわり、それがよかった。全体的に見てもひとつの頂点と言ってもいいかも。
で、その後の絵は、いろいろ逡巡も見られ、それでも描くんだって意思を感じた。それでも描くんだ。で、最晩年の、HIROSHIMA とかね、行き着いた感じで。よかった。絶筆は、ドン・キホーテ。いいなあ、ドン・キホーテ描いて死にたいなあ。
利根山光人展は、8月4日(日)まで、町田市立国際版画美術館にて。この美術館、初めて行きました。水遊びが出来る公園の中にあり、子どもらがパンツいっちょで遊んでました。でっかい、水車みたいなオブジェがよかった。
写真はうちの近所。申しわけない。
テストふたたび

ありゃりゃ、ちょっと変でしたね。文字も中央揃えになっちゃうの?
トップページに、写真の小窓がかわいいと思ってるんだけど、出ませんねえ。
リベンジ、もういちど、やってみます。
写真は近所。
夜はDVD

着物のご注文のお話をいただいている。イメージするのは、とあるアメリカ映画。それで、DVDを入手して、夜中に映画鑑賞。インテリアがきれいだなあ。ダイアン・キートンのすっきりした洋服姿もすてき。ゴージャスなんだけど、スッキリなんだな。
私はこれから毎夜毎夜、この映画を見るだろう。お話くださったお客様のご希望をどこまで掬い取れるか。
ニューヨークとハンプトンが舞台なのだけど、写真は神奈川県大和市。
表参道から渋谷

表参道のルイ・ヴィトンのギャラリーで、トーマス・バイルレというドイツのアーティストの展示会を見ました。フロアに這うような作品です。音楽がいい音でなってて、それがとても印象的だった。エリック・サティらしい。
写真は、作品とそれを覗き込む私。

そしてワイパーみたいなのが、規則正しくメトロノームのように動く。すごく合ってた。見張りに立ってる黒服の男性も作品の一部なのかな。すごく合ってた。

その後、渋谷パルコのロゴス・ギャラリーで、高橋理子展を見た。刺激的でした。「人々の日常に存在する固定概念を覆し、思いを巡らせるきっかけを生み出す。」ってガラスに書いてあります。やり切ってるなあ。くー、かっこいい。
プレゼントの経糸
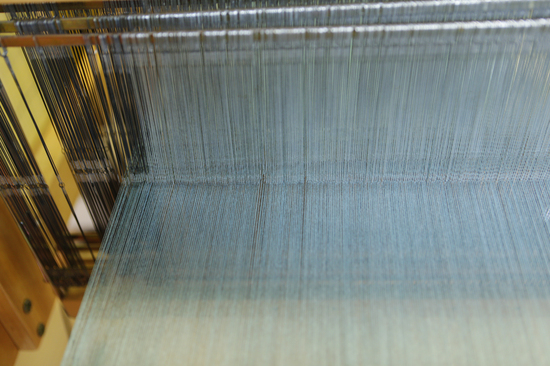
この写真はプレゼント企画のショールの経糸。
織り幅広いけど、筬は竹筬よん。今はもう作る人がいなくなった幻の竹筬、譲ってもらったのだ。
織りの道具も絹糸も、もちろん自分で買ったものが大半だけど、譲られたものも、相当ある。助けられて織ってるのだから、次にちゃんとバトンを渡すこと。
ああ、プレゼント企画っての、譲られたものを譲り直すって意味でもいいかも。謝恩祭って感じで企画したけど、感謝の気持ちは、お客様だけでなく、関係してくれた人、全てに。
写真は、武藤奈緒美さん撮影です。
いまだにテスト。すみません。

ごめんなさい。テストです。iPhoneからブログアップ。うーむ、写真の入れ方がわからない。
困ったなあ。前のブログからこちらへの完全移行を6月30日としているのだけど、できるのかしらん。機械に愛される私にならんとなあ。
写真は後からパソコンで入れました。空けたままも難だったので。ラブ・ロスコシリーズの帯です。
カメラマン、武藤奈緒美さん

先日、カメラマンの武藤奈緒美さんが、我がスタジオに遊びに来てくれた。武藤さんは、第一線のカメラマンなのだ。でもパっと見は、格好も持ち物も可愛い感じ。なのに袋の中からでっかくゴツいカメラが出て来ておどろく。おお、そんなのどこに入ってたの〜。
彼女の写真、すごくいいんです。今日の一枚は、武藤奈緒美さん撮影です。
武藤さんは文章もいい。きっとシャッターチャンスを逃さない目と感覚が、あの文才にも生きているのだと思う。
武藤さんのブログ「むーちょ写真日記」。おすすめです。トップページはここ。
私のことを書いてくれたのはここ。いいんだ、これが。
ウェブサイト、オープン2週間!(明日だけど)

サイトをオープンして、明日で2週間です。だから何だって言われちゃいそうだけど。私のドキドキは続いているのです。
書いた文章、いまもちょっとずつ校正してます。行間とか変だもんね。すみません、変なままアップしてしまっていて。少しずつ少しずつ直しますので、どうかご容赦のほど。
このブログのフォーマットもいまだ定まらず。落ち着かないので、元々のブログ、some origin も更新してます。ちょっとずつこっちに移行したいのだけど。
この写真も撮ってもらったの。いいでしょ、私の武器庫。
サイトオープン、一週間!
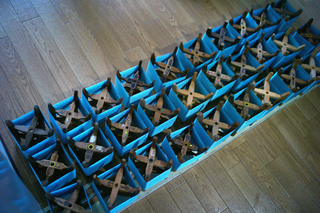
サイトがオープンしまして、一週間たちました。そわそわしてたのも、納まってきました(笑)。落ち着いて、じっくり仕事せねば。
今回のサイトオープンで、いろんな方にお便りしたら、メールやらお葉書やらで、やり取りでき、それがうれしい。
写真は、サイトのための撮影のときのです。私が撮ったんじゃないよ。プロの方。このサイトの写真の評判、とてもいいです(よね?そう思うでしょ?)。おかげさまです。ありがとう。
ウェブ、オープンするも、いまだドキドキ。

ウェブ、公開しまして4日目です。いまだ慣れず。
サイトの改善点など、仲よくさせていただいてる方から、アドバイスいただいてるのがうれしい。自分で見えなかったこと見えるのだもの。ありがたいです。
新しいブログ、むずかし。さっき、iPhoneから更新したら、消えました。染織の分野だと、思い通りにならないことの解決策を計るのは好きですが、機械はきらい。言うこと聞いて、お願い。
写真は近所。散歩の途中。
ウェブサイト、オープンしました!

ウェブサイト、どうにかオープンして丸一日。おっかなびっくりドキドキです。見切り発車ゆえ、靄の中をそろそろ進みます。お問い合わせ欄からメッセージいただいてるのがうれしいです。
今回は、ブログの更新、初のiPhoneから。できるのかしらん?とにかくやってみます。
写真はうちの近所です。散歩の途中から。
ウェブサイト、オープンです!

ドキドキしながら、ウェブサイトオープンいたします。はてさて、どうなることやら。いろいろ詰まってないことなどありながらもとにかく始めるんだって見切り発車です。どうか寛大なお心、お願いいたします。ご意見などいただけるとうれしいです。ブログの引っ越しも実はとても不安です。まあとにかく始めるのです!どうか、どうか、よろしくお願い申し上げます。
書きたいことなど、ボチボチ書きます。染織もますますがんばるのです。
写真はタンスの上にご注目。吉田作ブラッシングカラーズの花瓶敷きです。
テストふたたび

ブログテスト、二回目です。今度はちょっと長文テスト。行ってみよう。
新しいブログに移るのは、一抹の寂しさがありますね。実は今現在は、元のニフティのココログ「some origin」とこの新しいサイト内のブログ、両方更新しています。あちらは終幕を迎えようとしてて、こちらは胎動しています。去ろうとしてるものと、これから生まれでるもの。私はそのはざまにいて、日々の雑事に追われながらも、何だかしんみりしております。
昔、存夜気という言葉を追いかけてたことがありました。存夜気って、夜が終わりそう、朝がきそう、でもまだどちらでもない、そんな薄ぼんやりの、もやっとしたひと時のこと言うらしいです。まずめ時といいますか。孟子によると夜気と言って、邪気を刷新して、清く整える時間らしいよ。
そんな時間帯にいるみたいです。心を整えよう。清くはなかなかならんけど。
写真はスイミングプールの中から空を見上げる。金沢21世紀美術館にて。フォルダに残ってた写真より。
てすと

てすと、てすと、てすと。ただいまブログのテスト中。新しいの、はじめるよ。るるるー。
写真は、フォルダの中に残ってた昔のです。金沢21世紀美術館のスイミングプール。新しいことはね、水の中から生まれるのだよ。うふふ。